原田が長期の出張に旅立ち、東京から姿を消して二週間ほどが経っていた。けれど、今日もあいつは変わらない。それは今日だけという訳ではなく、昨日も一昨日も変わらず、きっと明日も変わらないことなのだろうと思う。千載一遇のチャンスと僅かながらにもそう思った俺はきっと愚かでしかない。喜ぶどころか、それは俺を惨めにするだけだった。 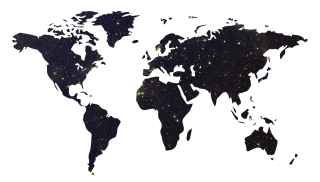 原田とあいつが付き合っていると分かって、初めて俺自身がどこか今まで外に出ないように押さえつけ、気づかないようにしていたその感情が沸いて出て俺を掻き乱した。もっとも、原田が移動してこなければ俺がその得体の知れない感情を自覚することもなかったのだろうけれど。果たして自覚したことを感謝すべきなのか、悔やむべきなのか。答えは、明白だった。 四国への長期出張は俺からの辞令ではない。俺よりももっと上役の人間が決めたことを俺が原田に伝えたというそれだけの事だ。転勤ではなく、出張かと少し残念に思ったのはもちろん回りの誰にも悟られないように気を配った。 あいつは俺が原田に辞令を出したと思って、怒るだろうか。それとも柄にもなく悲しむだろうか。いつだって喜怒哀楽の感情が薄いそんな女がそうにまでなるのであれば、それはそれで諦めがついていいとも思った。 原田が四国への長期出張へと旅立った翌日から、俺が思っている以上にはいつもと変わりなく働き、しっかりとやるべき仕事を片付けて定時で帰る。それはまるで、最初から原田がこの部署にいなかったかのように、自然なまでのあいつの姿だった。 「では、そういう事で。よろしくお願いします。」 いつもであれば原田がやっていた筈の業務に俺はついていた。取引先との顔合わせに出るのも随分と久しぶりな気がしていた。「今日は原田さんではないんですね。」なんて、どうでいい言葉を聴いてうんざりする。あいつの人気はどうやら社内だけに留まらないらしい。 会議室のドアにノックが響くと、がコーヒーを持って現れた。そっと来客用のコーヒーを二つ会議室に置いて、最後に俺の手元にも同じものを置いた。来るタイミングが遅いのではないかと、一度だけ軽くギロリと見ると何食わぬ顔であいつは一礼をして出て行った。そんなあいつが出て行って数分後、少しだけコーヒーに口を付けた客人達は帰っていった。 「部長、まだ五分も経ってないんですけど。早すぎませんか。」 「余計な話をしてやるほど俺は暇じゃない。」 「そういう事していると大事なお客さんに愛想尽かされますよ。」 「馬鹿。お前が持ってくるの遅いんだよ。」 きっと原田の場合、もう少し時間をかけて打ち合わせの場を設けていたのだろう。がコーヒーを持ってくるタイミングが、それを物語っていた。 「ちょうどいい。時間が余ったからこのまま打ち合わせに入るぞ。」 「…打ち合わせなんて聞いてないですよ。」 「お前に時間をくれてやってるんだ、感謝はあっても愚痴は受け付けていない。」 そういうと渋々と先ほどまでコーヒーが置いてあったテーブルに荷物を置いて、あいつは腰掛けた。こうしてあいつと一緒に二人で打ち合わせをすることは珍しい。 「ほんと、部長って俺様で強引ですよね。モテませんよ。」 「別にモテたくて仕事やってる訳じゃねえからな。」 ノートパソコンを繋いで、大きなスクリーンに映し出して俺は話を進める。別に二人で打ち合わせをする必要なんてどこにもなかった。が言われずとも勝手にするような仕事を、丁寧になぞって伝えるだけの不要とも言える時間でしかなかった。 人付き合いのいい原田であればもっと上手くやるのだろうが、俺にはそんな柔軟性はない。ましてや人の女を横から掻っ攫って酒でも飲みに行こうと片手を挙げて陽気に誘ってみたりでもしたら、あいつは白い目で俺見てくるだろう。それは想像にたやすい結末だ。 「言われなくてもやりますよ、それくらい。」 「上司に向かって随分な言い様だな。」 「こうしてる間にも時間過ぎていくし、戻りますね。」 なんとも可愛げのない女だと思いつつ、会議室を出て行くその背中に複雑な気持ちを覚えた。この反比例する気持ちに見切りをつける方法があるのなら誰かに教えてほしかった。 必要のない打ち合わせを終えてから、言葉のとおり黙って仕事を完璧に仕上げたあいつはアナログ時計が六時を示すとデスクを片していち早くオフィスを出て行く。今日はもう金曜日か、いつもより周りがざわついている事でそれを思い出して曜日感覚がなくなっているのだなと自覚した。原田にでも会いに行くのだろうか、そんな考えなくてもいい思いを浮かべて仕事を阻害した。 俺にとって金曜日は仕事に専念できる日だ。世の中のサラリーマンは華の金曜日とかこつけて酒を食らいに夜の街へと消えていくが、俺にとってはそんな奴等がさっさと退社して一人集中して仕事ができる環境を手に入れることができた。人とは違う金曜日の夜の有意義な過ごし方に自嘲せざるを得ない。翌日のことを考えなくていいのだから、俺はそう言い聞かせて薄暗くなったオフィスでパソコンと向き合いひたすらに仕事を続けた。 原田が居なくなってから相当に俺にかかる負担が大きくなっていた。どれだけ原田が有能で仕事を捌ける人間かを知っていたつもりではいたが、それは想像以上のものだったのだと改めて思う。 「土方さん?まだ残ってたんですか。」 思いもよらない声が、木霊する。こんな時間にあいつの声を聞いたことがあっただろうか。ついに俺の頭は幻覚まで映し出すまでにどうにかなってしまったのかとも考えたが、そこにはしっかりとあいつがいた。 「何だ、こんな時間に。忘れ物か。」 「原田さんが資料忘れたから送って欲しいって。仕方ないから取りに来ました。」 「そんなもん月曜にやればいいだろ。」 「大事な書類だったみたいなので。」 がこんな時間に自分の忘れ物ならいざ知らず、ほかの人間の忘れ物をとりに来るなんて不思議以外の何物でもなかった。そしてそれが、二人が今も尚変わらず関係を違わず育んでいると俺に見せ付けているようでもあった。 「じゃあ。私、帰りますね。」 「ああ。気をつけてな。」 送っていこうかと出掛かったが、それを紡ぐことはやめた。あいつのこんな行動を見ては、そんな事が言えるはずがないと。 まだモヤモヤとした何かが残っていたが、逆に今日は俺にとってはいい機会だったのかもしれない。得体の知れない感情に振り回されるのではなく、俺はこうして仕事に没頭していればいい。前から、そうだった筈だと。一つ、踏ん切りがついた気がした。人はいずれ何事にも順応していく生き物なのだから、きっと俺にもそう思える日が来るのだろうと思い込んだ。 残っている仕事を片付けるのは、一息ついてからでもいいだろう。タバコを胸ポケットから取り出して、立ち上がる。喫煙所に寄るついでに、コーヒーでも買おうかと考える。 薄暗いオフィスで、俺は目の前の出来事に驚いて、一度立ち止まった。 「帰ってと言っても聞いてくれないだろうし、コーヒーの置き土産くらいしておきますね。」 無感情で、可愛げがなくて、たった今その感情を断ち切ったはずなのに、こんな時まで仕事ができるあいつは本当にどうしようもなく酷でしかない。たった今買おうとしていたコーヒーは、昼間に会議室で見た湯気を立てて俺のデスクへと置かれていた。 「…ほんと、大馬鹿やろうだな。お前は。」 「何それ。褒めてるんですか。」 「自分で考えろ。」 ただ一つ、原田のほうが先にした事と言えば、しっかりと自分の意思をあいつに伝えたというその一点のみだろう。俺が先に伝えていれば、俺の隣にはいたのだろうか。 誰も居ないオフィスで、の手を引いて懐へと抱き寄せた。俺とは百八十度まるきり違う原田に、こんな事が知れたらどうなるのだろうか。不思議と、恐怖はなかった。 たた一つあったのは、穏やからならぬ強い過去への後悔だ。
|
