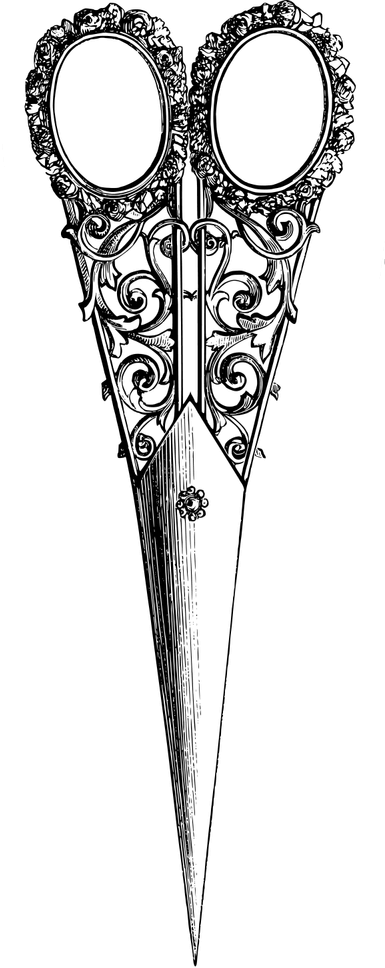 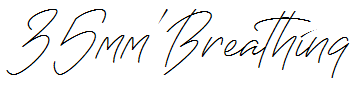 「却下。てか、お前馬鹿?」 ―――嗚呼、始まった。 こうなるのが分かっていたし、何度も頭の中でそうならないようにシュミレーションをしてきたにも関わらず迎えた現実は私が脳内で一番危惧していた想像通りに運んでいるのだから事は深刻だ。というか、最悪だ。 私がその違和感に気づいたのは、一ヶ月ほど前の事だ。仕事中にふと冷や汗をかく様な背中がぞくぞくと波立つような痛みを感じたと思えば、数分したら痛みは引いていく。一過性の胃痛だろうかと思って暫く放っておけば、不規則な感覚でまた同じ感覚に襲われる。 そんな不調を数日繰り替えし、仕事に折り合いをつけて受診した先で下された診断名を、私はひたこの一ヶ月彼に隠し通してきたのだ。冒頭で言われたその言葉を言われると分かっていながらも、どうにかしてそうならない未来を自分で作り出すため私なりに試行錯誤してみたものの、彼をもってすれば結局私の提案は通らず、答えはイエスではなくノーの一沢なのだ。分かってはいたが、本当にただの悪があきになってしまった。 「今更そのビール腹見られるのが恥ずかしいとかそんな阿呆みたいな理由じゃないだろうな。」 「……言っててありえないって分かってて言ってるでしょ。」 「ビール腹は本当だろ。」 話は数十分前から平行線を辿っている。あの手この手で所詮言い訳にしかすぎない言葉で戦いを挑んでみたものの、もう彼の言葉に勝つ術を持っていない私は降参一歩手前だ。頑固というものはこういう時はより効果を発揮して難儀なものだ。 話をまとめると、こういう事だ。 自分に近しい人でなくても遠い知り合いくらいのレベル感であれば、誰でもかかっている人を見たことがあるだろう。所謂盲腸だ。死ぬ病気でもないし、薬で散らすという一時的な対処法もある比較的ポピュラーな病だ。それに最近は開腹せずとも内視鏡手術と言って数箇所穴を開けるだけで出来てしまうのだから医学の進歩はすごいなと悲観する前に感心してしまったくらいだ。 だからこそ、あえて彼に言わなかったのだ。これがもちろん重大な病で長期にわたる治療や通院が必要ということであれば伝えなければいけないとも思うけれど、私の症状は盲腸だ。原因を取り去ってしまえば、特別問題はない。 とは言え数日の入院が必要になる点を踏まえると、彼に言わずに勝手に入院して退院するというのは望ましくない。というか、ほぼ確実と言えるくらいの高確率で綻びが出て事が発覚するのは想像に容易い。ならばもう決定事項として入院するという事実を伝えればいいのだと、ようやく来週にまで入院が迫ったタイミングで彼に告げた結果が、あれだ。 「いや、だからもう手続きもして来たって言ってるじゃん。」 「時期をずらせばいいだけの事だろ。」 「もうそこに合わせて有給も取ってあるしそんな事言われても困る。」 「そんな事を直前まで俺に言わないお前が悪い。」 確かにそれは一理ある。こうなる事はどう足掻いても回避できない事を分かっていたのだからその通りすぎて一瞬言葉に詰まってしまった。 本来であれば自分自身が盲腸で、そして入院と手術が必要な事を彼である宇髄に伝えるのは何ら問題はないのだが、そこを尻込みしてしまったのにはきちんとした理由が介在している訳で、そんな気持ちを汲み取ってくれないだろうかと慈悲を求めて視線を送ったところで結果は変わりそうもない。 「だって言ったら絶対自分が執刀するって言うでしょ。」 「当たり前だろ。逆にこの境遇でそうならない奴いなくね。」 「色々と抵抗ある訳、なんか気恥ずかしいし。」 「お前にそんな恥じらいの感情があったとは知らなかったな。」 「話を逸らさないでよ。」 話がここまで複雑化し、ひどく面倒なのは彼の職業が医者であり、また外科医であるというたった一つの理由に他ならない。彼の性格上どう考慮しても何万パターンと想定をしても万に一つにもそのままほかの病院で入院を許してくれるという回答は得ることは出来ないだろう。そんな事は分かっている。単純な事なのだ、私は万に一つの賭けにでて、ものの見事玉砕したといううだけの事なのだから。 「そっちだってやり難いでしょ?」 「別に。逆に他の病院で受けられた方が苛ついて日常生活に支障出るわ。」 彼の性格を考慮すれば、彼の言っている事は至極真っ当で言いたいことも理解ができるのだろうけれど、当事者が自分となるとそうも言っていられないだろう。 きっと私のように、知り合いや恋人、家族に医者が居ない限り自分自身が手術をする事になった場合の想定などしないだろう。私だって宇髄と付き合うまではそんな事を考えたこともなかったし、知人からの紹介やネットでの口コミで病院を決めていただろうと思う。 けれど彼が医者である限り、万が一自分が病気になったら?と一度は考えるものだ。もちろんそんな日がやってこないのが一番いいに越したことはないのだが、生きるという事は常に何かのリスクを負っているのだから病気になることもあるのだ。そんな事を以前ぼんやりと考えていたが、まさかそれが現実になるとは私とて思ってはいなかった。けれどその時、はっきり思ったのだ。 「信頼してないとかじゃなくてさ、嫌でも心配するでしょ。」 確かに彼の言うとおり自分の知りえない所で入院や手術をされる事の方が気になって不安になるのかもしれないし、それは私にだって理解は出来る。けれど、いくら死を伴う病気ではないとはいえ自分の近しい人間を手術するとなると気分がいいものではないだろう。そんな事を、かつての私は思っていた。 私の言いたい事を一定理解したのか、少し言葉を飲み込んで間を作った宇髄に万に一つの希望が通じたのかとも思ったけれど結局私の希望はただの願望で音を立てて崩れ去った。 「心配は何処にいようがするもんだろ。あー、明日入院の書類取ってくるから持って行くわ。」 こうして、私の賭けは玉砕という結果に終わり、翌日ヒラヒラと紙を目の前でチラつかせる彼に見張られながら書類を書くという結果に収束した。 少ししんみりと言ったあの雰囲気を返してほしい。何だか少し癪に障る。 入院まで、あと五日。前途は多難だ。 結局何だかんだ言いながら私は宇髄の働く大学病院に入院した。 金曜日ギリギリまで仕事をして、土曜日を待って入院した。手術は月曜日に行われる。てっきり翌日には手術するものなのかと思っていたが、執刀医がたまたま土日休みだったらしい。もっとも、その執刀医が誰なのかは想像に難くないと思うので省略することとする。 「非番の日まで来る理由作るなんてお前も粋だな。」 「…何の嫌味?自分でそう仕向けた癖に。それに見舞いに来いなんて頼んでない。」 「主治医からの事前の労いてやつだ。」 よく意味も分からなければ、分かりたくもないような理由を漕ぎ着けて見舞いにやってきた宇髄は特段いつもと変わらないように見えた。実のところ私は彼の白衣姿を見たことがない。だからこうして手術前にいつもの彼がいてくれて少しだけ安心したような気がした。 宇髄から聞いた話だとそこまで時間は掛からず処置は済むようで、傷跡も最小限残らないような配慮が出来るらしい。 日常的に仕事に追われている事が多く、こうして何も考えずのんびりとするのは久しぶりな気がする。逆にこういう時に何をして暇を潰せばいいのかその案を持ち得ない私は入院には酷く不向きだろう。今現段階で体が元気なだけに余計とそう感じる。 「…暇って手術より苦痛かも。」 「だから個室入るかって聞いただろ。」 「そんな特別扱いされる理由ないし。」 「普段がめつい割りにはそういう所気にするよな、お前。」 確かに彼の勤め先であるこの病院への入院が決まった時、個室にするかと聞かれたことを思い出す。入院経験のない私は大部屋に抵抗はあったものの、そこまで待遇してもらう理由もないと断ったのだ。その方が自分も顔が出しやすいからそうして欲しいという提案を跳ね除けてまでだ。――今になって、少しだけ後悔の念に駆られた。 「今日は適当に過ごしとけ。明日もし眠れないようだったら連絡してこい。」 「今日明日休みでしょ。」 「どうせ月曜の朝からオペなんだ。日曜の夜から来るつもりだ。」 ふうん、と流して聞いてその日は彼が帰ってから本を読んだり何だかんだ時間が過ぎ、一週間の仕事の疲れもあってかいつもよりも早く自然と眠りにつくことができた。 そう思っていたのは、入院した初日だけだった。明日に手術が迫っているのかと思うと、自分の知らないうちに大きな不安とプレッシャーがかかっていたらしく、何度か見回りに来た看護師が来るたびに修学旅行で狸の寝入りを決める生徒のように眠った振りを決め込んで、スマホを見ると午前零時を過ぎていた。手術は、もう目前まで迫っていた。 昨日宇髄に言われた事を思い出して、スマホの画面を立ち上げる。前日入りするとは言っていたが、もう来ているだろうか。 ―――もう、病院いる? あまり期待はせず、このまま自然に寝れるのであればそのまま寝てしまおうと、メッセージを送っておきながら画面をひっくり返しえ寝返りを打つとすぐにブッブッブとベッドの上で振動した。 ―――寝れないのか。 ―――何か変に目が冴えちゃって。 ―――次の見回りまでかなり時間がある筈だ。トイレ行くふりして二階まで降りれるか。 体をベッドから起こして、スリッパに足を突っ込んで私は戸を開く。辺りに人影はない。何だか少し悪いことをしているような気分に陥って、左右を念入りに確認をして私は階段を下りた。 「。」 私がすぐにやってくるのが分かっていたと言わんばかりに、階段の先には宇髄がいた。きっとこうなるであろうと想定でもしていたかのようで少し負けたような気はしつつも、少しだけ不安な気持ちが解消されていくような気がした。 「柄にもなく緊張してるのか。」 「…想像してたよりは。」 「やけに素直なんだな。いじらしいじゃん。」 「ちょっと見縊ってた。」 死ぬ病気じゃないと粋がっていたのは自分の筈なのに、やはり不安になるものなのかと医者の言うことは聞いておくものだなと少しだけ思う。あれだけ頑なに違う病院でと言っておきながらも、こうして彼が傍にいてくれる事が私にとっては大きな意味を持っているのだと気づく。 何をどうした所で何も変わらないと分かりつつ、手持ち無沙汰でどうしていいか分からない時にきちんと傍にいてくれるのだから、彼が何よりの精神安定剤なのかもしれないと絶対に口には出せないそんな事を考えた。 「大丈夫だ。寝て、起きたら終わってる。」 そういって、暗がりの中でもそのかんばせに救われて少しばかり気持ちが落ち着いた気がした。ぽんと私をあやす様に置かれた彼の右手がとても偉大なものに感じられて、少し距離を縮めると大きな懐が私を包み込んで安心させてくれる。 「何せ執刀医、俺だしな。」 「…自信過剰。」 言葉とは裏腹に、今回ばかりは彼の言うとおり私は彼に救われたような気がした。 病室まで送り届けてもらってからは不思議とすぐに眠りに落ちることが出来て、気づいたら朝になっていた。起きてから間もなく少しだけ覚悟を決めると、麻酔が入って目の前にいる宇髄が徐々にかすんで見えて、そして次に目を覚ました時には全てが終わっていた。 何度か目を覚ました気もするけれど、どれもぼんやりとした記憶しかなく定かではない。きちんとした記憶を持って意識を戻したのはどうやら随分と時間が経ってからだったらしい。傷の痛みと多少体の火照りを感じるものの、幸いな事に想像していたより体の状態は悪くなかった。 周りは頻繁にナースコールを押して如実に具合が悪いのだと分かると、私は恵まれているのかもしれないなとぼんやりとした意識の中でそんな事を思った。 「さん、気づきました?」 シャアっとカーテンが引かれる音がして急に意識がはっきりとしていく。腹部に違和感を感じているという事は全てが終わって、そして私が無事手術を終えて生きているという事なのだと理解した。 「術後アレルギーで発疹出て、宇髄先生が定期的に見に来てくださってたんですよ。」 喉が掠れて上手くしゃべれない私に、定期的に時間を作って彼が見に来てくれていたのだと聞いて表現しがたい感情に襲われた。どうせ傷をつけなくてはいけないのであれば、それが彼であってよかたと思った。 朝になれば一部管が抜けて、歩行訓練が出来るらしい。もう少しだけ眠れば楽になりますからねと言われて、その言葉に安心して再び眠りについた。火照った熱に息苦しさを感じながら、時折手のひらに温もりを感じたような気がしていた。 翌朝目を覚ますと、一度目覚めた時よりも意識ははっきりとしていて、全てが現実のことなのだと理解できるまでに回復していた。少しばかりまだ体は火照っていたけれど、動くのに支障をきたす程ではない。 僅かに感じた手の温もりを感じながら体を起こす。すぐに看護師が近づいてきて今後のスケジュールを教えてくれて、私は問題ないと判断されて点滴をぶら下げながら看護師に体を支えられながら廊下を歩いていく。術後日数に比例して十週するといいですよと言われて五週目に差し掛かった頃調度宇髄が白衣を着て通り過ぎていくのを見かけた。 仕事をしているだけなのに、いちいち黄色い声が蔓延っているのだからさすだなと思う。私は彼の働いている所を見るのはこれが初めてだったけれど、今目にしている光景が毎日繰り広げられているのだろうなと想像にはしていた想定範囲内の出来事だった。 けれど人とは不思議なものだ。分かってはいても、実際に視界にそれを映し出して認識するのとでは天と地ほどの差があるらしい。一定の状況を理解しつつも、なんだかもやもやとした感情が渦巻いた。 結局私は七周の“俳諧”ともいえる歩行訓練を終えて、目標である十周を終えず病室へと戻った。 そこからは腹の傷がより一層痛む気がして、何も手につかない。読んでいた本も奇しくも数ページの伏線回収を残して読み終えてしまった。有料のテレビカードを買わない限り見れないテレビを視界に映し出して若干の苛立たしさを感じていた時、丁度カーテンが開いて知った顔が私の視界に広がった。 「術後良好と聞いてますがお加減いかがですか。」 しれっとした何食わぬ顔で、そして少しだけ含み笑いを宿しているような彼のかんばせに私はうまく答える術を持ち合わせず、ぶっきら棒に「先生の腕が素晴らしかったようで意図せず元気です。」と答えると、そうですかと一般的な答えが私の耳を掠った。 「一応、診察しますね。」 そんな如何にも医者らしい事を言いながら腹に当てられた聴診器を前に、意図しない行動を自分が繰り出そうとしているのだと、体と感情が一致する。 彼の白衣を一度右手でぐっと握り締めて、手繰り寄せて抱きついた。きっと、少しばかりの嫉妬があったのだと、そしてそれが彼の策略で思う壺である事を理解しながらも、この時ばかりは自分から彼を求めてしまったのだから少し悔しい。 「それだけ動ければ問題なく予定日に退院できますね。」 「先生の、おかげですね。」 少し皮肉めいたようにそう言えば、静かに唇が重なって、ようやくここが現実の空間である事を思い出した。カーテンで覆われた、私と彼だけが知る状況を逆手に取ったその状況が、何処か悪いことをしているような秘め事のような気がして胸が高鳴った。 「ガスでたら教えてくださいね。」 「はい。“看護師さん”に言いますね。」 離れていく唇を名残惜しいと思いながら、憎まれ口を叩きながら彼は出て行った。思えば、私から積極的気に彼を求めたのは初めてのことだったかもしれない。これが彼の思い描いた壮大なプランだったのかもしれないと思うと何処か納得できないようであって、そして今回ばかりは負けを認めざるを得ないと思った。 ―――大部屋でスリルを感じたくて個室拒んだのか。 ―――まさか。自惚れるのも対外にしてほしい。 その後しばらくしてからメッセージが届くと、私も素直になりきれないまま返信を打つ。もっと甘えたようにできたら、感謝の念を素直に伝えられる性格だったらいいのにと思いながらも、今更そんな事できないのだからと改めようとも思わない。 ―――屁の報告、待ってる。 その返信に殺意を感じながらも、ベッドの隣に肩身が狭そうに佇んでいた健康祈願のお守りを見て、一度打ちかけていた返信内容をすべて消し去って、思う壺だなと思いながら私は返信を書き直すのだ。 ―――大好き。 もしかすると、皆が憧れる男が私のものである事は何よりも優越感に浸れるもので、そしてそんな男を彼に持つ私は誰よりも幸せな女なのかもしれない。 入院と手術という代償を払って分かったものは、思いのほか大きかったのかもしれない。 35mm、呼吸 |