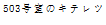|
ニュースをつけても、何処か信憑性のないこんな話題で持ち切りだった。パソコンを開いて、検索画面に辿りつくと、そこにも嫌でも目が付くほどに見出しをつけた、そんな話題でにぎわっていた。本当に馬鹿らしいと、私はそんな事に目もくれなかった。 「は?お前そんな事信じてるのかよ。馬鹿じゃん。」 「いや、普通に言っただけじゃん。」 あまりにも彼があっけらかんとした表情で言うものだから、私もおちょけた様に彼の語尾を真似して返事をした。とは言いつつも、学内でもその話題が何処ともなく犇めいていたのだから、私は取りあえずそれを知ってるのだと言う事を証明したかったかのように、手近にいたブン太に軽く告げた。言った当人も大して興味がなさそうであれば、それを聞いたブン太も聊かにも興味がないようで、結局私達のその話題についての会話はそこでひとまずの終わりを見た。 隣の席で講義を受けていたブン太と成り行きでそのまま下校する事になって、私達は初めて外の異変に気づいて、呆気に取られた。 「今日の天気予報降水確率ゼロだったぜ。」 「うん。柳に今日のお天気は?って聞いたら雨の確立ゼロパーセントって私も言われた。」 「お前柳の事お天気キャスターと勘違いしてんのか。」 「してないとは言い切れないかも。」 今朝方、家を出た時に傘を持っている人は誰もいなかったし、あの柳が雨の心配はないと言っていたのだから、私達は目の前でザーザーと音を立てて地を叩く雨に呆気に取られ、今にも雷でも鳴りそうな空に立ち往生になっていた。 かろうじて持っていた折り畳み傘を開いた私は、「じゃあ。おつかれ。」なんて言いながら何事もなかったかのように進んで行くと、案の定待ったの声と共に、右肩に圧力を感じた。 「普通おいていくかよ、この状況で。」 「いや、まあ、だって傘ひとつしかないし。」 「入れろよ。」 「…知ってる?折りたたみ傘ってコンパクトに持ち歩けて便利な分すごく狭い範囲でしか雨しのげないって。」 まるで聞く耳を持っていないかのように「お前と相合傘してやってるんだから感謝しろ。」とブン太。酷く上からのその目線に、私は一度軽く彼の足に蹴りを入れた。蹴られた彼も、何か言いたそうにこちらを見たけれど、自分が雨に濡れない最善を考えたのか、それ以上は開きかけた口を閉じて、傘を持った。 「なんでアンタが持つの。これ私の傘なんだけど。」 「お前の方が背低いからだろい。」 「言う程に変わらないと思うんだけど。」 そう言えば、耐えきれなくなったブン太の口が大きく開き、けれど、やはり何かを我慢するように再びそれを閉じ、控えめに先ほどの私と同じように、軽く私の足に蹴りを入れてきた。 ブン太とは、大学に入って出会った。在校生の半数以上がエスカレーター式に上がって来るこの立海で、私の様な存在は酷く珍しい。人とつるむのを不得意とする私にとって、大学というコミュニティーは予想通りフィットしない。いつだって隣でスヤスヤと寝息を立てる、いかにも今時の大学生と言った風体のブン太は定期的にノートをせがんでくる、そんな関係に過ぎない。ブン太の中での私の役割は、きっとノートを貸してくれる女というものでしかないだろう。けれど、私の性格上、それくらいの関係性が一番しっくりとしていた。見るからに交友関係の広い彼に、何人かの友人を紹介され、徐々に私の知り合いは全てブン太の友人で埋め尽くされていた。 「お前、今日何か予定あるの?バイトとか。」 「ないけど。」 地方出身者の私はもちろん一人暮らしをしていて、それを彼も知っている。教えた事はなかったけれど、なんとなく学校の近くに住んでいる事を知っていたのだろう。はたまた、大学に行くために一人暮らしをしている人間が、余程の理由がない限り学校近辺に住まない訳はないと踏んでいたのかもしれない。次にブン太の口から出るであろう言葉は、なんとなく私にも理解が出来た。 「ちょっと雨宿りさせるくらいいいだろ?」 その言葉に私は一度傘から奥を覗き込むように、荒れ狂う空を見た。 「いや、そんなすぐに止むんだったら頼まねえよ。」 珍しく、彼の言葉が酷く正論で、私は一息おいてから承諾の言葉を口にした。テレビに映るどんな天気予報士よりも天気に関して信頼を置いている柳の予報が外れたのだから、この雨は本当に暫く止む事がないのだろうなと、そんなどうでもいい事を思った。 承諾の言葉を口にしてからものの数分、私達はようやく傘を畳んで、マンションのロビーに到着した。 「入れば。」 「あのさあ。俺が言うのも何だけど隠すもんとかねえの?下着干したままとか、そういうの。」 「生憎今日は洗濯機回してない。」 「不衛生な奴。」 「一人暮らしで毎日洗濯機回さなきゃならない程着るものに困ってません。」 そう言えば、ああ、なんて珍しく納得したように彼は頷いていたけれど、「本当にパンツ大丈夫か。」なんて繰り返してきたものだから、取りあえずもう一度蹴りを入れて、イテテと大げさに振る舞うブン太をようやく部屋へと導いた。 「予想通りと言えば予想通りすぎるけど、もう少し女ッ気のある部屋にしてもいいだろ。」 「期待に添えたようで何よりです。」 彼は、本当に必要最低限な家具しか置かれていない我が家に何だかがっかりしたように靴を脱いだ。 「男をこうも簡単に入れるっていうのもどうなんだよお前。」 「アンタが言うな。」 口を開けば、ブン太とはいつだってこんな事ばかりだった。八割の会話がこうで、あとの残りの二割はノートをコピーさせてくれと必死に頼んでくるブン太の一方的な会話だ。もちろん、学校の外で会ったりしたり、ましてや遊びに行く事もなかったし、遊ぼうという話にすら発展する事もなかった。そんなブン太が、部屋にいるのが何だか妙な感じだった。 「俺ココア。」 「そんな洒落たものうちには置いてません。」 「女子力どこだ。」 「甘い物が女子力って一体いつ決まったの。」 世界の常識、そんな言葉と同時に彼はまるで我が家にいるかのように寛ぎ始めた。やかんに水を入れて火にかけると、まだかと催促してくるブン太があまりにも苛立たしく感じられて、思わず火を消しそうになった自分の手を必死に止めた。必死の形相で沸かしたお湯に粉末のコーヒーを溶かし入れ、意味もなくペアのマグカップを彼の前に差し出した。 「牛乳。」 「ない。」 「冗談。」 「本当。」 ぶつぶつ言うブン太に、実家から送られてきた記憶のある角砂糖を、キッチンの奥の方の棚から取りだすと、彼は聊か機嫌を直したように角砂糖を二、三個がばっと掴んで、迷うことなくそれを溶かし入れた。 大量に入れた角砂糖にもまだ甘さに納得がいかないのか、やはりココアがいいと言ってきたブン太にいい加減手が出そうになったのと同じころ、ピシャンと落ちた光と、同時に雷鳴が鳴り響いた。 「嘘だろ。今すげえ近かったぞ。お前、雷平気か。」 「…うん、まあ、それなりには普通。」 「やっぱり可愛くねえなあ、お前って。」 私に一体何を求めてるんだと言えば、何にもと言う答えが返って来る事が、容易に想像できたので、私は取りあえず黙っておいた。停電はしていないものの、いつ停電しても可笑しくはない天気模様だった。 ブン太が慌てたようにリモコンを要求する。私も、反抗することなく、慌ただしくリモコンを手にして、彼に渡す。学校帰りにやっていたはずのドラマの再放送は、見当たらない。どのチャンネルをまわしても、映像は荒れ狂った異常気象についての事ばかりだった。暫くかじりつく様にして見ていたニュースの上に、文字が流れる。ブン太の声が、あ、と響いた。 「……俺帰れねえじゃん。」 「は、」 もう一度同じテロップが流れてくるまで、そう時間はかからなかった。そのテロップは、立海生が通学に使う電車の終日運休を知らせていた。私と、ブン太は、互いに顔を見合わせた。 結局そのテロップが運休再開に変わる事はなく、関東近辺を繋ぐ首都圏の交通網はほとんどシャットアウトされつつあった。帰る手段を無くしたブン太は、取りあえず友人の家に泊まるという内容のメールを親に送っていた。意外とそういう所に対してはマメで私は当然のように驚いた。すると、すぐに彼の携帯が鳴り響いた。声のトーンから察するに、母親ではなく、兄弟からの電話のようであった。電話の奥の相手を諭すように、酷く優しく、柔らかいトーンだった。私はこんなブン太を知らない。 「電話、誰。」 「何だよ。急に彼女面かよ。」 「いい加減怒るよ。」 そう言えば、弟からだよってブン太はぶっきら棒に答えた後、色々と話を聞かせてくれた。年の離れた弟が二人いて、酷く懐かれているのだと。案外面倒見がいいのかもしれないと思って、なんとなく学内で彼の交友関係が広く、皆に慕われているのかを初めて窺い知る事になった。 「地球最後の日に家族一緒にいないなんて可笑しいって言ってたな。結構信じてる奴多いんだな。」 地球最後の日というにはあまりにもしっくりとくるお天気模様に、本当に数時間後には隕石が落ちてくるのかもしれない。馬鹿馬鹿しいと一蹴していた私でさえ、何だかそれが人ごとのようではない気がしていた。本当に地球が明日、滅亡するかどうかという事を別にしても、地球最後の日には酷く相応しい、そんな形相だった。 「地球最後の日に一緒に居るのがお前とか俺色気ねー。」 「大丈夫。それは私も一緒だから。」 まだ辛うじて残された電気のライフラインを頼りに、本当に下らない話をこたつの中で永遠とした。これが人生最後の日ともなれば、それこそ笑うしかないだろうと思う程に、酷く、ただの日常のカケラに違いなかった。高校時代の話だとか、何で立海に入ったのだとか、もっと遡ってブン太がテニス部に入っていた話だとか、本当に色んな話をした。テニスサークルに入っているのは知っていたけれど、ブン太が全国でも名の知れたテニスプレイヤーであった事を知らなかった私にとって、悔しいかな、彼の話を聞くのは楽しかった。自分の事を滅多に人に話さない私も、何故か吃驚するほどに口が進んで、彼に色々と聞かせていた。 「お前はさ、人生最後の日何かしたい事とかある?」 「ああ、うーん…そうだなあ。何か思いつかないかも、案外。」 「お前人間的に冷めてるってよく言われないか。」 「煩い。死ぬ時は死ぬんだからしょうがない。」 もちろんブン太はそんな私の発言に、お決まりの突っ込みを入れた。でも、実際の認識なんてそんなものだと思う。死ぬと決まった事は変えられるものではないし、どうしようもない。一日で何かが出来る訳でも、到底ない。ならばせめて、ありきたりな、今までと何変わらぬ日常を過ごしたい。 私の酷く冷めた思考に、彼は「夢も希望もへったくれもないな。お前。」なんて言ってのけたものだから、私が同じ質問を彼に与えると、私以上に下らない答えが空間を彷徨った。 「俺?俺はそうだなあ、取りあえずおっぱいでも揉んどくかな。」 「私今確信した。アンタよりはよっぽど普通の感覚持ってるわ。」 「いや、そこは「ブン太の最後の願いだったら…」っていうお前の言葉が入るだろ、常識的に考えて。」 「何、追い出されたいの。」 「冗談だろい。」 結局ブン太とはいつもこうだから、実際のところ彼が何を考えているのか、私にはよく分からない。別に知る必要もなければ、特別知りたいと思う事もないのが救いだと思った。 「あー、でも免許欲しかったな。ドライブしたかった。」 「初心者マークで?」 「あ、それは恰好わるいな。」 存外小さな夢で、少し笑えてしまった。私のような地方出身者は、高校卒業前にもなればほとんどの人間が免許を取るのだが、都心の実家暮らしの人間はそうではないらしい。財布の中から取り出した免許を彼に見せびらかすと、彼もポケットの中にあった財布をごそごそと弄り、あろうことか場にそぐわない程に美系な写真の載った免許証を見せてきた。 「俺も持ってるっての。原付だけだけど。」 ああ、と私は、原付にまたがって三〇キロで走行するブン太を想像して妙なフィット感に酷く納得させられた。ブン太には車よりもそちらの方が幾分もお似合いだと思った。 「何それ。何の自慢にもなってないけど。」 「まあどうせ地球明日で滅ぶとかないからいいんだけどな。車の免許取ればいいだけだし。」 ブン太は冷めた甘ったるいコーヒーを飲みほして、暇そうに外を見た。まだ、外は外出を許してはくれなさそうだった。地球最後の日に相応しいほどに、未だ、雨と雷のオンパレードは留まるところを知らない。 時計の針がカチっと音を立て、午後九時を指す。テレビも相変わらず、どのチャンネルを回しても同じ内容ばかりを放送している。暇を持て余したブン太は、何もない我が家を何度もぐるぐると見渡して、本当に何もないとぼやく様に言った。私が当然のように何もないよと呟いて、何かを見つけたのか、彼はそれを取るためにコタツに足を入れたまま伸びるような体制で手を伸ばす。 「なんだよお前、良いもの持ってるじゃん。」 ニカっとした笑顔のブン太が握っていたのは、赤いリキュールだった。嘗て、興味本位で買ったそのリキュールは、私には幾分も甘ったるかった。ブン太は鞄の中からペットボトルのオレンジジュースを取りだし、新しいグラスにそれらを足した。 「しょうがないからお前にも分けてやるよ。」 「いや、半分は私のなんだけど。てか別に私はいらないんだけど。」 「まあそう言わずにさ。乾杯しようぜ。」 「…何に。」 仮称、地球の最後の日に 大して酒に強くない私達は、結局そのジュースの様な飲みモノを一杯のんだだけで、自然と眠りについていた。途中で寒さに目覚めた私はこっそりとベッドにもぐった。何故か、追う様に、眠気眼を擦ったブン太も、同じタイミングで私の隣でベッドにもぐってきた。拒絶しようと思えばそれも出来ただろうが、如何せん眠気の強かった私は、微量に残るアルコールに免じ、そのまま彼をベッドに受け入れた。彼となら何もないと、確信していたから出来た事だったのかもしれない。 私の目覚めは最悪だった。血相を変えたブン太の声が鼓膜で響く、騒々しい朝。それこそ地球が滅んだ事にブン太が驚いているのだろうかと、夢見心地にそんな事を考えたが、そうであればそもそもこんな煩い声を私が聞く事も、ブン太が言う事も、出来ないのだ。ごろん、とブン太の方へと寝がえりを打って、取りあえずおはようとあいさつをした。片面をブン太に取られていたせいか、思いのほか体が痛い。 「お前呑気すぎだろい。」 「いや、まあ、だって寝起きだし。低血圧だし。」 ブン太は不安そうに私を見ていたけれど、いつもと何も変わらない無愛想な私を見ると、何故か安心したようにホっと胸をなでおろしているようだった。今一現状を理解出来ない私は、きっと寝起きで頭がついていかないのだろうと、そう考える事くらいしか出来ない。本当にまだ頭が目覚めていない。 「お前、死んだんじゃないかと思ったら急に不安になった。」 「何で勝手に殺すの。そんなに憎いの。」 「だって地球滅亡するとか散々言ってたから、なんかこいつ死んでるんじゃないかと思ったんだよ。」 私がその話しをしただけで、信じてるのかと馬鹿にしてきた男の言葉とは到底思えない程に、本当に彼は心配しているようだった。自分が生きてる時点で地球は滅亡してないから安心しなよと言えば、ああそっかといとも簡単に納得した彼を見て私は心底彼の頭を心配してしまった。 「青葉。」 「なに。」 「あのよ。」 「うん。」 ブン太は何故かもったいぶるように、無意味に単語を羅列させた。私も、無意味に返事を羅列させる。酷く戸惑っているようなブン太を、私は初めて目の当たりにし、やはり驚く。授業のノートをまるまるコピーさせて欲しいという旨さえ戸惑いや申し訳なさを窺わせる事のないブン太だからこその、驚き。滅亡はしなかったにしろ、地球はもしかしたらどうかしてしまったのかもしれない。やはり、私は眠い。きっと、寝ぼけている。 「昨日例えばの話したろ。地球が滅亡したらって。今起きてみて、なんか思ったんだよ。もし今日が来なくて、もうお前とこういう風に喋れなくなったら、嫌だなって。」 私は寝ぼけている。まだ、夢から抜け切れていない。そう、確信した。けれど、彼の口は止まらない。私の夢の中でのブン太は、現実と相反するほどに真面目だった。現実と夢で感じるのは、凄まじいまでのギャップだけだ。 「つまり、なんか、よく分からねえ。もしかしたら好きかもしれない。」 「は、」 呆気に取られる私を前に、ブン太は案外冷静に自己分析を始めた。もしかしたら、という単語が最初についているにしろ、こうもあっさりと恥ずかしげもなく告白してくる男は他にいるのだろうか。否、私はそんな男聞いた事はない。何だか逆に、調子が狂う。 「付き合う?俺ら。」 「いや、そんな簡単に言われても。そもそもまだ好きと確定した訳じゃないし。落ちつこうよ。私、取りあえず柳に今日の天気電話してみる。私はそれで落ちつけると思うから。」 「お前が落ちつけよ。あと、いい加減柳を天気予報に使うの止めろ。」 柄にもなく暴走する自分に修正をかけられない、それ程にきっと私はパニックなのだろうと思う。時計を見ると、針は七時を指している。この時間に電話して万が一寝ていたら、と考え私は柳にメールを打つ。冷静に考え直して、柳がこんな時間に寝ているなどという事はないと思ったけれど、それを理解したと同時に私の指はメールを送信し終えた。 「落ちつこうかブン太。蜜柑でも食べよう。」 「おお、食わせろ蜜柑。」 実家から大量に送られてきた蜜柑を段ボールから二つ、取りだしてこたつの上に置いた。ブン太は、まるで自分の部屋の様に、慣れた手つきでコタツのスイッチをオンにして、足を放り込んだ。 「おー、甘い。これ美味いな、蜜柑。」 「うん。私もそう思う。」 先ほどの会話が嘘のように、私達は元あるべきいつもの光景に戻っていた。あまりにも部屋に違和感を感じさせない彼を、私は横目で見る。すると、そんな私の視線に気づいたのか、ブン太が首をかしげた。「何だよ。あんまジロジロ見んなって。」そう言って、したり顔で私を見た。いつもであれば出てくる小言が、不思議とこの瞬間だけは、思いつかない。あれだけ自然と口にしていた皮肉が、何も出てこない。代わりに、蜜柑をひと房、口へと放り込んだ。 これが恋であるのか、私には分からない。それは私が恋に不慣れであるからなのかもしれない。もしかすると、本当に恋とは程遠いものなのかもしれない。それすら、私には分からない。けれど、こうして蜜柑を剥きながらコタツで彼と一緒にいるのは、悪い気分ではなかった。妙にしっくりと来るこの感じが、そうであるのか、そうでないのか。でも、今はまだ分からなくていいと思った。ただ、そこにブン太がいて、それが嫌ではないという事実だけで、蜜柑はより甘く感じられた。 「これもう一個くれよ。うまい。」 「うん。」 地球が滅ぶ前に満喫する日常もいいかもしれない。けれど、不確定で未知なものでありながら、私には地球が滅亡する前にしたいと思う事が、新たに出来ていた。地球が滅ぶ前には、恋というものをしてみるのもいい、と。してみたいと、純粋にそう思った。地球が滅亡していたら、到底今私がそう思う事も叶わなかっただろう。考えれば考えるほど、何だかよく分からなくなった。 「あ、一限。」 「馬鹿。今日土曜だろ。」 「そうだった。」 もう少しゆっくりさせろよ、そう言ったブン太は最早自分の部屋にいるように、コタツで大の字を描いた。見慣れないものを見るように、じとじととした視線を浴びせると、お前もやればなんて言われて、忘れたころにやってくるように眠気が到来した。私も、ブン太の隣で控えめに大の字を作った。 「やっぱ俺お前好きだわ。」 「え。どのタイミング。」 よく分からないタイミングでのカミングアウトに、本当にブン太という人間が分からなくなった。一体この瞬間のどこで私を好きだと思ったのだろう。考えようとしたけれど、眠気が再来した私の眼は限界を迎えたように閉じていく。取りあえずこれが、壮大な夢ではありませんようにと祈りながら。
春が近いといい。今はそう思っている。柄にもなく、春を望んだ。 ( 20120305 ) |