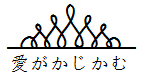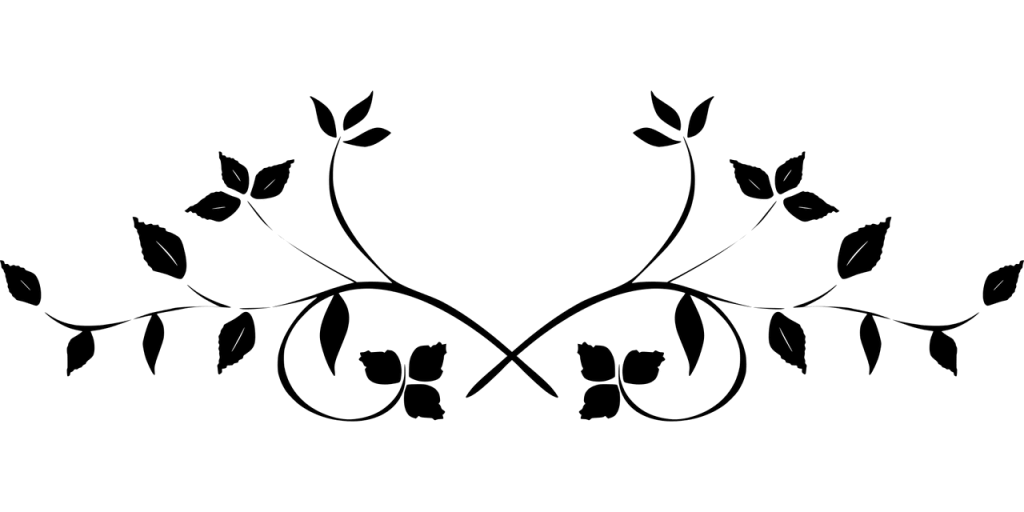 囚われの身ながら、少し前に元の女の姿をする機会があった。 島原という自分には恐れの多い場所で、女性としての格好をしただけでなくどうにも気恥ずかしいような立派な着物や装飾をつけられ芸子の真似事をしたのだ。これには理由があったにせよ、私には恐れの多いことと気が滅入っていたが、大いに皆が喜び楽しんでいたのでそれはそれでいいと思い気分は悪くはなかった。 何より、私が嬉しかったのは彼の言葉だった。 「馬子にも衣装、てか。」 「恐れ多いのでやめてください。」 「、言葉の意味分かってるか。」 「…え。」 言葉の意味を勘違いした自分に、今度こそ体中が熱くなる感覚を覚えた。褒めて貰ったのだと思っていた事が、皮肉だったことに気づかなかった自分が酷く恥ずかしい。女の格好をしたのですら数年ぶりでどこか照れくさいのに、それに増して自分の勘違いにどうしたものかと私は焦っていた。 「おいおい。真に受けんなって。」 中々次につながる言葉を私は見つけることが出来ないでいた。単純に、今のこの現状が恥ずかしくて仕方がない。彼は普段と何一つ変わりないのに、いつだって直視できていた筈の彼の顔を私は見ることが出来ない。まるで自分が女である事を突然、思い出したかのようだった。 「似合ってるって言ってんだよ。」 その言葉は、冷静さを取り戻そうとしていた私を再び困惑へと誘う。どうして彼はこうも直球で人が言えないことをいえるのだろうと思いつつも、どうしようもなくそれが嬉しかったのも事実だった。 「またからかってます?」 「お前も疑り深いんだな。」 「そうさせた原田さんが悪い。」 やり場のない私は、体の火照りを冷まそうと自分にできる最善を探す。彼の前にあった銚子を手にとって、強引に彼の杯へと酒を注いだ。 「まだ飲み終わってねえよ。」 「どうせまだ飲むんですし、早いか遅いかの違いです。」 「俺を酔わせてどうするつもりだ。」 そう言って不適に笑う彼に、私は戸惑いを覚える。彼とこうして酒を酌み交わすのは初めてではない。一緒に島原へ連れて行ってもらった事もあれば、屯所で他愛もない話をしながら呑んだ事も数え知れない。いつだって気さくな彼に、好意を覚えてもそれを女性としての何かと感じ取ったことなどなかった。 「じゃあ私が酔います。」 「何処に客を前に酔っ払う芸子がいるんだよ。」 それもそうか。そう思いつつも、この状況を打破するには酒を飲むのが一番早いに違いない。先ほど彼に振舞った銚子を手にする。まだ少し酒は残っているようだ。迷わず、手酌で自分自身の杯に残りを注いだ。柄にもなく、くいっとその液体を流し込んだ。 彼は呆れたように笑いながらも、そんな私を横目にいつもと変わらぬ酒豪っぷりで杯を早々にあけていた。運ばれてくる銚子をもって、私はただひたすらに彼へ酒を注いだ。 屯所で茶をすする。先日の島原での出来事を、ふいに思い出した。それは今まで自分が生きてきた中でもかなり印象深い出来事だった。芸子でもない私が煌びやかな格好をして、女として振舞う。長い間新撰組で女性としての生活など忘れていた私には信じがたい夢のような思い出だ。 あの酒宴にいた新撰組幹部連中にはその後何度かその話をされることもあったが、彼は違った。 新撰組と生活を共にするようになって数年。私にとって一番話しをする機会が多いのは原田だった。気を使わずに話せる上に、彼は気遣い上手だ。更にはその気遣いを人には悟られないよう自然と体現できる男だ。一緒にいて、一番心を許せる相手だった。 そんな彼があの島原の酒宴以来、私に対して距離を置いているように見えた。私自身積極的に話をする方ではないのだから、たまたまという可能性も考えられたがどうにも違和感があった。目が合っても、少しはにかんだように笑いつつすぐに反らされることが多くなっていた。 「平助って、いいな。」 「何だよ藪から棒に。」 「ううん。ちょっと言ってみたかっただけ。」 事実、彼は何も変わらない。そこから私だけが切り抜かれてしまったようと表現するのが正しいだろうか。いつもと変わらず彼と仲良く話している平助が羨ましいとふと思った。 茶を飲み終わった私はその湯飲みを勝手場へと戻そうと歩いていく。ギシギシと軋む床を歩いていく先に、あの時と同じように酒を飲んでいる彼を視界の先で見つける。 「何やってるんですか。」 「…ん?満月が出てたからな。それを肴に酒でも飲もうと思ってな。」 中庭で彼は腰を下ろしていた。私はそのまま歩みを進めると、いつものように彼の隣に腰掛けた。いつだってしていたその当たり前の行為が少しだけ、気まずさを育んでいた。どこか、いつもと違って居心地が悪い。 隣に腰掛けた私に彼は何も言わない。私も特に何を言う訳でもなく、彼がするようにまん丸に象られている月を見上げた。そうすれば、彼の考えていることが少しくらいは分かるのだろうか。 「何も言わねえのか。」 「月が綺麗ですから。」 「確かにな。月見酒ってのはいいもんだ。」 そう言うと彼は私に銚子を見せた。誰か来るのを待っていたのか、彼の隣に置いてあった杯を差し出されて、私も月を見上げながら注がれた酒に口をつけた。それはいつもと同じようであって、いつもと違う感じがした。 「なあ。」 「なんですか。」 あの島原での酒宴以来の名前を呼ばれる。何を言われるのだろうかと思いつつ、私は冷静を装って杯の酒に再び口をつけた。 「お前って女なんだよなってそう思って。」 この人は何を言っているのだろうか。今の私の現状を考えればそれを忘れてしまうのも頷けるが、いつだって優しくて時には守ってくれる彼は私のことをきちんと女と思ってくれていると思っていたのだから驚きの言葉だった。その言葉の真意が分かりかねる。 「お酒の飲みすぎで性別まで分からなくなりましたか。」 「馬鹿。そうじゃねえよ。」 彼はそう言うと再び酒に口をつけて、黙り込んでしまう。いつだって騒がしい彼が、どうにもあれ以来私に対しての様子が不可思議だった。特にあれから何かがあった訳でもないのに。 「女としてのお前の人生を奪ってるのは、他でもない俺たちなんだよなって思ったんだよ。」 島原での出来事を彼は語り始める。あの場では私を褒め、その場を楽しんでいた彼だったのに何故突然そんな事を思ったのだろうか。 「普通の女みたいに化粧して、綺麗な着物着て、そんな人生もあっただろ。」 「まあ、そんな人生もあったかもしれないですね。」 「お前はどうなんだよ。こんなむさ苦しい男所帯じゃなく、女としての人生を歩みたいか。」 彼にそう尋ねられて、私は即答することが出来ない。彼らには、特に彼にはよくしてもらっている。囚われの身でありながらそれを忘れさせてくれるくらいには私は不思議と満たされた生活を送っている。 だからこそ、女としての生活に戻りたいのかと聞かれたときにすぐに答えが思いが浮かばない。そんな事、ここしばらく考えたことすらなかったからだ。 「分かりませんけど、少なくとも今の生活を嫌と思った事はない、かな。」 「お前も変わり者だな。」 この屯所に居つくようになった当初は、いつ逃げ出すかばかり考えていた。自分から男装をして京まで来たものの、まさかそれが長く続くものとは思っていなかった。どうすれば不自由なこの環境から抜け出せるのかを考え、酷く悲観していた。 いつからだっただろうか。そんな風に思っていたこの場所が、とても自分にとって居心地のいい場所へと変わったのは。自分でも思い出すことが出来ないけれど、ひとつだけわかる事があった。 「は女だ。女には女として幸せになる権利がある。誰にだってな。」 「男にはその権利、ないんですか。」 「今はそんな事言ってられる時代じゃねえからな。」 そんな時代になればいいんだけどな。そう言って、彼は酒を飲み干した。 何故距離を置かれたのか、ずっと考えていた。何か気に障る事をしてしまったのだろうか、何かしらの理由を探していたけれどそれは違った。彼はあまりにも優しい。この混沌としている時代で、たった一人の小娘の事を考え気に病んでいるなんてあまりにもそれは 「もしお前が自由の身となったらどうする。」 「今だって充分自由ですよ、私は。」 「だってここを出れば、一人の女に戻れるだろ。」 もし私が一人の女に戻ったとして、一体私には何が残るのだろうかと思う。京に残るにしろ、江戸に戻るにしろ、私には何も残っていない。そんな状況で女に戻ったところで、どうしていいのか分からない。少し前まであれだけ望んでいたその形が、今はどうでもいい事に感じられた。 ただ、もし一つ女に戻ったとしたら。 「好きな人が出来て、一緒になって、子供ができて、そんなありきたりな生活も悪くないですね。」 ずっと思い描いていた夢。今でこそ忘れかけていたけれどそんな事を夢見た事もあった。それは女として生まれたからには当然そうなるものだと思っていた。恋をして、所帯を持って、家族に囲まれた幸せな生活をしたいと。きっと誰もが思い描くような当たり前の未来を。 「でも、それよりも私は此処にいたい。」 「女として生きるよりも、か。」 「女というよりも人としての意志です。」 あれだけ出たいと思っていた場所が、自分にとって何よりも掛け替えのない場所になっていたのだと改めて気づかされる。突然彼にそんな事を言われると、突き放されたようなどうしようもない虚無感に苛まれる。私自身がここい居たいと願っても、彼らにとってそれは相互の思いではないのだと。特別役に立つ何かを思っている訳でもない私は、求めてもらう理由もないのだから。 「此処にいたら、迷惑になりますか。」 「誰がそんな事言ったんだよ。」 「だって原田さん困ってるから。」 「違えよ。俺が困ってるのは、寧ろ逆の理由だ。」 今日の彼はずっと私の想像と逆のことを言う。まったく持って何を彼が言いたいのか今の私には理解が出来ない 「女としてのお前の人生を応援すれば、お前は此処を出ざるを得ないだろ。」 自分自身と格闘しているような彼のかんばせだった。これ程までに揺らいでいる彼を見たのは初めてのことだった。いつだってどこか大人で、物分りがよくて、割り切っているようなそんな彼が直面から壁にぶつかっているような 「出て行って欲しくない気持ちと、女として生きて欲しいって気持ち、どっちもあるから笑えるだろ。」 そんな事を彼は思い悩んでいたのか。そう思うと、急に力が抜けた。私がここに居てもいいという理由が、こんなにも近くにあるなんて知らなかった。彼がそんな事を思ってくれているなんて思いもしなかった。ただの頼りになる兄貴分としか思っていなかったはずの彼が、どうしようもなく愛しく見える。何かがぎゅっと締め付けられるような感覚だった。 「馬鹿だな、原田さんは。」 「ほんとだな。俺もそう思う。」 「出て行く筈なんてないのに。」 答えなんてここにあるのに、彼は分からないのだろうか。察しのいい彼にも察し得ない事があるのだなと思った。聞くまでもなく私の答えなんて決まっているのに。 「こんな不安そうな顔してる原田さん、置いていける訳ない。」 「言ってくれるな。」 彼は女としての私の幸せを願っていると言った。だとすれば、その願いはもう既に成就されているに違いない。気づかない間で、きっと私はこの男に恋をしていた。気遣いが出来るのにそれを表に出さない、おおざっぱで男くさい彼に。今になって気づくなんて、私も言っておきながら馬鹿なのかもしれない。 「理屈なく好きな人と一緒にいれる世になるといいな。」 杯を置いて、柄にもなく彼の肩にもたれ掛かる。今出来る、最大限の気持ちを表現しながら。 「でかい仕事を任せてくれたもんだ。」 久しぶりに私の頭上に、大きな彼の手が覆いかぶさった。それは女として綺麗な着物で着飾るよりもよっぽど幸せなことだ。でも、もしかすると最大の幸せは彼に対しての色づいた感情に自覚したことかもしれない。女は、こうでなくちゃいけないのだから。 「お前は、ここにいろ。」
|