 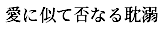 半年に一度行われる柱合会議が、私は限りなく嫌いだった。 お館様に会いたくない、そういう訳ではない。お館様の事は何よりも人としてこの上なく尊敬もしていたし、忠誠を誓っている。理由はそれ以外のところにあった。 出来る事なら顔を合わせたくないその相手とは、元忍びという一見地味そうに聞こえて何がどうしたらこうなるのか疑問に思う程派手に着飾った男だ。私は、彼に会いたくない。それは“嫌い”や“苦手”という感情とは違う、表現しがたい感情だ。 「義勇、お館様来ちゃうよ。早く。」 「ああ。」 彼の事を下の名で呼ぶのは、柱の中でも私だけだ。別にそう呼ぶ必要もないけれど、あえてそう呼んでいた。そう呼ぶ事で、ただの“仲間”であった私たちが今までとは違う関係へと発展しているのだと匂わせる為だった。 案の定、皆がそれとなく察してくれているようで有り難かった。 実は義勇と付き合っているのだと大々的に公表してもよかったけれど、自分自身そんな大胆な事をしたいとも思わなかったし、何よりそんな事をすれば義勇に呆れられるのではないかと思った。自分が付き合っている女の頭の筋が一本違えているともなれば、可哀想なのは私ではなく義勇の方だ。 「ちゃん、え、もしかして…え、いつから?」 「あ、うん。ちょうど前の柱合会議の後くらいかな。」 「ええー、そうだったの!全然知らなかったあ!」 こうして自分ではなく、周りが騒いでくれることは更に私には好都合だった。私が言ったのではなく、周りが言っているのだからそれも仕方ないと丸く収まる。まさに私の思い描いた展開へと、事は順調に進んで行った。 義勇とは前回の柱合会議で久しぶりの再会となった。今まで数ヶ月に一度は同じ任務に就く事もあったけれど、その半年間は一度も顔を合わせる事もなく、本当に随分と久しぶりの顔合わせだった。 彼は感情をあまり表に出さない人で、口数が少なく、その分誤解の多い人間だ。 私はそんな彼が嫌いではなかった。柱合会議の度に、一人遠くの方で佇んでいる彼を見て少しだけ愛おしいとすら感じた。それが恋愛感情としてのものなのかは別として、異性としてもそれは嫌いな部類ではないというだけで充分だった。 動いたのは、私の方からだった。好きと言えば、彼は私を女として見れくれると分かっていたから迷わずに動くことが出来た。感情が乏しいながらも、彼が私の事を好意的に思っている事はなんとなく昔から知っていた。 「私には義勇が丁度いいのかも。一緒にいて、すごく楽だから。」 それは紛れもない私の本心からの言葉だ。彼の隣は、居心地がいいというよりは楽だった。今まで自分が置かれていた環境を思い返すと、それが一番だと思ったのだ。だから彼の隣にこれからも居続けようと、私はそう決めていた。 「、久しぶりだな。」 私が顔を合わせたくない宇髄との関係を保つには、これ以外に最良な案はない。 : : 柱合会議が終わり、私は自分の帰るべき場所へと戻ろうとしたが、義勇がお館様に別件の報告があるのだと奥へと消えていったものだから、私も彼を待つ為庭先で暇を持て余していた。たまに砂利を転がして遊んでもみたけれど、酷く退屈な時間だった。 柱の一人、また一人とその場を後にして行き、面白そうに私と義勇の関係を聞いてきた蜜璃も満足したのか、お腹いっぱいと言いながら帰路へと着いた。私は、一人になった。 「おいおい、師範の俺をあんまり邪険に扱うなって。」 「……まだ居たの。」 「酷い言われようだな。ちょっとは気使えよ。」 「別に邪険に扱った覚えはないけど。」 私があえて遠ざけ、距離を置いているのを知っていて彼は私へと近づいてくる。誰も居なくなった時を見計らって近づいてくるのだから、間違いなく確信犯だろう。本当に迷惑極まりない話だ。 宇髄と顔を合わせるのは、前回の柱合会議以来で実に半年振りだった。 私はこうなる事をずっと不安視していた。自分が柱である以上会議には参加の義務があったし、自ら理由もなく柱から降りるという事もできない。それにはそれなりに大きな理由が必要なのだから、如何に上手く宇髄を交わしながらその会義に参加するのかを考えるしかなかった。 嫌でも、半年に一度は顔を合わせないといけないのだ。私が死ぬか、宇髄が死ぬか、そのどちらかがやってくるまでは。 「いつからだ。」 「…何のはなし。」 「冨岡の事だよ。分かってて地味に話逸らしてんじゃねえ。」 最初のうちは茶化しているような口調も、本気で怒りが篭っている口調へと変わっているのが見て取れた。私は冷静に、自分の心を落ち着かせることに全集中して、平然を装う。彼の波長に惑わされては、いけない。 真っ直ぐに私を見る宇髄の視線が、痛いほどに私を射してくる。今にも何かがぷつんと、糸が切れるように撓んでしまいそうになるのを必死に堪えた。 「お前、そんなに俺を妬かせたい訳。」 「冗談もほどほどにして。」 「冗談言ってる雰囲気に見えるかこれ。もしそうならお前まじで頭イってる。」 私には、彼を受け止める事が出来ない。彼の気持ちが嘘偽りのない、本物だと分かっているからこそ余計と辛く私の精神を抉っていく。宇髄は自分の感情に忠実な人間で、そして嘘を付かない男だ。だからこそ彼のこの言葉や、私にぶつけてくる感情がまがいもなく本物である事を裏付けていた。 彼の強い眼差しに負けそうになる。すぐに、気が緩んで目の前の彼に手を伸ばしそうになる。 けれど、それは許されない。私は嘗てそれを受け入れようとして、そして失敗した。私には耐えうることの出来ない感情に自分が壊れ行くさまが、効果音をつけたように脳内を巡っていた。地獄のようなあの日々は、絶対に繰り返してはならぬのだ。 あの時私が全力で愛した男が、今目の前にいる。 : : 私が宇髄の継子になったのは、今から四年ほど前に時が遡る。継子になるのは、大体が弟子入り方式に準ずる。私も例に漏れず、自ら弟子入りした人間だった。 師範に彼を選んだのは、他にぴんと来る人間が居なかったからという事もあった。胡蝶や蜜璃であれば年齢も近く、性別も同じという事もあって入門するには最適な人材であったのかもしれない。けれど、私は半分興味本位な好奇心を元に宇髄の元へと弟子入りを志願しにいった。 「継子って、お前がか?まじで言ってるかそれ。」 「大まじです。」 宇髄にとっての私の第一印象はあまりいいものではなかったようだった。彼とは何度か任務を一緒にした事があったけれど、数多くいる隊員の中で、特別に私のことなど覚えても居ないだろう。仕方がないと少し落胆はしたものの、それくらいの事は想像の範疇を出ない。こんな所で挫けては、それこそ弟子入りなんて夢のまた夢だと思い気力を振るった。 「いやだってお前、めちゃ弱そうだし。俺の貴重な限られた時間使うとか勿体無いわ。」 数年かかって“甲”まで上げた階級を示しても、然程興味がないのか、宇髄の姿勢は前のめりにはならなかった。そのあと私が継子として認めてもらったのは、何回か屋敷へと通い詰め、そして彼に手合わせをして貰った後の事だった。 継子に経って数ヶ月が経った。口は悪いが、彼の教育能力は酷く長けており私はみるみる力を付け、成長していった。 宇髄には三人の嫁がいた。宇髄自身も元忍びで、彼女達三人も元忍び“くの一”なのだという。忍びの里では、複数の者と婚姻関係を結ぶ事も珍しくなく、奇異の目で見られる事でもないらしい。自分の知らない世界とは、随分と不思議なものだなと思った。 宇髄の元に弟子入りした理由は、大きく二つあった。 一つ目は、彼の派手な性格故、誰よりも目立ち、強く見えたという単純な理由からだった。強いものに教えを請えば、強くなれると思うのは道理に適っている正統な理由だ。 二つ目は、酷く自分勝手で、そして自分の抑えることのできない好奇心に由来するもの。彼は私が憧れを抱く存在だった。それはもちろん強さからくるものもあったけれど、何より私には異性として魅力的に思えたのだ。この時は、彼に嫁がいるという事は知らなかった。 元々あった好奇心は悪い方へと進んでゆき、想像したとおり私は彼のことがあっという間に好きになった。 口は悪いけれどふいに見せる優しさや、懐の大きさがたまらなく好きだった。嫁がいると分かっていながらも、歯止めが利かなくなったように気持ちを膨らませていけば、彼も私に呼応するようにそれに応えてくれた。 「私、柱になりたい。」 「はあ?どの口が言ってんだ。一億光年早いわ。」 宇髄に弟子入りした時は、柱になりたいとは思っていた訳ではなかった。強くなりたいとは思っていたが、その行き着く先が柱という形ではなかった。 けれど、彼を好きになっていく中で、私は彼の一番になりたいと願ってしまった。叶う筈のない、そんな大それた考えを不幸なことに持ち合わせてしまったのだ。彼と肩を並べ私が柱になれば、私が特別で唯一の存在になれると考えた。その時瞬時として、悲劇が幕を開けた。 どうしようもなく宇髄が好きだった。その好きという感情を元に、私は厳しい修行に耐え、強くなっていく事で自分に自信を付けていった。彼は私だけのものであって、私は彼のものだけで在りたかった。 彼の嫁達は皆気立てがよく、面倒見のいい女だった。彼が嫁を大切にするのも頷けた。 次第に彼女達と打ち解けていく事で、酷く気持ちが悪いと感じるようになった。彼女達は人が良すぎる。何故私のような女に対しても手厚く持て成してくれるのだろうか、嫉妬という感情はないのだろうかと不思議に思う。忍びの里ではいくら複数の女と所帯を持つ事が珍しい訳ではないと頭では理解しながらも、心では理解出来ずにいた。私も忍びとして生まれていれば、こんな感情に苛まれることなくにこにことしていられたのだろうか。 劣等感なんてここでは必要のない事だったのかもしれない。優劣だって必要がない。皆が一番に愛されていて、平等なのだ。その環境に順応できないのは私だけだ。その事実がどうようもなく苦しく、私を苦しめ、そして地獄へと突き落としていく。 「認めてやるよ。お前、強くなったな。」 「師範に認められるなんて、私が柱になるのも近い将来かな。」 「それはどうかな。」 強くなった私への褒美と言わんばかりに、彼は大きな懐で私を抱きとめてくれる。地獄にいる私には、これがあったから耐えて来ることができたのだ。彼に愛されているという揺るぎのない事実に、唯一救われていた。そしてそれが私にとっては全てだった。 彼に認められた後、欠員が出たこともあり私は念願だった柱の職に就いた。これでようやく彼と肩を並べて生きていくことが出来る。私の目標だった事の一つが叶った瞬間だった。 「。」 自分の名前に振り返れば、優しい宇髄の顔が出迎えてくれる。頭を撫でられて、大きな腕で包まれる。どうしようもなく心地がよくて、同時にいつも心臓が張り裂けそうな程に鼓動を打った。生涯これ以上の感情を得るのは宇髄以外にいないと思うほどに、私は彼にのめり込んでいた。失うことなど、考えてもいなかった。 柱になった私は、今までよりももっと自分の感情に貪欲になった。 柱になれば自分が特別で、唯一のものになれると考えていたからだ。けれど、宇髄は今までと変わらなかった。変わらず私のことを愛してくれたけれど、私だけが唯一になる事はなかった。 今まではまだ我慢出来ていた。自分が柱になれば変わってくれるかもしれないと、淡い期待を持っていたからだ。柱になった今、その手段を叶えてしまった私は急に我慢の耐性を失ってしまった。何を目的に死に物狂いで努力して、柱にまでなったのか分からなくなった。 そもそも鬼殺隊は恋愛をする場所でもないし、私が入隊したのは至極正当な理由からの筈だったのに今はそれを思い出す事が出来ない。自分の欲望のままに感情を留める事の出来ない私は、知性も理性も低い下等な鬼のように思えた。 「どうした。ご機嫌斜めか。」 「…そんな事ない。」 「ならあんまり俺を困らせるんじゃねえよ。」 いつだって私に注がれる愛情は最大限であって、そして他の三人と平等なものだった。気が狂いそうな程に胸が苦しい。私だけが可笑しいのだろうかと随分思い悩んだ。 こんなに好きなのに、どうして幸せな気持ちに浸る事が出来ないのだろうか。私も忍びに生まれていればそんな煩わしい感情からも解放されて幸せになれたかもしれないのにと思う反面、きっと私が忍びの生まれであったとしても結果は同じだったとも思った。どうしても私は彼の唯一のものにもなりたかったし、彼を私だけのものにしたかった。 「好き。一番、誰よりも一番好き。」 「べた惚れかい。」 彼にこんなにも愛されているにも関わらず満たされない何かが、いつだって私を貶めていった。彼に抱かれるその腕も、真っ直ぐな瞳も、いい声も、全部が全部私のものであって、そして他の誰かと共有しているものなのかと思うと自分の感情を平常に保つ事は不可能だった。 何もかもを忘れ、彼が好きである事だけを考え抱かれた夜。私は宇髄の元を去った。 その真っ直ぐで、真剣で、平等に注がれる愛に私は打ち勝つことが出来なかったのだ。今から一年程前の出来事だった。 : : 目の前にいる宇髄に、弱い私は手を伸ばしそうになる。何度も何度もその感情を押し殺し、自分を律した。彼の前を逃げ出したその時から、もう彼には感情を見せないと決めていた。隙を見せれば、私はまた彼の言葉に甘く溶けるただの女に戻ってしまう。柱である私はその力だけでなく、精神も強く在らねばならないのだからと言い聞かせる。 「冨岡なんてやめてもどって来いよ。お前冨岡の事なんて大して好きでもないだろ。」 宇髄は私の心を見透かしたように全てを言い当てる。その通りだからこそ、瞬時に言葉が出てこない。義勇の事は嫌いではない。人として、仲間として、掛け替えのない存在である事に違はない。私はその感情を私だけの都合で無理やり捻じ曲げて、男として好きであるのだと思い込んでいるのだ。我ながらなんとも酷い話だと思う。 「…好きだよ。いい人だし、義勇。」 「だとしてもが俺を好きな気持ちに比べたら足元にも及ばないんだろ。」 「そんな事ない。もう気変わりしたんだよ、私義勇が好き。」 真っ直ぐに私へと伸びてくる宇髄の視線があまりにも辛くて、私は視線を逸らす。逸らすと「何で逸らすんだ。」と低い声で問いかけられる。彼の問いに答えることの出来ない私は黙り込んで、ただ解放されるその時を待っていた。 一向に何も言おうとしない私に痺れを切らしたかのように、宇髄の大きな手のひらに顔を挟まれた。強制的に目と目が合わさって、久しぶりに彼の顔をきちんと見たような気がした。 「やめて。」 「やめねえよ。」 「怒るよ。」 「じゃあ何でお前泣いてんだ。」 言われて初めて気が付いた。頬を掠めた暖かい何かは、彼が言うものだったのだろうと理解に至った。涙なんて意図して出すものではないのだから仕方がないと言えばそれまでなのかもしれないけれど、まるで自分の言っている事が嘘である事を証明しているようで後ろめたい気持ちに陥った。 「泣くくらいなら、俺を選べ。」 言われて、心が揺らぐ。私は柱になっても心は最弱のままだったあの頃と何も変わっていないのだと思わざるを得ない。宇髄が好きだという感情を前に、覚悟をしていたもの全てが崩れ去った。 溜まらず手を伸ばせば、彼もあの大きな懐で私を受け入れてくれる。流れ出て止まる事を知らない涙を、拭ってくれる。私が知っている彼と、何も変わらないそのままの姿だ。 「…ずるい。」 「ずるくない。」 こんなに好きで、こんなにも彼に思われているのに、それに手を伸ばした所で私に待ち受けているのは地獄のみだ。幸せな結末は彼を好きになる事では絶対におき得ない事象なのだ。どれだけ望み、どれだけ好きという気持ちがあっても天国は私には用意されていない。 触れるか触れないかの微かな唇の重なりでさえ、懐かしくて余計と涙が止まらない。私は彼と幸せになりたいだけなのに、何故それを叶える事が出来ないのだろうか。相思相愛という言葉の意味が、分からなくなる。 後ろに気配を感じて、ふいに身じろぎする。彼にかかっていた私の手は離れ、そして彼も音を立てることなくその場から姿を消していた。 「さん、まだいらっしゃったんですね。」 「義勇を待ってるの。忍さんこそ戻ってきて何か用事?」 「そんな所です。お館様のお耳にも入れて頂きたい情報を思い出しまして。」 すぐに涙を拭った。彼女は感が鋭く、抜け目のない女だ。口には出さないものの、きっと私が宇髄と継子と師範の関係を越えていると気づいているのは彼女だけだっただろうと思う。だからこそ、迂闊に次に続く言葉を放り出すことは出来なかった。 どうかされましたか?と私に近づいてくる胡蝶に、私はそんなにも酷い顔をしているのだろかと思う。涙は拭った筈だった。けれど、それを除いても私は人が心配するような表情をしているのだろうか。 「そういえばさん。宇髄さんと何かありましたか、喧嘩でもされました?」 「……何突然、藪から棒に。」 「いえ。ただ、以前は継子と師範としてもの凄く仲が良かったので気になったんです。」 余計なお世話でしたかねと笑う胡蝶に、本当に余計なお世話だと口からでかかって必死に飲み込んだ。彼女は全てを見透かしている。私の気持ちを宇髄が全て見透かしたように、的確に。 私だって、何がどうしてこうなったのか分からない。寧ろその答えを知っているのであれば教えてほしかった。私は自分の感情と体が泣分かれてしまっている。自分の感情を優先すれば心は死に、体を優先すれば私の感情は死ぬ。どちらをとっても希望の光など見えないのだ。 「待たせたな、。」 義勇が戻ってきて、入れ替わるように胡蝶がお館様の元へと向かっていく。助かったと思う反面、義勇を視界に映し出す事で今までやんわりとしか感じていなかった罪の意識で心が張り裂けそうになった。 「顔色が悪い。気分でも悪いのか。」 「ごめんね。大丈夫。」 義勇の隣を歩いて、帰路に着く。私は義勇の隣をこれからも歩いていく。そう決めたのだ。半年前のあの日、自分の下らない理由で義勇を利用した私には拒否権など持ち合わせていないのだ。私は義勇を選んだ。それが今の全てだ。 隣を歩いているのは義勇のはずなのに、脳裏には別の男がずっと居座り続ける。義勇と一緒にいるようになってからも一度たりとも切り捨てる事の出来ないその残像が私をいつまでも苦しめ、そして嫉妬に狂わせるのだ。 「今日鮭大根にしようか。」 いかにも義勇を愛しているような言葉を紡ぐ私は本当のところ上の空で、いつだって宇髄の事を想っていた。 彼の呪縛からは逃げる事など出来ないのだ。一生。何故なら私達は相思相愛で、彼が私を好きなように私も彼が好きなのだから。ただそこには一生這い上がってくる事の出来ない深い、深い、地獄が待ち受けているというそれだけのはなしだ。 愛に似て否なる耽溺 |