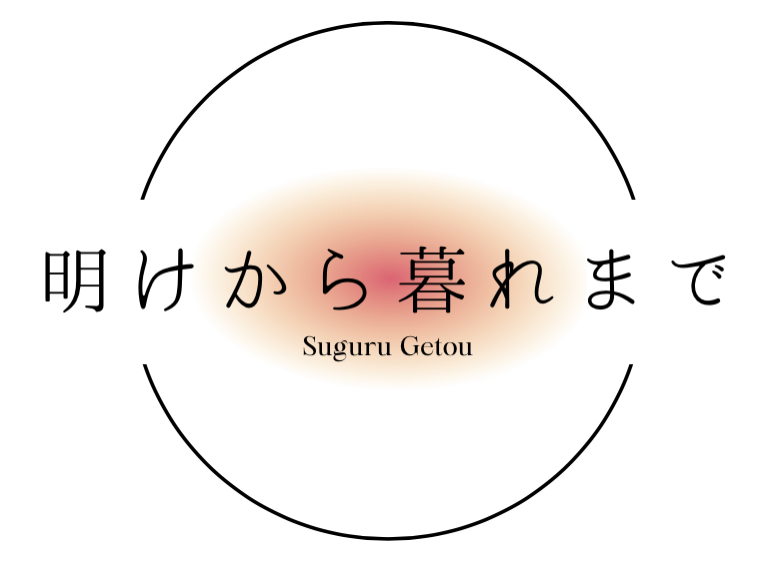 渋谷の街は、いつだって人が多い。手でも繋いでいないと逸れてしまいそうなくらいにごった返している人の波を避けて、進行方向へと進んでいく。こういう時、タッパがある人間と行動するのは都合がいいものだなと思った。 「どう、これで全部揃ったか?」 「うーん、まだみたい所あるけどもうギブだわ。」 「…しかし、凄い人だな。」 ここ半年、任務に追われて全く若人としての青春を謳歌できていないなと不意に思い立って、渋谷に行こうと決めた。コスメだったり、洋服だったり、細々した小物類だったりを無駄に買い占めて、その買い物に傑を付き合わせた。洋服なんて何着買ったところで、基本制服で過ごすのだからあまり意味はない。しかし何事もリフレッシュが必要だ。周りの同じ歳の若い学生が当たり前にしている事がやっぱり羨ましくて、わざわざ渋谷までやってきた。 「これ傑じゃなかったら逸れてたよ、多分。」 「ん?なんで私なら逸れないんだ。」 「タッパあるじゃん。普通に見失ってもすぐそのお団子見つけられる。」 「そんな所で役に立つとは思わなかったな。」 高専で昼ごはんを食べてから渋谷に出て、私が見たい店にいくつか付き合ってもらっていたらもう既に夕方になっていた。何枚か服を買えば欲は満たされると思ったけれど、案外私は欲深いらしくまだまだ周りたいと思ったがこの人混みはその欲すら断念させる。新宿も人混みがすごいけれど、進行方向に向かって左側通行の人が多く歩きやすい。渋谷は、そこらじゅうに人がいて、右も左も関係なく人が屯していて酷く歩きづらかった。 「そういえば、傑は行きたいところあった?流石に付き合うよ。」 私自身も買い物袋をいくつか持っているけれど、それ以上に傑の方が荷物番をやってくれている。そもそも、今日一人ではなく傑を連れてきたのはその依頼も大きかった。あとは、方向音痴で渋谷の地理に自信のない自分に理由をつけて、彼を誘った。明日渋谷に一緒に行こう、そんな一言で。 「特に見たい所はないけど、少し小腹が空いたかな。」 「じゃあ折角だしお洒落な所でご飯食べていこうよ。」 「お、いいね。」 「荷物持ちと、付き合ってくれたお礼に奢るよ。」 そういえば、傑は荷物を持ち直してにっこりと私に笑顔を見せてくれた。私は、傑のこういう面倒見がよく、付き合いがいいところが好きだ。悟と比較すると本当に面倒見がよく、悟であれば途中で面倒と離脱していくような私の話でも傑は最後までしっかりと聞いて頷いて、きちんと欲しい言葉をくれる。だからと言って優しすぎるのかと言えばそうでもなくて、角が立たない程度には自分の意見を言える傑が同級生なのだろうかと時折驚く事がある。 「ところで何で渋谷だったんだ?人混み嫌なら他にもあっただろ。」 「高専だけど私高校生だよ?渋谷で買い物とか憧れるじゃん。」 「って見かけによらず結構ミーハーだよね。」 「……見かけによらずって何?芋くさいとか言ったらぶっ飛ばすよ。」 自分の事ながら、私は可愛げがないなと思う。もう少し可愛らしくすればいいし、感謝しているのであればもっと素直にその感情を表現すればいいのに、私はいつも途中でそれが恥ずかしくなって、やり切る事ができない。恐らくは、悟がそういう場面でいつだって揶揄ってくるものだから、その予防線としてこうなってしまったのだろうと思う。 「は構えすぎ。そんな事思ってないよ。」 「…そう言われると、こっちとしても返答に困る。」 「そういう所飾らないが好きだよ。」 傑は、距離感の詰めかたが絶妙に上手い。こうして好きと言っても、それは恋愛ではなく人としてというようにも感じられるし、言われて嫌な人間などいないだろう。悟ではなく、傑を渋谷に誘ったのはいくつか理由があったけれど、この男はそれを分かっているのだろうか。 「実は良さげなお店いくつか目星つけてるんだよね。傑、何食べたい?」 「目星と言ってもの事だし選択肢ないだろ。」 「……前から思ってたんだけどさ、傑ってエスパーだったりする?」 「というよりは思ってる事全部顔に出るからね。」 傑のいう通り、私はあらかじめ行きたいを店を決めていた。渋谷から少し歩いてある、表参道のお洒落な店だ。その店の何が食べたいのかと言われたら私は困ってしまう。なぜならばただのミーハー心で、この店に行きたいと思ったきっかけもオープンテラスでお洒落だからという人には言いたくないような理由だ。お洒落な店で食べるものは何でも美味しいと相場は決まっている、それが私の持論だ。 「楽しみだね。何系の料理?」 「イタリアン。パスタがすごく美味しいんだって。」 「それは、楽しみだ。」 表参道へと続く道を歩きながら、いくつか小道を通り抜けていくとひっそりとした立地にお洒落な佇まいのオープンテラスがあった。事前に調べていた通りとても素敵だと心が躍る前に、店の先に夥しい人の行列があってすっかりそんな気持ちは吹き飛んだ。 「すごいね、行列。」 「二時間とか待ちそうだね。」 「が行きたいんだったら私は待てるよ。」 「お腹、空いてるのに?」 「空腹を我慢出来ない程子供じゃないさ。」 自分の計画性の無さにうんざりして、流石にこんな荷物を持って二時間も傑をこの行列に付き合わせるのは忍びなくて断念した。この行列を前にしても、私が並んででも食べたいのであれば待てるとそう言ってくれる傑は大人だ。こんな状況でも、相手のことを考えて行動ができるのは人として尊敬に値するし、一方で自分の未熟さを痛感させられてなんだか少し恥ずかしかった。 私たちは渋谷の駅の方へと来た道を戻って、結局どこでも食べれる馴染みのある某ハンバーガーショップに入って、渋谷に来たのにいつもと同じメニューを頼んでトレイを持って階段を上がり、空いている席に腰をかける。妙な、安心感があった。今日は少し背伸びをしすぎていたのかもしれない。 「悔しいけどいつものこのチープな味、落ち着くわ。」 「それは私も同感だな。」 傑と同じハンバーガーを口に運んで、その味はどこで食べても変わらないものだなと噛み締める。結局お洒落な店でなくても、美味しいものは美味しい。 「ナゲット半分こしよ、ソースマスタードで大丈夫?」 「うん、平気。ありがとう。」 もう既に、あの人気のイタリアンで食事ができなかった事は記憶から薄れていた。結局私はあの店に行きたかったのではなく、傑とお洒落な店にいくというシチュエーションが欲しかっただけだ。それを実行するための、それは口実でしかない。不自然がないよう、取って付けたような理由を付けただけ。 今日一日、私の買い物に付き合って貴重な休日を過ごした傑は今どう思っているのだろうか。面倒見がいい分人に尽くしがちだけど、それは万人に適応されるものなのだろうか。そんな事をぐるぐる考えていると、しばらくナゲットを持ったままぼうっとしてしまった。 「ナゲット、食べないの?」 「え、あ、うん。ちょっとぼうっとしてた。」 「沢山歩いたし、疲れたんだろうね。」 「傑は、本当に買い物しなくていいの?」 彼にだって渋谷まで来たら見たいものくらいあるだろう。それが洋服とかじゃなかったとしても、アクセサリーとか、欲しかったCDとか、渋谷に来て買い物をしないなんて選択肢が果たしてあるのだろうか。傑には、欲というものは存在しないのかと不思議に思う。 「それで言うと今日は買い物しに来るつもりじゃなかったから。」 「え、そうなの?」 「“明日一緒に渋谷行こう“って言われたら、買い物とは思わない。」 「そうかな。渋谷って主に買い物する場所じゃん。」 そこまで言われて、鈍い私でもようやく察知した。自分が昨日の夜、唐突に言った言葉は多分手段を伝えただけで、用件を全く伝えられていない。傑も、「あ、うん、いいけど。」と了承してくれた上で、何をしに行くのかと聞いてこなかったかので私も買い物に行きたいからという理由を伝える事なくそのまま渋谷に来てしまった。 「デートかなって、普通期待するよ。」 急に自分でも昨日の自分の言葉に恥ずかしくなって、それに追い討ちをかけるように傑の言葉がそれを後押しする。ちらっと隣の傑を見上げると、困っているどころか愉快そうにこちらを見ていて、それはどこか悪戯心が働いている時の悟と同じように見えた。 「それはご期待に添えず、すみませんね。」 「そんな事はないさ、これも立派にデートだろう。」 「これが、デートねえ…。」 買い物に行きたい、それは私のしっかりとした目的でもあって、傑と一緒に出掛けるための口実と手段であったと言えば、傑はどう思うのだろうか。もし自分が今の私たちの姿を第三者目線で見れば、このまま付き合ってしまえばいいのにと思うだろう。けれど、自分事になると人は急に臆病になるものだ。確信が掴めない限り、その一言は口から出てこない。 「今日のお礼に次は私のお願いも聞いてもらわないと。」 「バーガーとナゲットご馳走したじゃん。」 「それは割に合わない、全然足りないな。」 “好き“というその簡単な言葉を言ってしまった方が心が楽になると分かっているのに、やっぱりその言葉は出てこない。傑が、それを言わせようとしているからなのかもしれない。私の気持ちなんてとっくに気づいている筈の傑は、こういう時ばかりは酷く意地が悪い。思いやりがあって優しい傑が好きな一方で、こんなずる賢い傑は嫌いだ。いつまで経っても、私の欲しい言葉をくれず、私を焦らすからだ。 「……検討しとく。」 ナゲットを勢いよく口へと放り込んで、出そうになった言葉を塞いだ。目の前にあったジュースを手にとって、ずずずと音を立てて吸い上げてみたけれど、氷だけがカラカラとぶつかり合って喉を潤す事はなかった。 私の頬についたマスタードを拭い取った傑の親指が、ぺろりと彼の口へと当てがわれた。私の好きになった男は優しいだけでなく、とんだ策士だったのかもしれない。夏油傑は、私をいつだって焦らすのだ。
明けから暮れまで |