 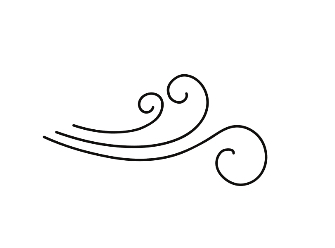 髪を切ることに理由なんて必要ない。 強いて言えば伸びるからだ。生きてる限り生え続けてくるから適度に切りに行かないと管理しきれない。髪を切ったから失恋した?ここ最近その描写は少女漫画でも見てない気がする。 そんな事を言ってくるのは会社の古いおじ様くらいなもので、決まってデリカシーに欠ける。けれどおじ様という一つのカテゴリーに括り付けてはいけない。デリカシーのあるおじ様もちゃんといるからだ。そういうおじ様方が会社のお誕生日席に座っているので世の中ちゃんと上手いこと出来ている。 「おかえり……って、え?」 「きっちゃった!」 「いや、切っちゃったってそんな簡単に?」 「なんというか…勢い?」 「衝動的すぎるっしょ。」 リョータの瞼が大きく開いて、くりっとした黒目がのぞいている。 驚くのも無理はないだろう。会社に行ってくるといつものように家を出て、帰ってきたら彼女の長かった髪がバッサリ短くなっているのだから。長さにして二十センチくらいは切っただろうか。とても軽い。 「あれ……変だった?」 きっと喜んでくれるだろうと思った。どんなメイクをしても、どんな服を着ても、何をしてもちゃんと最後に褒めてくれるリョータだから。いつだって私を彼女として最大限のもてなしをしてくれる。 あまり口達者ではないから、なんだかちょっとぎこちないけど。でも、だからこそ本当にそう思ってくれているのが分かってとても幸せな気持ちになれる。 「…そんな事ないけど。」 「そう?」 「てか普通に可愛いし。」 「へへ、やった。」 発せられる言葉のテンションはそんなに高くないし、どちらかと言えば低いのかもしれない。その代わりにリョータはちゃんと言葉以外で表現してくれる。彼の大きくてごつごつとした手が大好きで、その手で優しくゆさゆさと髪を撫でられるのがたまらなく心地いい。 「でもなんで急に切ったんだよ?」 「街歩いてたらカットモデルやらないかって。」 「なに、ナンパ?」 「話聞いてた?全然ナンパじゃないでしょ。」 一度ムッと歪んだその顔はとても幼くて、どうしようもない事を言っているのになんだか可愛らしくて。髪をセットしていないリョータの本来の姿がそれをより引き立たせているのかもしれない。 「どうせ近々切ろうと思ってたしタダならいいじゃん?」 特別伸ばしていた訳じゃなかったし、あまり躊躇はなかった。ちょうどここ最近暑くて長い髪が鬱陶しく感じていたところだ。タダほど高いものはないという言葉があるけど、やっぱりタダほど安いものなんてない。物理的に。 「それにリョータもきっと楽でしょ?」 「俺?」 「私の半乾きの髪ドライヤーしてくれるでしょ。」 我ながらズボラな性格だとそう思う。思っているだけで改善しようとしない怠惰な性格も知ってる。つまりどうしようもない。そんなどうしようもない私のそれを埋めるように、私の日常にはリョータがいる。 彼氏という表現はとても正しくて、私の生活の一部という表現はもっと正しい。 リョータと同棲するまで私はどうやって一人で生活をしていたのか、今となっては思い出すことができない。リョータありきな生活になってしまっているのだと今更ながらそう思った。 リョータがいると、つい自分にも甘くなってしまう。甘くなっても生きていけるくらいにそれをリョータが満たしてくれるからだ。とても幸せで、とても怠惰な生活。それが、私の日常だ。 「流石にこの長さならすぐに乾くだろうから。」 ドライヤーを全くしないほど甘ったれてる訳じゃない。なんとなく乾いたかな?と思ったタイミングで止めているだけ。ただでさえお風呂上がりで体が火照っているのに、この時期のドライヤーは結構しんどい。 「……ふうん?」 「なに、不服なの?」 「別に。」 「しこりあるな〜。」 ちゃんと髪乾かさないと風邪ひくよ! いつも私の耳に入ってくるリョータの言葉は、今日も一日が終わったんだと知らせてくれる。タオルを首にかけてぐびぐびと牛乳を飲む私の手を引いて、リョータは私をローテーブルの前に座らせる。 窓側にある電源タップにコードを差し込んで、リョータは一段上がってソファに座って少し上から私の髪を乾かしていく。そんな私の日常で、リョータにとっても日常の光景。 日常に組み込まれた行動のことを、ルーティンと呼ぶらしい。 「リョータ?」 「カレー作ってあるから食べるよ。」 「あ、うん。はあい。」 ちょっと大きめにカットした具材がとってもゴロゴロしているカレーだった。じゃがいもに芯を感じられたのはきっと新鮮な証拠だろう。でも胃に入れば内容物は一緒だし、カレーの味は美味しい。市販のルウは間違いがない。 「リョータお風呂もう入ったの?」 「風呂掃除するついでに入ったからもう沸いてる。」 「じゃあ入ろっと。」 バッサリと切り落とした髪がどれくらい軽くなっているか少し楽しみだ。私の怠惰によってリョータに一つ余計な工程をさせてしまっていたけれど、短くなった髪はきっとドライヤーの時間も圧倒的に短くなるだろう。 それは思った通りで、髪を乾かす時間だけでなく髪を洗う手間も随分と削減されている。いつもは二回押さないと足りないシャンプーも、ワンプッシュで十分に行き届く。環境にも財布にもエコだ。 湯船でゆっくり全身を伸ばしながら少し火照りを感じたあたりで湯船をでる。 今日のメインディッシュ、ドライヤーとの格闘だ。 電源を差し込んで乾かしていくと、軽やかに髪が指を抜けていく。乾いていく体感速度がいつもの二倍以上は早い気がする。鏡と睨めっこをしながら前髪、サイド、バックと角度を変えながら一周すればすっかり髪は乾き切っていた。 髪を短くするとメリットが多いらしい。 「リョータみて!」 「ん?」 「髪の毛。」 「うん、乾いてるね?」 「そう、乾いてるの。」 「そりゃその長さならね?」 だからもう半乾きの髪を乾かし直すというルーティンはなくて、リョータの作業を一つ減らした事になる。それなのにリョータの表情はあまり芳しくなくて、どちらかと言えばなんだか不服そうだ。実際、さっきからずっとこの感じだ。 私は牛乳をコップに入れてリョータが座るソファーの左側に座る。大人一人分を乗せたソファーは柔らかく沈んで、そして私を受け入れた。仕事も終わってようやく解放された気持ちになる。お風呂上がりのビール……は飲めないので、もっぱら牛乳だけど。 「ねえ、チャンネル変えてもいい?」 「……いいけど。」 「なんか見たいのあった?」 「別に。」 その返事はリョータの機嫌があまりよくない事を表している。機嫌がよくない時のリョータの返事は決まって「別に」だ。いつだか同じような事を言っていた俳優さんがいたような気がする。この現象にはちゃんとした名前があるんだろうか。 「ねえリョータくん。」 「なに。」 「なんで機嫌悪いのか教えてよ?」 「別に悪くないし。」 いやいや、その言い方明らかに悪いでしょ。少なくとも絶対に良くはないでしょ。全然顔笑ってないし、なんならめちゃくちゃむすっとしてますけど。そんな顔で私を見るって、それは私が原因って事ですか?まるで心覚にないのですが。 「そう?」 「そう!」 めちゃくちゃ食い気味じゃないですか。こうなるともう私にできる事なんて何もないので、そっとリョータの機嫌が治るまでのらりくらり牛乳を飲むくらいしかない。本当にのらりくらり飲んでいたもんだから、随分と温くなってしまった。 私がソファーの背もたれに体を預けると、そっとリョータの視線が私の方向を向く。 明らかに何か言いたげなのに、何も話してこない。一体なんのつもりなんだろう。気になる。けど私が聞いたらさっきと同じ会話が繰り返されるだけのような気がして、一度だけチラッと視線を合わせた。 何も聞いてこない私に今度は痺れを切らせたのか、リョータの重たい口が開いた。 「……ねえ。」 「ん?なあに。」 「いつものしないの?」 「……いつもの?」 いつものとは一体なんなのか。ひとまず家に帰ってきてからのルーティンを思い出す。 ご飯を作って(時々リョータが野菜大きめな料理を作ってくれる)、お皿を洗って、お風呂の掃除をしてから栓をして給湯ボタンを押し込む。 お風呂が沸くまではリョータと今日あったそれぞれの出来事を喋りながらテレビを見て、聞き馴染みのあるあの音楽が流れたらお風呂に入る。 お風呂から上がると髪を乾かしてリビングに戻る。肩からタオルをかけて牛乳を飲んでいると、リョータのお決まりの声がかかって、そして私は床にリョータはソファーに座って乾き切っていない髪を乾かしてもらって………ようやくリョータの訴えかけるようなその眼差しが何を指しているのかが分かった。多分。 「えっと、ドライヤーの後のあれの事?」 「……だからするの?しないの?」 そんな子どもみたいな駄々捏ねた顔をしないで欲しい。改まって考えると、私の方まで恥ずかしくなるから。リョータの手が私のシャツをキュッと握っていて、最早拒否権なんてないのでは?そう思いながら、けれど満更でもなくて。 「あの、します………」 「渋々?」 「いえ、あの、させて下さい………」 「うん。」 昨日までのルーティンを思い出す。私はリョータに髪を乾かしてもらうと、引っ張られるようにしてソファーに座らされる。少し広いエル字になっているところに腰掛けると、後ろからぎゅうっと私を包み込んでくれる。 髪を乾かしてもらうというルーティンがなくなった事で、そんな当たり前にあったリョータとのルーティンがひとつ無くなったのだと今になって気がついた。私自身なんだか得体の知れない物足りなさを感じていたのは、きっとこれだったんだろう。 「機嫌悪かったのこれ?」 「………ちょっと黙ってて。」 「え〜……」 「気づかなかった罰。」 とても強気な男らしい一面がありながら、リョータは結構奥手だったりする。私の方から甘えるタイプじゃないのもあってか、時々こうしてとても不器用な愛情表現をしてくる。そんな確認なんてしなくても、ルーティンじゃなくても自分の意志でそうしてくれていいのに。 「リョータの不器用……」 一度リョータの体を剥がして、そしてその腕の中に飛び込んだ。 私の愛情も、大概不器用らしい。
アナザールーティン |