 そう言わざるを得ない。生まれてはじめての感覚に、気が遠くなっていく。それもその筈だ、この感覚は一度きりしか体験することはない。それは鬼だけでなく人間も、生命体すべてに当てはまる紛れもない事実だ。 この色男になら首を切られてもいいか、なんてただの冗談でしかない台詞が事実になってしまった。嘘から出た誠だ。自分の生き死にがかかっているのだから笑えない。 私は、幼い頃に鬼になった。まだ十にもならない時だ。自らの意思ではなかった。 鬼の中には自ら望んで鬼化した者と、そうではない者に二分化される。私は後者の方だ。鬼になったのはただの悲劇でしかなかった。何故人間の敵である忌まわしき鬼にならねばならないのかと随分と思い悩んだが、それでも死ぬのは怖かった。逆らっても死、鬼である事をやめようとしても死、生きていくという道筋は鬼として生きていくという一本道しか残されていなかった。 首を跳ねられた男が色男だったからだろうか。自分は恋をした事がないとふいに思う。人として好きという感情はもちろん感じた事はあっただろうが、異性として好きという感情を私は知り得なかった。人であったのはまだ十になる前の少女の時なのだから、それも当然の事だ。 無惨によって鬼は群れる事ができない様になっている。もちろん鬼の世界にも男女というものは存在するがただの性でしかなく、恋愛という感情は存在しない。いかに人を食らって強くなるか、その一点のみの欲で生きているのだ。私もその例に漏れない。 最後に思い残した事がまさか、女として恋をしてみたかったという、如何にも人間らしい事なのだから自分自身でも笑えてくる。全てはこの男がそう掻き立てた。私は悪くない。 「あの世でしっかり罪償ってこい。」 「…鬼になりたくてなった訳じゃないのに惨い。」 「過程は聞いてねえんだよ。」 それもそうか、そう納得した。私が鬼で、目の前にいる男は鬼狩りだ。私が鬼として生きる為に人を喰うのが使命のように、この男にとっても私を殺すのが使命なのだ。過程などどうでもいいに違いがない。情けは無用なのだ。 私に待ち受けているのは半永久に続く地獄だろう。死ぬのが怖いのは、生命体として終わる事よりもそこへ行く事の方が強かった。死んだ者は生きかえらないし、死んだ者は口をきかない。だから誰も死後の世界を知らない。視覚で捕らえられる事が全てだからこそ、予想にも出来ないその国は恐ろしかった。死ぬのは、怖かった。 いつか地獄での試練を終えて生まれ変わる日が来るのであれば、次は真っ当な人間の女として恋がしたい。 「じゃあな。」 私が人間のような言葉を最後に吐き捨てたからだろうか。情けをかけてくれたのかもしれない。脆く散っていく私の顔に、豆で硬くなった大きな手が触れた。 それは、暖かく、優しかった。 上弦の鬼だった私の長すぎる命は、ここで幕を閉じた。 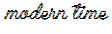 仕事が終わらない。 時刻は夜の九時半。最近は毎日こんな感じだった。所謂大手企業と呼ばれる所に就職できたのだから、この残業も然るべきものと思わないといけないのだろうか。金銭を稼ぐという事は本当に肉体的にも精神的にも疲れるものだと思う。 周りに人もいなくなって来たのをタイミングに、私もノートパソコンの画面をパタンと閉じて鞄の中に放り込んだ。今日は金曜日だ。明日家で補えばいい。 電車に乗って、最寄の駅を目指す。会社に程いい距離と思って奮発して借りた家は、思いがけず去年の人事異動で会社から二本電車を乗り継がないと付かない場所になってしまった。帰りが遅い分だけ家が遠いのは苦痛だ。 酒気を帯びた金曜日の電車に揺られてようやくたどり着いた最寄の駅で、コンビニに立ち寄って私も酒を買う。社会人の金曜日の特権だ、誰にも文句を言われる筋合いはないとばかりに堂々とレジに突き出した。 高層階のエレベーターに乗り込んで、ボタンを押す。鍵を取り出して部屋に入ると、明かりが灯っていた。キッチンの方からかガザガザと音が聞こえて、彼が来ているのだと想像が付いた。そうでなければ、ただの泥棒だ。私は死ぬだろう。 「来るなら連絡の一本くらい入れてよね。」 「俺が居た方がお前も嬉しいだろ。」 「そういう俺様発言、社会人として控えた方がいいと思うよ。」 「嫌いじゃないくせによく言う。」 私の家で主である私以上に寛ぎ、そしてきちんとその機能を使いこなしているのは天元の方だといつも思わされる。私は料理を滅多にしないが、彼は私の家に上がりこんでは勝手に料理をササっと作っていたりする。所謂男飯なるものなのだが、これが侮れず結構美味しかったりする。無駄に高機能なキッチンも、彼が来る時ばかりは喜んでいるように見えた。 スエットを着てすっかり寛ぎモードな彼はもやしとニンニクの芽を炒めた簡易的な料理を皿に持って、テーブルに置く。酒のツマミには絶好の一品だ。さすがだと思わざるを得ない。 「近くで仕事でもあった?」 「まあな。寄ってやってもいいかなって思ってよ。」 壁を見れば綺麗に高級そうなスーツがハンガーにかかっていた。いつもはもう少しオフィスカジュアルな服装が多いが、きっと今日は外で大きな商談でもあったのだろう。いつ見ても彼の服は規格外の大きさだとどうでもいい事を思った。 買ってきたコンビニの袋を開けてビールを取り出す。彼は冷蔵庫へと向かって、自分自身も同じく買ってきていたと思われるキンキンに冷えたビールを取り出してプルタブを開いた。 「天元のやつの方が美味しそう。キンキンじゃん。」 「そりゃ俺のだからのより美味いに決まってるだろ。」 注いだグラスで、互いのビールの差が分かった。私のグラスよりも彼のグラスの方が早く曇って、グラスの周りに汗をかかせていた。きっと冷凍庫で冷やしたのだろう。同じ銘柄の同じものであるはずなのに、彼の方が勝って見えて少しだけいじけた。本当に、下らない話だと我ながら自覚はあった。 「ほら、美味いだろ。」 曇ったグラスのキンキンに冷えたビールを一口、私の口へと流し込んできた。触れたグラスは、唇からも冷えている事が伝わる冷たさで、一週間たまりにたまった疲れを吹き飛ばすまさに爽快さで、これぞビールという感じだった。 「ガキだからすぐむくれるしな。」 「やっぱりビールは冷えてた方が美味しいね。」 私が素直にそう言えば、「だろ?」とニカっと大きな笑みを浮かべて、機嫌が良さそうに料理に箸をつけ始めた。こんな瞬間があるからこそ、私は生きて行けるのだなと思う。私にとって、天元はなくてはならない存在なのだと改めてそう思わされる。 今までも恋愛をしてきた事は何度かあった。けれど、私は淡白な性格であまり可愛げのない女だ。物事に対する頓着もあまりない。だから気づいたら自然消滅しているパターンや、相手に合わせるのが面倒になって終わったパターン等、取りあえず長続きしない。いつからか別に男という存在は自分にはなくてもいいのではないかと思うようになった。 丁度そんな時に彼と出会った。暑苦しくて、地味な生き方を好む私には到底合わない男の筈だったが、何処か心地がよくて、暖かいものを感じた。初めて会った時から、何処かで会った事のあるような感じを抱かせる、不思議な人だった。 「あー、やっぱニンニクの芽最高。ビールに合う。天元天才じゃん。」 「今頃気づくとかまじで時代遅れ。」 ゴツンと軽く頭突かれて、顔が重なり合う。どちらからともなく吸いつけられるように導かれて、唇を重ねる。嗚呼、こういうのが女の幸せなんだろうなと思って、普段空っぽの筈の心が彼と会っている時だけはどうしようもなく満たされた。恋をするというのは、女の特権なのかもしれない。 買ってきたビールを数本飲み干しているうちに、私はソファーにもたれ掛かりながら意識を失っていた。どれくらい眠っていたのだろうか。布団に入ろうと立ち上がろうとした時、肩からずるりと何かが落ちた。 彼も私と同じく飲んでいる間に転寝してしまったらしい。 あまりにもすやすやと気持ち良さそうに眠ってる彼の顔を見ると動くに動けなくなり、ふいに彼の顔を眺めた。自分の彼の事をこんな風に言うのはおかしいのだろうなと思いつつ、本当に整った顔をした色男だなと思う。何故こんな私に飽きずに付き合ってくれているのだろうかと、たまに不思議になる事がある。 手を伸ばして、その綺麗なかんばせに触れると、じんわりと暖かみが伝わってきて、愛おしいと感じる。まるで初めて恋をした相手のように、彼は私に始めての感情をいくつも与えてくれる。 「…あんまり勝手な事してんじゃねえよ。」 「起きてたの。」 「…途中からな。」 めでたく二人で目覚めて風邪を引かずにベッドへとたどり着いた。私がベッドの奥のほうに転がると、それを確認して天元が布団を被せてくれる。春は過ぎたけれど、時折寒い時がある。ひんやりと少しだけ冷えた空気をさえぎる様に布団の温もりが心地よかった。 「。」 「…ん?」 振り向けば、ぎゅうっと抱きしめられた。寝る瞬間までこんなに幸せでいいのだろうかと恐れ多いほどに、夢見心地だった。仕事がいかに大変でも、私の人生は捨てたもんじゃないなと思う。 求められる事は、幸せな事だと思う。彼とのセックスはもちろん好きだった。けれど、以前からずっと気になっていた事があった。聞くに聞けないまま今に至ってしまったが、それは初めて彼とそうなった時から感じていた疑問だった。 天元はいつも私の首に必要以上に触れる。それはバイオレンスに首を絞めてくる訳ではなく、何かを償うかのように優しく、壊れ物を扱うように丁寧に触れるのだ。何故彼がそこまで首に執着したように触るのかが、私には分からなかった。 最初は首を絞められるのかと恐怖を覚えたものだが、まるきりその逆であるその彼の行為は一体何なのだろうか。気にはなっても、いつもそんな余裕はなく、気づいた頃には全てが終わって、満たされた感情だけが残される。 肌と肌を触れ合わせて、心地のいい温もりを感じながら私は再び眠りに落ちた。 時代は、大正時代。もちろん、私の知らない世界だ。 私は鬼と呼ばれる、人間から忌み嫌われた存在だった。鬼になった事にもがき悩みながらも死を恐れている、哀れな鬼だ。そもそも鬼という存在が何かというのも分からないけれど、視覚として捕らえたその光景にあまり違和感は感じなかった。 夢の中の私は、鬼としての自分に悩みながらも人を喰らう化け物だった。人を喰らう事で、どんどん人間であった頃の自我を失って、ただの化け物へと成り下がっていく様は第三者から見ても異様な光景だった。 百年近く生きている化け物の私は、ある男に出会う。そして、自分が恋をした事がないのだなとふいに思うのだ。結果として、私はその男に首を跳ねられ、長い歴史に終止符を打った。 辛く苦しいその長い時間を、最後に浄化してくれた男に夢の中ながらも感謝の念を抱いた。鬼としての終わりをつけてくれて、そして人間としての感情を呼び起こしてくれたその男に。夢の中の私は、恋をしたいと渇望しながら息絶えた。酷く虚しく、悲しい話だった。 あまりの衝撃的な夢に私は目を覚ます。濡れた瞼を擦って、視界に映る男を映し出して、再び涙が伝った。 これはただの夢に違いないけれど、あの時の私は、きっと強く念じた事で現世で夢を叶えたのではないかと思ったのだ。目の前でまだ眠っている天元は、夢の中の男と酷く似ていた。執拗に彼が私の首を触る事に、もしこの夢が付随しているのであれば、それはどうしようもなく暖かい話だと思った。 「…何泣いてんだ。」 静かに目を開いた彼のかんばせが、夢の中の男と重なって、再び涙が伝った。夢で泣くことはあっても、夢から覚めても尚涙が止まらないのは初めてだった。 「ううん、何でもない。」 右手ですうっと私の涙を拭ってくれた彼に、感謝の念しか浮かばない。夢の中の私に、私は言ってあげたいと思ったのだ。貴方が望んだ願いはきちんと生まれ変わることによって叶ったのだと。誰よりも一番に、伝えてあげたいと思った。 「天元、ありがとう。」 泣きやまない私に不思議そうにしていた彼は、困ったように笑って私の首に腕を回した。 私は、私に生まれ変わったことをこれ以上感謝することはないだろう。
|