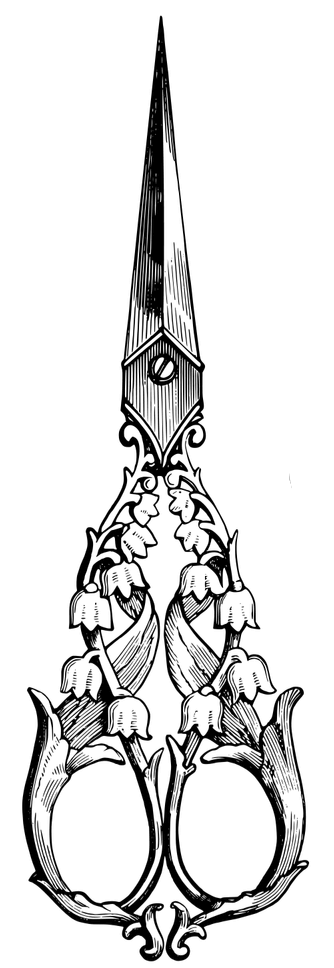 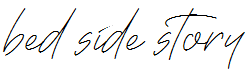 ふいに魔が差したのは、いつの事だったであろうか。特別日常に不満があった訳ではなかったけれど、本当にただ魔が差しただけだった。同じサークルの同期でしかなかった千石という男と一晩の過ちを犯してしまった。 大学一年の夏になる前、私には付き合っている彼がいた。どうしようもなく恋焦がれた関係という訳ではなかったけれど、一緒にいる事に対しての苦痛はなかったし、顔だって悪くなかった。大きく非を打つところもなく、私にとってはちょうど身の丈にあった男だった。大学のクラスの必修授業が同じで、その飲み会で仲良くなったのがきっかけで後々付き合うことになった。 特別入りたいと思ったサークルもなく、なんだかミーハーの集まりのような“サークル”という響きに一歩踏み出す事無く私は真面目に大学に行って、授業に出て、授業が終わればバイトへと向かうために学校を出る。平凡すぎるそんな私の日常を不憫に思ったのか、クラスで少し目立つ存在だった女に自分自身のサークルの夏合宿に参加しないかと呼ばれ、参加したのがサークルに入るきっかけでもあり、千石という男と出会う最初のきっかけだった。 魔、一 正直気乗りしなかった。大学生活も夏休みになれば、概ね行動をする人間やパターンは形状化される。そんな中、関係の出来上がった自分の見知らぬ輩が群がるサークルの合宿だ。その手の話に舞い上がっているような女であれば、私は迷わず入学して早々にサークルに入っていただろう。けれど、その場へと足を踏み出してしまったのはたった一人のある意味強引な女の一言から始まった。その時点で、きっと私は魔が差していたのだろう。これが、すべての始まりだった。 季節は、夏。大学に入ってから初めての長期休み。天気は、晴れ。快晴がじりじりと肌に染みる海日和だった。東京の外れにある小さな島へと船で十時間、そこからして既に地獄だった。フェリーだなんて大層な乗り物ではなく、なんとか丸という庶民的な船を少し大きくしたようなその船で、多くの人間がトイレに篭り、皆が酔い止めを握り締めていた。ようやく陸へとあがった時、誰もが皆青い顔をしてこれから海で夏を満喫しようという感じではなかった。もちろん、私も多くの内の一人だ。気分も悪ければ、具合も悪かった。 昼になるにつれて、体力を回復する者も多く、次々へと透き通った海へと消えて行ったが、船酔いは冷めてもとても私はそこに加勢する気になれず少し離れたところでそんな若気の至りを具現化したような若者たちを見ていた。私を誘ったその女は、私のことなど忘れたかのように海の中で無邪気にはしゃぎ、時折先輩の男にその体を波に投げられ楽しそうにしていた。 「君、この合宿から?うちのサークル。」 「…いえ、ただの付き添い。多分入らないと思う。いや、絶対に。」 「そっか。でもさ、こんなもんだよどのサークルも。」 そうか、サークルとはどこもやはりこんなものなのか。それを知れただけでもいい勉強になったと思うことにした。私にはサークルというものは心底肌に合わない。このサークルだけでなく、他のサークルにもきっと一生入ることはないだろう。 「そういう貴方は、海入らないんですか。」 「あ、俺?去年充分青春したしねここの海で。それに知らない女の子が一人だと気になるじゃん。」 「だってサークルってそういうものなんでしょ?だったら、今年も青春すればいいのに。」 「いいじゃん。なに、それとも俺がいると邪魔なの。」 邪魔なようでもあって、邪魔なようでもない。別にいなくても、いてもどちらでもよかった。そもそも私を呼びつけたその女が私を放り出して全力で自分の楽しみを優先している時点で、ここにいるのが果てしなく無駄に思えた。特別何かに期待をしていた訳ではないけれど、きっと私は社会勉強ならぬ大学勉強をここにしに来ただけなのだから。痛い大学生達をきちんと見つめて、今後に活かせばいいのだ。反面教師とはこういう事だ。絶対にああはなりたくないと思った。 「俺は二年の千石清純。清純って呼んでくれていいよ。」 「…呼びませんよ。サークル入らないし。」 「別にサークル入らなくたって同じ学校だし、友達でいいじゃん。」 サークルという輪に属している人間は皆こうも軽い感じなのだろうか。恐ろしい場所だ。それは、大学入学当初に私が想像していたサークルとほぼほぼ一致していた。軽い人間が群がって、社会人になるまでの四年の猶予をこうして過ごしていくのだ。そして社会人になった時に、学生のころは無茶したねとか痛かったよねと語るための材料作りをしているに違いない。私には、そんな思い出はまるきり必要ない。 「海が嫌なら、そこの海の家で俺とカクテルでも飲みにいく?」 「行くような女に見えているのであれば、千石さんは随分頭の中がお花畑だと思う。」 「君面白いこと言うね。たいがいこう言えば、女の子は落とせるんだけどなあ。」 「このサークルにいそうな女性陣と一緒にしないで欲しいです。」 これが彼にとってのナンパの定石なのだろうか。本当にこんな安い言葉で彼と海の家に消えていく女がいるのだろうかと不思議に思いつつ、このサークルにいる女は私をつれて来た元凶であるその女をはじめついていくのだろうなとも思う。自分と彼氏の関係性は酷く健全で、やはり身の丈にあっているのとかみ締めた。この合宿から帰ったら、もっと彼を大切にしようと誓った。 「気が済んだなら早く海で遊んできてください。」 「連れないなあ。そんな事言われると余計に行けないの、分かってる?」 そう言って、彼は笑って私の顔を覗き込んだ。そんな事をすれば更に私が嫌がると分かっていながら、わざとそうしてからかい、遊んでいるのだ。 「俺は君みたいな子、好きだけどな。ちゃん。」 伝えてもいない名を呼ばれて、どきっとした。それは恋の類のものではない。何故私の名を知っているのかという謎からくるものだ。あとから私をここへと連れてきたその女に聞いたら、サークルの中ただ一人知らない顔を見つけた千石に聞かれて名を教えたのだと聞かされた。この時から私はターゲティングされていたのかもしれない、彼の暇つぶしの相手として。 魔、二 悪夢のような夏合宿から帰ってくると、ようやく私の日常が戻ってきた。彼氏には「合宿どうだった?」なんて呑気な事を聞かれたので、やっぱりサークルは私には向いていなかったとだけ一言伝えて、内容を伝えることはしなかった。千石という男を思い出して、彼氏と見比べてみると随分と自分は平凡な人間と付き合っているのだなと思った。平凡ではない男と付き合いたいと酷く頭の悪い事を思ったわけではなかったけれど、どこかしょうもなく見えた。そして、自分が一番しょうもなく思えた。 季節は秋になり、すぐに冬になった。夏合宿の後、しょうもないと一度思った彼氏とはまだ付き合いを続けていた。元々燃えるような恋だった訳でもないのが幸いしたのか、付かず離れずなちょうどいい関係性が継続されていた。 私を夏合宿に連れて行ったあの女は、一年生の後半に差し掛かるとあまり授業に顔を出さないようになっていた。テスト前の時期にひょろりと顔を覗かせて、ノートを見せてと声をかけて来るくらいの希薄な関係性だ。そんな彼女が何かの気まぐれか、暇つぶしのように授業へとやってきた。 「あ、!久しぶり、元気だった?」 馴れ馴れしく隣に座ってきた彼女は、夏合宿の話を皮切りに色々とサークルの話をし始めた。たいして興味もない私のこと等お構いなしに、自分が大学生活を謳歌しているのだと何処か誇らしげで頭が悪いなと思わざるを得なかった。持ち上がり式の学校とはいえど、彼女と同じ学校に通っている自分を悲しく思った。 どうでもいい話が耳から耳へと消えて中、知っている単語が耳を竦めて、少しだけボールペンを走らせる右手を止めて、彼女のほうへと私は顔を向ける。 「清純さん、ほんと彼女と仲良くってさあ。」 「それって千石って人?」 「ああ、そうそう。彼女夏合宿には来てなかったんだけどさもう付き合って長いんだ。」 「なんで夏合宿にこないの?付き合ってたら普通来るでしょ。」 「なんでも肌焼けるのが嫌って、夏合宿は来ないんだよね。」 千石という男はそういう女が好きなのかと考える。私とは似ても似つかない女の事を大切にしている。女から敵の多そうな女を彼女にしている彼を不思議に思いながらも、なんだかしっくりと腑に落ちた。あの夏合宿で彼が好き勝手動いて、私の周りをちょろちょろしていたのはそういう理由だったのだ。 「そうだ。久しぶりにサークルに遊びに来たらいいじゃん。」 「いいよ。私、今日はバイトあるし。」 「じゃあバイトの時間まででいいからさ。ね。」 心の中で毒づきながらも、私は人の誘いを断る勇気を持ち合わせていない。自分から嫌いな人間を作るくせに、自分が嫌われるのが怖くて断ることができない。それが私の弱さであって、夏の悲劇を生んだ元凶でもあるのだ。今も、その例外ではない。 授業が終わり、私は女に強引に連れられ、久しぶりにそのサークルの会合に顔を出していた。 「お、ちゃんじゃん。久しぶりだね。」 私の友人面をしたその女は我が物顔で私をその会合で紹介した。夏合宿に来たと、誰もが望んでいない他人紹介をする事で自分の存在を誇示しているかのようだった。自分を見世物にされているようで気分が悪かった。そんな時、いち早く私の元へとやってきたのが千石だった。あの時と変わらぬ、ニコニコと絵に描いたような笑みをかんばせに塗りつけながら。 「なに、ついにサークル入る気になった?」 「なってないですよ。」 「なんだ、それは残念。」 二、三彼と言葉を交わして、あとはあの夏合宿と同じ光景が広がった。私を連れ込んだ彼女はいつの間にやら他の人間と楽しそうに言葉を交わし、私のことなど忘れ去ったように盛り上がる。そんな私に構っているのは、やはり千石という男だけだった。誰も夏合宿に一度だけ来て、誰とも親睦を深めなかった女の事など気にも留めない。やはり、私にはサークルというものが肌に合わないのだ。 ろくでもない会話が辺りで飛び交う中、一瞬静けさが到来して、その後に異様に肌の白い女がやってきた。一目見て、それが千石の彼女であるのだと察した。 「お、姫!お疲れ。」 他の面子から姫と呼ばれた千石の彼女は、その言葉に気を悪くするでもなく喜ぶでもなく、もはや呼ばれ慣れているとばかりに平然とした顔で千石の隣に腰を下ろした。 「なんだ。もう授業終わったの。」 「うん。先生が学会で、今日は休講だって。」 「そっか。お疲れ様。」 私の知人である女が言ったように、千石とその彼女は仲睦まじげな理想的な恋人同士に見えた。平々凡々な私と、その身の丈にあった彼氏との恋人同士とは訳が違うように、きれいに輝いて見えて酷く惨めに思えた。別に千石が好き、そう思っている訳でもないのに負けた気がしたのだ。 「私そろそろバイトだから帰るね。誘ってくれてありがとう。」 一言だけ、遠くにいる彼女にそう声をかけたが、ざわめきの中その声もかき消されたのか彼女には届いていないようだった。 魔、三 冬休みが終わり、私は無事に大学二年生になった。運悪く、学年があがっても強引さがウリと言わんばかりのあの女とクラスが一緒になってしまったのは、この後の私の人生を見つめなおす上で最大の不幸だった。 彼女は一年の時よりも授業に来るようになっていた。一年次の取得単位が親の目に入り大目玉を食らって仕方なくと舌を出していたけれど、そんな彼女と一緒に授業を受けないといけない私は舌を出してチャーミングにウインクする事などできない。甚だ迷惑な女でしかない。 二年になって数ヶ月が経過したころ、彼女は落ち込んだ表情で私の前に現れてサークル内にいた彼氏に振られたのだと告げてきた。ざまあみろと少しいい気分に浸っていたのもつかの間、またこの女は思ってもみない奇想天外な言葉を紡いだ。 「もうサークルに顔だせないし、一緒に来てくれない?」 「…そんなサークル辞めればいいじゃん。」 「私からサークルとったら何もなくなるし。が一緒なら行ける気がするから。」 こうして私はまた、誘いを断りきれず、彼女の横暴としか言えない私情に振り回されながらサークルへと顔を出す。彼に振られてばかりの彼女は以前と違い傷心しているからなのか、ずっと私の傍にいた。仕方なく、私は二年になってから意味の分からない理由でサークルに入った。 もうすぐ、夏合宿の季節になろうとしていた。 このサークルの夏合宿は毎年同じ場所と相場は決まっていると聞いたのは行く直前のことだった。何故みんなして酔い止めを握り締めながらトイレの奪い合いをしなければたどり着けないようなあんな場所に毎年行くのかと不思議だった。 今年の夏も、千石の彼女である“姫”と呼ばれる女の姿はなかった。 すっかりと失恋の傷心から立ち直った彼女は、去年と同じように私を置き去りにして海の中でぷかぷかと浮かんでいた。まるでくらげのように、どこまでの浮ついた軽い女だなと哀れを通り越して滑稽で、苛立ちは最早なかった。 「今年も海入らないの、は。」 「そういう千石さんも。」 「話せる子は出来たけど、海は入る気がしなくて。私も千石さんの彼女みたいに夏合宿、来なきゃいいのか。」 「そしたら俺が暇になっちゃうじゃない。」 私を覗き込んで、千石はいたずらっぽくそう告げた。あの時の再現でもしているのだろうか。だとすれば酷く悪趣味だけれど、なんだか可笑しくなって二人して笑ってしまった。私と千石しか知らない、二人の思い出だった。 「ねえ、ちょっと来て。」 彼に手を引かれるままに、私は砂浜を歩く。時折ビーチサンダルの中に入ってくる熱を帯びた砂に足を取られながらたどり着いたのは、一隻の船だった。彼は迷う事無くロープを伝って無人のその船へとあがりこみ、私に手を伸ばしてきた。そこに何があるのだろうかと思いながらも彼の手をとり、船上へとあがり、彼の視線の先にある海面へと私も視線を落とした。 「…くらげ?」 「そう。くらげだよ。危ないよね、こんな浅瀬だっていうのに。」 「ほんとに。もう、夏も終わりなのかな。」 どうしようもない常夏の地で、夏の終わりをなぜか感じていた。ぷかぷかと数匹で群れをなすそのくらげ達は、私が知ってる強引な女とは違い、とても透き通ってきれいに見えて、どこか切なくも儚く綺麗に輝いて見えた。 「自由でいいね、くらげはさ。俺もくらげになりたいよ。」 先ほど船上へと引き上げられた時のように、彼に右手を引かれて間合いを詰められた。しまった、そう思った時にはもう、くらげのようになんとも柔らかい感触が唇に触れていた。 やめてとすぐに彼の体を弾き飛ばせば「なあんてね。」とそんな一言で終わっていたのかもしれない。けれど、私の体内にはもう既に毒が回りこんでいたのだろう。離すことは、出来なかった。 魔、四 あれだけ自分には合わないと自身を持って嫌っていたサークルに、私は頻繁に出入りするようになっていた。痛い青春も、以前に思っていた程悪いものとは思わなくなったのだから自分自身が一番驚いた。 一年から付き合っている彼氏は形上また付き合いを続けてはいたが、何の興味すらなくなっていった。別れるきっかけがないというだけで、最早なんの感情もそこには齎さない。薄情な女だなと思いつつ、この時ばかりはサークルに無理やり私を引き釣り込んだ彼女に少しばかり感謝の念を抱いていた。 夏合宿から、私の生活は少しずつ変わっていた。人間、秘密の関係というものにぞくぞくとした背徳を感じるらしい。私もその頭の悪い人間側だ。彼の彼女になりたいだなんて、そんな事は思うこともなく、今のこのスリルのある関係を楽しんでいた。私は、姫でなくてよかった。 冬の合宿は行かなかった。私には、彼との秘密の思い出の夏合宿だけで充分なのだからと言い聞かせていたけれど、やはり姫と彼が楽しそうにゲレンデを滑り降りてくる姿をみたいとは思わなかった。そのおかげもあってか、私は嫉妬に狂う事もなく今も彼とこの関係を続けることが出来ていた。 ある時、久しぶりに彼に呼び出された。付き合い始めてもう少しで三年になろうとしていた時だった。家に呼ばれた時、久しぶりに彼に触れられて得体の知れない感情に苛まれた。以前までは嫌と思うこともなかったが、触れられるだけでもぞっとしたのだ。あの時船上で千石を突き飛ばす事は出来なかったのに、仮にも付き合っている彼氏と呼ばれる存在の彼は簡単に突き飛ばすことが出来た。しまったと思った後、顔をあげた時に見た彼の顔は今も忘れることが出来ない。 そこから関係性は悪化していき、どこのタイミングでかスマホのメッセージのやり取りを見られて私は振られた。最低だなという言葉を捨て台詞に、三年の付き合いが終焉を迎えた。 ある意味自由で、身軽になった私は、以前よりも千石と会うようになっていた。 「さ、彼氏は。喧嘩とかしてない?」 「してないしてない。全然だよ。キヨは。」 「俺も。前と変わらないな。」 それはつまる所“姫”と上手くいっているという順調そのものを示していて、私も自分も同じような状況だと彼に伝えた。そう伝えることで、彼とのこの関係を継続できると思ったからだった。ここで彼氏とは別れたとでも言えば、私が本気になったのだと思ってすうっと消えていくような気がしていた。居もしない彼氏との順調な付き合いを演じながら、あの女と千石だけには既に別れている事を悟られないように細心の注意を払った。 「は来年も夏合宿、行く?」 「行くよ。キヨ、は。」 「どうかな。就職活動次第じゃないかな。」 来年、彼は最上級生になり、そしていずれ卒業していく。そんな彼との思い出に、どうしてももう一度あの夏合宿に二人で行きたいと思っていた。彼の現実的なその言葉は、私を夢見心地から攫っていった。 千石さんと呼んでいた私は、キヨと彼の名前を呼ぶ。これは、“姫”が呼んでいる彼の名前だった。そう呼ぶ事で、私も千石の特別になりたかった。彼女でなくていい、ただ特別な枠には嵌っていたいと思うようになっていた。 小さな1Kの部屋のベッドの右側に、いつも彼は寝そべった。私を左側に閉じ込めるように追いやって、優しくキスをしてくれる。くらげがたゆたうように自由に、優しく。私には、それだけで充分だった。 「行けると、いいな。」 甘えたようにそう言うと、少し間をおいてくすくすと笑いながらそうだねと賛同の意を口にしてくれた。 ついに、私は大学三年生になり、千石は最上級生になった。彼の就職はまだ決まっていない。早く決まらないかなと思っていれば、またあの女は私に付きまとうように同じクラスになった。切っても切れない縁や運命の相手は、もしかすると彼女なのかもしれないと思わせるほどに。 三年にあがったタイミングで、彼女はまた予見できないような爆弾を私に投げかけてくる。毎年学年があがるたびに、彼女の発言に振り回されるのは私の運命なのだろうか。今度は、千石が昔から好きだったという意味の分からない言葉だった。 「…いつから?好きだったの。」 「うーん、サークル入ってすぐかな。でももう姫いたし、無理だって諦めてたんだよね。」 けれど、もうすぐ彼も卒業だからと自分の気持ちをぶつけて見ようと思うのだと言った。本当に彼女は何年経っても頭が悪いのだと思う反面、万が一にも千石がその気持ちを利用したら。私と同じように秘密の関係を気づきあげたとしたら。 「別れないよ、あの二人は。あんなに仲良いのよく知ってるでしょ。」 そう言ったところで、素直に彼女が私の言葉を聞くはずもない。そんな事は私が一番よく知っていたが、私も冷静さを欠いてしまう一大事に、無駄な事を言ってしまったと後悔した。あとは、千石に委ねるしかない。彼を信じようと思った。彼の彼女でもない私が何を信じるのかと自問自答して、哀れになった。 思い立ったら即行動に移す彼女は、私に宣言したとおり千石に告白して、優しくやんわりと振られたのだと私の胸に抱きついてきて永遠と泣いた。少しだけ自分を優位に思った私も、彼女と同じで愚かだ。 魔、五 結局、千石の就職が決まったのは夏合宿が終わってすぐの事だった。今年は“姫”だけでなく、千石も夏の合宿に姿を現さなかった。去年の二人だけの秘密の思い出は、私一人だけの夏の思い出に塗り変わっていた。千石に振られてまだ完全に傷が癒えていない彼女だけは、何処か解放的に今年も夏を満喫していて腹立たしい。 冬の合宿には行くからと聞いてはいたが、もちろん私が冬の合宿に参加することもなく、千石は卒業して私はついに最上級生になっていた。この時期お決まりの恒例行事など最早誰も聞きたくないだろう。また、私の隣には彼女がぴたりと陣取っていた。 新人の研修が終わったからと、彼が社会人になってから初めて誘われた夜。少しでも彼に近づきたいと思って、面接があった訳でもないのに就職活動は疲れるねと言わんばかりにスーツで彼と会っていた。 「もついに就職活動か。最後の学生生活、どう?みんな元気かな。」 「元気だよ。みんな今年が最後の夏合宿だからって張り切ってる。」 「は俺みたいになるなよ。早めに就職決めないと。」 「そうだね。キヨみたいに私は選り好みできる程余裕ないんだけど。」 「はは、俺だってそんな選り好みしてなんてないよ。」 個室の居酒屋で、スーツ姿の彼を前に私はビールを喉に通す。直接彼には聞かなかったけれど、今も千石は“姫”と順調に付き合っているらしい。これだけ遊び上手な男が、四年も同じ女と付き合えているのはきっとそれが“姫”という彼女だからなのだろう。私は、それにはどう転んでもなれない。 「やっぱ好きだわ。落ち着く。」 そういって私の額を小突いて、むくれたような顔を見せ付けるとすぐに彼の手のひらが優しく私の髪を撫でる。私はこうしておけば満足するのだと、私の属性をよく知っているのだろう。そう考えると、居たたまれなくなった。 何故、こうも彼に惹かれてしまうのだろうか。確かに要領もよく何でも卒なくこなす彼はよくモテる男ではあるけれど、背が高い訳でも、絶世の美男子な訳でもなく、一般的な男を少し格好良くしただけの筈なのに、どうしてこうも ストーリーは決まっているのだ。私が初めて夏の合宿に行った時から、そしてこの後も。私と千石の関係はベッドサイドでしか、その意味を成さない。 「彼氏とはどう。喧嘩してない?」 お決まりのテンプレートのような彼の言葉は、用意されたバッド・サイド・ストーリの様に、私は“姫”が辿る幸せなメインの幸せなエンディングを迎えることは出来ないのだ。 この男との繋がりを望むがばかりに、 私の四年は本当に痛い青春になるのだろう。 ベッド・サイド・ストーリー |