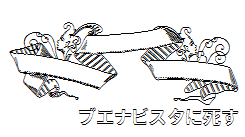 金曜日の夜は、誘いが多い。 金曜日と言えば、多くの社会人や学生が週の締めくくりを迎える日だ。仕事にしても、バイトにしても、学業にしても、来る土日に向けて開放的になり、人々は思い思いの人と時を過ごす。次の日を考える必要のない金曜日が、皆好きなのだろう。物は、考えようだ。 金曜日になってくれば私を誘って、そして金曜日以外は私を誘ってくれない彼もきっと解放的な気持ちを元にいつだって私を誘ってくるのだろう。次の日のことを考えなくていい、その日に誘われる私はもしかしたら勝ち組なのだろうか。 土曜日や、ましてや日曜日に彼からの誘いが絶対にない事を、今だけは忘れることにしよう。 金曜日は、スマホが気になる。 土日休みの会社に勤める私にとって、金曜日はそれなりに忙しい日だ。取引先はこちらが土日祝休みという事を知って、こぞって金曜日に滑り込みで電話やら提出物を出してくる。いわば、ひとつの締切日のようなものなのかもしれない。金曜日も忙しければ、もちろん土日で仕事を怠っている分月曜日も忙しいことには違いないが、その違いは次の日が休みなのか、そこから一週間が始まるのか、だ。 午前中は特に仕事が立て込む。取引先がこぞって問い合わせをしてくるのであれば、受ける側の私たちもさっさと仕事を終わらせようと躍起になって取り組むものだがら、全国的に見ても金曜日は仕事がはかどる日と言えるのかも知れないと、私事を世間に当てはめるように考えた。 慌しい午前中をなんとかやり過ごして、私は社内で鳴り響く電話を避けるようにデスクを離れ、ランチへと出かけた。特に外食がしたかった訳ではないが、デスクにいればいらない仕事が入ってくる事もあり、金曜日はランチに一人で出かけるのが私のデフォルトだった。金曜日だけは、仕事を早く終わらせる必要があった。 「、今日部署飲みするって。お前、来るだろ。」 「今日?ずいぶん急じゃない。今日は先約あるから、また今度。」 「おいおい。金曜は会社の人間と飲みに行くような日だろ。」 ランチへと出かける手前、同じ部署の同僚に声をかけられて私は席を立ったタイミングを誤ってしまったと思った。金曜日は、こんな誘いが多いからこそ声をかけられないように早々に席を立っていたのに、今日は運が悪い。 また今度、なんて言いながらここ半年会社の部署飲みには顔を出していなかった。よくもこれだけ誘いに応じない私を誘い続けてくれるものだ、と少し呆れながら。 「また事前に誘ってよ。いつもほんと、ごめん。」 大して思ってもいないその場を繕うだけの言葉を放って、私はいそいそと外部へと続くエレベーターのボタンを二度ほど押した。 本当は、予定なんてない。いや 私のスケジュール帳の金曜日はいつだって空欄だ。平日は仕事関係でびっしりと埋められた筆跡を縫うように、金曜日だけが綺麗に空欄を描いている。それは、どれくらい前からの事だっただろうか。 スマホを握って、ランチに出かけた私は大して入りたいとも思っていないイタリアンに向かい、席にかける。ここを選んだのは、半個室の空間があるというそれだけのことだ。味の濃いナポリタンはいつだっておいしくなく、舌の上にずっと残っていたけれど私はこの為に毎週金曜日に千円を支払う。金曜日になれば、彼からの誘いが来るかもしれないという、あてもない約束に払う代金だ。 なれた様にナポリタンを頼もうとした時、逆に店員から「ナポリタンでよろしいですか。」と聞かれて、店の人間に自分の存在が認識されていることを知った。ああ、もうここに来るのも潮時かもしれないなと思いながら、あとで一人でも入れるランチの店を探そうと思う。 その店の検索をする前に、私はメッセージの確認をする。これが、私の金曜日の楽しみのようなものだった。 まるで私が金曜日にまったく予定がないと分かっているような、上から目線のメッセージに私は少しふてくされながらも、意気揚々とフリック入力をする指を動かしていく。彼はきっと、金曜日にいつだって暇にしている私の本当の姿など知らない。 毎度こうして理由をつけて暇であることを言うのも難しくなってきたなと思いつつ、文章を打っていく。次に帰ってくる、時間指定だけを、私は待っていた。ナポリタンを待っている訳ではなく、ここで私が待っているのは彼からの返事だけだった。 そう言いつつ、いつだって私が彼と会う金曜日に遅れた事などなかった。その為に平日夜遅くまで残り、仕事をこなしているのだから。善処すると伝えたのは、少しの皮肉。私ばかりが彼に会いたいという気持ちが少しでも表に出ないように、少しばかりの強がりに違いなかった。 五分待っても、返事は来ない。この時間は彼も昼に出ていることが多いと知っていたが、同僚とランチにでも行っているのだろうか。もどかしく返事を待っていた時、待っていたものとは違うものが運ばれてきた。 「オマタセシマシタ、ナッポリタンです。」 外人なまりのその言い方が、酷く癪に障った。 定時の七時になった時、私は早々にデスクを立った。忙しかったが仕事の合間を縫ってトイレに向かい、少しずつ化粧を仕上げた。普段は風邪をひいて仕事に穴を空けてはいけないと、思ってもいない理由をつけて顔を覆っているマスクのおかげでそれも誰にも気づかれていないようだった。 あとはもう一度トイレに向かい、マスクをはずして口紅を塗りなおして、電車に乗るだけだった。 時刻は、七時二十分。約束の十分前には、約束の場所へとたどり着く手はずだ。酷く計画的な自分の金曜日に哀れみを感じながらも、私の心は酷く弾んでいた。それは、明日仕事がないという理由からだと自分自身にきつく言いつけているようだった。 「ブン太。」 「、お前遅いっつうの。」 「まだ十分前だし。」 私よりも前に来るブン太なんて、今まで見たことがあっただろうかと思う。案の定、彼は少しばかり気分を悪くしたように不機嫌だった。約束した時間の十分前に現れた私に対しては摩訶不思議な態度だ。 けれど、私はそこに対しての負の感情はなかった。私を待ってくれていたという事に、裏づいた理由はいらない。素直に、うれしいと思う私は生粋の馬鹿なのだろうと思う。理由が何であれ、私を待ってくれているというそのたった一つの事実だけで、これから飲むであろう酒が美味くなると思った。 「今日は何食べたい気分なの、ブン太は。」 「え、ピザ食いたい。」 「じゃあ、一緒にワインでも空ける?」 「ワインとか興味ねえし。」 彼はいつだって大学生のような赤いカクテルを好んで飲んでいる。もはや学生でもないのに、彼の趣味思考は変わらないのだなと改めて認識して、少し笑った。いかにも、彼らしい言葉と思った。 彼の要望どおり、私は嘗てに行ったことのあるピザのおいしい店を思い出し、道のりを急ぐ。本当は一緒に赤ワインでも空けたかったけれど、彼と居れるだけで最早私には満足だったのかもしれない。ワインを飲みたいと思っていたことも、すでに忘れていた。 馴染みの空間で、ピザを食す。この店へは女子会で来ただけで、男の人と来たのは初めてだった。こんな素敵な店に好きな男とこれたら幸せだろうなと、なんとなく思っていたが、今私はその思いを叶えていた。 「ピザは逃げないんだからもう少し品よく食べなよ。」 「あ?これ食べに来たんだろ。」 「…まあそうだけどさ。食事もかねて今日は飲みに来たんじゃないの。」 「ああ、そっか。忘れてた。」 彼の赤いカクテルは食べ物を前にして、全くその量を減らしてはいなかった。こんな風に目の前の食材にかぶりつく彼を見て、某ファミリーレストランを思い出した。彼には、そちらの方がよかったのかもしれない。本当に味わっているのかもよく分からない食いっぷりだった。雰囲気もへったくれもないと文句を言いたいところではあったが、そんな彼を見るのも少し愛おしく感じる私は変人なのだろうか。きっと、間違いなくそうなのだろう。 「お前、食わないの。」 「さっき食べたじゃん。お酒飲みながら、ブン太みたいにそんなに食べれないでしょ。」 「なんだ。勿体無い奴。」 しばらく、彼は運ばれてくる料理に手をとめる事はなかった。中学の頃と何も変わらない彼に、少し微笑ましくなった。彼は、変わらない。変わってしまった、私たちの関係だけを、思い出さないようにして。 半年前、私は数年ぶりに彼に再会した。同窓会という、ベタな再会だ。 彼とは中学以来こうして約束をして会うことはなかった。社会人になりたての頃はお互い実家に住んでいた事もあって通勤時間帯にたまたま出くわす事はあったが、今はお互い実家を出て一人で暮らしている。 私は、私たちはその同窓会で過ちを犯した。ワンナイトと割り切ればよかったが、もともと馬が合うと思っていた彼と一緒に居ることに、すっかり私は嵌ってしまっていた。 「いいよ。酒はの家で飲めばいいしな。」 「今日も来ること前提で物を言わないでよね。」 そうは言いつつ、私はこの為にいつだって金曜日の予定を空けていた。半年間、違うことなく、それを実行していた。 彼を好きだったのは、中学の頃に遡る。伝えた訳ではなかったが、私は彼のことが好きだった。玉砕して今までの関係がなくなるくらいであればそのまま彼と友情を築いた方が得策だと当時は思った。彼との友人関係を失ってまで、手にしたいとは思わなかった。 同窓会での彼は、酷くその場を楽しみ酒に酔っていた。だからこそ、おきえた事象だったことは私も理解に及んでいる。けれど、今彼は彼女は居ないと言った。ならば、一夜といえど共にした私にも勝機があるのではないだろうかという感情の元、昔の感情をすっかり取り戻してしまった。 「ふう。よく食ったぜ。俺様もう大満足。」 この後彼から紡がれる言葉なんて、容易く想像につく。 「帰ろうぜ、お前の家に。疲れたし。」 私は、きっとこの言葉を待っていた。 飲み足りない私を他所に、彼は私の家に伸びる道をなれた足取りで進んでいく。私が待ってと言えば、遅いと言って諭した。まるでそれが自分の家へと帰るような彼の足取りだった。気分は、悪くなかった。酒を飲んでいるから気持ちが高ぶっているのかもしれない。 彼に会う金曜日、私の家で彼は私を抱いた。それは私が勘違いを起こしてもおかしくないような、日常となっていた。なぜこんな状況が続いていながら、彼は私に付き合おうと言ってこないのだろうと不思議に思うくらいに。 「ブン太はさ、何で彼女作らないの。」 「何だよ、突然。」 私を彼女にすればいいのに。 彼女がいないのであれば、彼女にしてくれてもいいのにと思う気持ちは常にあったが、それを言う勇気もなかった。 「彼女なんて作るもんじゃないだろ。気づいたら、出来てるもんだろ。」 「何それ。キザだなあブン太にしては。」 「お前に馬鹿にされる覚えはないっつうの。」 という事は、私は彼女にするにも値しない存在なのだろうかと思う。いつだってそんな事を考えていたけれど、ならば彼が頻繁に金曜日に誘ってくる筈もないのだと自分自身を落ち着かせようとした。 私の家につけば酒を飲むといった彼の言葉に、私たちは近場のコンビニへと足を運んで、その袋を下げていた。鞄から家の鍵を取り出して、穴にねじ入れる。そうするとガチャリと不思議なからくりが音を立てて、私の居住空間を視界に写しだす。 「じゃあ、飲みなおそうか。」 その私の言葉を皮切りに、彼は大して酔ってもいない体で私を包み込む。それは、勘違いを起こすには酷く罪深いような、強い抱擁だった。 「早くベッド、行こうぜ。」 「…飲みなおすって、そう言ったじゃん。」 「飲みなおすのはその後でもいいだろ。」 私の体は、ベッドへと落ちていく。いつも一人で寝ているベッドに、彼と堕ちていく。 これを望んでいたようであって、きっと望んでいなかった。いつだって家で飲みなおすという口実を元に彼は我が家を訪れて、飲むこともなく私を押し倒して、それが終わった頃に家が近いからと帰り、朝まで居ることはなかった。 「抱かれたかったくせに、お前。」 もっともな彼の言葉に、私は何も言えなくなる。それが私自身の本心なのだから抗う術がない。酷く反発したい気持ちに駆られながらも、いつだって私は言葉に翻弄される。拒絶することなど到底できなければ、もっとと、望む希望の言葉も紡げない。 すべての行為が終わったあと、金曜日が終わったように彼はベッドの下に散らばる服を拾い上げて、袖を通していく。 「ブン太。帰るの?」 「俺歯軋りひどいし、お前が気の毒だからよ。」 いかにも私のことを思いやっていそうで、ただの彼の都合でしかない言葉に、傷つく。今日だけでなく、彼と会う金曜はいつだってそうだった。 飲み直すからと我が家に来たはずなのに、それをも先延ばしにされて、結局それをもしないで帰ってしまう。もはや、いつもの事なのだから驚くことはないけれど。 「明日ね、暇なんだ。どっか、付き合ってよ。」 去り際に、私は同じ言葉を紡ぐ。何か、私と彼を繋ぐ確証がほしかったのだと思う。不規則な金曜日に会うだけのその関係に、私は確固たる証が欲しかった。 「悪い。明日は予定あるんだ。また誘う。」 こんな会話は何回目だろうか。いつだって金曜日の夜更けにこの言葉を紡いでは、同じ答えを耳にした。ある程度その意味を理解しつつも、それを認めてしまっては私のプライドや尊厳が崩れ去ってしまうような気がして、いつだって彼は忙しく所謂リア充というものなのだろうと言い聞かせて。聞けばすぐに分かるようなその本音を、分かろうともせず。 「また来るわ。おやすみ。」 そう言って、彼は私にキスをして、玄関のドアを開けて去っていった。そうではないと、そう言いたげな私の感情など分かってもいないかのように。キスをしておけば、私が満足するとでも言いたげに。 私は、結局金曜日にしか会って貰えない女という事なのだろうか。一緒に買った酒すら、一緒に飲んではくれないのだから。笑えるほどに酷い話だと思う。 散らばった服を拾いあげることもなく、私はコンビニ袋をたくし上げて、まだ飲んでいないその酒を手に持った。プルタブを開くと、プシュウと酷く音をたてて飛沫を上げた。 「もしもし?今お前の家の近くで飲んでるんだけど、来ないか?」 いつだって断っていたその誘いを、受けて私は外に飛び出した。
|