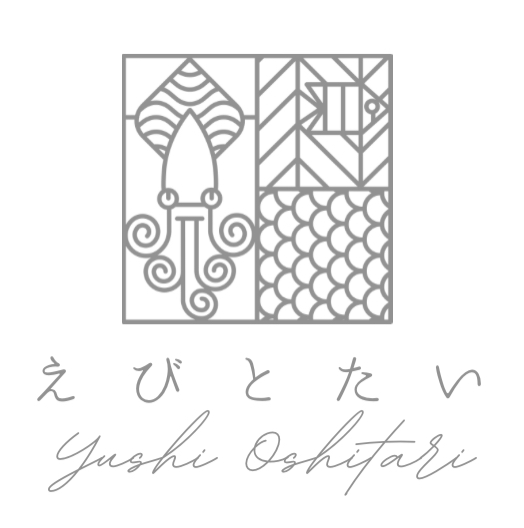 週末になると、私はとある高層マンションへと向かう。ほぼ違うことなく、毎週の出来事だ。かつての友人達からは「通い妻じゃんいいなあ。」なんて言われる事もあったけれど、彼女たちが言うように今私がやっている事は人に羨んでもらえるような羨ましい事なのだろうかと考える。嗚呼、私にはそうではなくても彼女たちにとってはそうなのかと主観でしか考えていないことを思い出して、冷静に自分を分析したけれど、その分析がされる前に私は高層マンションのロビーまでたどり着いて、その考えをとめて彼から渡されている合鍵を差し込んで自動ドアを開けた。 エレベータで八階のボタンを押す。態々八階に住むなんて、彼らしいなと思う。このマンションの最上階である三十二階にだって住めるくらいの財力を持っているくせに、そういう所で驕る人ではないのところが少し憎く、そして彼が昔から人気がある一つの所以なのだろうと思う。 「おかえり。ベル鳴らさんでもええっていつも言うとるやろ。」 「だって勝手に入って忍足が変な事してたら、私が困る。」 「お前、俺の事どんな獣やと思とんねん。エレガントに紳士でしかないやん。」 「自分で言っちゃうあたり、そろそろ治したほうがいいと思うよ。」 午後九時を過ぎた頃、私は彼の家へとたどり着いて薄手のコートを脱ぎかけるとすっと後ろからコートを取り上げられて、すぐにハンガーを持った彼が綺麗にかけてくれる。いつ私が来てもいいようにと、確実に歓迎されているかのようにこちらへ向いているスリッパに足をかけてリビングへと進んでいけば、ダイニングテーブルには女である私の気が引けるくらいに立派な和食仕立てな夕飯が並んでいる。最初のうちは驚きのあまり自分も料理サイトを見て研究してみたりもしたが、それももうしなくなった。慣れとは人を駄目にしていくものだ。 「好きやろ?出し巻き。」 「あー、まあまあ好きかな。」 「可愛くできひんのか。」 「それを求めてるなら私はお門違いでしょ。」 それもそうやなって、胡散臭い関西弁で切り抜ける忍足も私の交わし方をよく心得ていて、だからこそこんな関係も継続できているのだろう。彼は私の性質をよく知った上で、私を放し飼いのように飼っているのかもしれない。放し飼いのように見えて、家の中でだけ自由にできるリードを付けられたように、私も居心地が悪くないそこを永遠とうろうろとしている。 こんなどうしようもなく曖昧な関係を作り出したのは、私が勝手に恋をして、自爆したように勝手にその恋が終わった時と同じ時だった。あの時忍足が来ていなければその残酷な結末を知ることももう少し後に引き伸ばされていたかもしれないけれど、彼がいなければ私は混沌とした闇しかない世界から這い上がることはなかっただろう。今でさえ、その闇から陸に上がりきっているかと言えば微妙な所でしかないが、確実に必要な存在だった。 十五年近く好意を寄せていた男に振られた訳でも、雑に扱われた訳でもなく、遠まわしにやんわりと遠ざけられた傷は、今もまだ絆創膏では防ぐことのできない傷跡を残していた。傍から見ればこんなにも羨ましいと皆が口をそろえる環境を手に入れた、今でも。 「自分めちゃ疲れとるやん。何かあったんか。」 こうやって、私が面倒がる一歩手前の程よい気遣いで私を労ってくれるその言葉は生ぬるく、傷口をえぐって行く。 「何もないよ。ただ、最近残業多くてちょっと疲れただけ。」 「仕事変えたらええやん。」 「営業以外出来ないし、もう銀行業界からも離れられないし。」 「そう思ってるんやったら好きにしたらええけど。たまには甘えてみてもいいんちゃうか。」 「甘えるってどうやってやるんだろう。私、その作法知らないかも。」 こんな事を言えば、それを実演でもされるのだろうかと思ったが、一度眼鏡を触っただけで、特にこちらに寄ってきて抱きしめるわけでもなく、甘い言葉をささやく訳でもない。それを望んでいないと分かっている私を傍に置き続ける彼も体外な変人だ。そのルックスや財力、気遣いも含めて間違いなく女からモテるであろうに何故だろうかと不思議に思うほどに。 彼の作った料理を前に、箸を掴んで迷わせる。彩りだけでも食欲をそそるその料理はいつだって美味しかった。唯一料理レシピを見ることなく作れる私の自慢料理であった出し巻きですら、遥かに私が作るものよりも美味しくて時折腹立たしく思った。知らぬこととは言っても、出し巻きを私に出してくるなんてなんとも憎い男だ。 一年前、幼馴染の慈郎に彼女がいると分かった夜。私の隣にいたのは忍足だった。弱った私を押し倒す訳でもなく、からかうでもなく、ずっと黙って傍にいてくれた。彼と初めて寝たのは、それから数ヶ月経ってからの事だ。 「なあ。」 「ん?」 「これやるわ。一応、誕生日プレゼントな。」 「知ってたんだ。さすがだね、忍足は。」 「他人行儀やなあ。」 来週にまで迫っている私の誕生日に彼がチョイスしたのは、立派な万年筆だった。ここでアクセサリーなどを選んで渡してこないあたり、本当によく分かっていると思う。きっと私はそれを受け取った瞬間に彼の傍から姿を消すのだから。それを、知っているのだ。 いつだか営業先で安物のボールペンを使って恥をかいた事があるのだというさりげない言葉をこの男は覚えていたに違いない。策士とはやはり忍足の為にあるような言葉だと思った。主張しすぎないその万年筆は今の私にはちょうどよかった。 「センスいいね、ほんと。悔しいくらい。」 「長い付き合いやしな。」 「付き合いが長ければいいってもんじゃないでしょ。」 付き合いが誰よりも長かった慈郎の事を思い出して、自嘲してしまった。忍足よりも遥かに付き合いの長い慈郎は忍足よりも私を知らないだろう。 忍足と初めて寝たとき、半分私は自暴自棄になっていた。慈郎に失恋したと分かった時、十五年という長い年月をすべて彼に捧げてきた自分に絶望したのだ。確かにそれは恋に違いなかったけれど、私は意思疎通した恋愛を経験する事無く俗に言ういい年齢になっていた。一年前まで処女だっただなんて、口が裂けても周りには言えなかった。高校二年の時、告白してきた男と付き合っていれば私の人生は少しばかりは今よりもまだ明るい色を描いていたのだろうか。考えても意味がないことと知りつつも、考えざるを得なかった。 「暇そうやな。」 「暇だね。」 「俺と一緒におってそんな暇持て余してる女もそうおらんはずやけど。」 「じゃあ、きっと私は変わった女なんだよ。」 高校二年の夏、今のようなトーンで告白をしてきた男に、私はそれから何年も経って酸いも甘いも分かった大人になったのに、あの時と同じような曖昧な態度でいろんな事から逃げていく。人間は長い年月をかけたところで大した成長を遂げないらしい。 永遠に変わらない私の態度に対しても、忍足も永遠に態度を変える事無く私に接する。隙を見せればすぐに溺れてしまう私は必死にその波の中で孤島の陸に手をかけて抗っているだけなのだ。その先にあるのが幸せという名の、自分自身が最も望んでいるものかもしれないのにそこに手を伸ばすことに抵抗しかなかった。 週末になれば彼は私を呼び寄せたし、私も断る事無く自発的にそこへと向かう。ぬるま湯につかっているようなどっち付かずな態度で、今も、そしてこれからも。 「つれへん女や、は。」 「別に釣ってくれなくていいよ。」 「意味、違うやん。」 そっと抱き寄せられて、本当に私もひどく頭の悪い女なのだろうなと思う。彼は、高校二年の夏以来、そのときに告げた同じ言葉を告げてはこない。私は、彼の彼女ではない。それを言わせまいとする私にいつ隙が出来るのか、きっと冷静に分析しているのだろう。 忍足を知る学生時代の友人達からは、は馬鹿だと言われるけれど、きっと世間様から見ると本当にそうなのだろう。慈郎という名の海老で、忍足という皆が手に入れることの出来ない鯛を手に入れることの出来る環境を持っているにも関わらず、私はまだ釣竿を垂らしたままだ。 けれど思うのだ。海老の方が自分にとって価値があるものなのか、鯛の方が価値があるのか、美味いのか、それは個人の主観でしかないのだから“海老で鯛を釣る”なんて言葉は結局のところその言葉を考えた人間の感想なのだ。 どちらが自分にとって価値の高いものなのかは主観でしかない筈なのに、私という物語の主人公である私が一番その価値を図りかねて、答えを出せないでいた。
|
