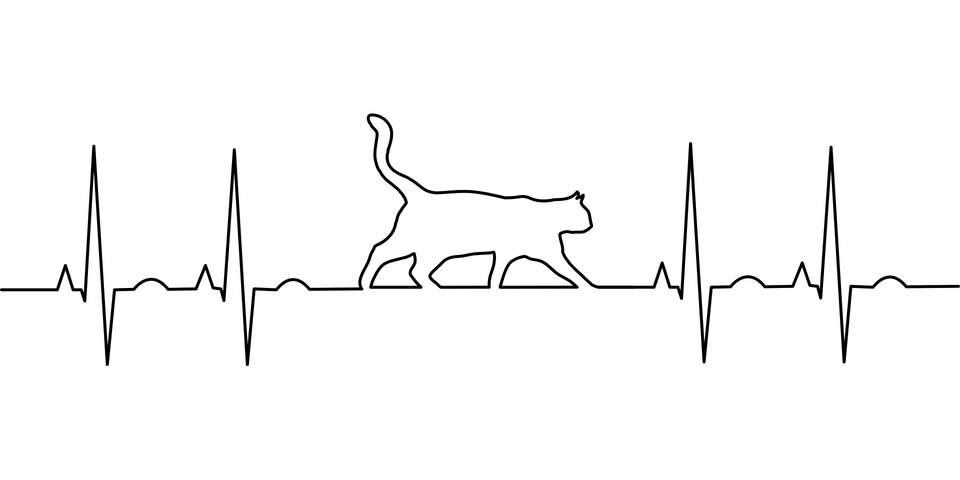 何故かは知らないが、あいつは気づくと俺の近くにいる事が多かった。 中学を卒業して、高校へ進学するつもりはなかった。 中学だって別に行きたくて行っていた訳でもなければ、ただ“義務教育”というくだらない制度の下に仕方なく通っていただけだった。 そこで自分自身の居場所を見つけられたのは思いがけない幸運ではあったけれど、それを手に入れてしまえば別に新しいものはいらない。くだらない“義務”の課せられた教育も中学で終わるのだし、勉強は得意な方だった。高校へと進学しても自分の能力にはふさわしくない学問を受けるだけで、高校に行かずとも行っている奴よりも勉強ができない気はしなかった。 季節は初夏、もう時期に俺も十八になる。早く大人になりたいと思った。この世の中は大人のほうが何かと都合がよく、未成年というのは面倒だった。 高校も三年、あと何ヶ月かすればそれこそ学生を終わらせることが出来る。ある意味、こんな生活を終わらせるそのエピローグの日が一刻と近づいてくる事に楽しみを寄せていた。 「あ、獄寺くん。おはよう。」 「いちいち話しかけんなよ。」 「なんで。別に朝に会ったら挨拶するの普通じゃん。」 「偶然あった風に言いうな。」 高校を出ることによって困る事はないから進学した方がいいんじゃないかと言う十代目の言葉で進学を決めたものの、肝心の十代目と一緒に受けた高校は俺だけが受かって離れ離れになった。同じ中学から知り合いと呼べるレベルの会話をした事がある人間で、同じ高校へと進学したのは一人だけだった。 「物好きな女。」 「そうだね。でも獄寺くんだっていなくて、私いなきゃ一日口開く機会ないと思って。」 「余計な世話だわ、まじで。」 早起きは別に嫌いじゃないし、苦手じゃなかった。家にいてもする事もないし、どうせ学校に行くのだから早く行ったところで別に害はない。鞄を机に置いて屋上で転がりながらタバコをふかすのが俺の日常だった。“高校生”というのは大人というカテゴリーには分類されていないのだから、堂々と吸うこともできずこうするしかないのだから未成年は本当に面倒くさい。 「単純に好きなんだよ。」 「はあ?」 「煙草の匂い。好きなんだと思う。」 「お前奇人って言われないか。」 「言われた事はないけど、変わってる部類だとは思う。」 毎朝飽きることもなく屋上へ来て、偶然会ったかのように挨拶をしてくるこの女を面倒と思ったことはもちろんあるが、自分自身がどこかに移動したり、癇癪起こして怒鳴り散らすこともなかった。 居心地がいいと思うわけではないけれど、それを虐げる程に居心地が悪いわけでもない。よく、分からない女だった。 「死んだ父さんが煙草吸ってたから、懐かしいのかな。」 「ファザコンかよ。」 「別にファザコンって訳でもないだろうけど、ないもの強請りじゃん?」 「そういうもんなのか。」 「多分そんなもんだよ。人間なんて結構単純。」 返事をする事もなく、もう一本煙草を取り出して加えると、あいつもコンクリートに地べたをついて座っていた。何をする訳でもなく、ただ空気のように気が向いたときに少しだけ会話を交わすだけだ。 「なんか獄寺くんって、いつも気だるそうだよね。」 「実際気だるいからな。」 「中学の頃って、もうちょっと楽しそうだったけど。」 「何かの見間違いじゃね?」 確かに中学の頃は今よりも少し騒がしい日常だったと思う。面倒と思うことも今以上に多かったけれど、振り返って思うのは悪くなかったという感情だったのかもしれない。 中学時代に経験した事は、人生の中でも間違いなく一番色濃い時間であったのは違いないだろう。いろんな事が日々あちらこちらで勃発していて、正直ついていけない事もおおかったけれど、一番生きているという当たり前の事を実感する時期でもあった。 十年後の世界に行き、壮絶な経験をしてきたからこそ何だか物足りなさを感じているのもまた事実だった。未来に行った時に何より縋り、目的としていた事は、平和なこの時代に戻るという事だったはずなのであれだけの出来事を経験した後にもどってきた現実はあまりにも退屈に思えることの連続だった。 「周りも受験受験って一色に染まってるし、なんか自分も受験したほうがいいのかなって錯覚する。」 「そう思うならすりゃいいだろ。」 「まあそうなんだけど。うち母子家庭だしお金ないし、でもここ進学校だし。」 「別に周りに合わせて生きてく必要なんてない。」 「そうなんだよね。だから周りに合わせて生きてない獄寺くんの傍は落ち着く。」 「は。俺からしたらそんなもん愚問でしかないわ。」 思ったままの感情を吐き出せばあいつは「そうだよね。私もそう思う。」と苦いわけでもなく、カラっとした清いわけでもない笑みを浮かべて風にそよぐ煙草の煙に鼻を動かしていた。 周りに流されそうになっているとは思えないような女だったが、そんなあいつでも周りに合わせて悩むこともあるんだなと俺には知りえない感情に少しだけ気苦労をねぎらう気持ちを覚えた。人は誰しもその規模に関わらず小さいなり大きいなり悩みを抱えているのだなと改めて思う。 「でもさ、獄寺くんも何かに囚われてるよね。中学の頃から、ずっと。」 何のことを言っているのだろうかと一瞬考えて、ふと蘇るものがあった。別に誰に話した訳でもない、本当にくだらない昔の話を思い出した。 日本に来た時から、ずっと晴れない事があった。 それは十年後の世界に行って、姉貴に真実を聞かされたあとでもしっくりと腑に落ちない自分自身の出生の事だった。頭では理解が出来ても、実際のところまだ気持ちの部分で本当の消化が出来ていないのだろうか。 「なあ、お前不倫ってどう思う。」 「不倫?何、私と不倫したいの?私まだ独身だからまずは結婚してからじゃないと出来ないな。」 「…聞く相手間違えた。頭沸いてるだろお前。」 こいつはやっぱり変な奴だと思う。変な奴である事は事実だから罵る事に何の後ろめたさもないが、それでも平然と顔色ひとつ変えずに飄々としているのだから余計に変な女であるに違いない。UMAとはでは行かないにしても、やっぱり普通ではない。 他人の事を変な奴と考えてはいたものの、わが身を振り返ったときに自分はどうなのだろうかとふいに思って、俺ももしかしたら同じような部類の人間なのかもしれないと考える。今よりももっと若い頃、一例を挙げるのであれば中学の頃の自分だったら間違いなく否定して反発しただろう。どこが変なのだ、自分は至極普通なのだと言い張るに違いない。そうじゃないと気づくまでには随分と時間がかかった。 「別に詮索するつもりもないし、否定するつもりもないけど、きっと獄寺くんの家庭の話なんだろうね、それ。」 「それを詮索してるってお前知らないのか。」 「詮索してないよ。聞いたんじゃなくて、言っただけだもん。」 言われて初めて、こいつが傍にいても億劫じゃない理由が分かった気がした。回りの人間は色んなことを詮索してくるものだと、そう思っている俺の固定概念だ。確かにこいついは何かに対して追求してきたことは今まで一度たりともなかった。 「獄寺くんさ、学校の前のたこ焼き屋さんの角の家知ってる?」 「猛犬注意のシール大量に貼ってるあれか。」 「そう、それそれ。」 街中の事なんて普段気にする事のない俺でも知っている事だった。たこ焼き屋は下校時間によくうちの生徒で賑わっていたから嫌でも目に付いたが、俺にはそれよりもその先にある“猛犬注意”が大量に貼られている家の方が記憶の中に残っていた。犬を飼っている家が義務付けて貼らされる犬のシールが何枚も更新されるように羅列されていたから、大量の犬を飼っているのか、猛犬注意と貼っているだけあって一匹の犬が強靭な生命力で長生きしているのかどちらなのだろうとどうでもいい事を考えたことがあった。 「でもさ、あそこから犬の姿とか鳴き声って聞いたことある?」 「あー、そういやないかもな。」 「私気になってさ、たこ焼きの店員さんに聞いたことがあるんだよ。」 あれだけ煌々と光るシールを貼っているにも関わらず、その主を見かけた事は確かになかった。けれど、それを不思議に思ったことはなかった。関心がなかったからと言えばそれまでだ。実は猛犬と呼ばれる犬が態のいい室内犬だったのかもしれないし、老衰していて声もなくひっそり生きていたのかもしれないし、はたまた元々犬なんていなくて防犯のためにそうしていただけなのかもしれない。目を引くだけで知ってはいたものの、結局は興味がなかったのだと気づく。 「もうね、十年も前に死んじゃったんだって。」 そう言われたら、ああ、そうなのかとそれだけのことなのだと思えた。それ以上追求する気にもならなければ、気になることもない。 「だから同じなんだよ。」 「何がだよ。お前まじで意味わかんねえ。」 「だから、関係ないんだよ。」 やっぱりこいつは頭が可笑しいのだろうかと思う。螺子の一本か四、五本抜け落ちているのだろうか。会話のつながりの銅線を見つけることがどう頭をひねっても出来ないのだからきっとそうなのだろう。 「例えば不倫の末に生まれた子だろうと、未成年なのに屋上にバカスカ煙草吸おうが、関係ないんだよ。」 「表現に悪意しか感じねえが。」 「そう?でもさ、猛犬注意のシールと全部一緒なんだよ。」 そこからやっぱりあいつは特別何かを言うわけでもなく、懐かしそうに俺が吐き散らした灰色の煙に鼻を動かせて懐かしそうにしているだけだった。 特別する事もなく暇だったから、その言葉の意味を考える。考えたところであいつの真意が何だったのかは分からないが、全てはどうでもよく思えた。昔から何もかもどうでもいいと目の前の事を流してきてはいたけれど、それよりももっと軽い気持ちでどうでもいいと思えた。 「煙草の匂いに懐かしさを感じなきゃ私こうして獄寺くんと話してなかっただろうし。」 「頼んだ覚えはないんだけどな。」 「そうだね。でもさ、それがなければこうはならなかった。煙草を吸うのが未成年にとっては悪とされてるけどだからこそ今こうしてお喋り出来てるんだし、私はよかったと思うよ。世の中には特別な意味を持ちながら、特別な意味もない事があるんだよ。全ては、当たり前の事なんだから。」 言っている事は支離滅裂で、こいつは進学校であるこの学校でも上位に食い込む成績を持っているらしいけれど、やっぱり頭が悪いのだと思う。 「やっぱお前、奇人だわ。UMA一歩手前。」 「じゃあ獄寺くんの興味対象の一歩手前だ。」 「UMAなめんじゃねえ。」 別にこの言葉に救われることはなかったし、やっぱりあいつの言っている事に完全なる理解はできなかったけれど、なんだかすべてがどうでもよくなった。それは投げやりなどうでもいいという感情ではなく、何故自分はこんなちっぽけな事に長年縛られ、そして囚われてきたのだろうかと。事実は知ったところで変わるわけでもなく、ただそこに当たり前に存在していているのだから。 俺は今の環境が気に入っている。常に一緒にいるという訳ではないが、居場所は出来た。それは、俺が今まで歩んできた時にろくでもない道を歩まなければ遭遇できなかったものだ。 それに意味があったと言えば相当な意味と理由はあっただろうけれど、意味のない事と言えばそうでもあるような気がした。過程ではなく、今というこの時空が“現実”というのが全てなような気がした。 「あ、でも煙草は出来れば辞めて欲しいな。」 こんなやっかいな事を言って俺の頭を悩ます人間は、そういえば十年後の世界にはいなかったなとふいに思う。いきなり十年後にワープしていた事があるなんて非現実的な事を言うつもりはなかったから言わなかったが、こいつなら信じたのだろうか。 「そんなの決断するまでもねえわ。」 こんなやっかいな女がいたらそれこそ本当の右腕になんてなれるはずもないのだから、十年後の世界でこいつがいなかったのはそれこそ至極真っ当で、未来に起きえる“現実”なのかもしれない。 他のパラレルワールドでも、どうか俺の近くにこの女が居ないようにと、少しばかり願う。 「案外義理堅い男って知ってるんだけどな、私。」 「の思い過ごしだろ。」 未来が決まっているのであれば、こいつとのこの会話も俺に必要な過程だったのだろうか。 分かりはしないけれど、それを否定する気にもならなかった。 ghost fragment |