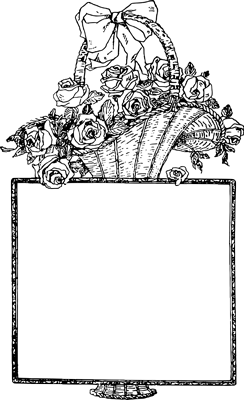 あいつが旅支度をすると言ってから、四年以上の年月が過ぎ去っていた。 俺自身あまり過去を振り返ることはしない。あの時こうしていれば――、もしも違う道を選んでいれば――そんな“たられば”を言った所でそこからの軌道修正ができる訳ではないのだから必要がないと考えているというだけの事だ。それ以上でもそれ以下でもなく、後悔したところで新たに生まれるものなど何もない。 この考え方はきっと俺の生まれや育ちが大きく関係しているのだろう。心を無にして生き、そこに理由は必要ない俺たち忍にとって後悔という感情は存在せず、また未来もない。あるのは、標的とされる相手を如何に効率的に射止め、殺すかという計画を考える能力だけでほかの物は邪魔なものと見なされる。 そんな俺に反して、はよく後悔を口にする女だった。 あの時こうしていれば、というのはあいつの口癖だ。過ぎ去ったものに拘った所で先を見るしかない俺たちにとって邪魔でしかない感情だと最初のうちはあまり快く思わないきらいがあった。 「過去を悔やんでばかりいると次に死ぬのは自分だと思った方がいい。」 「確かに、本当にそうなのかもしれない。」 比較的物分りのいい女ではあったが、人の癖というものは簡単に直せるものではないらしい。幼少期と呼ばれる頃には既に人格がほぼ形成されるのだからこの歳になってそれを直せと言っても難しいのだろう。俺が元来持ち得ていた考え方を変えることが出来ないのと同じだ。 「天元みたいに表面上で割り切れる大人に私もなれたらいいのにな。」 俺が柱を引退し、一線を退いてからすぐに聞いたその言葉を最後には過去を振り返らなくなった。そして局面は最終決戦を向かえ、全てを終焉へと誘った。千年続いた変わらぬ世が変わった瞬間だった。 柱ではないながらも俺とは違い第一線で活躍の場を設けたあいつは憑き物が取れたようにすっきりとしたかんばせで俺の前へと戻り、そして未来を語った。酷く短絡的で直近な未来を。 「一つだけやりたい事あった。思う存分、呑みたいな。」 あいつが過去を見ず、且つ自分の願望を口にする事はあまり見た事がなかったのだから少し驚きはしたがあまりにも簡単に叶ってしまうその近い未来の願いを叶えるべく俺たちは日が昇る街を後にして帰るべき場所へと歩き始めた。 そこからの四年の月日は、長かったようにも感じられて実際酷く短くも感じられた。 おそらくそれは捉え方の問題なのだろう。ただ過ぎ去っていく四年と、猶予や期日を設けられている四年というのは他人から見れば同じでも当人である俺たちにとってはまったく持って違う意味を果たしていたのだと思う。 全てが終わってから俺たちはすぐに旅に出た。旅なんて大げさに言ってはみたが、あくまでそれはその事象をより大きく、そして特別であるように誇張しただけの小さな散歩のようなものだった。過去の任務で訪れた宿の温泉が思いのほかの広く、居心地がよかったという事をがふいに思い出したというだけの事だ。思い立ったが吉日、俺たちはすぐに少量の荷物を纏めて“旅支度”を済ませその足で目的地へと向かっていた。 里にいた時も鬼殺隊にいた時も一般の人間と比べると自由というものに乏しかった俺は、柄にもなくこの暇を持て余していた。出てくるのはを労う言葉や、愛の言葉ではなく、どうでもいいその場の感情や戯言だ。いつもであれば何てことなく出てくる会話に少しばかり苦戦しているのだから妙な感じだ。 温泉旅行を提案してきたに、何の深い意味もなく聞いてみる事にした。 「そういやお前人に提案するくらいの余裕なんだ、自分のやりたい事は見つかったのか。」 「あー、うん。まあね。」 「…なんだよ、勿体ぶりやがって。」 「そりゃ、ない知恵捻って考えた事だから勿体ぶりもするよ。」 何を勿体ぶることがあるのだろうかと思いつつも、こんな無駄な会話一つも平和が齎しているものなのかと思うと不思議と心が休まるような気がした。実際、呼吸も使わずゆっくりと何も考えずに歩を進めているその隣にあいつがいるだけで心が満たされた。言葉にするのは、何かと難しいのだと思い知る。 「旅支度、するんだ。」 的を得てないその回答に、俺は腕組みを解いてあきれた様に視線の随分と下の方に映るに焦点を合わせて口を開いた。 「さっきしてばっかだろ。」 「違うよ、自分の人生の旅支度。」 聞き返しておいて、俺は次の言葉を瞬時に紡ぐ事が出来ず黙ってしまった。のその言葉が何を指しているのかに気づいたからだ。至極真っ当な言葉に反して、全身がひやりと少し冷えるような感覚を覚えた。 きっと、否間違いなく自身の痣の事を言っているのだろう。ある一定の規定とされる二十五という数字に向かってのの決意表明のようなものだった。 「未来を生きるためには、大事でしょ。」 遠慮ぶったようではなく快活に笑顔でそう言ったの言葉が四年経った今でも鮮やかに蘇る。 それからはああしたい、こうしたいとはよく願望を口にするようになった。その願望ともいえる提案に俺自身否定的な要因もなく、何よりのしたい事成し遂げたい事がいつしか俺の願いにも通ずるようになっていた。 いつだって活発的で弱音を吐かないと過ごした四年はあっという間に過ぎ去り、そして現在へと至る。足を止め、床に伏せる事が多くなったのはここ数ヶ月の出来事だった。 「ねえ。」 ここ最近は以前に増して縋る様に甘えてくる事が多くなった。鬼殺隊にいた時には考えられないような、そんな姿にきっとあいつを知る人間は驚くだろう。甘えろと言った所で素直にそれが出来なかった昔のは、もうここには居なかった。 「次は何の要望だ。」 「ひどい言い方だなあ。要望じゃなくて、提案っていうんだよこういうの。」 「ならさっきも使ったから今日はあと一つな。」 「大きい図体してケチだね。」 人を小ばかにした様に突いて来るその言葉とは反比例するように口調は酷く弱弱しい。まるで虚勢を張っているようなそんな姿にすぐに手を差し伸べたくもあるが、しっかりとの言葉をこの耳で留めて置きたいと思った。 「天元は頭いいけど学校行ってなかったから“修学旅行”って知らないでしょ。」 「なんだそれ。」 それは明治になってから新しい試みとして出来た旅行なのだとは言う。同じ学問を学ぶ同級生と一緒に出かける旅行の事を指すらしく、主に何を目的に旅行をするのかと尋ねると急に考え出すような仕草をして悩んでいるようでもあったがぽろりと口を出た言葉に思わずため息にも近いような言葉を漏らしてしまう。 「なんだろう…枕投げたりして親睦を深める感じかな。」 「枕投げて親睦が深まるなら冨岡に投げまくってたわ。」 「義勇と親睦深めたいって気はあったんだ。意外。」 「御幣しか感じない。」 力なく笑ったに、俺も言葉とは裏腹に想像して少し表情筋が緩まったような気がした。修学旅行というものは随分と下らなく意味のないものなのだなと感想を述べると、も続けるように確かに本当に今考えると下らないかもしれないと同じく賛同した。 「前みたいに今は旅行できないけど、二人で修学旅行風なら出来るかなと思って。」 過去を振り返る事もなく、ただ前向きに事を捉えるのその言葉がどこまでも深い意味を持っていて、緩んだ筈の筋肉が少し強張るような気がして、それを打ち消す慣れた口調で「阿呆。」と一言添えた。 少し前に冨岡が死に、続くように不死川も死んだ。 予期もしていたし、準備も覚悟もしていたつもりだったが不完全燃焼のまま俺はまだその事実を消化し切れていない。もちろんそれは同じ柱として戦った戦友として無念に思う側面も強かったが、何よりその事実がの未来にも通ずるものがあるという印象を拭えない事への感情のほうが強いように思う。 同じ宿命を宿したが俺は愚か他の誰よりその事実を受け入れがたく、恐怖である事は違いないが、二人の死を事実として理解しているはそれ以降もその話を持ち出すどころか自暴自棄になる事もなく過ぎ去る情景のように触れる事はなかった。 過去を振り返らないという己との誓いを体現しているのだとすれば人間として尊敬に値する事象でもあるが、何よりその事実をしっかりと噛み砕いて消化しているのかと思うと何もしてやる事の出来ない自分の不甲斐なさと、愛おしさでの提案より前に俺が先に動いてしまうのだから本当に適わないと思わざるを得ない。 「……修学旅行は、こんな事しないけどな。」 「なら項目に追加しておけ。」 以前よりも一回り小さく感じるをすっぽりと覆い隠した。過去を振り返っても仕方がないと言っていた自分がこの時ばかりは過去を悔やんでしまうのだから本末転倒だなと思いながらも、温かみのあるその体を片腕だけでなく両の腕で包む事が出来ればよかったのにと柄にもない事を考えた。 ―――一緒に昼寝しよ。なんだかすごく、眠いんだ。 添い寝を要求してきたの傍に俺も同じく横になると、最早甘える事に抵抗を無くしたのか手を伸ばして「ねえ。」と聞きなれた提案前のその合図となる言葉が耳に木霊する。その先に続く言葉を待たずして今日はこちらに手繰り寄せた。 あまり見せないような少し不安げなその表情に、俺は確かにこの耳に蔓延るの心音に合わせて背中に手のひらをポン――ポンと重ねた。 ―――ちょっと昼寝して、起きたらご飯一緒に食べよ。 あえて未来を語る事で笑顔を取り戻したは子守唄でも聞く童のようにすぅと目を閉じて、眠る前の挨拶を告げた。――おやすみ、天元。 鼓動に合わせて触れていた俺の手は、時間が経過するごとに緩やかになり、そして暫くして完全に止まった。 本当は、今日がその日になるのではないかと薄々感づいていたが、今日ばかりはその直感を信じたくないと願った。自分の幕引きをきちんと心得ているからの言葉一つで、直感などなくとも概ね想像はつくのにそれを認めたくないのは俺自身のただの我侭だったのだろうか。 の提案は、もう金輪際二度と聞く事が出来ないのだとぼんやりとした脳で理解をすると、包み込むようにして抱いていたを力の限り手繰り寄せた。 不安を感じさせないようにといつもどおり余裕がある自分は所詮演じていたものなのだと今更ながらに気づく。寧ろ余裕がないのは、きっと俺のほうだった。提案をしてくるを存分に甘やかせてやる事はできても、俺から縋るようにを求める事は出来なかった。そうする事で、終わりを受け入れられなくなると確信していたからだ。 の体がまだ自由に動いていた頃に一度だけ耳にした言葉があった。 過去を振り返るのは嘆いているのではなく、未来に繋げる為なのだと。 過去に囚われない筈の俺が、この先未来を生きながらも過去を振り返るのだとすればのおかげであって、のせいなのだろうと思う。 過去があって未来があるという学びを俺に体現したその存在を映し出す事で、初めて流れ出る何かを感じ取った。
|