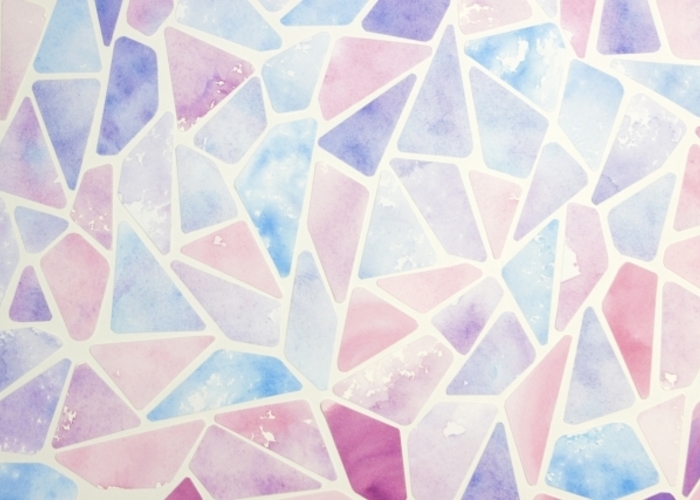 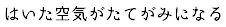 一、 最初は、なんて愛想のない女なんだろうかと思っていた。 何を頼んでも返事は一緒だ。「はい。」か「いいえ。」の二択しか選択肢がないのかと思ってしまうかのように、酷く機械的に感じる。仕事をする上で、別に感情なんてものは必要がないと割り切ることの出来る俺にとっては、不思議に思いながらもあいつに仕事を頼むのは然して苦痛な事ではなかった。 議事録を取らせてもそこそこ八十点くらいのレベルには仕上げていたし、エクセルの関数もずれていることが稀にあったが九十点はあげてもいいだろう。その十点、十五点足りないのが、いかにもあいつらしいのかもしれない。 「関数治しておいた。今度から気をつけろ。」 「部長の方がエクセル得意なんですし、部長がやればいいじゃないですか。」 「人には役割ってもんがあるんだよ。俺は忙しい。」 「私のことを随分と暇人みたいに言うんですね。」 入社して一年が経ったころ、あいつは以前よりも話すようになった。日常的な会話が少しだけ交わせるほどになったというだけの小さい成長だった。話すというよりは、基本的に俺に対する不平不満の類のぼやきだ。 「土方さんって、彼女とかいないんですか。」 「何だその同僚に話しかけるみたいな喋り口は。舐めてんのか。」 「いや、単純に気になったから。」 言われて、馬鹿馬鹿しいと思いつつもそう言えば彼女と呼ばれる存在がいたのもどれくらい前のことだったかと指折り考えるほどにそれは遠い昔のことだった。別に特別欲しいと思っているわけではなかったけれど、指を折らないとそれを思い出せないほどにそんな存在がいない自分自身を少しみっともないと思った。 「お前に言う義理もないだろう。」 「不倫、ですか。」 「お前の耳を俺は今心配している。」 「優しいですね、部長。」 そう言った後に、「美形で仕事が出来てお金もあるなんて三点拍子揃ってるんですから不倫は辞めたほうがいいと思います。」と澄ませたかんばせで言ってくるに俺は押し黙って、再びパソコンへと向き合った。 俺からの明確な返答がない事に観念したのか、も大人しく仕事を開始していた。周りから恐れられ、滅多に人が寄ってこない俺に対してこんな態度をとるのはこの女くらいなものだろう。 もうすぐ、あいつが入社して二年目になろうとしていた。 二、 繁忙期ともなると、部長職は忙しい。適当に仕事を切り上げて、俺は社食へと足を運んでいた。普段であれば別に昼飯を一食抜いたところで死ぬわけでもないのだから食べないという選択肢も大いにあったが、今日の業務量を思い出すと終電前で帰ることになりそうだった。今を逃すとタイミングがないと、渋々自分の腹を満たすことに対して大切な限られた時間を潰していた。 さっさと食事を済まして一刻も早くデスクへと戻ろうと、一番早く食べれそうな食べ物が並ぶそのブースで俺の足は止まっていた。これなら五分と持たず食べ終わるだろうと、そんな事を考えていたと思う。 三百円を払うと十円がお釣で帰ってくる。そんな小銭を受け取るのも面倒なのだからもういっその事税込み三百円にすればいいのではないかと少し苛立ちを覚えたころには、俺の手元に注文されたそれは湯気を上げて飛んできた。 「ああ、土方さん。」 「…友達じゃねえんだ。部長と呼べ。」 「今日はお昼、食べるんですね。」 「今のうちに腹ごしらえしておかないと今日は遅くなりそうだしな。」 俺が何度役職で呼べと言った所で、すぐに忘れたように馴れ馴れしく俺の名を口にした。もう言い直すのも面倒とあきらめて自分自身の皿を引き寄せ、割り箸を割って手をつけた。 「うどん、好きなんですか。」 「嫌いじゃないが特別好物って訳でもない。」 「私は好きですよ。さっさと食べれるから。」 「時間が有り余ってるお前には珍しい意見だな。」 「さっさと食べて、定時で帰りたいですもん。」 ああ、なるほどなと思う。は極力残業をしない。もちろん必要とあらば残るときは残るが、他の人間に比べると圧倒的に少ないと言えるだろう。もっとも、それがやるべき事を放っておいて定時だからという理由で帰っているのであれば怒号のひとつでも上げているところだが、彼女の場合それは違っていた。どうしようもなく要領が良いという訳ではないが、きちんと定時になるまでに終わらせるべき事を成しているという理由に他ならない。俺は、そんなの仕事ぶりを買っているところがある。 「部長にはうどんって最適なパートナーですよね。」 「俺のパートナーを勝手にうどんに置き換えるな。」 「だって効率的な食べ物だし。うどんみたいなツルっとした女性いたら紹介しますね。」 「そりゃあ、どうも。」 まともに聞いていたらそのまま俺の大事な時間があっという間に過ぎていきそうで、ずるずると麺をすすることに集中した。急に飛び込んできたうどんに胃が驚いたようで、もっといたわって欲しいと言われているようだった。俺はスープを飲み干すことなく、空になったうどん皿を載せたトレイを戻すべき場所へと運ぶため席を立った。そうすれば、も俺と同じく空になったうどん皿を持って席を立った。 特に会話はなかった。もともとはお喋りな方ではない。たまに悪態ついたように話しかけてくることはあるが、基本は大人しい。時折そんな会話をするくらいの関係が、どこか心地良い気がしていた。 三、 あいつが入社してきて丸二年。ちょうど三年目になった時、俺は三十路になった。別に女でもなければ、年齢を気にするような柄でもなかったが、二十代から三十代になるという事には少しばかり考えることもあった。二十代で部長まで上り詰めたと周りからちやほやされていた時期もあったが、もう三十だ。より一層に気を引き締めないといけないなと自分自身にリマインドをかけた。 がこの企画に配属されてもうそれなりの時間が過ぎていた。ここ最近は、八十点だった議事録も、九十点だったエクセルも、ほぼほぼ満点近くまで完成度を上げていた。キャラクター的には目立たず、仕事嫌いに見えるかもしれないが確実にあいつの仕事に対する効率は向上していた。 春の人事異動で、久しぶりに企画に新しい顔ぶれがあった。俺自身が営業だったときに、そこに同じくいた原田という男だ。特別何かを必死にやらなくても頂点を取れる、才能に秀でた男だった。営業として入社して三ヶ月も経った頃、あいつは既にトップセールスになっていた。すごい新人が入ってきたものだと思っていた頃、俺は昇進して企画の部長職についた。元々営業課と企画の課長を兼任していた俺は、完全に営業から足を洗った。 「よう、土方さん。なんか久しぶりだな、一緒に働くの。」 「そもそもお前とは数ヶ月しか働いてないだろ。」 「そうだっけか。何だかんだ、入社してばっかの頃は土方さんに聞いてた気がしてな。」 「よく言う。人のナレッジだけで這い上がったくせしてな。」 「何だ、それ。褒めてんのか。」 調子のいい奴だなと相変わらずの原田を見て苦笑はしたものの、自分の部に来てくれるとなればかなり頼もしい存在で正直ありがたい人事異動でしかなかった。きっと原田ならすぐに仕事にも慣れて他の社員を先導してくれるだろうと思った。役職を与えずとも、俺とは違って原田の周りにはいつだって人だかりが耐えない。その裏表のない性格も、ここには必要だったのかもしれない。 少しだけ肩の荷が下りた気がした。たまたま一つ空いていた一番端にある席に、荷物をまとめる様に告げると原田はダンボール箱一つを手に持って、そこにどかんと置いた。の、隣なら心配もないだろう。 「、お前には原田のサポート業務にも入ってもらうと思う。頼んだぞ。」 「わかりました。」 いつかに見た、あいつのかんばせと合致して見えた。 ここ数年、新しい人間が入ってくることもなかったのだから、そんな事も俺は忘れていた。いつだって俺に悪態をついてくるその女は、その人見知りの本領を発揮しているかのように一度よろしくお願いしますと会釈をして、何事もなかったかのように自分の業務に戻り、いつも以上にパソコンに見入っていた。 「だろ?隣なんだし、もう少し歓迎してくれてもいいんじゃないか。」 「…別に歓迎していない訳ではないです。」 ちらりと、原田を見てそう一言告げるだけに留まっていた。 俺と、は似ているのかもしれないとそう思う。わざわざ人が集まるところへと、自ら歩み寄ることはしない。結局、俺もあいつも一人ぼっちなのかもしれない。そんな所が似ていたところで、特別に何も得はしないのだけれど。 俺が席へと戻ってからも、原田は大して話したくもなさそうなを面白がるように話をしていた。うるさいと声を上げればそれまでの事ではあったが、引越しの作業が終わるまではそれも多めに見てやってもいいだろうと放っておいた。原田の参入で、企画は少しだけにぎやかな舞台になってくような気がした。 四、 原田が企画職についてから、数ヶ月が経っていた。やはり俺が思い描いたとおり、少しだけ雰囲気がにぎやかになっていた。悪いことではなかったが、煩いと怒号を振りかざすことも多くなっていた。けれど、俺自身の仕事が原田の機転のよさと力量で軽減されていた。喜ばしいとも取れて、少しばかりの危機感も同時に抱かせてくれる俺には必要な存在だったのかもしれない。部長という職についている自分自身の気を引き締めるリマインダーとして大いに役割を全うしてくれていた。 少し暇ができれば、素っ気がないのが取り柄といえるにあいつは話しかけていた。面倒くさそうに話していたも、毎日の事になれて来たのか、俺と話すときと同じような態度を原田の前でもとるようになっていた。 ちょうど新入社員が原田の研修を終えて、うちの部に一人新しい新入社員が配属となった。にとっては、初めての部下となる女だった。 「部長、今度の会議で使う資料作っておきました。あと、この間の議事録です。」 「ああ。確認しておく。」 言ったことにしかその役割を果たさなかったは、俺に言われるまでもなく先読みをして必要なものを用意してくれるようになっていた。人は、変わる。こうまで機転が利くまでに成長するとは、当初思っていたなかったといい意味で俺を裏切るそんな仕事っぷりだった。 その仕事ぶりにも成長を感じたが、あいつは俺のことを土方さんと呼ばなくなった。どれだけ言っても部長とは呼ばなかったが、後輩ができた事によって自分自身の立ち居地を少し理解したのだろう。 二つ目は、以前よりも感情が豊かになったような気がしていた。今でも愛想があるとはけして言えないものではあったが、喜怒哀楽の感情が前よりもほんの少し濃くなったような気がしていた。それも、原田に影響してのことなのだろうかと思う。きっと、そんなあいつの変化に気づいているのも俺だけなのだろうけれど。 仕事が出来るようになったに、手直しを頼むこともなくなり、以前よりも俺たちは関わりが薄くなっていた。もっとも、俺が仕事を依頼する前に必要なものを用意してしまうのだから、その機会すら少ない。隣にいる原田と、主に話しているようだった。 あいつと関わることが減った分、原田と関わることが多くなった。仕事をする上で、幾分も数年前よりは効率よく仕事は回っていたが、何だか手持ち無沙汰な気持ちもあった。 こういう時、原田であれば自然と理由をつけて飲みにでも誘えるのだろうが、俺はそういう任には向いていない。ただ過ぎていく日常に、流されているばかりだった。 「土方さん、企画って飲み会とかあんまやらないのか。」 「それを開催する奴がいないってだけだろ。」 「本当は下戸だから、醜態さらしたくないとかそんな理由じゃなくてか。」 「冗談抜かすな。俺は飲めないんじゃなくて、飲まないだけだ。」 そんな事を言ってから、原田が主催する部署の飲み会が多くなった。さすが営業出身なだけあって、そういう手配がうまいなとつくづく思う。俺も営業出身とは言え、いつだって誘われない限り自分から人を誘うことはなかった。久しぶりに、と話してみるのもいいなと、少しばかりそんな飲み会に参加するようになっていた。 あまり毎度参加すると、部下達の憂さも晴らせないだろうと思い三回に一度くらいの参加に留めていたが、もそれは同じようだった。大勢の場が苦手なあいつらしいと言えばあいつらしいと思った。半期決算の打ち上げの時、久しぶりに飲み会に参加したとき、珍しくあいつもその席にいた。 「部長が来るなんて珍しい。」 「そういうお前だって珍しいだろ、。」 「私は部長と違ってお酒強いので。」 「どいつもこいつも俺の事なんだと思ってやがる。」 不機嫌面でそうは言いつつも、俺の気分は悪くなかった。あいつとまともに世間話をしたのは、とても久しぶりだった。少し前まであったその日常が、取り戻された事に機嫌がよくなったのか、柄にもなく珍しく俺も人並みに酒を飲んでいた。楽しいと少しだけ感じる思いだけで、酒が俺を酔わすこともこの時ばかりはなかった。皆が酒の場が好きだと思う理由が、ほんの少しだけ理解できたような気がした。 五、 たまに行われる、飲み会に顔を出すようになって気づいた事があった。 あいつの隣には、いつも原田がいた。あいつが原田の傍にあえて行っているのではなく、それはその逆だった。原田が、の隣にいることが多くなっていた。仕事上でも直接関わりがあるのだから、当然のことと言えばそうなのかもしれない。前にもまして、あいつの感情が豊かになった気がしていた。 あいつが入社して丸三年が経とうとしていた頃、一つの噂話が俺の耳を掠めていた。二人が付き合っているという、そんな事だった。 考えてみれば違和感はない。原田は確実にの事を気にかけていただろうし、あいつもあいつで原田と一緒の空間にいるのはこちらから見ていても居心地が悪いものではないと理解できたからだ。 「、この間の資料赤入れしといたから刷りなおしてくれるか。」 「分かりました。これからやります。」 いつからか、あいつに仕事を振るのは俺の仕事ではなく、原田の仕事になっていた。俺がそれを止めるのもおかしいし、止める理由すらないのだからただ黙って見ていた。たまに、いつだか俺とあいつがしていたようなどうでもいいやり取りが耳に入って、あまり気分がよくなかった。 「お前ら煩いぞ。さっさと仕事しやがれ。」 「部長もこんなくだらない会話聞いてるくらいなら仕事進めてください。」 「なんだ、殴られたいのか。」 「訴えますよ。」 その噂が誠であると認識したのは、その間もなく後のことだった。聞いてしまえば、二人が付き合っているようにしか見えなかった。帰る電車の方向が同じだからと、いつだって飲み会の帰り道はああでもないこうでもないと言いながらが少しむくれながら、原田はその表情をからかい楽しんでいるように見えた。ふいに、心がざわついた。 仕事も繁忙期に差し掛かり、俺はうどんを食べに社食に並ぶ。いくら原田からうちに来たからと言っても、繁忙期はその言葉の意味を成すように皆にも疲労の色が見えていた。今日も終電帰りだろうなと思い、いつだかと同じ状況にその列へと並んでいた。 うどんを持ってさっさと食べ干してしまおうとしていた時、数年前に見たあいつそのままの姿が、そこにはあった。 俺と同じきつねうどんを前に、ずるずると小さい口で太い喉越しのある麺を啜っているの姿だった。これだけ見ていれば、あの時と何も変わらない俺との姿のように見えた。気づかなかった事にして違うテーブルに着こうとした時、あざとくそんな俺に気づいたあいつは、同じような言葉を紡いだ。 「ああ、部長。今日も残業なんですね。」 「何も言ってないだろ。」 「部長がうどん食べる時はいつも遅くまで残業するって相場は決まってますから。」 反論しようもないその言葉に、俺も方向を変えてあいつのいるテーブルへと皿を置き、椅子に腰掛けていた。 「そう言えば、人から聞いた話なんですけど。」 何を言い始めるのかと思って聞いていると、思いもしない言葉を言われてしまった。以前のであれば、絶対に口にはしないようなそんな言葉だった。 「あったかいものって人をほっとさせるらしいですよ。」 「…何の話だ。」 「うどんですよ。うどんを求める部長は、きっと無意識にそういう物を求めてるんじゃないかな。」 いかにもあいつらしくない言葉に、返しに困る。まるでその暖かい何かに自分は満たされているとでも言わんばかりに、皮肉もなければ落ち着いた表情だった。それが、原田という存在だとでも誇示しているように見えて仕方がなかった。 「土方さんには、やっぱりうどんみたいに温かくてつるっとした女の人がいいですね。」 「相変わらずお前の言うことには理解に苦しむ。」 「部長の事を思ってじゃないですか。そんな人、出来ればいいですね。」 その言葉が、俺を突き放しているようだった。それは、私ではないのだと言われているような気がして。 「あんまり俺が理解に苦しむこと言ってないで仕事してろ。」 とっととうどんを胃にへと流し込んで、俺は席を立った。また、胃が文句を言っているような気がした。 六、 うどんを早く流し込みすぎて、反抗してくる胃に反発するように俺はデスクに戻ると煙草を手に取った。今のご時勢喫煙者はかなりその数を減らしていたが、それでもまだ愛煙家はいる。だからこそオフィス内に喫煙室というものがまだ存在しているのだろう。 一度デスクへと戻りカバンから煙草を取り出した。喫煙室へ行ったところで、その八割は電子煙草という最早煙草とも言えないそれを吸っているのだから、俺は喫煙室でさえ疎まれているのだろう。 「土方さん、煙草ですか。」 先ほど聞いてばかりのあいつの声が、耳を掠めて廊下を歩いていた俺は足を止める。久しぶりに聞いた、役職ではない俺の名前だった。 「お前に文句なんて言う道理はない筈だろ。」 「別に文句なんて言いませんよ。」 俺よりもゆっくりとうどんを食べていたは、いかにも腹が膨れたと言わんばかりの仕草を見せていた。同じものを食していながら、こうも違うものなのかと思う。 「ただ、将来土方さんがうどんのような女性を見つけた時その人が可愛そうだから。長生きしてください。」 言われて、俺は笑う。俺にとってうどんのような、彼女が言う存在は彼女でしかないという事をあいつは知らない。ほっとするように暖かい存在とは少し違ったが、つるっとした女なんてお前以外に居ないだろうと口に出掛かって、やはり止めた。 「…考えておく。」 俺がそう言えば、満足げにはオフィスへと繋がる道へと歩いていく。途中、トイレから出てきた原田に声をかけられ、面倒くさそうにしていながらも、やはりその表情は豊かだった。 俺の元に、うどんのように温かい存在はいつになったら来るのだろうか。
|