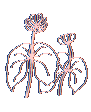 山本武と出会ったのは、中学に入学して間もない頃だった。学区の広い並盛は三つの小学校が並盛中学へと進学する。私は山本とは違う小学校に通っていた為に彼を知らなかったが、最初に彼を見たときの印象は衝撃的だった。 クラス発表があるとすぐに部活の体験入部が始まり、一週間もすれば皆どこかの部に所属する。 特別部活を強制する学校でもなかったので私は何処にも所属せず、のんびりと放課後のグラウンドを通って家路へと付こうとしていた時に初めて山本を見た。 野球に興味がある訳でもなかったし、そもそもルールだってうろ覚えくらいのものだったけれど一目見て彼がずば抜けている事だけは分かった。まっすぐに伸びていくボールの先を見れば、小さく粒ほどの大きさになって何処かへと消えてしまった。 それから一ヶ月もすれば、山本は学年の人気者になっていた。学生時代というのはいかんせん運動神経のいい男子がモテるのだと相場は決まっているように、彼もそれに漏れず該当していた。 野球で好成績を出している山本は正直にかっこいいなと思える対象で、私自身それは恋心なんだと思っていた。 何故沢田や獄寺という何の共通点もなさそうな面子でよく一緒にいるのかは分からなかったけれど、人柄のいい山本は誰とでも仲良くなれるから深い意味はないのかもしれない。私はきっと、山本武という男のすべてが好きだった。自分の理想を具現化したように完璧に思えたのだ。 野球をやっているのに時折傷だらけになっていたり、マフィアごっこをしているという意味の分からない事を口走っている事もあったが、自分が彼を好きと思う感情を前にしては然して気にもならなかった。 中学三年の時、山本が野球部を引退するタイミングで動き出したのは私の方だった。 ずっと付き合いたいと思ってはいたけれど、クラスメイトとしての距離は近づいてもそれが男女としての形に繋がることはなかった。山本が野球という対象から目を外した瞬間であれば隙があるかもしれないと。この時をずっと待っていた。 積極的に一緒に帰るようにしたり、貰った小遣いで奮発して竹すしまで行って会いに行くことだってあった。こうでもしないと酷く鈍感な彼は気づいてくれないと思ったのだ。 「ってさ、もしかして俺の事好きだったりする?」 それらしい動きが出始めたのは、卒業間際になってのことだった。普通の人であれば瞬時に気づくであろう行為も山本相手だと半年かけてもこの有様だ。けれど、ようやくここまで到達することが出来たのだ。 「なに、急に。」 「いや、最近が俺の近くにいる事多いなと思って。そんだけ。」 「そっか。だって、仲いいじゃんうちら。」 「確かにそれもそうだな。違いねえ。」 先ほどの彼の問いに私が頷けばそれは簡単な事だったのかもしれないけれど、どうしても彼から言って欲しいとこの時の私は酷く強情だった気がする。そもそも自分が彼の質問に首を縦に振っていた所で、肯定的ないい返事が返ってくる確証もないのだからそうするのが得策だった。 結局こんな曖昧な関係を保ちながら私たちは中学を卒業して、それぞれの進路へと進んだ。 事態が急激に進展したのは、高校一年の夏。久しぶりに学校帰りに山本に遭遇した。いつだって部活に励んでいる彼と遭遇したのは中学を卒業してから初めてのことだった。 駅から一緒に帰って、他愛のない会話をしながら歩いていた時にその瞬間がやってきた。 「ってさ、俺の事好きだったりする?」 「何か前にも聞いた事ある台詞だね。」 「だな。久しぶりに言った気がする。」 「まあ、うちら中学の時仲良かったもんね。」 「確かに。でも、好きだったらいいのになって、そう思ってさ。」 その後、彼の口から「付き合う?俺ら。」と言われて、好きという言葉が聞けなかった事に少しばかりの不満を感じながらも私は首を縦に振って、無事私たちは付き合うことになった。 三年の年月をかけて自分自身が欲しいものを手に入れたのは、これが初めてだった。 じっくりじっくり時間をかけてあれだけ望んだものを手に入れたのだから、きっとこの先に待ち受けているのはばら色の日々に違いないと、どこにも根拠のない不確かな事を思い浮かべて幸せに浸った。 高校生活を終え、私は大学へは進学せず就職した。昨日まで学生だった私も、春を境にまだ十八の未成年ながらも社会人になった。 大学へ進学しなかったのは家庭の都合だった。余裕な蓄えのある家ではなかった。無理をして奨学金を貰いながら大学に行くこともできない訳ではなかったけれど、そこまでして大学でやりたいと思うこともなければ、何より早く家を出たかった。そうする事で、彼と一緒にいる空間を作る事ができると考えたからだ。 「何かわりぃな。」 「何が?別に何も悪くないでしょ。」 「俺が家でれりゃいいんだけどな。」 「しょうがないよ。仕事あるし。」 彼も大学へは進学せず、竹すしで本格的に働き始めていた。見習いの身という事もあり給料と呼べるものもきっとそこまでないだろうし、何より自宅が職場なのだから彼が一人暮らしをする必要はない。何もそんな申し訳なさそうにしなくてもいいのにと思いつつ、そう考えてくれている事に素直に心が躍った。 「ほんと優しいよな。そういうとこまじで好き。」 「なにそれ、別に普通だよ。」 そう言っていながらも、どうしようもなく幸せに溢れていた。 今までは違う学校に通っていたし、彼には野球があったから平日はおろか土日だって部活の練習があった為にそこまで頻繁にあっていた訳ではなかった。だからこそ、私は彼と一緒にいる事の出来るこの空間がどうしても欲しかったのだ。ようやく、待ちに待った生活が出来ると、そう思っていた。 「合鍵、失くさないでね。」 「俺もらってもいいのか。」 「もちろん。時間あるとき、いつでも来て。」 以前よりも更に背が伸びた山本にそっと引き寄せられて触れた胸板に男を感じた。彼に抱かれた事は何度かあったけれど、それでもその時以上になんだか恥ずかしくて、そしてむず痒いような心地のいい感情を覚えた。 「ほんとありがとな。俺も寿司にぎって持ってくるわ。」 「うん。特上のやつね。」 「贅沢なやつ。」 もしかすると私の幸せピークはこの時だったかもしれない。限界を自分で諮れないように、ピークだって人生の終わりになって振り返ってみた時にしかないのだろうけれど、それくらいに幸せだった。合鍵を渡すのも、彼と一緒にいる事の出来る環境を手に入れたのも、彼の気持ちを自分に向ける事ができた喜びも、新しく始まる社会人生活で不安な気持ちすらかき消していた。 社会人になって、三ヶ月が経った。 最初のうちは転職も考えたが、最近ようやく仕事が軌道にのってくるようになって少しずつ楽しさややりがいを感じるようになっていた。頑張れば頑張った分だけきちんと給料にも反映される点が、より一層私を仕事のほうへと向けていった。 彼とは今も進行形で付き合っている。もうそろそろ付き合って三年になる。今までは私のほうが記念日やらクリスマスのイベント等においても楽しみにしていたけれど、今年はすっかりそんな事忘れていた。学生と社会人では、色んなことが違って見えた。 くたくたになって家へと帰る。今日はすぐにシャワーを浴びて寝てしまいたい程に疲れていた。明日も仕事だし、こんな日は早く寝るに限る。 自宅マンションが近づいてきて鍵を取り出したところで、自宅に明かりが灯っている事に気づいた。 「…武?」 「お、お帰り。遅かったな。」 「来てたんだ。」 「だって今日記念日だろ、付き合って三年の。」 言われるまで何故この男は突然人の家にやってきたのだろうか?と少し重い空気を感じていたが、あれだけ自分が大事にしていた記念日を忘れていたという事実に急に後ろめたくなった。 テーブルにはいつかに私が言ったように特上の寿司がずらりと並んでいて、いつもであれば喜ばしいのだろうけれど疲れて帰ってきた日にこんなに脂の乗ったネタを食べるのも正直気乗りしなかったけれど、忘れてしまっていたという後ろめたさもあってそんな事は言ってられなかった。 「ありがとう。嬉しい。」 「よかった。これ、俺握ったんだよ、食べようぜ。」 「うん。」 嬉しくない訳ではなかった。けれど、どうしようもなく嬉しく、幸せで満たされる気分では到底なかった。もしかすると仕事で疲れているからそう思わなかった、というだけの理由ではないのかもしれない。少し前から、小さな違和感には自覚していた。 仕事が上手くいっていない時は逆に何も感じなかった。依存する何かがなければ仕事での不安や不満を解消することなど出来ないのだから彼という存在は私にとって間違いなく必要だった。 研修の一ヶ月が過ぎた頃、ようやく仕事にも慣れてき始めた頃からその違和感には気づいていた。社会人には社会人の付き合いがあって、彼と一緒にいるよりも長い時間を過ごす職場の人間の方が学びが多く、為になる知識を与えてくれた。そして何より、皆が大人に見えて私も早く大人になりたいと思った。 ちょうどその頃くらいからだろうか、積極的に彼と会わなくなった。以前はよく電話したり、昼休みの度にメールをしたり、いつだって発信源は私だった。会いたいなと言うのも、うちに来ない?と言うのも私だった。けれど、ここ二ヶ月ほど自発的な発信はしなくなった。ただ、受身で何かが来るのを待つだけだ。 「、最近仕事忙しいのか。」 「うん、ちょっと今繁忙期でさ。今が頑張り時なんだよね。」 「そっか。やっぱ社会人って大変な。」 疲れた私を察してか、それ以上しゃべって来ることはなかった。初めてこの家に彼を招待したときのように、ふと長い彼の腕が私を巻き取って腕の中へと誘われたけれど、あの時と同じ感情は感じることができなかった。 「あんま頑張りすぎんなよ。何かあったらいつでも相談のるから。」 「…うん。ありがとう武。」 それらしく私も顔をうずめるようにしたら、ぽんぽんと頭上に優しく彼の手が置かれていた。これは、間違いなく私が望んでいた未来に限りなく近いはずだった。 けれど、その望んでいた未来が現実になった時、こんな気持ちに果たしてなるのだろうかと疑問に思う。この数ヶ月間気づかないように蓋をしていただけのかもしれない。 彼が寿司職人として働きながらも何か別の顔があるのはなんとなく分かっていた。それが中学の頃にマフィアごっこと言っていた何かに関連するものであることも薄々感づいていた。別に言われたところで拒絶する事もないのに、彼は未だ私には何も告げてこない。今まではなんとも思っていなかったけれど、何故言わないのだろうかと苛立たしく思うようになった。 以前だったらそんな所もかわいいなと思えたのだろうけれど、ウォーターサーバーのお湯の出し方が分からないと嘆いている彼を見て何でそんなことも出来ないのかと半ば呆れそうになるのを必死に我慢した。この時から、もう気持ちは以前と違うものへと変化しているのだと気づきながら、自分の気持ちに知らないふりをしていた。 「、これからも一緒にいような。」 その言葉に瞬時に答えを紡ぐことの出来ない私は、誤解を与えないように取りあえず先ほどよりももっと深く彼に顔を埋めて、背中に手を回した。本当は、今の表情を見られたくないというだけと悟らせないように。 私の望むものはすべてがここにある。 確かに私は山本武という男が好きなのだ。それは今も揺るぐことのない事実だろう。けれど同時に、私が恋焦がれたのは山本武ではなく、キラキラと光り輝く皆の人気者である中学時代の山本武なのだと気づいてしまったのだ。自覚していながら、知らないふりをしてきた代償が、今重く脂の乗った寿司と共に圧し掛かった。 野球が上手くて、皆から好かれ人気者で、常にムードメーカーだった彼が私は今も好きだった。 よく分からないマフィアごっこをしているのも、何処かほかの人間と違って特別に思えてよかったのだ。 けれど、それはあの頃の事実で、今もきっと私は昔の彼が好きなんだろうと思う。だからこそ、手に入れてしまった山本武にという男に、今の私はゴールを見出すことが出来ないのだ。 平和な戦場 |