 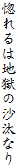 彼と出会ったのは大学時代の事だった。出会った当時、こんなにも美しい顔をした男がこの世の中にいるのだろうかと思うほど、私の理想を絵に書いたような男だと思った。彼に密かな思いを寄せるだけで楽しかった三年、彼が卒業してからの最後の一年は地獄のような日々だった。初めて、自分のものにしたいとどうしようもない独占欲に駆られた。 大学を卒業した後、私は印刷会社に就職した。大学時代にサークルの先輩だった永倉のいる会社だった。そこに就職したのはたまたまだったけれど、私がそのツテを利用しないはずもないだろう。就職して、すぐにそのツテを利用して私は三人で会う場を設けてもらった。第一希望だったその美しい男がいる会社は、一時選考で落ちた。 「、久しぶりだな。元気だったか。」 「元気なのが取り柄ですからね。」 そう言うと、数年前と変わらないように彼は大きな手のひらで私の髪を撫でてくれた。私はこの瞬間が何よりも幸せだった。今も、昔もそれは何も違わない事実だ。理想を絵に描いたようなその男は、美しいだけでなくどうしようもなく優しかった。 一度スキームを作り上げれば、彼と会うのは簡単だった。最初のうちは三人で飲みに行っていたが次第に二人で飲みに行くようになった。彼女はいない、そんな情報を引き出すのも他愛無かった。 いつからか、どうしたら彼を自分の男にできるだろうかと一日中考えるようになっていた。昔のようにただの憧れの先輩というポジションでは諦めがつかなくなっていた。その手で髪を撫でられるのも、この美しい笑顔も私だけに向けてくれるものだったらいいのにとどうしようもなく私利私欲に満ちた願いで溢れていた。 二人で飲みに行くようになって一年、あれから関係性に発展はなかった。自分から好きだと言ってみようとも思ったが、その勇気は微塵にも出る気配がなくいつもただ思うだけでその感情を酒で流し込んだ。やはり、自分を女として見ては貰えないだろうかと毎度落ち込んだ。 大学時代、彼には付き合っている女がいた。結果としては一年ほどで別れてしまったのだけれど、酷く大切に扱われているその女が単純に羨ましかった。彼と付き合うとこんなにも大切にしてもらえるのかと思うと、他の男からの告白なんて受ける気にもならなかった。 「最近は物騒な事件も多いしな、送っていく。」 「先輩は心配性だなあ。そんな言葉言ったら、女から惚れられちゃいますよ。」 「何だ、お前は惚れてくれないのか。」 居酒屋を出て、駅とは逆方面に私たちは歩いていく。今日も自分の気持ちを伝えることが出来なければ、彼から告白されることもなかったと気落ちしていた時だった。何てことのない世間話が、思いも寄らない方向へと転がり落ちた。私に、なんとも都合がいい方向へと転じたのだ。 「、好きだ。」 ずっと待ち望んだその言葉に、すぐには返事が出てこなかった。幸せという感情に不慣れな私は、あまりにも信じがたいその現実に追いつくことが出来ないでいた。 「なんだよ。返事、聞けないのか。」 「だって、いきなりすぎて吃驚した。」 「否定しないっていう事は肯定と捕らえていいってことか?」 しばらくの間をあけて、私は首を縦に下ろした。それを合図にするかのように、抱きしめられた。ずっと望んでいたそのポジションに、私は包まれてどようしようもない幸せに溺れていった。私は、あの時望んだ彼の女になれたのだ。大事に大事に愛してくれる男の、女になったのだ。それだけで満足だった。 彼の女になって、また一年が経過していた。思い描いた理想を、彼はすべて現実にしてくれた。毎日のように優しく髪を撫でてくれて、して欲しいと思ったタイミングでキスをしてくれる。ぴとりと体を寄せると、どうしようもなく優しく私を抱いた。昔彼が愛してた女のように、私は酷く大切にされていた。けれど不思議と抱くのは幸せではなく、恐怖だった。恐怖で毎日つぶされそうになっていた。 「どうしたんだ。不安そうな顔して。」 「そうかな?私そんな顔してる?」 「何かあったか。」 どうしてこんなにも大切にされているのに、私は不安なのだろうかと不思議に思う。彼に、この得たいの知れない不安をなんて言葉で伝えればいいのだろうか。きっと、伝わらないと思う。 「何もないよ。左之さんが好きすぎて、ちょっと不安なだけ。」 「なんだ、俺が浮気するとでも思ってるのか。」 「ううん。左之さんはそんな事しないって分かってる。」 そう少しだけかわいい言葉でまとめると、私を安心させるように大きな懐に包み込まれる。この大きな手も、抱き寄せられた懐も、優しいその笑みも、全部が全部私のものだというのに、満たされない何かがあった。幸せと同時に存在するのは、その幸せがいつか壊れるのではないかという反比例した感情だった。 昔に授業で習った平家物語を思い出す。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。 「どうしたらは安心するんだ。」 「どうかな。一生安心しないかも。」 「困った奴。」 困ったように笑う彼に、私が返事をし損ねていると、続くように言葉が振ってきた。いつだって、私が望む言葉を彼は紡いでくれるのだ。それはルートが決まっているかのように、正確に。 「結婚しよう、。」 いとも簡単に、私は再び幸せを手にした。その幸せが大きく膨れ上がるほど、私の恐怖も同時に膨張していくのだった。幸せな箱を差し出されて、いろんな意味で涙が出た。 プロポーズをされてから半年、私たちは来年入籍をする事になった。今は婚約中という形だ。 一緒に住む為の家具を二人で探して、無理をして二人で新築のマンションを買った。一生ローン地獄だなと苦笑いする彼に私も同じように笑ってみたけれど、内心はそれでいいと思っていた。このローンしかない新築のマンションがあれば、彼は私の元から居なくならないと狂気じみた女が考えそうな事を思っていたのだ。これから旦那になる彼は、私がこんな事を考えているどうしようもない女という事は知らない。知っていたら、一緒になどいてくれるはずもない。 段ボールだらけだった部屋を片付けて、オーダーメイドの家具がようやく手元にそろって家らしくなったその晩、新しいベッドで彼はいつも以上に優しくキスをしてきた。私の全身をも愛してくれているような、そんなキスだった。 「なあ。お前の子供が欲しい。」 「…子供?」 「駄目か?」 彼から頼まれることなんて滅多になかった。彼の望むことは私の望むことでもあると思っていた。けれど、その願いは私の望むところとは違っていた。彼の希望を叶えてあげたいと思う反面、子供が出来たときの事を考えると背筋が凍るようだった。私は、その子を愛せるだろうか。その子に彼を取られるという母親としてありえない感情に支配されるのではないだろうか。私の恐怖が、一つ増えた。 けれど、がっかりした彼の顔など見たいわけもなく、私はいいよと伝えるとどうしようもなく嬉しそうな彼のかんばせがあった。私はこの人のこのかんばせだけで生きていける。酷く、愛おしかった。 キスを再開した彼は、時間をかけて私を抱いた。初めて、彼の欲望を直接受け止めた夜だった。 子供が出来たかもしれないと不安に思って病院に行こうか翌日考えていた時、予定していたより少し早く生理がきた。とりあえず安堵しながらも、私はやはり病院へと足を運んだ。そこで処方された薬を毎日昼の十二時に飲んで、コントロールすることにしたのだ。そうすれば、彼をがっかりさせる事無く事に及ぶことが出来るからだ。酷い女だと自分のことながらに思った。 あの晩を境に、彼は避妊をしなくなった。いつ子供ができてもいいという覚悟を持ち合わせているのだろう。私が避妊薬を飲んでいるとは露知らず、いつになったら子供が出来るかなと子供についての話をすることが多くなった。 「左之さんは、女の子と男の子どっちがいい。」 「そうだな。女だと手塩にかけて育てても他の男に取られちまうからな。」 「左之さんは絶対子煩悩になりそうだよね。いいパパだ。」 「まあな。女でも男でもどっちでもいいんだ本当は。お前の子なら、どっちでもいい。」 そう言って、先ほど私を抱いてばかりなのに彼は私を抱き寄せてもう一度濃厚に舌を絡ませてくる。以前にも増して、彼に抱かれる頻度が増えていた。理由がどうであれ、彼に求められているのだと思うと少しだけ恐怖のない幸せを感じることが出来た。いつになっても子供が出来ないことに彼が違和感を覚えるのは、あとどれくらい先のことだろうか。一生そんな時が来なければいいのに。 「、愛してる。」 私もと言うと、もう何度目になるかも忘れたその欲望を受け止めた。 きっと、それだけは嘘偽りのない真実だ。 惚れるは地獄の沙汰なり |