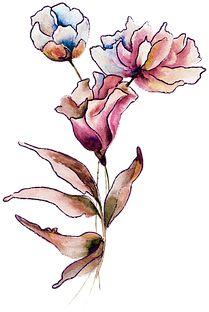壬生浪士組という名を授かり江戸を去った彼らは名を変え そんな彼らが江戸に向けて陣を移していると知ったのは、稀に届く文からではなく、街での風の便りだった。試衛館にいた彼らが、どうやら江戸に来るらしいともっぱらの噂だった。何故今になって、京から江戸へと陣を移すのだろうか。 戦況がよくないことを聞き及んでいたが、京の都を警護する事を生業としている彼らが京を出るという事はそれだけ大きな意味を含んでいることくらい無知な私にも理解が出来る。 彼らが戻ってくるという事で僅かながらに心を弾ませながらも、それを素直に喜ぶだけの材料が手元にないのだから、どうにも複雑な心境だった。そもそも彼らが江戸に向かっているというのも、ただの噂で何の確証もないのだから、そんな事で一喜一憂しても仕方がないのだろうけれど。 近藤の妻であるつねから聞いた話だった。やはり彼らは江戸に向かっているのだと、少し前に彼女宛の文が届いたのだという。 本当に戻ってきたのか、とそう思うと同時に私はぼんやりと一人の男の姿を思い出した。以前私に置き土産を残して、京へと旅立っていった男の事だ。あの大きな背中が、小さくなっていくあの姿が最後に見た彼の姿だった。新撰組が江戸にいるというのであれば、恐らく彼もそこにいるのだろうと、そう考えて。 どうしたものかと、少し悩む。彼らが江戸に戻ったと言っても私には会いに行く理由は特にない。終戦を迎え、勝利でその幕を下ろしたというのであれば理由も必要がないのだろうけれど、今は戦の真っ只中だ。それも、劣勢である事に違いない。ならば、おいそれと私が顔を出したところで、きっと皆が困るだけであることが想像できた。そして、そこまで図々しくも自分の意思を貫けるほどの何かも私にはなかった。 「つねさんは、近藤さんに会いにいくの?」 「そうは言ってもね。今会っても、私には何もできないし。」 彼女も、私と同じ考えを持っていたようで、やはり皆思うことは同じなのかと私の気持ちも一歩下がる。きっと、何事もなかったように私もここを動かないほうがいいのだと、勝手に理由をつけて。 少しばかり抱いた希望を捨てて、私は私の日常へと戻る。いつかのように、そしていつもの様に買い物へと出かける。あの日からも私の日常は何も変わらない。いつだか彼に言われた恋というものも、特にない。これから好きな人くらい出来るだろうと言った彼の言葉は、今のところまだその結果を私に齎してはいなかった。 まわりが戦争をしている事は知っていたが、まだ江戸の街は以前と変わらぬ風景をとどめている。私が一人で買い物に出かけられているのだから、それが立派な証拠だろう。平和、とは言えないが今すぐにでも切った張ったの戦が繰り広げられる雰囲気もない。 野菜を買って、魚を買う。それを買い物籠に入れて、元来た道を帰る。来る日も来る日も変わらない、私の日常に変わりはない。そんな私も変わらなければ、その景色も変わらず視界へと映し出された。 「おい、ちゃんか。なあ、そうだろ。」 ただ一つ、非日常的な今に私は立ち止まる。その名を呼ばれ、振り返った先にいたのは以前よりも更に肉体を鍛え上げたのか、懐かしい男の姿があった。 「新八さん。ほんとに、江戸に戻ってたんだ。」 「なんだ、知ってたんだな。」 「つねさんが、近藤さんから文で知らせを受けてたから聞いてはいた。」 「そうか。…にしても、簪なんて挿してるから最初気づかなかったぜ。」 ああ、と私は自らの髪に差し込まれている簪に触れた。確かに彼らがいた時には、こんな格好をすることもなかった。道場の娘として洒落込む必要もなければ、生きていく上で特別必要でもないものだ。彼が置き土産にこんなものを残していかなければ、今だって自らそんなものを着飾ることはしないだろう。 久しぶりの再会を彼は喜んでくれているようだったけれど、結局立ち話でそれも終わってしまった。やはり、状況的には旧友との再会を手放しで喜べるほどに楽観的なものではないのだと、彼の言動が物語っていた。 じゃあ、と手を上げた彼を見送ろうとした時、思い出したように一度だけ私のほうを振り返り、少し意味ありげな余白を生んで、もう一度口を開く。 「左之には、会わないのか。」 「何それ。なんで、左之さん限定?」 「いや、なんとなく。」 「今会ったところで、手放しで再会を喜べる状況でもないでしょ。」 「ま、それはそうだけどさ。」 決まりが悪いように何かを言いたげだったが、それ以上は特に何も言わなかった。彼も江戸を出てから、成長したのだろうかと少し可笑しくなって私は笑う。笑えば、もっと決まりが悪いように何だよと声を荒げる彼を見て、そんな所は江戸にいた頃と変わらないのだなと余計と可笑しくなった。彼が女としての私の気持ちを推し量るなんて、なんだか不思議な感じだった。 「一応、俺は言ったからな。じゃあな。」 「じゃあね、新八さん。元気で。」 これが最後と言わんばかりに、私はあえて別れの言葉を告げる。私はあの時から何も変わらないけれど、彼らは変わっているのだ。確実に、変わっている。いつまでも成長できない私をおいて、遠くに行っているような気がした。あれだけ京と江戸というどうしようもなく遠い距離から、こんなにも近づいていながらも。 予想外な旧友との再会を済ませた私は、再び元来た道へと戻る。挿していた簪を一度髪から引き抜いて、自分自身の視界で捕らえる。それは私にとって呪縛のようなものだった。これがある限り、きっと彼の事を忘れることはないだろう。いつまでも忘れるな、という事なのだろうか。であれば、彼はやはり罪深い男だなと思う。 永倉の話だと、彼らはこの近辺で仮住まいをしているという事だった。会おうと思えば、すぐにでも会える距離だ。事実、偶然にも彼に出くわしたのだからこの呪縛のような置き土産を残したあの男にも、会うことは叶うだろう。けれど、足はまっすぐ帰るべき道へと進んでいく。 会いに行く理由が、何か一つでもあればいいのにと思いつつ、その理由があって彼に会いに行った所で現状は何も変わらない。寧ろ会いに行く事によって、自分自身に毒を盛る結果にだってなり得るだろう。そこまで自分を追い詰めるほど私も馬鹿ではない筈だ。いっそ、見合いでもして嫁いでしまおうか。そうすれば、順序は逆であっても人を好きになれるだろうか。この宙ぶらりんな感情に、私は見切りをつけたかった。何の当てもないものを待ち続けるのは、想像するより遥かに気苦労が多い。 そんな事を考えていたら、既に帰るべき場所へと私はたどり着いていた。買い物籠を置いて、中身を勝手場へと運ぶ。この魚を焼いて、野菜を切って、毎日代わり映えもしないと文句が飛んできそうな料理でもしようかと、袖を捲くった。 大して料理がうまい方でも、要領がいい訳でもないけれど、今日は一段と段取りが悪く、思うようにいかない。全てを放り出したくなった。そして、放り出した。 「買い忘れた食材があるから、出かけてくる。」 何を買い足すのかと思われる程の食材を並べた勝手場を、私は出て行く。ぽつぽつと少しずつ頭上を濡らす雨を見て、傘を持った。柄にもなく、小走りに息を切らせながらただ真っ直ぐに向かった。 京まで走っていくくらいの覚悟を持って飛び出たものの、思いの他すぐに目的に場所へとたどり着く。膝に手をかけ、息をあげている私に聞きなれた声が響く。 「随分な姿だな、。お前がそんな走るなんて。」 「私にだって走るときくらい、あるよ。」 まだ呼吸が荒く、整わない。こんな姿を見られるのも癪だと思ったけれど、今はその方が好都合かもしれない。冷静な状況で彼と話せるほどの度胸は、私にはない。 「久しぶりだな。元気か。って、元気そうだな、間違いなく。」 「嫌味?」 「捻くれたやつ。よかったって意味だろ。」 「左之さんも、相変わらずだね。」 彼も、元気そうだった。今は元気だけで生きていける世の中ではないのだろうけれど、一先ずそれを知れただけでもよかったと、私にしては珍しくそう思った。京での彼を私は知らない。どのように生きてきたのかを、知らない。聞くことに対しての恐怖が僅かながらあった。聞きたい気持ちと、聞くことへの恐怖心から次の言葉をうまく紡ぐことができないでいた。 そんな私に見かねたのか、苦笑いをした彼が私の代わりに口を開いた。一歩、一歩と私への距離をつめて、近づきながら。 「金持ちの男は、見つかったか。」 「残念ながら縁がないみたい。」 「そっか。じゃあお前の夢も未だ叶わずか。」 「私の夢って、そんな下らなかったっけ。」 いつかの、雨の日の出来事を思い出す。どんな男がいいのか、と彼とありもしない架空の出来事を想像しながら帰った雨の道。金があるに越したことはないと言った私と、金に執着はないと言った彼と。一言、どきりとするような殺し文句だけを呟いた彼を。 「知ってるか。新撰組幹部ともなりゃ、結構給金あるんだぜ。」 「左之さんには似合わないね、そんな台詞。」 「お前はどうしても俺を貧乏人にしたいみたいだな。」 私のこの皮肉っぽい言い草も、成長しないなと自分の事ながら思った。彼も、私のそんな所を変わらないなと呆れているだろうか。本当に成長しない、女だと。 ようやく呼吸が落ち着いて、私はその場に居直る。大きな彼を見上げると、やっぱりあの頃と変わらずやさしい彼のかんばせがそこにはあって、視界が歪んで行くのを感じた。雨が伝っているだけと、自分自身に言い聞かせて。 「いつだかの借りを返しに来たんだ。」 そう言って、私は左手に持っていた傘を彼に手渡す。いつだか買い物に出かけたとき、大雨に降られた事があった。江戸の街で私を見つけて、傘を持ってきてくれたいつかの彼を思い出す。その借りを、今返すとでも言わんばかりに。 「そんなもん、返すもんじゃないだろ。」 ふわりと、懐かしい香りがした。いつかの、懐かしい彼の匂い。男の匂いがした。私がずっと望んでいたのは、この瞬間だったのだと自覚すると、虚勢を張っていた心もゆるりと解けていった。 「傘、持ってきたのに意味ないじゃん。」 地面に落ちた傘を拾うこともなく、私が渡した傘をさすこともなく、雨に降られていた。私の髪を着飾っている簪に触れる彼の指が、かすかに揺れた。今だけはと、柄にもなく私は素直に彼に甘えてみる事にする。彼に素直に甘えることができなかった昔の自分を捨てて、彼の首に手を伸ばしてみる。 恋が楽しいものとは、誰が言ったのだろうか。私の中での恋は、こんなにも切なくつらい。恋をする相手を目の前にしても、胸が軋むような感覚に陥る。それを埋めるように彼を縋ってみたけれど、一向にその感覚は収まらず、勢いを増して私に襲い掛かる。 けれどその反面、それを埋めようと自ら彼に甘えられるのであれば、それは捻くれ者の私にとってはいい薬なのかもしれない。こうでもしないと、私が恋を始めることなんて出来ないのだから。 私に振ってきたその唇に、胸の奥で傷が染みるような感じがした。 ♯敬愛なる傾慕 |