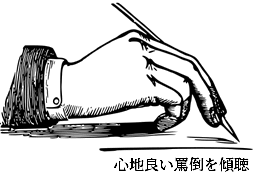
俺はあまり酒を飲まない。飲めないのではなく、酒の場の雰囲気が好きではないというその一点のみが理由だ。だからこそ彼女の気持ちが分からない、けれどその分約束もない俺は彼女からの週末にだけかかってくる電話を待ち続けることが出来るのだろう。幸か不幸かは分からないし、他人に評価されたくない。 彼女を知ったのは、もう随分と昔のはなしになる。氷帝に通う多くの人間は持ち上がり式の為、幼稚園から大学まで顔見知りが多い珍しい環境だ。の事も、昔から当然のように知っていた。一学年上の先輩だ。 始めて言葉を交わしたのは中学に進学し、テニス部に入部した時だった。マネージャーをやっている彼女はいい女だった。それは容姿だけのことではなく、頭の回転もよく賢く、嫌味がない愛想のある皆から好かれるテンプレートのようで、その証拠に彼女は跡部さんの彼女だった。 別にそこを引き剥がしてまで付き合いたいと思っていた訳でもなければ、いい女だなと少し思う程度でそこまでのめり込むこともなかった。 状況が変わったのは、大学四年の時だ。テニス部の面子で久しぶりに集まる機会ががあった。飲み会に毛ほどの興味もない俺は不参加を表明していたが、同じ学部の鳳がしつこく行こう行こうと日々纏わりついてくるのが面倒でいく事にした、その場に彼女がいた。 噂には聞いていた。彼女と跡部さんは随分と前に別れたらしいと聞く。婚約者が出来たという事で大学進学と共に、別れたらしい。家柄を考えれば仕方がない事だったのだろう。然して気にも留めていなかった。 「わっ、日吉くんじゃん!めちゃ久しぶり、来ないと思ってた。」 「…来たら悪かったですか。」 「そんな事私言ってないじゃん。嬉しいって言ってるの。」 清楚なイメージだった彼女は、少し派手になったような気がしていた。小ぶりながらも揺れるピアスを下げて、スリットの入ったスカートに御そろいの色をしたジャケット、ピリッと伸びたシャツが社会人らしさを表現していた。派手になったのではなく、社会人になった事でより俺より大人になったのだなと思った。少し昔と印象派違ったが、それでもこのしょうもない飲み会に来たのは無駄ではなかったと思える時間になった。 近くで彼女を見ていたが、よく酒を飲む。以前のイメージであれば、あまり酒など飲まず皆を気遣って水などを手配する役割を買って出そうなのに、そんな事様子は微塵も見られず飲んだ分だけ酔っているようだった。 「先輩しっかりして下さい。」 「心配してくれてるの?もう一軒いく?お姉さん奢るよ。」 「別に奢って貰わなくても大丈夫ですし帰ったほうがいい。」 「何、日吉くんってお酒弱いんだ。」 その言葉が俺を煽ると知ってか知らずか、これが俺に火をつけさせたのかも知れない。酒が弱いと言われるのは不本意だ。飲まないだけで弱いと決め付けることはやめてほしい。結局こう言われてしまえば、俺の口から出てくる言葉は一つしかない。 「潰れられたら面倒ですから、ほどほどにしてくださいね。」 結局千鳥足で気分がさぞ良さそうな彼女を連れて、少し入り組んだところにある唯一昔に行った事のある雰囲気のいいバルへ連れて行った。少し話をして、酔いが覚めたころに帰ればいいとそう思っていた。 二人でドリンクを選んで、手を上げてオーダーをしてトイレに行くと席を立った時、彼女はまだ先ほどの酒の余韻が残っているのかご機嫌な様子でパタパタとトイレに行くだけの俺に手を振っていた。実に愉快な女だ。昔の印象と随分とずれを感じた。 トイレから戻ろうとした時、先ほどまであれほどご機嫌だった彼女が少し冷静さを取り戻したように冷静にスマートフォンに目をやっていて、暫く声をかけられなかった。 「あ、日吉お帰り!飲み物来たから早く飲もう。」 「あんたまだ本当に飲めるんですか。」 「何それ。あ、私弱そうに見えるかよく言われる。でも結構飲めるんだよ。」 そう言って本当に彼女は勢いよく酒を飲み干して、俺なんかよりもよっぽど酒に強いと思った。結局朝まで彼女は飲み続けて、俺は彼女を家まで送り届けて自宅へと帰った。朝まで外にいたのは久しぶりの事だった。あと数ヶ月もすれば、俺の学生生活も終わる。その生活が終わる事で、少しだけ彼女に近づけるのかもしれないなんて柄にもない事を考えた。 改めて連絡先を交換したあの飲み会から、割と頻繁に連絡が来るようになった。決まって、それは金曜日の終電が終わった後に限定される。なんとなく理由は分かっていたが、気づかないふりをした。 「何してるの、飲んでた?」 「…あんたと違って俺はそんな酒乱じゃないので飲みません。」 「金曜日の夜なのに寂しいなあ。もうすぐ卒業なのに。」 学生生活も残すところ数ヶ月、俺は無事に内定先を決めて卒業を待つだけの身となっていた。卒論を書く以外は酷く暇な時間をすごす事が多くなっていた。可もなければ不可もない、どうって事のない期間だった。回りは卒業に向けての思い出作りや、単位がない愚かな人間は勤しんで学校へ行ったりと、そのどちらも俺にとっては下らないと感じた。そのどちらでもない俺には、ただひとつ金曜日にひとつの習慣が出来ていた。 「来週会おっか。」 「何で会うんです。理由がないでしょう。」 「私が日吉に会いたいからじゃ駄目なの。」 いつだって電話をかけてくる彼女は、酷く酒に飲まれているようだった。まるで昔の面影もない彼女の行動に少し呆れながらも、俺は電話に出る。結局俺は彼女のことが気になっているのだと認めざるを得ない。 遠い昔にほんのりと感じた淡い気持ちと、先日二軒目に飲みに行った時の彼女の寂しそうなかんばせが何処か忘れることができないでいた。彼女は今、幸せではないのだろうか。 「会いたいから会うってだけじゃ理由にならないの?」 彼女はずるいと思う。こんな事を言われて断れるはずがないと分かっているのかもしれないのだから悔しいけれど、やはり俺には断ることが出来ない。それは同情ではないのだからそれがより悔しかった。 酔っ払いの電話で、来週の週末に会う約束をした。彼女は果たして覚えているのだろうかと不安に思いながらも、バイトのシフトを休み希望で入れた。これは俺が学生最後に遊べというお告げに違いないと思い、迷うことは止めた。何も気にすることなく前回と同じように彼女と会って飲む、ただそれだけでいい。 あれから毎週のように週末の終電後に電話はしていたものの、彼女と会うのは久しぶりだった。柄にもなくどんな店に連れて行けば彼女は喜ぶのだろうかと考え、今までしなかった店のリサーチもして、ある程度プランが固まっていた。 何時に会うという約束もなかったのだから、今日何時にしますか?と夕方に送ったメッセージは暫く既読にならない。仕事が押してるのだろうと思い暫く待っていたが、結局返事が返ってきたのは八時過ぎだった。 この時は、仕方がないと諦めがついた。仕事といわれた時、しがない学生の俺にはそれ以上に返す言葉は持ち合わせていないのだから了承するしかないし、駄々を捏ねた所で何も始まらない。また埋め合わせの次回があるだろうと、そう思っていた。 案の定、その日の終電後、彼女からいつもどおり電話がかかってくる。 「日吉今日はごめんね。近いうちに埋め合わせするから。」 「別にいいですよ仕事なら仕方ないですし。」 「物分りいい日吉は大人だな。そういうところ、好きだよ。」 「…さん、もしかして酔ってます?」 そう聞けば、仕事終わりに少しだけ飲んだのだと彼女は言った。声のトーンからして、少しだけではなく割りと酔っているように感じられたのは気のせいだろうと自分を言いくるめた。社会人にもなれば、学生の自分たちと違って酒に酔わないとやってられない事があるのだろうと勝手に理由付けて。 「ねえ日吉。」 「なんです。」 「会いたいな。ほんと、会いたいんだよ。嫌じゃない?」 この言葉に、俺は弱い。気にしないでいいですよと、いつだって言い続けてしまう。いつその埋め合わせの日がやってくるのだろうかと思いつつも、酔っ払いの電話に付き合うことしか俺には出来ない。少しでも彼女にとって興味の対象であれるからこそ、電話がいつもかかってくるのだと思うことにしていた。そうでなければ、彼女に当日約束を反故にされた数を数えるのすら苦痛になっていた。久しぶりの再会をしてから半年、電話をするようになってからも半年、俺はまだ彼女に会えていない。繋がっていられるのは、電話だけだ。 「日吉、好きだよ。」 この言葉が、いつだって俺を縛り付けて現状に甘んじる。 彼女からの誘いにも関わらず、それが実現せず五回の約束が反故にされていた。六回目の正直と思い、空けていた六回目の週末にイレギュラーな案件が舞い込んできた。バイト先で急遽病欠が出たという理由で、代わりが誰もおらず声がかかっていた。次の約束も何処か当日に断られれるのかもしれないと、今までの悲しい経験で俺はその誘いを渋々受けることにした。以前彼女との約束を理由に、何度かバイトを変わって貰った事があったからだった。 酷く気乗りしないが、彼女にメッセージを打つ。どうしても外せない用事が入ってしまったと、連絡をする。 本当は、いつだって仕事を理由に当日に断ってくる彼女に俺も暇ではない事をアピールしたかったのかもしれない。本当は、暇なんて吐く程ある自分が、少しはしてやったりしたかったのしれない。代わりを他に探してくれと言えばそれまでだったが、それで彼女の事を試したかったのかもしれない。 ようやく、彼女と同等になれた気がして、少し気分がよかった。これで自分ばかりが不安に思うことはない。どこどこの店に行こうと思ってたんだけど、バイト頑張ってねというそのメッセージで、彼女が俺にまったく会うつもりがないという訳ではない事を知れたいい機会だった。何処か、心地がよかった。 「日吉、お前あがってもいいぞ。元々代打だし、何か予定あったんだろ。」 その言葉にしめたと、渋ることもなく甘んじた。まだ時刻は八時だ。まだ彼女に会えるかもしれない。俺は急いでユニフォームを脱いで、私服へと着替えてメッセージを打つ。予定よりも早く用事が終わったからこれから会えないか、と。 返信どころか既読がつかない事にもどかしかさを感じながら帰り道を歩いている時に、あの飲み会へと俺と連れて行った鳳にばったり出くわした。 今のこと、就職先のこと、社会人になったらどうなるんだろうかという下らない話をあいつはしてくる。聞いているだけで飽きるような話の中で、突如気になるフレーズを聞いた。 「そういえば、日吉はあの後先輩にあった?」 突然何を言い始めるのかと思い、会っていないと答えると、自分自身不思議に思っていた事が紐解けて行くように納得するような言葉が耳に入った。 「先輩、まだ跡部さんの事忘れられないらしくてさ。なんか自棄になってるって聞いた。」 酷く合点のいく話だった。随分と雰囲気が変わってしまったのも、それに起因してのことなのだろうか。結局、自分は寂しさを紛らわせる飲み要因でもなければ、その寂しさを酒で紛らわせたあとのはけ口でしかなかったのだと察知した。自分自身のことを哀れに思いながらも、けれど、不思議と彼女に対する気持ちは変わらなかった。 「先輩、随分昔と雰囲気変わったよな。」 「…人間時間を重ねれば変わるのは当たり前だろう。お前は進歩のない男だな。」 結局、俺がバイトを早く終わらせて彼女に連絡したところで返事が返ってこないのは、そういう事なのだろう。酔いに任せて俺に連絡してきては寂しさを紛らわせ、そして素面になって会うべきでないといつだって断りを入れて他の人間と飲みに行っている構図が容易く浮かんだ。 「これ以上用がないなら俺は帰る。」 「そっか。飲みにでも行かないかなと思ったんだけど、どうかな。」 「知ってるだろ。俺は飲みに興味はない。」 そう言いながら鳳と別れて、ひた道を歩いていく。もう一度スマートフォンのメッセージを確認するが返信もなければ、既読にもなっていない。けれど、何処か確信していた。十二時を過ぎれば、きっと彼女から電話がかかってくるとという予感が。 それが、自分との約束がなくなったから即座に他の人間と飲みに行っているのか、それともそもそも俺と会う気がない中で俺から会えないと言われて罪悪感から解放されて飲んでいるのかは分からない。 けれど、たった一つ言えるとすれば、そのどの結果だったとしても、俺は十二時過ぎにかかって来る電話に応答するという事実だけだ。 心地良い罵倒を傾聴 |