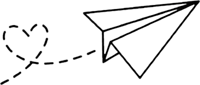 彼がうちにに来るのはいつだって、週末の終電後だった。 私は新宿に程近い所に住んでいる。理由は、仕事をする上でそこに住むのが一番効率がいいというだけの事であって、他意はない。この土地に思い入れがある訳ではない。仕事をする上でも友人と遊ぶにしても都心に近いほうが自分自身に楽という理由から、私は人より少しだけ高い家賃を払ってこの地に住んでいた。 そんな私の自宅の便利さにいち早く気づいたのは、仁王だった。 彼は中学時代の同級生だ。何を考えているのかよく分からない男だと思っていたが、大人になった今はより分からない。何を考えているか分からない男に惹かれるという話を昔雑誌で読んだことがあったけれど、まったく理解ができなかった。そんな人を好きになっても辛い思いをするのは自分なのだから。 午前零時半、普通であれば通報してもいいような眠りにつく時間、私の家のチャイムがなった。 「いつも悪いのう。ほれ、酒。」 「…私があんまりお酒飲まないの知ってていつも土産がこれってどうなの。」 「手ぶらでくるのも気が引けるじゃろ。」 なれた様に私の玄関で靴を並べると、ずかずかと部屋へとあがって来る彼に、私も何も言わない。綺麗にそろえられた靴を見ながら、いつものように鍵をかけて私もその背中に続いた。 甘いもののひとつでも買ってくればいいのにと小言を言えば、そんな所に顔を出さないから考えも浮かばなかったと彼は言う。夜中にそんなものを食べたら太るだろうと、そんな余計な言葉を付け加えて。 私の白いソファーに腰掛けると、コンビニの袋から酒を取り出して無表情なそのかんばせで、プシュとプルタブが明けられた。飲んできているだろうに、まだ飲み足りないのだろうか。終電まで飲んでいたのに、まだ飲みたいと思うものなのだろうか。酒を飲まない私には、それが分からない。 「今日は誰と?」 「ブン太とか柳生と。そういえば、隣にたまたま氷帝のやつ等もいたかもしれない。」 「いたかもしれないって、それって居たって事でしょ。」 話をしてくれるのに、仁王は肝心なところをぼかす事が多い。そこを追求しても彼からその答えが返ってこない事を知っている私は、一度それを尋ねるだけでその先を聞こうとはしない。暗黙のルールとでも言うのだろうか。私がそれを追求するような女なのであれば、きっと彼は終電帰りにうちに来ることなどないだろう。 「飲むか?」 「飲んでほしいなら飲むけど。酔うよ、私。」 「なら、止めとく。」 飲みたい訳でもなかったが、私を酔わせることすらさせてくれないのだなと思う。酔って、万が一にでも甘えてみれば彼にとってそれは面倒なのだろう。仁王にとっての私の家など、ただ終電を逃したときの行き先でしかない。 こんな摩訶不思議な関係は、どれくらい前からだろうかとふと思う。大学に入ったころは、こんな事はなかった。大学近辺には住んでいたものの、彼の方がもっと大学に近いところにすんでいたのだから。 「ほんとこんな時間に来てさ、仁王は自分勝手。」 「そうじゃな。俺もそう思う。」 「私に彼氏が出来たら飲み会帰りどうするの。」 「俺の帰り先が、一つ減ってしまうの。」 帰り先が、いくつもあるのだろうか?そう、少しだけ考えた。彼にならあり得るとも思ったけれど、やはりそれはないと思った。居心地を重視する彼に、私以外の女でそんな関係を築くことなど出来ないと少しだけ贅沢に気持ちに陥ってみる。 「それとも、彼氏でも欲しいんか。」 「別に。いてもいなくても、日常なんて変わらないし。」 「冷めた女じゃ。だから、お前の隣は心地いい。」 喜んでいいのか、そうではないのか、いつだって仁王の言葉は曖昧に空気に漂っていく。私が欲しいと思った言葉など、絶対に紡ぎはしない男だ。 「やっぱり、私も飲んでみようかな。」 「ほう、珍しい。」 ハイボールが数本並んでいるコンビニ袋に、一つだけ私が飲めそうなチューハイがあった。このたった一本を、私への土産といっているのだから笑えるなと思う。宿泊代にしては、あまりに安価すぎる。 「仁王はさ、何で終電で帰らないの。いつも。」 「楽しいからじゃろ。」 「でもさ、帰って自分の家で寝たいとは思わない?」 「別に寝るところが変わっても、同じじゃよ。」 まるで、彼はバックパッカーのような男だと、そう思う。こうして私の家以外にもふらふらと出入りしているのだろうか。 「ブン太とか柳生の家、行けばいいじゃん。」 「あいつらは翌日が大変だしの。」 「ああ、帰ってからも飲むもんね。」 「そういう事じゃ。」 それから小一時間程が経過したとき、彼は空き缶をゴミ箱へと片して、ソファーから立つ。時刻は、三時近いのに仁王には眠そうな表情はなかった。 「洗面台貸してくれ。」 「うん。私も行く。」 洗面台に二つ立ちそびえるその歯ブラシの一つを手にとって、それに歯磨き粉をつける。彼のそれは、中々に痛み始めていた。この間買い換えてばかりの私のものと比べると、彼がどれだけここに通っているのかを裏付けているようだった。 「買っとく?もう、随分痛んでるし。」 「甲斐甲斐しいのう。」 「健康は口からっていうし。そんなんで健康害されても困る。」 「なら、買っておいてくれるか。」 痛んだ歯ブラシを口の中に放り込んで、数分して私たちは部屋へと戻っていた。電気を暗くして、ベッドに入る。男の人がいると、いつもより狭くなる事実はあっても、それは心地が悪いものではなかった。 「おやすみ。」 そう言って、彼は目を瞑る、おやすみのキスもなければ、ハグもない。ただ、布団が一つしかないからという理由で私と同じベッドで眠っているという一つの理由しかない。 いつだって週末になると、眠い目を擦って待っていた。いつ、仁王が着てもいいように。けれどそんな事にもほとほと疲れた気がした。こんなにも近くで呼吸をしている男に、私と描く未来はないのかと思うと急に眠気が覚めていくようだった。 突然、仁王がうちに来なくなった。最後にあった時、珍しく酒に酔った私は、ソファーで寛いでいる仁王に、体を寄せた。酒の力を借りないと、出来ないことに違いなかった。 仁王は、何も言わない。何か言って欲しかった訳ではないけれど、何も反応がないというのもこちらとしても次の動作に困った。 私は飲みなれない、彼が飲むハイボールに口をつける。コンビニで買った安物でしかないその瓶で彼はいつもハイボールを作る。いつだってすまし顔で飲んでいるくせに美味しいと言うものだから、そんなに美味しいものなのだろうかと思い、酔いの回った私はそのグラスへと手を伸ばした。それはもちろん、私には合わない味だった。 「ねえ。」 「なんじゃ。」 「そんなうちに頻繁に来るなら、ずっといればいいのに。」 「変わった事を言うんじゃな。」 今まで、こんな事を言えなかった。そんな事を言えば、彼がここに来なくなると思ったからだ。酒の力とは、偉大なものだと改めて思う。その結果がいい方へ転ぶか、悪いほうへと転がり落ちていくかなんて分かっていたのに。冷静な判断を失わすには、最適な逸材だ。 「そしたら終電なんて気にしなくていいじゃん。」 「そんなに飲んだら肝臓がどうにかなる。」 「そっか。確かにそれはそうだね。」 少しだけ冷静を取り戻して、私も我に返った。私よりも幾分にもその量を多く体内へと流し込んでいる彼は、酔いというものを感じるのだろうか。体質一つで、そこまで変わるのだろうかと不思議に思った。 いかんせんその体質に恵まれていない私は、酔いが冷めた後に後悔するであろうその言葉を紡いだ。 「仁王、キスしてよ。」 「随分大胆な事言うんじゃな。」 「今言わないで、いつ言うの。」 そう言えば、いとも簡単に彼の唇を手に入れることが出来た。酔うのもたまには悪くないと、そう思えるくらいには。 小鳥のさえずりで、翌朝目を覚ます。ひどくズキズキとうずくその頭にひどくうんざりした。 二日酔いが生じている以外には、いつもと何も変わらない朝だ。私はきちんとパジャマを着ていて、布団をかぶって寝ていた。かすかに思い出した昨日の晩の事に対して後悔が過ぎった。後悔を抱く対象のいないベッドで、二日酔いの頭を抱える。キスはしても、それ以上は何もなかった。 月に数回はうちに来ていた仁王は、そこからぱったり来なくなった。元々連絡もうちに来るときにしかしてこない男だ。私には、何故うちに来なくなったのかと連絡を入れる勇気すらない。その理由が何であるかを分かっている私は、そこまで馬鹿ではない。 彼が残していったウイスキーのボトルに、想いを馳せる。自ら彼が好きだったウイスキーでハイボールを作る気もしなければ、ロックで飲もうとももちろん思わない。 ただただ埃をかぶって行くそのウイスキーに、いつになったらそれを飲む人間が帰ってくるのだろうかと思案することくらいしか私には出来なかった。 仁王がうちに来なくなってから、一年程が経過していた。 仕事から帰ってポストを覗くと一枚のはがきが入っていた。裏を返してみれば、それは同窓会の出欠を知らせるものだった。今のご時勢紙でそれを出すなんて気づかない人もいるだろう。センスがないなと思って部屋へと入った。 中学を卒業してから、どれくらいの時が経っただろうか。考えるのも、うんざりしてやめた。 私たちの学校はエスカレーター式で、ほとんどが大学までを一緒に過ごす。もちろん大学ともなれば高校まで一緒に居た人間以外も入ってくるのだから疎遠になっていたが、キャンパスで顔を合わせることはあったのだから表立って同窓会というのは、初めてのことなのかもしれない。 取りあえずそんな二ヶ月先の予定なんて今から入っていないのだから、出席に丸をつけてポストへと投函した。手紙を出すことすら、久しぶりだった。 今は皆東京で生活をしている人間の方が多い。通勤に少し不便な地元に、私はあまり帰らない。久しぶりの、帰郷だった。その男が同級生であったという事を、すっかり忘れていた。 数十人の群れの中で、ひときわ落ち着いている彼を見つけて私は後悔する。誰かと話そうと思って左右を見たが、皆既にほかの人間と話しこんでいた。 「久しぶりじゃな。」 「仁王がこんな飲み会に来るなんて珍しいね。」 「俺のことを何じゃと思ってる、お前。」 「こういう飲み会、好きじゃないと思って。すごい意外。」 いかにも、久しぶりに会ったような違和感のない彼の態度だった。もっとも、久しぶりに会うという事には違いがなかったが、どうやら気まずいと思っているのは私だけらしい。 「仁王はさ……最近何してるの。」 彼女が出来たのか。そう聞こうと思ったけれど、あわてて口をふさいだ。あの時のように、私は酔ってはいない。醜態をそこでさらす必要はないと思った。あれから、より一層酒は飲まなくなった。一種の、トラウマだった。 「何って、前と変わらんよ。そういうお前は。」 「私も、前と変わらないな、行きたくもない会社に行って、帰って、寝て、それだけ。」 平然と言いながら、何処か鼓動が煩かった。どうして彼はこんなにも平然と話すことが出来るのだろうかと不思議に思いながらも、やはり酒を飲んでいないからこそその理由が分かった。彼にとって、私はそれに値する女ではなかったと、そういう事だ。ただの一度だけキスをした、それだけのことだ。 「たまにはまた飲みにいくか。」 「馬鹿。元々仁王と飲みに行ってなかったじゃん。」 「確かに。それもそうじゃの。」 いつだって会ったのは、飲み屋ではなく、うちだった。思えば、私は飲みにも誘ってもらえない女だったという事なのだろうか。利便性の高い所に家を構えた事にほんのりとした幸せを抱いたこともあったが、やはりそれはじんわりとした地獄でしかない。 「もう数年会ってない子もいるし、私行くね。」 「あんまり酔いすぎんようにな。」 きっと挨拶程度に私に話しかけてきたのだと思う。仁王から離れるような言葉をかけたのは私に違いなかったけれど、それを止めては貰えなかった。他所へ行くという私の言葉に、本当は引き止めて欲しかった。求める相手が違うと分かっていながらも望んでしまった自分が酷く悲しかった。 「仁王、またね。」 いかにも楽しい空間に紛れ込んでいるように見せかけて、私の気持ちはどん底へと落ちていた。もう期待はしない。何年期待しても、それはやってこなかったのだから。もう見切りをつけよう。 埃をかぶった、日に照らされたあのウイスキーも家に帰ったら流して捨てよう。 そう、思った。 ♯恍惚と劣等 |