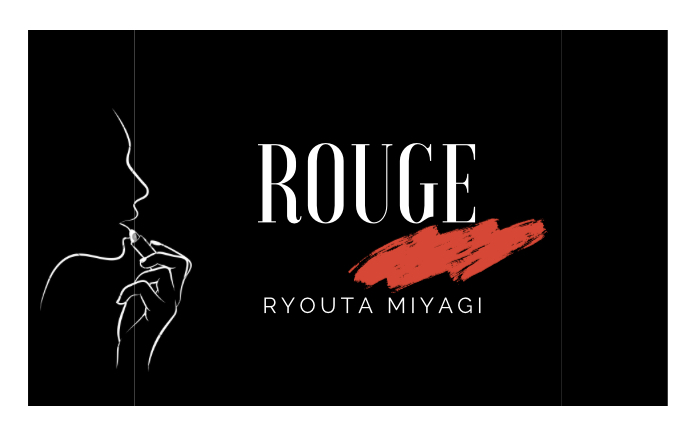 顔見知り程度でしかない同級生の宮城くんと再会した。そして、二回目の再会を果たして、彼は私の彼氏になった。顔見知り程度の関係から友達という関係を綺麗にすっ飛ばして、一気に進展しすぎて思考は追いついていない。いちいち緊張して正直気が気じゃない。 そんなあわあわしている私を他所に、宮城くんはマイペースだ。大きな筋の付いた二重は独特で、少しだけ眠そうだ。 「宮城くんって万年寝不足だったりする?」 「初めてのデートの一言目がそれ?」 「………うん、そうだね。ごめん忘れて。」 「ん、」 いつになったら心の底から楽しめるようになるんだろう。今の所私にはそのイメージが持てない。宮城くんと付き合っている限りずっとこんな緊張感を全身に浴び続けるんだろうか。私の分身が百体いても足りやしない。 「ちなみにめっちゃ寝てきて普通に元気なんだけど?」 「そう………それはよかったです。」 どんな会話なんだろう。自分でもよく分からない。付き合う事になったはいいものの、付き合い方がよく分からない。今まで彼氏がいなかった訳でもないのに、勝手が違いすぎてどうすべきか。これは恋に対するブランクが齎しているものなのであれば、徐々にリハビリすべきだが、もしかしたら付き合うかも?というあのモドカシイ感情を彷彿とさせた瞬間、電光石火のように宮城くんは私の彼氏になってしまった。リハビリもクソもない。スケジュール感が崩壊している。 「ってほんとお酒好きなんだな。」 「あ、うん。命の水っていうじゃん?」 「女子が言ってんのは聞いた事ないな。」 「結構周りで聞くけどな〜。」 「周りって、どのあたり?」 「どの辺り……会社の近くだから新橋かな。」 「それ結構特殊な界隈だろ。」 言った後に直ぐに後悔した。仮にも付き合ってばかりの、しかも初回のデートで私は何を言っているんだろうか。冷静でいればこんな会話になる筈はないので、間違いなく今私が冷静じゃない事はよく分かった。 でも、それでいい。今日は冷静さを失う為にここを初回のデート場所に選定したのだから。 酒を飲んで少々我を忘れたくらいじゃないと、目を見て宮城くんと話せる気がしない。酒を飲んでも骨かもしれないけれど。彼氏なのに?そもそも彼氏ってどういう存在なんだろうか。どうでもいいけど、ブランクって恐ろしい。 「で、なんで今日は赤提灯系?」 「宮城くんこういうの嫌いだった?」 「いや、寧ろこっちの方がっぽいつうか落ち着くけど。」 「…けど?」 初めて私服で会う宮城くんは、なんだか少しだけ高校時代の面影があってどきどきする。卒業ぶりに再会した時に見たスーツ姿もどきどきした。多分何を見てもどきどきするので無限に同じ感想ばかりになってしまう。多感な時期はもう遠に卒業した気でいたけれど、私は今が一番多感な時期なのかもしれない。 「この間みたいに個室じゃないんだ?」 「……バリエーション変えた方が楽しいでしょ。」 「ま、いんだけど。」 「シコリのある言い方するね?」 「ま〜ね?そりゃ。」 偶然二度も再会をした宮城くんと居酒屋に行ったのがほんの一週間前のはなしで、世にも奇妙なはなしが存在するもので私はそこで宮城くんの彼女になったのだ。特にチョイスの意味はない、一番近くにあったチェーン店の居酒屋がたまたま個室だったというだけの事。ただそれだけだ。 「二次会は個室にする?」 「まだ飲んでもないのに二次会のはなし?」 「事前確認ダイジ、社会人の基本。」 思い出しただけで私の平熱で三十五度しかない体がインフルエンザに侵されたくらいの体感になるので記憶の奥底に沈めているのに、宮城くんは悪びれる様子もなく簡単に掘り出してくる。多分無意識じゃない。明らかに故意にやっている。付き合いは短いし、今この瞬間がなんなら付き合ってから初めてのデートだし、卒業後宮城くんと会うのはこれで三回目だ。 「で、何飲む?」 宮城くんは空気を読むのが上手なんだと思う。私が欲しい言葉を欲しいタイミングで、それもさりげなくくれたりする。私が宮城くんを好きだと思うポイントその一だ。その二からその十までは、まだ心の内に秘めておこうと思う。言語化すると、十どころか百まで増えていそうなので、一旦寝かしておく。 もう一つ、再会してから分かった事がある。宮城くんは、マイペースだ。でも、かなりぐいぐい歩み寄ってくる感じのマイペースだ。私の都合なんて関係なしに距離感を詰めてきて、恋愛に対するリハビリなんて悠長なことはしてくれない。 「決まらないんだったら次の店行くけど。」 「…ビールにする。」 「そう、なら俺も同じのにするかな。」 俺もビールにすると言うのと、俺も同じのにすると言うのは同じ言葉のように聞こえて全然違う。と、私は思っているけれど、これは私の解釈がいよいよダム決壊を起こしているんだろうか。宮城くんが一言呟くだけでダムが決壊しているんじゃ、私の死期は割と近い。 「宮城くん、絶対わざとでしょ………」 「どの辺りの事言ってんの?」 「そういうところを言っています。」 「の頭の中覗けないから分かんねえよ。」 普段は割と虚無顔な宮城くんが、少しだけ悪い顔をしている。それが確固たる証拠だ。完全に意図的に言っているし、私が何を考え何を言いたいのかを数値化不能な程に分かっているに違いない。そう、宮城くんは駆け引きが上手い。高校時代と変わったと思ったのはそこだ。 「 ってあからさまだよな〜。」 「そう?」 「個室だとまた俺にキスされると思ったんでしょ。」 「………平然とした顔で言わないでくれる?」 「なんだよ、違うの?」 「違くないけど……」 散々シラを切って私に今日この場所を選んだ真意を聞いていたくせに、あっけらかんとした態度で普通に確信に迫る。私の事を何度半殺しにすれば気が済むんだろう。恋愛をするのってこんな命懸けだっただろうか。思い出しても、私にそんな戦争のような過去の恋愛は存在しない。 「正しい判断だと思うよ。多分、するから。」 「場所と科白があってない。」 「そのミスマッチはのせいじゃん。」 もう一度宮城くんは、「ま〜いんだけど」とそう言って、満足げにビールを二つ頼んだ。終始宮城くんのペースにはまりきっているのは不服だ。でも、どきどきはするので、やっぱりこれは戦争でもあって恋でもあるし、私の彼氏なんだとよく分からない所で納得させられた。これが盛大な動悸でなければ、きっと間違いなくこれは恋なのだろうから。 冷静さを失ったくらいの方がまともに喋れると思ってこの店をチョイスしているので、運ばれてきた生ビールジョッキを一度カチンと鳴らして、私は勢いよくその苦味を味わった。シラフでいた方が負けでしかない気がする。 「食べ物どしよっか、宮城くん嫌いなのある?」 「全然へーき、割と何でも食える。」 「食べれるものじゃなくて、好きなの聞きたい。」 「んじゃ、はなにが好き?」 再会してからずっと思ってはいたけれど、私は宮城くんの事をよく知らない。何が好きなのかも知らないし、普段何をして過ごしているのかも知らない。高校時代少し離れた所で見ていたくらいの薄い情報しかなく、バスケが上手かったなというペラペラ飛んでいきそうな情報量しかない。 私がこうして質問しても、毎回自然と私の話にすり替えられている気がする。私ばかりが自己開示していて、なんだか不公平だ。本音を言えば、もっと宮城くんの事を知りたいし、共感したい。それは彼氏だからという義務感から生じるものではなくて、純粋に彼を知りたいと思う気持ちだ。じゃなきゃ彼氏になんてなってる筈がない。 「砂肝串、レバニラ、枝豆、軟骨の唐揚げ、漬物盛り合わせと、あとはね………」 「ふは……全部新橋のリーマンチョイスじゃん。」 もうこの際宮城くんから主導権を奪おうなんて考えなければいい事に気がついて、思ったままを口にする事にした。宮城くんが私のどこを好きになってくれたのかは分からないけれど、ありのままの私を好きになって貰わないとまるで意味がない。 少し癪ではあるけれど、くしゃっと笑った顔を見れたので全部帳消しにされてしまう。やっぱり、ずるい。 「俺もそれ全部好き。頼んでいい?」 「……うん。」 暫くすると私の酔いもそこそこまわってきて、割といい感じだ。いい感じというのは、あまり肩肘張らずに宮城くんと話せるようになったという意味だ。この間居酒屋で飲んだ時のように、キスが出来るモチベーションになった訳ではない。 運ばれてきた小鉢で、テーブルはぱんぱんだ。中華にきたのかと錯覚するような並びだが、ちなみにテーブルは回らない。 緊張が解けたからか、急にお腹が空く。宮城くんと卒業ぶりに再会した時も、私は牛丼屋で定食(大盛)を食べていたし、今日はテーブルをプチ中華にするくらい注文した。きっとよく食べる女だと思っているに違いない。 「ん〜、至福の時だわ。」 「そ?」 「うん、好物並んでるんだもん。」 「ならよかった。」 忖度する事なく自分の感情のままに箸を割って、早速右に左にと箸を泳がせる。やっぱり暖かいうちにと思い立って箸を置き、砂肝串に串ごと齧り付いた。自分の取り皿に置いて、今度は口の中をさっぱりさせる為に漬物の盛り合わせに箸の照準を合わせる。普通に美味い。 「宮城くんは食べないの?」 「ん〜、食べる。」 「箸も割ってないじゃん。」 「そのうち食べるって。」 少食なんだろうか。そういえば牛丼屋で再会した時も、私が大盛りを注文しているのに対して宮城くんは普通盛りだったし、元運動部なんだから大盛りくらい注文すべきと言ったら偏見だと言われたような気がする。 じっ、と効果音がつきそうなくらい宮城くんがこちらを見ている。悠長に肘なんかついて、箸を割る様子もない。見られすぎて穴が空いたら困るし、ビームが出てももっと困るので出来ればやめて欲しい。 つい先ほど主導権争いは放棄した筈なのに、いい具合に酔いが回ったのも手伝ってか余計なことが口から滑り落ちた。 「一杯食べる君が好き〜とか思ってたりして?」 どこかのコマーシャルで聞き覚えのあるフレーズが急に脳内で再生されて、そのまま口にしてみる。私が勝手に持っている高校時代の宮城くんのイメージは、多分少しシャイボーイなんだと思う。だからこんな事を冗談半分で言えば、慌てて否定するんじゃないだろうか。それが私の浅はかな見解だった。 「うん。まあ、普通に思ってるよね。」 酔いが回ったのか、酔いが冷めたのかよく分からない状況だ。最悪だ。裏をかいてみようとして、逆にその裏をかかれてしまった。別に最悪じゃないけど、私の寿命が刻一刻と縮まっているのであればそれは最悪だ。 「……だから場所と科白があってない。」 「じゃあ場所変える?」 どこまで行っても完全にボールは宮城くんが持っているのかと思うとやっぱり少し悔しい。裏を読んでも、更にその裏を読まれている。ならば、どうするか。しばし、考える。 「場所変えてもいいよ、次個室にする?」 ようやく口を押さえて感情をかんばせに映し出した宮城くんが見れた私は、今日一番の笑顔で満足を噛み締めた。 久しぶりに塗ったルージュは、その為だ。
狂わしのルージュ |