 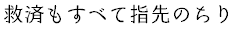  世の中は見違えるほどに平和だった。まるで鬼という存在がそもそも存在していなかったかのように、とても穏やかで、静かで、全てが終わったのだと私たちにそれを教えてくれる。 何をしようか、なんてのんびりとあてもなく考える。いつだって任務は与えられるもので、自分で考えて動くものではない。指示を下される事に慣れすぎた私は、自分のしたいと思う事すら容易には思い付かない。鬼殺隊に所属してから、ずいぶんと自発的に何かを考える事が苦手になっていた。 「おーい、暇人。暇してっか。」 「暇人に声かける暇を持て余す宇髄に言われたくないなあ。ちょっと癪。」 鬼殺隊としての役割は完全に終わった。排除すべき対象がいなくなった今、私たちが“鬼殺隊”である必要はない。時期にお館様より召集がかかるだろう。 もはや名ばかりの隊員でしかない私は完全に暇を持て余していた。召集が掛かり、解散を言い渡された後はどうしようかと考えるくらいにしか暇を持て余す術がなかった。まだ本部の近くにある住まいにかろうじているものの、私は極力同じく戦った仲間と顔を合わぬようひっそりと部屋の中にいた。 「何か用事?それともまさか指令?」 「んな訳ねえだろ。どうせ暇してると思って土産持ってきてやったんだ。」 「そう。頼んでないけどありがとう。」 彼は手土産と思わしき風呂敷を開いて、酒を取り出した。私に勧める前に自らその酒に口をつけるのだから、何が土産なのだろうかと思う。私も近くに寄れば、仕方がないとばかりに私にも酒を注いでもてなした。 思えばこうして酒を口にするのは久しぶりの事だった。元々嗜む程度くらいにしか酒は飲まなかったが、酒を飲んでいる余裕などなかった事を思い出してそれだけ自分が必死になって生きてきていたことを痛感させられる。必死だったからこそ、私は今まで救われていたのかもしれない。 「宇髄はお酒強そうだね。」 「は弱そうだな。」 「どうだろ。平均的じゃないかな、可もなく不可もなく。」 そう言えば何という言葉が返ってくるか想像できたが、久しぶりに彼のその言葉を聞いてみたいと思った。もうこんな会話を彼とすることもなく、きっとこれが最後になるのだろう。長い間共に戦った戦友に対する懐かしい気持ちだった。 「相変わらず地味な奴。」 予想していた台詞とどんぴしゃに重なって、可笑しくて笑えば少し不機嫌そうな宇髄の顔があったけれど特に気にはならない。こんな他愛もないやり取りをしたのはどれくらい前の事だっただろうか。思い出せないほどに、それは遠い過去の話のように思えた。 宇髄は私の同期にあたる男だった。彼は特別枠で最終選別には参加していなかったものの、同じ時期に隊員になった仲間だ。切磋琢磨して、ここまで切り抜けてきた。 「実際の所、生きて鬼のいない世を向かえられると思ってなかったんだ私。」 宇髄のように幼いころから戦いの世界を生きてきた訳でもない私は、ただの普通の女だった。特別何かに秀でる事もない、それこそ可もなく不可もない極々平凡な人間だった。 肉親を殺され、私には身寄りがなくなった。その時の苦痛を思い出すと未だに脈が崩れ、絶望の淵へと立たされているような気分に陥る。人としての再起を与えてくれたのは、鬼狩りをしているという鬼殺隊の人間だった。そこから私には鬼を滅するという明確な目的が生まれ、そしてそれを全うする事で自分の生きる意味を成していた。大して力もない自分がここまで生き残れるとは夢にも思っていなかった。 「俺と違って最後まで最前線にいてよく言うわ。」 「それは結果論に過ぎない。運がよかったんだと思う。」 「ここではそれが全てだろ。贅沢すぎる悩みだな。」 「…確かに。そうかもしれない。」 入隊した時から彼のほうが格段に強かった。結局はどれだけ必死になっても彼に敵うことはない。私がこうして何事もなく平然と終わりを迎えることが出来たのはただの幸運に過ぎないだろう。それが幸か不幸かは微妙なところだ。 別に死にたかった訳ではない。ただ、命を惜しく思うことはなかった。命からがら助かったとしても、私には何も残ってはいない。鬼殺隊に入る前に全てを失った私にとって、それに代わるものはないのだから。 「失うものがない人間のほうが強いって、あれ誰が言い始めたんだろう。」 「早々に酔ったか。」 「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。」 何処か人とかかわる事を、自分から遠ざけるようになっていた。それは隊に入ってからもそうだったし、全てが終わった今においては余計とその色が濃くなった気がする。自分でも意識しない中で、知らず知らず私は他人との距離を置いていたのだろう。 自分にとって、役割を課せられている事は幸せだった。生きる目的がなかった私に、鬼殺隊にいることは唯一の生きる理由になってくれた。だからこそ厳しい事にも耐えられたし、そして結果として今こうして生きているのだろうとも思う。 待ち望んでいた筈の平穏がやってきた時、嬉しさと共に徐々に違う感情に侵食されるものがあった。 役割を終えた私は、再びあの時と同じように目的を失ってしまった。今まで考える暇もなかった事が、自分の中でぐるぐると渦巻いていくその様にどうしようもない恐怖を感じた。 「宇髄はどうするの。これから。」 「そんなのゆっくり考える。別に差し迫って判断に迫られる事もなくなったからな。」 確かに彼の言うとおりだ。私たちはもう、自分の命が無くなるかもしれないという危機感に生きる必要もない。今までしたかったこと、出来なかった事、それをゆっくりと消化していけばいいのだ。頭ではそう分かってもいたけれど、如何せん自分の感情で動くことを忘れてしまった私は自分が何をしたいのか、したかったのかが分からないのだ。 「は何に怯えてる。」 「怯えてるのかな、私。」 「はが思う以上に、酒に弱いのかもしれないな。」 今までは目的があった。だからこそ、自分の気持ちに気づくこともなかった。彼は同じ釜の飯を分け合った戦友で、そして掛け替えのない存在だ。それは冨岡にしても、不死川にしても、他の隊員も同じだ。大切で、牛田痛くないとずっと思ってきた仲間だった。 予感はあった。けれど、自分のゆるぎない目的があって、それを成し遂げるまではずっとそのままで居られた。鬼のいる世を変えたいと思いながらも、自分が生きている限り“目的”がある世界で生きて居たかったのかもしれない。 「そっか。弱気になったのは、酔ったからか。」 「は弱いからな。」 その宇髄の言葉は的確だった。私の力にも、気持ちにも、酒にも、きっと全てが当てはまる。それが全て酒に弱いというだけの事であれば、幾分も気持ちは楽だったはずなのに。 鬼殺隊に入ってくる者の大半は、身内を鬼に殺された者だ。私もそうだった。一部、死んだ煉獄のように代々続く優れた鬼狩りの一族の者もいるが数は少ない。隊員の多くは鬼に憎しみ、そしてその大義名分を果たすためにここに入隊してくるのだ。 鬼殺隊に入ってからの日々は壮絶だった。私より能力に長けている鬼狩りなど沢山居て、常に上を目指すことに必死だった。言い換えると、必死になることが出来た。 そんな中でも同期という存在は特別だった。私の場合宇髄以外の同期は皆任務で死んでいったが、彼は柱になった。同期として、彼は私の誇りだった。私たちが叶えることの出来ないものを、彼なら叶えてくれると信じて疑わなかった。 微かに感じていた得体の知れない感情にも、今までは気づかないふりをしてこれた。それは私に隊務以外の何かに考えを至らす余裕がなかったからだ。彼は私にとって誇るべき同期で、そして鬼殺隊にとっての光なのだからとそう思っていた。 「バレてんだよ。お前都合が悪くなると俺の死角に隠れるだろ。」 綺麗だった彼の紅い瞳は、片方だけになってしまった。覆い隠すように覆っている彼のその左目は、私を映し出さない。意識をしていた訳ではなかった。きっと、無意識ながらも私は自分の都合が悪くなれば彼の死角である左側にいたのだろう。そんな弱みを、見せたくなどなかった。 「見えないくせしてよく見えるんだね、左目。」 「見縊られたもんだな。」 大切なものは、もういらないと思っていた。大切なものがあるからこそ、人は苦しむものだ。私自身がそれを一番よく知っている。そんなものがなけれな、失ったところで精神を病む事はない。もうあの苦しみを味わいたくはなかった。かろうじて助かった命を、再びいつ失うかもしれないものの為に一喜一憂されたくはなかった。 本当は自分の気持ちにも気づいていた。けれど、もう自分を苦しめることはしたくない。あの時には戻りたくはない。 役割が終わった今、自分の気持ちについて考える事が増えた。何がしたいのかは分からない。命じられた事にのみ忠実に働く事が出来ていたあの頃のほうがよっぽど私には生きる価値があった。それを終わらせる為に躍起になっていたのに、終われば自分が何をしたかったのか分からなくなった。 「私はこれ以上大切なものは増やしたくない。」 いつかは命にだって終わりが来る。修羅場を潜ってきた価値ある命でも、ふいに消えてなくなるのだ。それが事前に分かるものなのか、突如やってくるものなのかは分からない。けれど確実に終わりはやってくる。もちろん、私にも。 「大切なものがなく生きていく事の方がよっぽど寂しいもんだ。」 本当はもっと前から分かっていた。宇髄が遊郭で瀕死の重傷を負って戻ってきたとき、ふわふわと考えていただけのその感情が確信へと変わった。失うくらいなら、最初から関わる必要などないのだと。これ以上自分の心が壊れていきそうになる恐怖に、打ち勝てなかった。 「…酒豪の宇髄も酔った?」 「そういう事にしておいてやるよ。」 本当は冨岡とも、不死川とも、生きて全てを終わらせたことを喜びたかった。けれど、いつ消えてなくなるかも分からない彼らを失う恐怖に足が竦んだ。それを恐怖に思うのは私ではなく、彼ら本人に違いがないのに。 「終わったんだ。もう恐れることもないだろ。」 たったその一言が、恐怖に身動きの取れなかった私の強張った体を解いていくようだった。 「ねえ宇髄。」 「なんだよ。」 私が入隊から感じていた感情に嘘がなかったのだと気づかせてくれたこの男は、もしかするとどうしようもない罪な男なのかもしれない。いつかやってくるであろうその終わりに怯えながらも、きっと相反する喜びを感じながら過ごしていくのかもしれない。かかっていた呪縛が解けるように体が熱く、すうっとした。 「ありがとう。」 全てが終わってからずっともやの掛かっていた気持ちに、ようやく雲が引いたように晴れやかな気持ちになった。
|