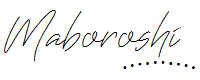 私の人生は、割と順調そのものだった。仕事でもそれなりに結果を出せていたし、私のことをよく理解してくれている私には過ぎた彼もいる。今のこの生活に、微塵も不満はなかった。公私共に充実していた。 中学のときも、高校のときも、大学のときもその時が人生で一番楽しいと思える人生だった。失敗をすることはあっても、後悔をしたような大きな出来事は特に記憶に残っていない。さすがに大学卒業間際は、学生ではなくこれから社会人になるのだから今までのように行かないと思っていたが、結果的には今というこの時代がやはり私にとっての変わらず一番だ。 そんな私にとって、ようやく初めて順調ではない出来事が訪れていた。その事に対する耐性が元々なかったからだろうか、私の気分は酷く落ちていった。ひとつの、まぼろしに、惑わされた。
左之と、セックスをした後の事だ。別に悪い事をした訳ではない。私たちは現に付き合っている間柄なのだから、その行為自体に悪や私が思い悩む事はなかった。問題は、その後の過程にあった。 彼とのセックスは好きだったし、何より私を思いやってくれるその気持ちが一番伝わってくるのだから嫌う必要はない。問題は、妊娠する可能性があると事後に発覚した事にあった。 すべてが終わった後に、事が発覚した。避妊具が完全無欠ではないものであるという理解がありつつ、今まで生きてきてその危険性を身に感じた事はなかったからどこか楽観的だったのかもしれない。私のせいでもなければ、それは左之のせいでもない事だった。誰も責める事は出来ない状況に違いなかった。 「なあ、。」 「うん。分かってる。」 「まだ何も言ってないだろ。」 「謝るの、分かってるから。」 不可抗力のこととは言え、私は焦っていた。まだそれが決定打で子どもが出来たという訳でもなかったが、それでも私はその不安を抱えながら生きていくことに対して酷く抵抗があった。 彼とは付き合って数年になる。短い付き合いという訳でもなければ、将来をまったく考えていない訳でもなかった。彼との将来があると思えばうれしい気持ちがありながらも、今すぐに子どもが出来て当たり前のように結婚をして、家庭を作りたいと思っていた訳ではなかった。 「大丈夫だよ。今の医学は発達してるし、どうにかなる。」 その言葉に彼は一度不思議そうにしていたが、翌朝病院に行くと言ったら意味を理解してくれていたようだった。望まない妊娠の可能性があるのであれば、それに頼るしかなかった。 「子ども出来たって分かった訳でもないのにか。」 「結婚もしてないのに、今出来ても困るでしょ。私も、左之も。」 本来であれば私もこんな気遣いの出来ない言葉を直接的に言うことはなかっただろうけれど、何よりこの時の私には微塵にも余裕がなかった。この先、どうすれば自分自身にとっての最善なのか、酷く自己中心的な考えのみが支配していた。こんな時男の人は自分ごとではないのだから、少し気が楽だろうななんて嫌な女でしかない事を考えていた。 こんな事を言えば、優しい彼が何を言うかなんていつもの私であれば分かっていたはずなのに、結果的に言わせるような言葉を紡いでしまった。 「、俺たち結婚しよう。」 「そんな…責任取らせるような形でプロポーズされても。困るよ。」 「俺はいつだってそう思ってた。タイミングは、間違えちまったが。」 言ってもらうのであれば、普通にプロポーズをされたかった。子どもが出来たかもしれないという口実の元に出てきた言葉は、そうではないと何処か分かっていながらも私を卑屈にさせた。本当に、嫌な女だなと自己嫌悪に陥るくらいには。 私が左之に振り向いて欲しいと思ってるだけのただの女なら、ただのお人よしだよそれ。そう出掛かった言葉を止めるのが、唯一私に出来る最大の配慮だった。 左之が結婚を意識してくれているのは知っていた。二人で出かけて、そんな風景を目にした時にそんな話で幸せな会話をした事も何度もあるのだから、こんな事がなければ間違いなく私はその先ほどの彼の言葉を素直に受け入れることが出来ただろう。そこにあった結末は、ただの幸せだったに違いない。 「本当に結婚したいと思ってる。…駄目、か。」 だんだんと酷くイケナイ事をしているような気分に陥った。確かに彼に思いやりのかけらもない言葉を放ってしまった私がある程度悪い事をしているという自覚はあったが、どうにも釈然としない。 「その気持ちは素直に嬉しい。」 「なら、何が駄目なんだ。」 「私、まだ仕事したいの。もう少しキャリア積んで、自分の力を試したい。」 そう言えば、左之が黙ってしまう事を分かっていながらも、言ってしまった。自分の本心を。プロポーズをしてくれた彼に対して、酷でしかない言葉だろうと思う。自分自身が逆の立場であっても、そう思うに違いない。 左之と結婚したいと思っていたという私の気持ちに嘘はない。事実、一緒になるのであれば彼以外は考えていなかった。それくらいに、私は彼が好きだった。安心できて、ずっと好きと思えるその環境を与えてくれる彼が間違いなく好きだった。ただひとつ彼と違うのは、もし子どもが出来たときにそれを産み落とすのは彼ではなく私だという事実だ。私はまだ、自分の人生を歩いていきたい。子どもを生んで、母になって生きていく覚悟もなかった。 「まだ、子どもは産めない。出来たって訳でもないけど。」 彼が子ども好きというのもよく知っている。私だって、嫌いな訳ではない。甥っ子姪っ子がいる左之はよく彼らの話をしていたし、その事を話す時の彼の顔を見ていれば直接的に聞いたわけではなくとも、自分の子どもが欲しいと思っている事は容易に想像がついた。そんな彼の夢に協力できないもどかしさを少し情けなく思いながらも、私はまだ大人になれない。 まだ出来たと決まった訳でもない、確証もなにもないそれをもみ消すという行為に酷く抵抗があるのだろうと思う。彼は、そういう人だ。けれど、事情も事情ゆえに彼も上手な言葉が見つけられないようだった。 プロポーズをされた筈のこの夜が、酷く気まずい時間になってしまった。 ベッドの下に散らかっていた服を拾い上げて、袖を通す。何故、つい先ほどまであれだけ幸せな気持ちだったのに、こうも気持ちが動転してしまうのだろうかと世の中の摂理を不思議に思いながら彼の元を去り、既に終わっていた終電に私はタクシーを一台呼んで、彼の家を後にした。この後、一体彼と私に待ち受けているのは継続なのか、それとも別れなのか。
緊急トラブルが発生したのだと、朝っぱらからその電話が知らせていた。内容を聞けば、自分が関係している事でもあったのだから、午前休が欲しく申請しようとしていた所だったとは言えるはずも無く私は結局現場に直行することになった。 なんとか昼前には一件落着となったものの、私はタイミングを逃してしまった。昨日の夜のことを思い出すと、一刻も早く病院へと出向いて処方を受けるべきと分かってもいたが、その後の後処理もありオフィスへと何事も無かったように戻った。 こういう日に限って、仕事が片付かない。元々の業務量と、緊急トラブルというイレギュラーな案件を抱えつつ、自分自身考えることが多すぎていつも以上に仕事が進まないのも事実だった。結局どこの病院ももはや開いてはいないだろうと諦めのつく時間になった時、私は諦めたように溜まった仕事に再び手をつけた。 ようやく仕事を終えて、私はオフィスを出る。いっぱいいっぱいで気づいていなかったが、彼からの連絡はなかった。こうしてひとつ、何かが終わっていくのだろうかとぼんやりと回らない頭で考えていた。酷く後味の悪い結末だなと思わず笑いたくなる。 自宅のロビーへとついた時、私を待ち構えていたのはまさに、今別れがよぎった彼の姿だった。夢を見ていた訳ではなかったけれど、これは正夢に近いものなのだろうか。 「。随分遅いんだな。」 「仕事でトラブルが起きて、今日はずっとその後処理してたから。」 彼の様子を見て、かなり長く私を待っていたのだろうなとうかがい知れた。ホットコーヒーらしきものを持っていた彼の手元からは湯気は出ていない。 「部屋で待ってればいいのに。それとも、鍵なくした?」 「勝手に入るのも気が引けるからな。」 スーツ姿の彼は、そう言って少し遠慮がちに笑った。彼の言い分ももっともだなと、私も冷静になって考える。昨日の夜の事を考えると左之にそんな事が出来るはずがないと。 「なら、電話くれたらよかったのに。」 もう一度自分の端末を確認して、彼の着信が無いことを確認する。それどころか、メールすら私には届いていない。直接別れの言葉でも告げに来たとでも言うのだろうか。 「電波を通しちまったら、何だか嘘っぽくなると思ったんだよ。」 実に彼らしい言葉だった。誠実さに長けた、その言葉に少しだけ安心した。別れを告げられる訳ではないと、なんとなく察知したからなのだろうか。けれど、果たして昨日以前の二人に私は戻ることが出来るのだろうか。このことが、私たちに蟠りをもたらす様な気がしていて、素直に喜ぶことが出来ないでいた。 こんな時何と彼に言葉をかけるのが正解なのだろうか。病院へは行き損ねたのだと、一言告げるべきか。伝えたところで、さして明るい雰囲気になる訳でもなければ、結果として私は今日それをしなかっただけで、きっと明日には実行するのだから。 「が好きだ。結婚して欲しいと思ってる。」 昨日と同じように、そう告げた。 昨日よりもしっかりと落ち着いて、私を射抜くようなその視線で、ぶれる事のない言葉を紡いでいくれた。それは、昨日の責任を取るという取り繕いの言葉ではなくて、しっかりとした彼の意思であるのだと私に告げるような声音だった。 「子ども、欲しいんじゃないの。」 「そりゃ欲しいとは思うが、にとってそれが今じゃないなら仕方ない。」 「いつ私がそう思うかなんて、分からないし。」 「そう思った時に作ればいいだろ。結婚したいって気持ちと昨日のことは関係ない。」 はっきりと言ってくれた彼に、私の気持ちも素直に固まっていた。私の首が横に振れる筈もないという事を彼は知らないのだろうか。こんな少女漫画の世界でしかないようなシチュエーションを前に、誰がそんな事を言えるというのかと思う。 「俺はお前と一緒にいたい。」 柄にもなく、絵に描いたような幸せな箱を彼は私に手渡してくれる。漫画の世界の出てくるようなヒロインに、私は今なれているだろうかとそんなくだらない事を思った。 私にはやりたい事がある。もっと仕事で経験をつけて、まだ自分に兼ね備わっていないスキルをつけたい。それは私の希望でもあり、本音でもある。けれど、そんな私の希望も本音も、彼を前にする事で塗り変わっていく。何よりも、彼と一緒にいる事こそが、私の本音だという事実に。 「ずるいね、左之は。」 「なんだよ。断ってんのか、それ。」 しっかりとその箱を受け取った私によく言うなと、思わず笑ってしまう。ほんの僅かばかり、今日の朝のトラブルに感謝をした自分がいた。確証のないまぼろしを、自ら摘みに行く必要もないのかもしれない。彼は、人の考え方を変える天才だと思った。 「こんなに好きにさせるなんて、ずるい。」
|
