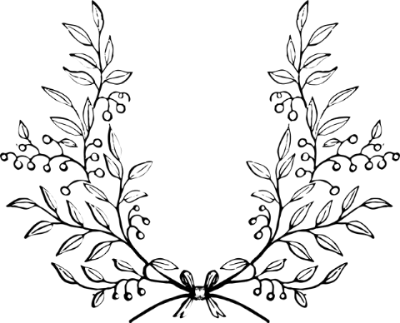 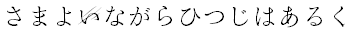 いつも周りから言われる言葉があまりにも正論すぎて耳を塞いだ。そんな男はやめたほうがいいと何度聞いたかそれは数えきることができない。誰に言っても返ってくる答えは同じ類で、私は自分を諦めさせるためにそんな同じ答えしか返ってこないと分かりながらも彼との関係を伝えていたのかもしれない。 彼と一緒にいるようになって、どれくらいが経つだろうか。ずっと前から一緒にいたと言われればそれもすうっと受け入れられたが、ついこの間知り合ってばかりだろうと言われればそれもしっくりとくる。私と彼の関係性は、それだけ自然であって、希薄なものだった。 「ねえ、どこか出かけようよたまには。」 「どこに行きたいんじゃ、は。」 「うーん。どこだろう。分かんないや。仁王と一緒ならどこでもいいよ。」 「今おるじゃろ、一緒に。」 おかしな奴。そう言って彼は笑った。いつだって仁王のペースに持ち込まれて、私が彼に合わせるような形になる。彼に合わせないと、私にはその先がないと本能的に私の体が知っているのだろう。いつだっておびえながら生きてきた。いつ、仁王が自分の前から消えてしまうのかと不安に怯えながら。 「仁王はさ、何かしたい事とかってないの?」 「なんじゃ藪から棒に。」 「そう言えば仁王がああしたいこうしたいって言ってるの聞いたことないなと思って。」 仁王は欲のない人間なのだろうかと考えたことがあった。何事にも頓着しない彼を、どこか人間とは似て非なるものだと感じることが多々あった。その頓着は物欲に対してだけでなく、私に対してもそうだ。きっと別れる理由もないからまだ私を傍においているというだけの事で私への執着など微塵も持ち合わせていない。 きっと、こんな事を言えば彼は笑顔で私の前から姿を消すだろうから、いつだって私は口を紡いだ。仁王の彼女である自分を演じた。 「欲なら、ある。」 そう言って、彼は私に触れた。まるで私が強請ったような形で、そっと冷たい仁王の手が服の中へと滑り込んだ。きっと、彼も演じているのだ。私の彼氏である自分を。このあたりで抱いておけば、きっと満足するのだろうとそんな理由で、ひねり出しても出てこないような欲を作り出したのだ。 何度仁王に抱かれても、満たされることは一度もなかった。どれだけ丁寧に愛撫されて、時間をかけた丁寧なセックスをしてくれても、不安に陥った。繋がっているのは心ではなく、下半身だけなのだといつも思わされた。 隣にいてほしいといつだって望む仁王はそこにいるのに、いつだってその存在が私を苦しめた。せめて普通のカップルがするようなデートでもすれば、私の気も晴れるだろうかと思い出かけたいと提案してみたものの、きっとそれを実行したところで満たされることはないのだろう。 本当は分かっていた。彼と別れない限り、この苦悩から私が解放される日なんて永遠にやってこないのだと。ただ、認めたくないだけだった。 「今日は何食べる?」 「何がいいかの。寒いし、鍋とか。」 「いいね。モツ鍋とかどうかな。」 彼のうなずきで、私は台所へと向かう。冷蔵庫を開けてみたけれど、見事なまでにそれは空っぽだった。コンビニに行ってくるねと声をかけて、小さな返事を聞くと私は食材を調達しに彼の家を出た。 スーパーに出向けばいいのに、それを面倒がっていつだって近所のコンビニで私は品ぞろいの悪さにため息をつきながら、野菜と肉を籠の中へと放り投げた。 普通のカップルであれば、一緒にスーパーに出向いて、ああでもないこうでもないと言い合って食材を選び、帰りに袋を半分に分けて持ったりするのだろうか。彼氏と呼ばれる存在は彼と付き合う前にも何人かいたはずなのに、すっかりと普通の恋人がどういうものであったのかを私は忘れてしまっていた。 コンビニを出て、少し歩く。すぐ目の前に、彼の家が映し出されて居心地が悪いそこへと私は帰っていく。ただいまと声をかければ、おかえりと聞こえた。 「ねえ、手伝ってよ。」 そういえば、気だるそうに台所へとやってきた。何も言うこともなく、袋の中から葱と取り出して、均等になるように包丁を入れていく。私は鍋にスープを入れて、それに火をかけた。 何故私はこうまで満たされないのだろうか。好きと言えば、俺もと答えてくれる彼がそこにいるのに、それを望んでいるはずなのに満たされない感情をなんと呼ぶのだろうか。 別れてしまえばいいと、分かっていた。そうすれば私はまた別の恋をして、他の男を好きになれるかもしれない。どの友人に話しても、仁王とは別れたほうがいいと言われるけれど、私はいつも一歩手前で考え、立ち止まった。今日こそはこの得体の知れない感情から解放されたいと、そう決意を固める。 「ねえ、仁王。」 「なんじゃ。」 葱を切り終えたのか、手持ち無沙汰になった仁王は包丁を置いて後ろから私を抱きしめた。こんな幸せな事はないはずなのに、どうしようもなく苦しい。私は一体彼に何を求めているのか、自分でも分からなくなっていた。 別れよう。その一言を紡げば、すぐにこの感情から開放されるのだ。別れたくないと引き止める仁王なんて、存在しないのだから。簡単な一言だけですべてが片付くのに、やっぱり私はその簡単な一言をいつだって口にすることができない。 「ううん。何でもない。好きだな、やっぱり仁王のこと。」 「俺も。」 そこにあるのは、私の唯一の“欲”だ。 ( 2020'03'16 ) |