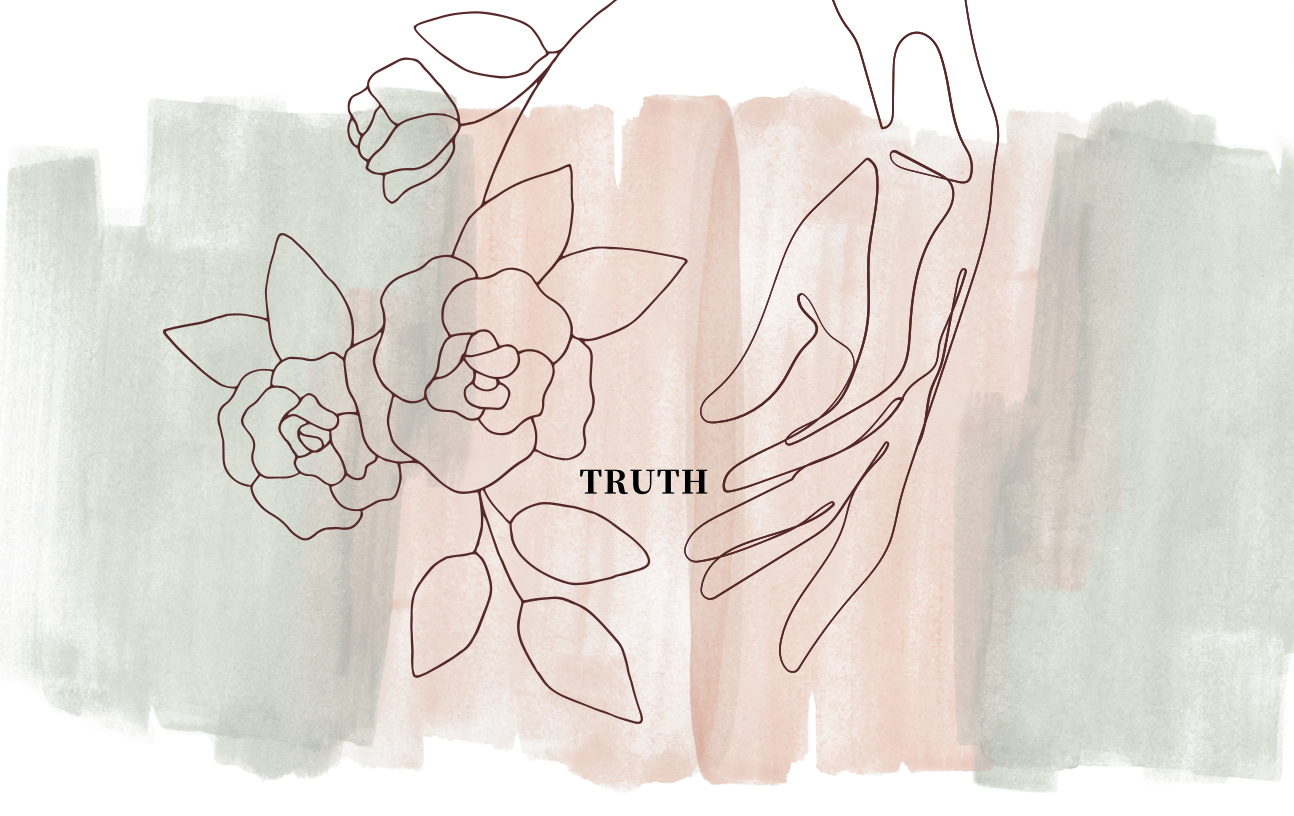 そろそろ一人暮らしでもしようかとスマホで物件情報をすいすい指で流しながら探していく。もちろん、防衛任務の合間の暇な時間を使ってだ。国の存亡がかかっているボーダーの任務中に小さい箱の情報を探しているなんて一体どういう神経をしているのかと怒られそうだが、そうそう防衛任務中にイレギュラーゲートが開いたり、国の存亡に関わることが起こっていたら流石に体力がもたない。 世間がボーダーにどういうイメージを持っているかは知らないが、見回りを含んでいる防衛任務は、何も起こらず終わることの方が圧倒的に多い。 「遅めの反抗期か?」 もう間も無く夜明けとなる午前四時前、あらぬ方向から聞こえてきた声に振り返ると嗅ぎ慣れた煙草の匂いと、見慣れたかんばせがセットでやってきた。私は彼以上に黒目と白目の比率が合わない男を知らない。 「冗談言うならカラコンつけてからにして。」 「その斬新な切り返しやめろ。」 いつも諏訪は重ための煙草の匂いと一緒にやってくる。“匂い”というものは特別感のあるものだ。好きな人と同じ香水を街中でふと感じた時にその人を思い出すように、そして人の禁忌を犯さないという本能に基づき父親の匂いに嫌悪感を感じるように、だ。諏訪はそのどちらにもぴたりとは当てはまらずとも、どちらかと絞れば前者よりは後者だろう。 「万年金欠の奴がどうやって一人で生活すんだよ。」 「諏訪と違って追い込まれたら出来るタイプだから。」 「あ?」 「夏休みのラスト三日とかで宿題できちゃうってこと。」 夏休みの宿題を終えて八月三十一日を迎えたことは一度もない。自慢どころか自分の汚点でしかないが、休み明けの学校での会話にはまず困らない。高校を卒業するまでの過程で、八月三十一日は唯一毎年私が必死に勉強をしている点においては“皆勤賞”なのである。 昔から要領はいい方だった。できる限り必要最低限のエネルギーで解決したいというただのずぼらな人間で、でもその分いつまでに何を挽回すれば間に合うかという悪知恵のような勝ち筋だけはいつだって考えていた。地道にコツコツと何かに取り組むのは苦手だ。 「諏訪は早くから宿題に手つけてるタイプでしょ?」 「お前と違って計画性があんだよ。」 大雑把に見えて、案外諏訪には几帳面なところがある。見た目からしてずぼら感満載のくせに、結構これでいて細かいところまで気の使える男だ。面倒見がいいのはそこに付随しているのだろう。諏訪を例えるなら、痒いところに手が届く孫の手のような男という表現が近い。 「諏訪と違って感性で動けるタイプだから、私。」 諏訪と同じ年の私がボーダーに入ったのは一年と少し前だ。諏訪のボーダー歴に比べたら半分くらいの歴しかない。ボーダーに入ったきっかけは、大学で知り合った諏訪の影響だった。彼がボーダー隊員である事を知ったタイミングで最短の入隊試験を受けて、見事合格となった。 一年と少し前に私の師匠であった諏訪はB級で、今の私の階級がAであることが何よりも私の言葉を真実味のあるものへとしてくれているだろう。あえてこれ以上言及することは控えるようにしている。 「男にそういう事言ってっとモテねえぞ。」 「別に諏訪からモテても。」 「換装解いたら覚えとけ。」 諏訪がどんな理由でボーダーに入ったのかは知らないけれど、少なくとも私の理由よりは幾分かマシだろうと思う。今まで聞かれたことがないというだけで言う事から難を逃れているが、大学に通うにあたってボーダーに入った方が自分にとって都合が良かっただけという酷く自己都合な理由でしかない。 入学して暫くした頃に行われた小テスト中、緊急で入ったボーダーの任務で諏訪はそのテストを途中退出したのだ。もちろんお咎めはなしだ。その後の小テストを寝坊して休んだ私の方が結果的にその講義の単位を落としたというお粗末な結果までがセットで笑い話である。夏休みに入る前、ダルそうに喫煙所で煙草をふかしていた諏訪に、私から声をかけた。 “ボーダーにはどうやったら入れるのか” 諏訪との付き合いはそれからだ。私は諏訪を知っていたけれど、諏訪は多分私のことをその時初めて知ったのだろうと思う。キャンパス内でも一番収容人数の多い大講義室の授業で、諏訪が見ず知らずの私を認識してるはずもない。だから私がボーダーに入った理由は恐らく諏訪の知るところではないだろうし、こちらとしては説明は割愛したい。 「で、なんで突然部屋探してんだよ。」 漠然としたその場のノリでしか動かない私にとって、こういったオープンクエッションは時に回答に困るものだ。大した理由もないのに、“なんで?”に回答するのは難しい。せめて二択形式で質問を投げかけてほしい。 「うーん、何でなんだろう?」 「こっちが質問してんだよ、聞くな。」 「じゃあ何で諏訪は一人暮らししてんの?」 「は?いや、普通に男だからだろ。」 私の質問返しも大概な返答だろうけれど、諏訪のこの返答も私からしたらよく分からない。高校を卒業した男は一人暮らしを義務付けられている訳でもないのだから、私の問いに対しての回答としては的を得ていない。 万年金欠と言われ言い返す事ができない私にも問題は山積みだが、A級と違って固定給のないB級の諏訪の方が普通に考えて実家から出る必要がないのではないだろうか。 「あ、下ネタ的な意味で?」 「中坊じゃねんだよ。」 「中坊を敵に回したよ、いま。」 何故私はこうして単身用の部屋を探しているのか、言われてみれば何故なのだろうかと自分自身でも気になってきた。本当に何故だろうか。大学入学のタイミングならまだしも、大学三年のこのタイミングというのもかなり不自然だ。何かしらの理由がないと、辻褄が合わない。 「きっかけみたいなものは幾つかあるけど……」 防衛任務のシフトは夜勤を含めて不規則で活動内容に対しても家族に心配をかけるなとか、ボーダーでも大学でも一人暮らしをしている人が多く自分が自立できていないのは実家にいるからなのだろうかとか、多分他にも理由や家を出ようというきっかけになるものはいくらでも出てくるけれど、決定的な理由というものはなく、結果的にただ何となくという表現に落ち着いてしまう。どれも今更?という内容だ。 「ところで、諏訪は幾ら貯金ある?」 「俺はお前の情緒がどうなってんのか聞きたい。」 ちなみに私の貯金はほとんどなく、毎月固定給をそこそこもらっているにも関わらずいつだってすっかんぴんだ。世の中はどんどんと便利になっているし、現金を持たずともスマートフォンで気軽に買い物ができてしまう時代だ。キャッシュレスという決済方法は現金よりも簡単にチャリチャリ音を鳴らすし、その代償を背負うのはリアルタイムではなく翌月の末に通知で知ったりするものだから反省や改善を試みにくいというデメリットがある。 「教えてくれてもいいじゃん。」 「俺に得がない。」 「大丈夫、風間くんぐらいにしか言わないから。」 「一番ダメだろ。」 一人暮らしを本当にするかどうかはわからない。ノリと勢いで始めた事は熱が冷めた瞬間、無に帰すこともあるのだから今回もその可能性は多いにあるだろう。実家を一度も出た事のない自分にとって単純に一人暮らしの相場が知りたかったり、六畳一間の四角いパーソナルスペースにどんな家具を配置するかという財布にエコなバーチャルごっこをしていただけの可能性は大いにある。 「諏訪もこっち側の人間っぽいんだけどね、一見。」 「理性も知性も持ち合わせてるもんで。」 派手に酒を飲むことはあるし、よく後輩に食事を奢ったりもしているからそこそこの出費はあるにしても、それ以外での諏訪の生活は質素だ。 防衛任務後に仲間内で飲みに出かけた事があるが、夜勤で明らかに寝不足だった私は珍しく早々にその場で居眠りを漕いてしまった。諏訪におぶられて彼の部屋へ一度だけ上がった事があったが、必要最低限のものしかないミニマリストに近い部屋だったのを覚えている。 灰皿に吸い殻はなく、喫煙者の部屋の割に嫌な匂いがあまりしない。しっかりと手入れが行き届いている築年数の古いアパートは、隣人がいつ帰ってきたのか分かるくらいに壁が薄かった。 若干の二日酔いで翌朝目覚めた私は、まだ酒が残っているせいもあってか〆る何かが欲しく、きっとストックされているであろうカップ麺を所望したが、彼の家にありそうなそれはなく、代わりにラップに小分けされている冷凍ご飯をチンしてお茶漬けを出してきた。 「節制した生活してるよね。貧乏くさいとも言うけど。」 諏訪の部屋の構造や、多めに炊いた米を小分けにして冷凍しておくという主婦技を披露した事を伝えたいのではなく、諏訪は多少人に金を使うことはあっても質素な生活をしているという事だ。だから、多くはないにしても貯金を幾らか蓄えているのではないかと思ったのだ。 「お前に危機管理能力ってもんはないのか。」 「それは本当にたまに思う、皆無だなって。」 「……自覚はあるんだな。」 多分、社会で生きていく中では私なんかよりも諏訪のように危機管理能力が備わっている人間の方が適合していくのだろう。だからこそ、私も社会に少しでも適合しようと思って、一人暮らし先を無意識に探し始めたのかもしれない。 「人生いつ終わるかわかったらそこに向けて調整できるのにな。」 人生がいつ終わるかなんて、誰も知りはしない予測不能の出来事だ。雑居ビルに行列ができる“よく当たる”と評判の占い師の主人だって、自分の人生の終焉なんて読むことは出来ないはずだ。だから人は、万が一に備えて貯蓄をするのだろうけれど、私の考え方はその逆なのかもしれない。いつ終わるかわからないからこそ、未来ではなく今に目を向けて生きている。我ごとながら、危機管理能力を測定できる機械があれば限りなくゼロに近い値が出るだろうと思う。 諏訪とは、考え方も性格も全然違うけれど何故か気があった。もしかするとそれは、諏訪が誰とでも上手くやっていけるという柔軟性を持ち合わせているから、私がそう思っているだけなのかもしれない。取り敢えず、諏訪の隣は落ち着く。一言で表すとすれば、居心地がいいのだ。 「んな事考えてどうすんだ。」 諏訪の言う通り、そんな事考えたところで意味はない。そんな事はわかっている。だから考えても仕方のない未来の事ではなく、今自分がどうしたいか、自分の本能に従順に従っているまでだ。 「だから考えてないんだってば。」 「終わりなんて考えてちゃ何も始まんねぇからな。」 諏訪のくせにそれっぽい格好いい言葉にするのは何だか無性に腹が立つ。けれど、確かに言う通り終わりを意識している時点で何も始められないし、何に対しても臆病になる。 その終わりがいつ来るか分かれば調整できるなんて言ったものの、やっぱりそれが分からないからこそ今を全力で生きることができるのかもしれない。ならば、私の元来持ち合わせた考え方はこれっぽっちも間違っちゃいない。 「じゃあ一人暮らししてもなんとかなるって事じゃん。」 その後、諏訪は特別返事をする事なく咥えていた煙草のフィルターに限りなく近いところまで吸いきってから携帯灰皿にぐしゃりとへし折った。 終わりなんて考えてないからこそ、こんな自由気ままに生きてこれたのは事実だ。けれど、果たして私にとって何か“始まった”ことはあっただろうか。ボーダーに入った事くらいしかそれらしいことが思い浮かばなかったので、興味本位で見ていただけの物件内覧申込ボタンを押した。 初夏に向かう夜明けは、早い。 引っ越しをしてから一ヶ月が経つ。初日はどうなるかと意気込んだが、人間の慣れというものはすごいもので、ものの数日で生活に順応できた。万が一困ったときは、実家から持ってきた自転車で十五分ほど骨を折れば実家の美味しいご飯にありつく事ができる。 変わったことと言えば、今までたいして興味のなかった酒を自発的に飲むようになった事くらいだろうか。 元々酒は嫌いじゃない。あれば飲むし、誘われたら飲む。けれど、自発的に飲むことは今までほとんどなかった。それが引っ越してきてから暫くすると、何故だか自分自身で理由を把握できないまま、気づいた時にはごく自然にコンビニで甘そうな酒を何本か買って帰ることが日常になっていた。まだアルコール依存症ではないと信じたい。 「諏訪、それそっちじゃない!右って言ったじゃん。」 「お前と逆方向向いてんだ、てめえの目線で言うな。」 引っ越しは諏訪に手伝ってもらった。理由は二つだけ、軽トラックの運転ができるマニュアル免許を持っているのが諏訪だけだった事、そして無条件で引っ越しの手伝いを依頼できるのが諏訪しかいなかったという単純明快な理由だ。あえて本人に理由を宣言しなかったのは、手伝ってくれた恩に対する対価だ。私には謝礼金を払う程の金銭的余裕はなく、感謝の念を贈ることくらいしか出来ない。 「つーかここ、俺の家から数分なの知ってっか。」 「意図せずご近所さんになれてよかったじゃん。」 「その上から目線イラつくからやめろ。」 「前行った時寝てたし、普通に知らなかった。」 そうか、この近所に諏訪の家があるのか。そう知った時、下心なくラッキーだと安易に思った。理由は簡単だ。何かあった時、すぐに助けを呼べるちょうどいい位置にいるのだと知れたからだ。 以前一度だけ運ばれるようにして上がった諏訪の家がどこにあるか、正確な位置など知る由もない。諏訪の近くに家を借りたのは本当にただの偶然だ。 ボーダー本部は三門市の中でも駅から離れた場所に存在している。私の実家は今の住まいよりもよっぽど本部に近く、言い換えるとそれだけ警戒区域に近いということだ。そんな場所にある実家と家族を守るべく守護の任についていると言えば格好もつくが、結局私は本部から遠くなる道を選んだ。毎日の通学に利便性が高いことを優先した結果だ。 「大丈夫、寂しいとか言って呼び出したりしないから。」 帰れる実家が目と鼻の先にあるとは言え、自ら必要に駆られていない一人暮らしをした私にとって、毎日のように実家に帰るという概念は既にない。“あんた何しに実家でたの?”そう言われるのがわかっているからだ。 元々人と戯れることがあまり得意ではなかった。小さい頃からおままごとをするより、ひとり遊びができる自己完結型の遊びが好きだった。だから、一人暮らしを始めたところで今までと何も変わらないと思っていたのだ。寧ろ、決まった時間に起こされたり、食事に呼ばれたり、学校に行けと口うるさく言われたり、自分以外の誰かにペースを乱されることがない分自由でストレスフリーな環境を手に入れたと思っていた。 けれど、現実は想像通りにはいかないのがセオリーになっている。少しばかり、一人きりの空間に寂しさを感じるようになっていた。無意識に帰りがけのコンビニで酒を買うようになったのはその頃からだ。 大学の授業が終わった後、防衛任務をして帰路に着く。ここ最近習慣的になっている、コンビニで新しい美味しそうな酒はないか確認して、あれば買う、なければ馴染み酒を買っていた。防衛任務で授業に欠席しがちな私たちは、学部を超えてお互いに協力して極力同じ授業をとっていた。 授業中に諏訪の姿はなかった。恐らくは夜勤シフトだったのだろう。よっぽどのことが無い限り、授業中に寝ている事はあっても諏訪は極力授業に参加していた。 今日大学で会わなかったから、何だか不思議な気持ちになったのかもしれない。諏訪とは学校かボーダーか、いずれかでほぼ毎日顔を合わせている。だからと言って胸が苦しくなるほど諏訪に恋焦がれている訳でも無ければ、少し気にかけるくらいのものだ。 慣れた様子でコンビニの入口から見て正面奥にあるアルコールコーナーにたどり着く。チューハイにするか、それとも格好よくビールを買うか、そんな私以外どうでもいい事を考えながら手を伸ばした先に、同じく逆方向から同じ酒に誰かの手が伸びる。 「あっ。」 「あ、」 酒から視線を移せば、見慣れた顔がそこにはあった。こんな事態が絶対にないと思っていた訳ではない。最寄りのコンビニが同じであれば、いつか偶然ばったり会うこともあるだろうとは思っていた。しかし、こんなに早くその時がやってくるとは思わない。 「何カッコつけてビールなんて取ってんだよ。」 「私だってビールの気分の時があるんだよ。」 実にややこしい事に、私は負けん気が強い性格だ。だから、嫌いではないけれど自発的に頼むかと聞かれたらそうではない生ビールを克服したいと思ったのだ。乾杯を生ビールでできない人間は面倒くさがられるという私の古い考えだ。 「えっと……一緒に飲む?」 諏訪が相手なのだから気を使う必要なんてないけれど、少しだけうかがってしまう。どんな表情をしているのかとか、その言葉に対してどんなかんばせをするのだろうかとか。 「なら外に飲みにいくか?」 もっともな提案だと思う。お互い飲みたい気分なのであればそうすべきだし、今まではそうしてきた。状況として変わったのは、私が一人暮らしを諏訪の家の近くで最近始めたということだけだ。 「引っ越したてで全財産使ってお金ないんだよ。」 その言葉だけで察したのか、諏訪は気まずそうなかんばせを見せつけてくる。理由は簡単だ。私が何を望んでいるのかをわかっているからだ。 「今に限らず万年金ないだろ。」 「それは言わない約束。」 結局会話のネタに困った私が「部屋も整ってきたし、折角なら“女子”の部屋で飲む?」と言えば特別拒絶の言葉はなく、諏訪の家ではなくうちにくる事になった。 今更諏訪に緊張する必要なんて微塵もないし、寧ろそんなのは癪だ。意識する必要なんてないと思うからこそ逆に意識してしまっているのか、妙な心境だった。こういう時にどうすればいいのかわからない私は、妙な緊張感と共に諏訪を部屋に上げる。 「心配すんな、これ飲んだら帰るからよ。」 その言葉がなんだか他人行儀で、遠ざけられているように感じられた。多分諏訪に他意はないだろうから、普通に私の立場を考えてくれた一言なのだろうと思う。 諏訪の顔なんて、好みじゃない。友人としては最高だけど、彼氏としては想像すらできない。それに私は自分のことを差し置いて割と面食いだ。烏丸くんや隠岐くんは可愛いと思うし、唐沢さんはかっこいいいと思う。だから諏訪なんて、異性の対象として見えていない。 「帰らないでほしいって言ったら?」 そもそも今日誘ったのは私の方だ。諏訪は幾分か、恐らくは性別上女性である私の部屋に上がることに抵抗を感じていたようだった。そこを無理に上がらせたのは私だ。何故強引にまでそうしたのかと言えば、まだ自分の感情をまとめられない。 「飲む前から酔ってんのか。」 「酔ったていでいた方が便利な時もあるでしょ。」 あまり強くはない酒を一気に飲み干してみる。諏訪はあーあ、という顔で私がこの後愚痴を散々言うからみ酒になると思ったのだろうけれど、今日の私はそこまで酔えていない。寧ろ、そこまで前後不覚になれる方が幸せなのかもしれない。 「折角だしゆっくりすればいいじゃん。どうせ暇でしょ?」 自分から言い始めたくせに、言った直後には後悔がじんわりと広がる。これではまるで私が諏訪を心底好きみたいじゃないか。好きなのか?と自分に問いかけてみたが答えはなく、一時の幻たと思う事にした。 「お前、自分の言葉にもっと責任持てよ。」 ソファーなんてない六畳一間の我が家でベットの枠を背もたれに座っていた私たちは、お互い居心地が悪そうに一度向き合って、合わない視線を泳がせる。 「ねえ、目合わないんだけど。」 「おめえが合わせないからだろ。」 「あ、そっか。」 白目の比率が異様に高い諏訪の目が視界に映って、妙な緊張感が漂った。一ミリたりとも酔えていないんだと思う。得意ではないビールを一気に煽ったとは思えないほど私は冷静で、それでいて冷静ではない。自分で逃げ道を絶っているこの現状に、一体私は何を求めているのだろうか。 こういう時、女としてどうするのが正解なのだろうか。自分で導いておきながら、よくわからなくなって頭がぐるぐるする。今になって急激に酔いが回ってきたのだろうか。人間には鼻という平面な顔から立体的になっているパーツがあるので、正面で突き合わせると鼻がぶつかってしまう。否、そもそも私はこの男と何をしようとしているのだろうか。完全にパニックだ。 もしかしたらあるかもしれない有事に首を少しだけ左斜め下に傾けると、同じタイミングで諏訪も同じ方向に顔を傾ける。ならばと逆方向に向ければ、また同じタイミングで諏訪も同じ方向で目が合う。結局、私たちはその後数回同じことを繰り返すという世にも奇妙な喜劇を体現した。 「えっと……なんか食べる?」 「そうだな。」 つまめる物が何もない冷蔵庫を開いて「何もないからコンビニで買ってくるわ。」と白々しく言った私に、諏訪も特別突っ込むことなく了承した。何かつまみたかったわけじゃない。この居た堪れない空気感から逃げ出すきっかけが欲しかったのと、今のこの現状はビール一本で拭い切れるものではなくもっと多くのアルコールをお互い摂取しないといけないと思ったのだ。 多分、今日はどれだけ飲んでも間違った方向に進むことはないと根拠のない自信を持った私は、コンビニで籠を手繰り寄せると手当たり次第の酒を重みが感じるほど投げ入れた。結局食べ物を何も買わずに戻ってきてしまったのに気づいたのは、袋から無限に出てくる酒を出している時で、やっぱり私はこの時点で酔っていたのかもしれない。 結局あの時、私は自分で望んだ様に酒で酔い潰れて一部の記憶を失った。肝心な部分に関しては残念ながらはっきりくっきりと覚えているが、その後どんな話をしていたのかははっきりとは覚えていない。けれど、普通に楽しくおしゃべりしている間に寝落ちしたようだという事は何となく覚えている。 不意に目が覚めた時、諏訪もベッドの枠に持たれながら寝ていて少し安心した気持ちになった。こういう時、一人であることを自覚させられるのは想像以上にダメージが大きい。そんなよく分からない安心からか、結局私はベッドに移動することもなく、床に突っ伏したまま再び眠りに入った。翌朝腰の痛みで目を覚ました時、電気は消されていて、私の体にはベッドにあるはずの布団がかけられていた。そこに、諏訪はいなかった。 久しぶりに何もない一日を過ごす。今日は土曜日だ。大学もなければ、土曜日にしては珍しくボーダーのシフトも入っていない。暇を持て余すとはこういう時に使う言葉なのだろうと思う。本当にする事がない。暇だ。 暇だと人はろくな事を考えない。何かを考える暇だけは無限にあるからだろう。結局私はこの間の諏訪との事を思い出す。何故あの時、諏訪を試すように私は暴挙に出たのだろうか。その意味も結局のところ分からず、そしてその暴挙は結果として失敗に終わった。何も“始まらなかった”点においては“終わらない”選択肢を作れたのかもしれないので、失敗とは言い切れないが成功という訳でもない。多分表現として正しいのは、しなくてもよかった事を余計にしてしまったという感じだ。 大人はアルコールの力に頼って色んな事を忘れようと、紛らわせようとする生き物だ。この時初めて、私自身がここ最近酒を手にとるようになった理由を理解したような気がした。 コンビニで再び酒を手に取る。まだ明るいうちから飲むのは些か抵抗があったが、法律上何ら問題がないのだからと言い聞かせて籠に入れた。レジに持って行くと、店員の背景になるように煙草がずらりと並んでいるのが目に入る。 諏訪が普段吸っているのはどれだろうと自然と目で追って、気づいた時には棚に貼られている札を読み上げて、私は生まれて初めて煙草を買った。これも法律上何ら問題がないのでおどおどする必要はないけれど、無駄に“煙草を買ってしまった”行為に血がどくどくと勢いよく流れる感覚が巡った。 家に帰ってから酒を開けて、意図せず買ってしまった諏訪が吸っている銘柄と同じ煙草を手に取る。剥がしてくれと言わんばかりにテロっとしたビニールが顔を覗かしていて、それをぐるりと一回りさせると本体が出てくる。さらに銀色の紙を剥がして行くと、ようやく煙草本体と出会うことができた。真新しいタ煙草のパッケージにトントンと指を鳴らしていた諏訪の姿を思い出して、一本迫り上がってきたそれを手に取った。ライターが無いことに気がついて、キッチンのガスコンロでそれに火をつけた。 いつも諏訪が近づいて来る時の匂いだ。とてもいい匂いとはいえないけれど、諏訪の匂いということで幾分か不思議と落ち着くその煙は、想像以上に不味かった。こんなものをわざわざお金を払って買っているのかと考えると、よくわからなかった。 結局一本吸い切らずに私の初めての煙草は、飲み掛けのビール缶にポトリと落ちた。これで大して得意でもないビールを飲む必要も無くなった。 やっぱり暇だと人はろくな事を考えないらしい。再び振り返るように諏訪との出来事を思い出した私は、夕方ごろにはそこそこの熱を出した。風邪をうつされたのではなく、おそらくは色んなことを考えすぎた知恵熱だろうと思う。 熱は下がらず、三日ほど動けずボーダーのシフトも変わってもらった。 風邪じゃないから咳は出ない。ただただ熱が出て辛いだけだ。馬鹿は風邪を引かないというけれど、馬鹿でも色々と考えることがあれば知恵熱を出すらしい。馬鹿は馬鹿なりに考えるものらしいと初めて知った。 大学へも行けていないし、ボーダーの任務も加古ちゃんに代わってもらった。休みを謳歌する余裕などもちろんないし、ここ数日何も食べていないからお腹が空いて仕方がない。 確か冷蔵庫に卵がまだ残っていたような気がする。卵がゆでも食べよう、そう思って開けた冷蔵庫には空になった卵パックだけが残っていた。実家に帰ろうかと考えるが、この状態で自転車を十五分漕ぐことは死を意味している。ならば母に助けを求めるべきだろうか。 考えているだけで余計と具合が悪くなりそうと思った時、今日のシフトを代わってくれた加古ちゃんからのメッセージに、私は何度かスマホの画面にめんちきっていたと思う。この三日間諏訪は三門を離れて任務をしていたらしいこと、そして加古ちゃんが私の体調不良を諏訪にそのまま伝えたと言う事だ。加古ちゃんの性格を考えれば、普通に私が具合が悪いということ以外にも色々と脚色して伝わっていると思う。案の定数分後、諏訪さんに見舞い品持たせて帰させたからという、いかにも部外者として楽しんでいそうなメッセージが届いた。熱は下がるどころか、上がるばかりだ。 そんな事をわざわざ聞かされた諏訪がどうするかなんて想像に容易い。一時間後、私のアパートのチャイムが鳴った。間違いなく諏訪が来たんだと直感的にそう思った。 「……なんだよ、その想定してたって顔。」 「しょうがないじゃん、想定してたんだから。」 諏訪の右手に持たれていた袋に視線を移すと、「もし腹減ってたら食うか?」とそう言って、胃に優しそうなものを袋の中から見せてくれた。状況はどうであれ、空腹であることには違いなく、私は諏訪を部屋に入れないという理由を失う。 加古ちゃんからもらったメッセージからすると、恐らく諏訪は私を見舞うように一言余計に言われたのだろうと思う。そうでなければ、自宅から近いとは言ってもわざわざ見舞いになどには来ないだろう。それとも、本当に諏訪は心配で来てくれたのだろうか。いずれにしても、その真実を測る事はできない。 「ねえ、喉乾いた。」 「そこにポカリ入ってるから勝手に飲め。」 諏訪の言葉通り袋の中にはポカリがあって、手にとってペットボトルの蓋を回す。人間熱が出ていると日頃できることでも簡単にできなくなるのだと思い知らされる。何度も掠りながら蓋を開けられない私に見かねた諏訪が、ペットボトルを取り上げて簡単に蓋を開けると私に差し出した。 「……ありがと。」 なんだかしっくりとこないまま、とりあえず言葉を発した。今はこういった優しさが身に染みる。弱っている時に人は落ちやすいとはよく言ったものだと思う。結局、こんなどうってこともない仕草の一つでも、今の私にはいちいち意味を持つのだから酷く気に食わない。 「なにしに来たの?」 「体調不良って聞いたから見舞いに来てんだよ。」 欲しい言葉を貰えたとは思わない。けれど、少なくとも諏訪は私のことを心配してくれているのであれば、それは及第点に近い。それだけでも充分に満たされているのに、体調が悪い時ほど人の本性が出るものだ。 「……本当にそれだけ?」 意味深にそう言えば、諏訪は一度深いため息をついて、私に問いかける。 「風邪じゃないんだな?」 うん、とそう頷いたすぐ後には諏訪の唇が重なっていた。数日前にあれだけ角度の問題でうまくいかなかったのが嘘のように、とても簡単にそれは重なった。気持ちいいかと言われたらそんな事はない。この間まずくて一本吸いきれなかった諏訪の吸う煙草が視界に入って、その味とやっぱり同じだと思った。 「…この間吸ったけど煙草と同じ味で不味いね。」 好きだと、その言葉の裏側にある言葉を言えない私は卑怯だと思う。諏訪は一度テーブルに置かれているその煙草を見て、呆れたように私を見る。まるで、私が今なにを考えているのか見透かされているようでひどく癪に触る。 「ニコチンは病みつきになんぞ。」 「まだ依存してないから。」 「んなもんは時間の問題だ。」 そうか、だからなのかと思う。既にそれは私の中で病みつきになっていて、また摂取したいと感じる中毒性を孕んでいるのだから。依存していないだけで、もう依存するためのスタートは切ってしまっている。 「もう不味いキスなんてしたくないから。」 そういえば諏訪が困るのはわかっていた。けれどこの時の私には正しい言葉だったと思う。このままだと、もう諏訪に対する感情がなんだったのか口にしそうだったからだ。そんなの、ダメだ。自分に期待を抱かせないために、あえて私は宿題を残したのだと思う。 翌朝目を覚ました頃にはすっかり熱は引いていて、私は大学に向かう。今日は諏訪と同じ授業がある日だが、諏訪はいるだろうか。この間の出来事の真意は、一体なんだったのだろうか。分かっているのは私が諏訪のことを恐らくは好きだという事だけで、諏訪がどうかなんてまるで分からない。キスをしたからと言って、それが答えとは限らない。 久しぶりに履いてみたヒールは、カンカンと煩い。ひっくり返してヒールの先を見てみると、ヒールの釘が出ている。道理でうるさい訳だ。もうそろそろこの靴ともお別れをすべきなのかもしれない。 大学へと続く階段を登った先に、喫煙所がある。無意識に、そこに諏訪がいないかを探した私の瞳はダルそうに電子煙草を吸っている諏訪を見つける。 「なに、紙煙草やめたの?」 「不味いらしいからな、やめた。」 それは答えと思ってもいいのだろうか。素直にそう聞けばいいのに、結局私は素直にそう聞くことなんてできない。やっぱり自分が諏訪のことを好きだと認めているようで、居た堪れないからだ。 今日は大学が終わったらなにも予定はない。この釘のでたヒールを、思う存分活かす方法を思いついてしまって、それを実行してみようと思った。 隣人がいつ帰ってきたのかすぐに分かるような諏訪のアパートで、私はあえてカンカンと音を立てて諏訪の部屋へと続く階段を上がって行こうと。そうする事で、諏訪に彼女という存在ができたのだと、隣人に知らしめてやるのだ。 まだなにも聞いてないのに、そんな悪知恵が働いた。 地道にコツコツと何かに取り組むのは苦手だ。だから今日、しっかりと諏訪の部屋で答えを問いただそうと思う。答えの分かっているものを問いただすのは、考えただけでも楽しい。早く、その答えを耳にしたい。 「もうあの味勘弁して欲しかったから、助かったわ。」 電子煙草の味は、どんな味なんだろう。今はそれがただただ楽しみだ。
目も覚めない真実 |