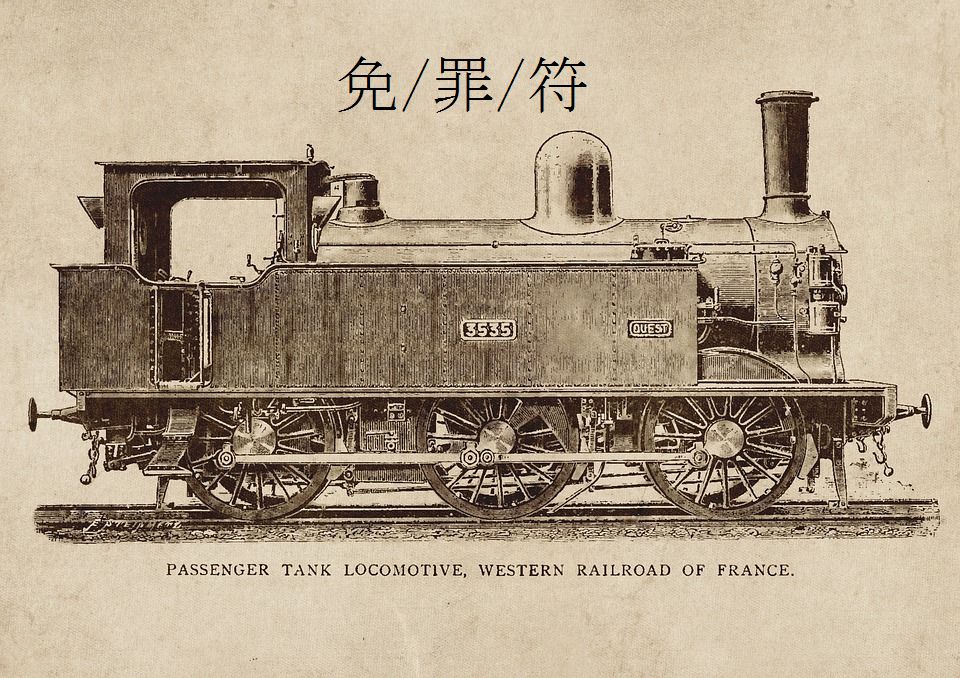 私は、彼の何処が好きだったのだろうか。今になって、それが酷く難解で、分からない事のように思えた。 鬼殺隊に入る前から、彼の事は知っていた。姉思いの優しい男だった。私の幼馴染のようなものだ。友人としてはもちろん好きという気持ちはあったけれど、確かにそれは恋ではなかった。 ならば何故、彼を私は好きになったのだろうか。自分の人生を振り返るように、ふとその理由を探してみた。 鬼殺隊に入隊してからの日々は、私が想像していた以上に過酷なものだった。過酷でしかないと分かっていながらも、どこか覚悟が足りなかったのかもしれない。自分が想像できる限界とは、今まで自分が経験した事のある限界値をどう足掻いても超えないものなのだ。 精神が壊れるのが先か、体が壊れるのが先か、そんな生活の日々で私には何かが必要だったのだろうと思う。 気づいた時には、ほんのりと色づいた感情を義勇に感じるようになっていた。自分よりも強い存在というものは、私の拠り所になり、そして全てだった。弱い私には、そこに縋るしかなかった。 死なないために必死だった。生きるか死ぬかの極限の世界で生きていた私は、何かを求めていた。そんな時にいつだって傍にいたのが義勇だった。理由は、案外単純なところにあったのかもしれない。 「急いでくれ。列車に遅れる。」 「あ、うん。すぐ行く。」 鬼との戦いが終わり、平和な世が築かれていこうとしていた。鬼殺隊は解散となり、それぞれに散り散りになった。私たちもこの地にとどまり続ける理由はなく、故郷へと戻る事にになり二人で列車へと乗り込む事になった。故郷へ戻るのは、どれくらいぶりだろうか。鬼殺隊に入ってからは、一度も帰っていない故郷だった。 義勇は肉親を殺された事がきっかけで鬼殺隊への入隊を志した。誰か肉親を殺された訳でもない私と彼には、この時点で覚悟の差があまりにも違っていた筈だったが、当時の私にはそれが分からなかった。 母は私を産んですぐに死んだらしい。父も物心ついた頃には新しい女を作って、私と祖母を置いて家を出た。私の肉親は祖母一人だったが、その祖母も里を離れる前に死んだ。私は天涯孤独だった。 近所に住んでいた義勇の姉が鬼に殺された。そして彼は鬼殺隊に入るのだと行って、里を出ると言ったのだ。もはや失うものなどない私には、この里に執着する必要もなく、義勇について私もこの里を出ることにしたのだ。今考えると、よくそんな軽い気持ちで鬼殺隊を目指したものだなと呆れる。私のようなふんわりとした覚悟しか持ち合わせていない者は、鬼殺隊には誰一人としていなかった。 最終選別に残れたのは、運がよかったのと、義勇や錆兎と行動を共にしていたからという理由に他ならない。錆兎は死んで、私が生き残った。今に思えば、死ぬべきだったのは私に違いないと思う。錆兎が生き延びた方が、よっぽど鬼殺隊には意味があっただろう。 「里に戻ったら、知ってる人まだいるかな。」 「どうだろう。随分と時間が経っている。」 「だったら別に他の所でもよかったんじゃない。浅草とかさ、賑やかそうでハイカラだし。」 「…お前は、そちらの方がよかったか。」 「ううん、ただ言ってみただけ。」 待っている者などいないのだから、別に故郷に拘る必要もないと考えていた。ならば残りの人生、華やかな街で暮らして、時代や文明の進化を見ていくのもいいなと、ふいにそんな事を思っただけで、どうしてもそこがいいという拘りもまたなかった。 「がいいならそれでもいい。」 「ほんとちょっと思いついただけだから。気にしないで。」 「そうか。」 義勇は口数の少ない男だ。幼い頃からあまりお喋りな方ではなかったけれど、姉を亡くしてからはより一層口数が減った。悪気はないのだろうけれど、言葉が足りない分誤解される事が多いのが玉に瑕だ。損をしているという事に、彼はどうやら気づいていないらしい。 走り始めた列車が、がたがたと体を揺らす。乗りなれない乗り物は私の体質にはあまり合わないようで、軽く酔ってしまった。こんな事で具合が悪くなるなんて、本当に情けない。 「酔ったのか。」 「…うん、ちょっとだけ。すぐ治るよ。」 私に見かねたのか、義勇は私の肩をすっと自分の方へと向けるように倒して、私は彼の肩を借りている状態になった。 「そういう時は眠った方がいい。」 言葉数は少ないけれど、不器用ながらも優しい義勇の事は本当に好きだった。友人だった昔の頃の私も、そして今の私も、彼の優しさには何度も救われたものだ。感謝してもしきれないとはこういう事を指すのだろうなと身を持って知る。 列車の揺れが、彼の体を通じて伝わってくる。直接感じる揺れよりも幾分か義勇を経由している為か軽減されたように感じる。 ゆらゆらと揺られ、ぼんやりとした頭で考える。義勇を好きになった理由は振り返る事で納得が出来た。そもそも私は何故こんな事を今になって考える必要があるのだろうか。笑ってしまう程に薄情な自分には、涙すら出てはこない。 「義勇はさ、何で私の事を受け入れてくれたの。」 理由を聞いたことがなかったと思い出して、聞いてみることにしたのだ。口数が少ない彼が、ペラペラとそんな事を自発的に話すはずもないのだから私から聞くしか知る術はない。 「…が里を離れて共に行くと言った時からそう思っていた。」 簡潔な一言だったけれど、優しい彼らしい言葉だなと思う。きっと里に居た時から大事に思っていてくれたのだろう。思い返してみると、思い当たる節がいくつかあった。 義勇は、私が里を出て共にいくと決めた理由が、彼が思うように綺麗なものではないと知ったらどう思うのだろうか。 怒り狂ったように発狂する筈もないし、その奥に隠された感情が白か黒かそのどちらであっても、きっと静かに「そうか。」と一言呟くだけだろう。感情の読み取りづらい、そのかんばせで。 「そっか。義勇はほんとに優しいね。そういう所、好き。」 返事はない。それはきっと肯定しているのだろうなと思い、私も返事を強要する事はしない。言葉などなくとも、私の知っている彼の優しさがそれを肯定しているのだから。 「浅草じゃなくていいのか。」 「まだ言う、それ。一緒に帰ろうよ、里に。」 私が言うと、少しだけ安心したように彼は私の手に自分の手を重ねてくる。ごつごつとした豆がある硬い手が、ずっと私を守ってきてくれた。片腕を失っても尚、今だって。 鬼舞辻無惨を倒し、全てが終わった時、本当に嬉しかった。これで世は変わっていく。私も義勇の傍で平穏に暮らしていくことが出来ると思っていた。失われた腕を補うくらいに、私が彼を守ろうとさえ思った。彼が隣に居れば、きっと幸せになれるに違いないと確信していた。 「…そうだな。」 私の手の上にあった義勇の手が、より面積を広げて包み込んでいく。これが、私の求めていた結末で、夢であった筈なのにどこか違うという違和感を抱くのだ。 最後の戦いを終えて暫くすると、呆気に取られたように日々が長く長く、終わりのないような錯覚に陥った。あれだけ望んだ平和は、どこか退屈に思えるもので、私は刺激的な人生を求めていたのだろうかと自分の事が分からなくなっていった。 今まで散々義勇に救われてきて、その度に彼を好きになっていく気持ちが深まった。好きという気持ちに疑念を抱くことなどもちろんなかったのだから、あえて考えることもなかった。 けれど、今はどうだろうかと自分を問いただすと、不思議な感情が生まれてくる。それは酷く薄情でしかない感情だ。 「幸せだな、私。」 言葉に出してみれば、それが現実にならないかと思い言葉にしてみる。その言葉は宙を舞って、言霊のように消えていくばかりで事実に変える効力は持ち合わせてなど居ないかのように列車の音に消えていく。 自分の身を守るために、強い彼を好きになる事で利用していたのかもしれない。こんな罰の悪い結末が他にあるだろうか。今まで読んできたどの書物よりも、後味の悪い結末だ。 彼がこんなにも大切に守り、想ってくれているのと反比例するような私の感情は一体何なのだろうか。優しすぎる彼の私への気持ちが、どうしようもなく傷を抉られる様に痛かった。どうして、あの時と同じ気持ちで彼を好きと想うことが出来ないのだろうか、自分でもその辻褄が分からない。そう出来た方が私も、義勇も、幸せで全てが丸く収まるというのに。 結局、私は幾つもの判断を誤ったのだ。軽い気持ちで里を離れ、鬼殺隊に入った事が彼を苦しめるのではなく、他でもない自分自身を苦しめることになってしまった。あのまま義勇を見送って里に留まっていれば、義勇とこうなる事もなかったし、こんな悲劇を生み出すことはなかったに違いない。 もし私が違う道を選んでいれば、全てを終わらせて戻ってきた義勇を違う気持ちで出迎える事が出来たのかもしれない。進んでしまった道を過去に戻る事は出来ないのだから、それは私の仮想に過ぎないけれど、今よりも確実にいい未来が待っていたのだろうと思う。 「少し休め。着いたら起こす。」 「…うん。そうする。」 目を瞑ると、より一層に残酷な自分の気持ちに嫌気が差して涙が出た。こんな私を好きでいる義勇が、不憫でならない気がした。目的地に着くまでに、私は一生この感情に蓋をして彼と生きていく覚悟を決めなければならない。 腕を失っても尚私を守り、戦ってくれた彼に対する私が出来る最大限の恩返しで、そして償いだ。 私の弱い覚悟が引き起こしてしまった悲劇に、責任を取らなければいけない。他責ではなく、自責として。全ての判断を誤ったのは私で、全ての判断を下したのも紛れもなく私なのだから。 伝った涙が、義勇の袖で拭われていた。 「ありがとう。おやすみ、義勇。」 これが、私の免罪符だ。
|
