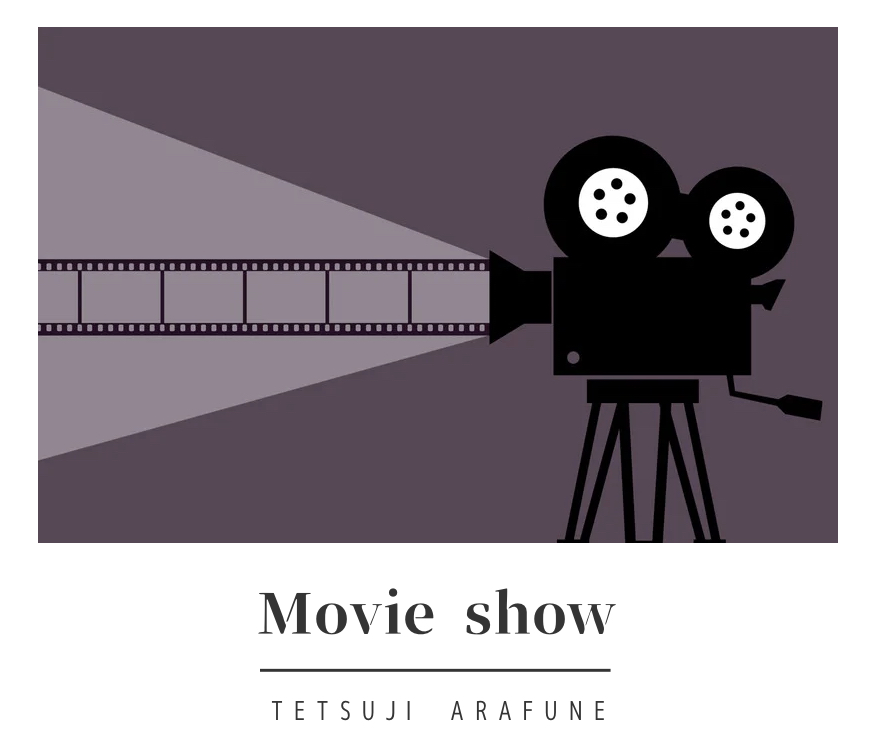 梅雨入りをしたという事もあって、ここ最近はずっと雨続きだった。じめじめとした湿度は人の心も湿らせる。特別理由はないが気分があまり乗らない。“五月病”という固有名詞が存在している五月が終わってばかりなのに、六月に入ったらすぐに梅雨だ。いつになったらいい事があるんだろうか。そんな他人任せな人生を送っている私に、急遽思っても見ない幸運が舞い込んできた。 一般企業に就職するのかボーダーに残るのか、まさに岐路に立たされていたタイミングだった。どっちに転んでもいいようにと同時進行で進めてはいたものの、想像以上に一般企業への就職活動は難航した。高校二年生からボーダーでの活動に従事していた私にとって、それは他の就活生よりも秀でた武器になると思っていたが現実はそこまで私に優位ではない。諏訪さんは卒業して一般企業に就職したけれど、それは彼自身の実力だったのだと痛感していた。 そんな時、歳の近いボーダー隊員で飲みに行くことになった。ボーダー自体は世間に知れ渡った組織だが、その実態はあまり表に出ていない。それは表に出すべきではない情報がボーダー内に多く存在しているという事を同時に表している。だから隊員同士で飲むのが一番話が早く、そして共感も得られやすい。こんな感じで結局ボーダーに就職するのだろうなと思っていた。 荒船と付き合うきっかけになったのは私の言葉でも荒船の言葉でもなかった。 「荒船いるのに全然チャンス物にしないじゃん!」 ひどく酒に酔った友人が放ったこの一言で、全てが変わった。急激に酔いが醒めていく感覚を覚えたのはこの時が初めてだ。背中の中心がヒヤっと冷えて、暑くもない筈のなのに汗が流れたような気がした。酔っていたとしても言っていい言葉と駄目な言葉がある。 「…ちょっと!悪酔いしすぎ!」 大勢で飲んでいた筈なのに、一言でその場が静まり返った。大して酒に興味のない荒船はもちろん酔っている筈もなく、私が穴があったら入りたいという状況を見て少し気まずそうにしていた。そんな光景を自分で見るのは地獄以外の何物でもない。明日からどう生きていけばいいのか、今後の自分の生き方について色んな事が渦巻いて言葉が出なかった。 私は荒船のことが好きだった。それはここ最近の話という訳でもなくて、結構前からのことだ。だから仲のいい数人のボーダー内の友人には伝えていたものの、まさかこんな状態で荒船の耳へと入る事は全くもって想定していなかった。 荒船に告白するつもりなんて微塵もなかった。私と違って自分に対してストイックで、人に対して思いやりの心がある荒船が好きだった。自分と荒船が付き合うことなんて想像にもできなかったし、荒船が私を選ぶことも想像はできない。ただ好きなだけでいいと思っていた。だから今まで適当に告白された男とも付き合ってきた。そんな私にとって、この状況は完全に想定外だ。 「ごめん荒船!前に女子会で、ボーダー内なら誰がかっこいいかって話してた時に荒船の名前出しちゃっただけでそんな深い意味はないから……」 飲みの場ではまだ通用するであろうそんな嘘をついてみたけれど、周りの静けさはより増していくだけで、本当にこのまま死んでしまいたいと思った。誰か何かしら野次を飛ばしてくれたらなんとかやり過ごせるのに、それすら叶わない状況だ。 「謝らなくてもいいだろう?」 大勢の前で振られるという公開処刑を避けたかった私の気持ちを察してくれたのかもしれない。荒船はいつもと変わらないかんばせで、あっけらかんと言って退けた。 「俺もの事好きだし、付き合うか?」 荒船が私の事を嫌いではないことくらいは理解していたつもりだ。けれど、それが好きなのかと言えばそんな事はなかったと思う。もしかしたらどうしようもない窮地へと貶められている私を気遣ってくれた一言だったのかもしれない。だとしたら哀れだけれど、でも私にとっては想定外の奇跡だった。 「…本気で言ってる?」 「キャラ的にそこは信じてもらいたいところだな。」 その後、ようやく静まり返っていた場がピューと口笛を吹く音や野次で賑わいを盛り返した。結局、その空気の読めない友人のおかげで私は長年好きだった荒船と付き合うことになった。棚からぼたもちとはこういった事をいうのだろうか。嬉しさと興奮が半分で、残りの半分は荒船が私を見かねてその場で言ってしまったんじゃないかという不安となんとも言えない感情だった。 結局そこからは冷やかしの嵐で、飲み屋を出たところで「この後はお二人でどうぞ。」なんて言われて、他のメンツは二軒目へと移動して置いてけぼりを食らってしまった。この時の気まずさと言えば表現しようがない。 「……荒船、なんかごめん。恥かかせちゃったね。」 「別にそんな事は思ってない。」 なんと言葉をかけるのが正解か分からず、目的地もなくただ真っ直ぐ歩く。誰とも付き合った事がないという訳でもないのに、その経験値は全くもって役に立たなくて腹が立つ。このまま抱きついて荒船の家に押しかけるのが正解だったりするのだろうか。 「来週の土曜、シフト入ってるか?」 「…ううん、オフだよ。」 「嫌じゃなければうちで映画でも見ないか?」 先ほど魔が差したように考えたことを実行に移さなくて本当に良かったと思った。忘れていたけれど、私と違って荒船はまともで誠実な人間だ。付き合っていきなりどうにかなるなんて事はないし、そんな事を仕掛けていたら付き合った瞬間に終わっていたかもしれない。嫌悪感とはこういう時に感じる物なのかもしれない。 「全然!嫌じゃない!むしろ嬉しい!」 「そっか、なら決まりだな。」 そう言ってニカっと笑う荒船が、私にはあまりにも眩しすぎるように思えた。釣り合わない。そんな気持ちが渦巻きながらも、分不相応な幸せにこの時は飲み込まれていた。来週の土曜日まで、どうやって生きていけばいいだろうかと不安になる。荒船と別れた後、久しぶりに諏訪さんへ電話をかけた。 楽しみにしているドラマがあった。 基本的に私はドラマにしてもアニメにしても完結しない限り見ることはない。生きていれば間違いなく確実にその日がやってくるのは理解しながらも、その空白の一週間をどう生きていいか分からないからだ。楽しみとは、時にその空白の時間を長く感じさせる。一つのことに夢中になった時の自分の性格を、私はよく知っている。 この一週間をどう過ごそうかと、荒船と付き合った瞬間から憂鬱だった。自分がこれだけ好きだったと男と付き合うのが初めてだったからだ。今までは適当に暇を潰してくれるそこそこの男としか付き合ってこなかった。会えない時間にヤキモキしないという自分への期待値調整をする為にそういう男としか付き合ってこなかったのかもしれない。 いざその日を迎えて目が覚めると、下腹部に鈍痛がしてトイレで絶望した。中学校の修学旅行の時も、高校の卒業旅行も、同じようなことがあったからだ。想像していた予定日よりもそれはかなり前倒しでやってきた。 手土産にどら焼きを買って、私は荒船の家の近くの公園へ向かう。予定よりも十五分前でかなり余裕を持って着いたつもりだったけれど、既にそこには荒船の姿があって無駄に取り乱した。 「荒船久しぶり!」 「……昨日基地で会ったぞ。」 「そういえばそうだね……」 荒船に菓子折りの入った紙袋を渡すと、ここのどら焼き美味いよなとさりげない言葉をかけてくれた。こういうさり気ない優しさが私は好きだった。いつも荒船は私の欲しい言葉を欲しいタイミングでくれる。だから多分、私は荒船を好きになったんだと思う。 先週久しぶりに聴いた諏訪さんの声はひどく疲れていて、そしてこんな夜中に電話をしてくるなと怒られた。けれど、結局私の話を夜中の三時まで聞いてくれた。アドバイスは特にない。ボーダー内の事情を知っていて、且つボーダーを辞めている諏訪さんには色んな事が話せた。荒船と会話をするよりもスムーズで、そして自然だった。私は荒船と付き合って月日を重ねたら、諏訪さんのように円滑な会話ができるようになるだろうか。今から不安だった。 「テレビめっちゃ大きい。」 「穂刈には部屋とテレビのサイズが合ってないって言われた。」 「穂刈くんは来たことあるんだ。」 「だな、が二人目。」 荒船は天然なところがあると思う。本人が意図していないところで、パワーワードを発していることに、恐らく荒船自身は気づいていない。心臓に悪い。言葉としてちゃんともらった訳でもないのに、自分が特別だと言われているようで無駄に体が熱ってしまう。 「は酒好きだよな。俺はあまり飲まないから適当に買ってきたけど、好きなのあるか?」 自分が酒好きな女だと思われている事に少しばかり恥ずかしさを感じたのは初めてだった。酒が飲めるというのはあらゆる意味で重宝される。十代だった頃よりも諏訪さんと仲良くなったきっかけも、酒だった。何事も共通するきっかけというものは大切だ。私と荒船を繋ぐ共通項は何があるだろうかと考える。恐らくは、“ボーダー”という共通項くらいしかないだろう。私は荒船を好きだけれど、荒船は私のどこを好きになってくれたんだろうか。 「ごめん、今日薬飲んじゃったからお酒飲めなくて…」 その一言でもちろん荒船が察してくれる事はなく、無駄に心配されてしまった。体調が悪い中来たのかと思っているようだ。体調が悪い訳じゃない。こういう時どう伝えるのが正解なのだろうか、やっぱり私は分からない。 「体調悪いならまた次でいいぞ?大丈夫か。」 「……体調悪い訳じゃなくて、生理きただけだから。」 私がそう言えば、荒船はすまんと一言だけ気まずそうにそう言って変な空気になってしまった。毎月アプリの通知通りに来るはずの生理がこれ以上憎い事はない。私自身だけでなく、荒船の言葉も詰まらせてしまったからだ。 男は大抵そういう事を期待して生きている生き物だと私は定義している。そう思わされるきっかけは以前付き合っていた男が発端だ。そうだと分かっていれば会わなかったのにと言われた事があった。私自身が夢中にならないように男と付き合っていたのだから、そんな男に当たってしまったのだとろうと思ったけれど、それが欲望に忠実な答えだと思った。 「ごめん、やっぱり来なかった方がよかったよね。」 昨日浮かれてよく寝れなかった自分を急に恥ずかしく思って、俯いてしまった。この先に続く言葉を聞くのが怖くて、このまま帰ってしまった方が得策かと思っていた時、今までの概念が覆されるような言葉が耳に入った。 「俺は男だからその辛さは分からんが、別に今日会うことには関係ないだろ。」 寧ろ来てくれて嬉しいと言ってくれるその言葉に、嬉さと同時に違和感を感じてしまった。分かっていた事とは言っても、このままでは荒船に夢中になる自分が想像できてしまったからだ。夢中にならない為に、自分の執着心を出さないでもいい男としか付き合ってこなかったというのに。このまま自分の欲求に正しく荒船を好きになってしまえば、荒船に嫌われるのではないかと本能的にそう思ってしまった。 「本当に迷惑じゃない?」 「ぜんぜん。」 「荒船って優しいね。」 「そうか?普通だろ。」 自分の思う普通がおかしいのかもしれないと思いつつも、荒船の優しさは私には不釣り合いな気がして仕方ない。私はこんなに優しくされてもいいのだろうか。そんなよく分からない後ろめたさを感じながら、小さい二人掛けソファーに座らされた。 「こういう時、何を出すのが正解なんだ?」 「なんだろう…よく分からないけどお茶でいい。」 「ならどら焼きにちょうど合うな。」 荒船のポジティブさと私のネガティブさは、このまま付き合い続けることで交わるのだろうかと考える。付き合っているのだから、そんなことを考える必要なんてないのに。最初のデートが家ということもあって、どうにかなってしまった方が楽だと思ってしまった自分がどうしようもなく汚らわしく思えた。こんな私のどこを、荒船は好きになってくれたんだろうか。それが一番気になっているのに、それを聞く勇気はなかった。 「この間見つけた面白いフランス映画があって、」 再生されたフランス映画はとても単調で、全く頭に入って来なかった。まるで頭に入ってこないそのフランス映画にこくりと寝入りそうになって荒船の硬い胸板を感じた時、急に目が覚めた。 「…ごめん!」 寝ぼけ眼で顔を上げるとそこには荒船の顔が正面にあって、もう一度寝入るように目を閉じた時、初めて荒船とキスをした。 ボーダー本部基地へと行けば、荒船とはうまくやっているのか?と飲み会の場にいた連中に聞かれるのがここ最近のルーティンだ。恐らくは、上手くいっているのだと思う。荒船は私のことを大切に扱ってくれるし、ボーダーでも隠すことなく私を彼女として扱ってくれる。やっぱり、私は荒船が好きだ。 「、帰るのか?」 「ちょうど今防衛任務終わったところ。」 「そうか、じゃあ一緒に帰るか。」 世間的に見れば私は大切にされている荒船の彼女だ。初めてのデート以降も、荒船は暇を見つけて私をデートに誘ってくれる。大学でも一つくらいは一緒に授業を取ろうと言ってくれて、会う機会も以前よりも多くなっていた。この上ない幸せであって、私には未だに引っかかる点があった。 「お前ってさ、俺といて楽しいか?」 その言葉を言われて、急に心臓がぎゅっとなった気がした。荒船を好きなことは自分の中で揺るぎない事実でありながら、楽しいのかと言われたら疑問に感じてしまったからだ。あの始まりとなった場所で公開処刑を免れても、私はやはり荒船に振られる結末を変えられないのだろうか。 「荒船は楽しくないの?」 「質問返しなんて随分はぐらかすんだな。」 結局その問いに応えることなく、私はいつものように荒船の家に行く。フランス映画はもう二十本程見たが、まだ面白いと思えるものには出会えていない。結局、どうしたら荒船に嫌われないだろうかとばかり考える私は、荒船との付き合いを楽しめていなかった。 「一般企業に内定もらったんだろ。何で言わないんだ。」 付き合ってしばらくしてからも、荒船に大切にさてれていると分かってからも、結局私の不安は消えてはくれなかった。それは荒船を好きだからこそ、増していく需要でもあった。 「荒船がボーダーに残るって知ってるからかな。」 「それ理由にならなくないか?」 荒船のいう通り、それは何の理由にもならない。私は、着々と荒船に振られてもいい自分の環境を整えてきたのだ。大切にされるほどに、それが自分の一方的な感情であるような気がして、自分でもよく分からない間にその準備をしていたのもしれない。最近、諏訪さんに電話をする頻度が増えた。 「諏訪さんの就職した会社だろ、内定でたの。」 どこでそんな情報を得たのだろうか。全ての事情を知っている諏訪さんが荒船に言うはずもないし、私も誰にも言っていない。 「そうだよ。」 「俺には相談しないのに、諏訪さんにはするんだな。」 「一般企業に就職した人に相談するのが手っ取り早い。」 荒船は慎重だ。感情のままに手を出してくることはないし、結局私と付き合った理由を私は知らない。棚からぼたもちと思っていた事実がありながら、結局その真実が分からない事が私を苦しめた。想定していない幸運は、育むうちにその真実が分からないことで負の感情を募らせてしまった。 「だって、荒船は私の気持ちわかってくれないじゃん。」 でも、私がこう言うように仕向けたのは他でもない諏訪さんだ。どこにも内定をもらっていない私に、うちの会社を受けてみないかと言ってのは諏訪さんだ。全てを知った上でそう言っているんだから、私を自分の会社に入れることにメリットを感じてくれたのだろうか。 「随分見くびられたもんだな、俺も。」 珍しく荒船から私を求めるように触れられた。諏訪さんに嫉妬をしているのか、それとも何も言わずにことを進めていたことに腹を立てたのか。どちらかは分からない。けれど、私の思いとは裏腹に事が進んでいく。 「は、俺の事もう好きじゃないのか?」 この言葉は、私が好きだと変換しても私の間違いではないのだろうか。 「俺は、好きだ。」 初めて、荒船からその言葉を聞いたような気がする。付き合ってきたけれど、間違いなく初めてその言葉を私は聞いて、その言葉に対してどう返答していいか分からなかった。 「…答えが聞きたい。」 その言葉は私が何よりも欲しかった言葉で、そして私の精神をようやく落ち着かせる言葉でもあった。好きだからこそ、言葉と言うものがどれだけ必要なのかもわかった気がする。でも、まだそれは言わない。私自身が焦らされたように、荒船も焦らされたらいい。 「知ってるくせに。」 結局、私は駆け引きという勝負にこの時負けてしまった。 あいも変わらず荒船がチョイスするフランス映画はつまらない。私は体質的にフランス映画に合わないのだろうと思う。けれど今日も私は新しいフランス映画を見ている。単調で、動きのないその映画のなにが荒船を突き動かすのだろうか。私には分からない。 「荒船、もう飽きちゃった。」 思ったことをそのまま口にすれば、荒船は困った顔をしながらもしっかり私を視界に移す。お互い趣味は合わないことはもう理解が及んでいる。それでも、荒船は私と付き合ってくれているし、やっぱり私は荒船が大好きだ。 「趣味合わせる努力しろよ。」 「趣味の合わない私を好きになった荒船も悪いよね?」 動きのないフランス映画の途中で私がキスを求めれば、荒船はしっかりわかったように私に構ってくれる。結局は諏訪さんのアドバイスどおりに、全てがうまくいっているから憎らしい。 「お前は手がかかる。」 諏訪さんがかつて言った同じ言葉が、とてつもなくパワーワードとして私に降りかかってきた。多分、私は一般企業に就職はできない。後味の悪いはずのムービーショウはまさかのハッピーエンドを作り出したのだ。
ムービーショウ |