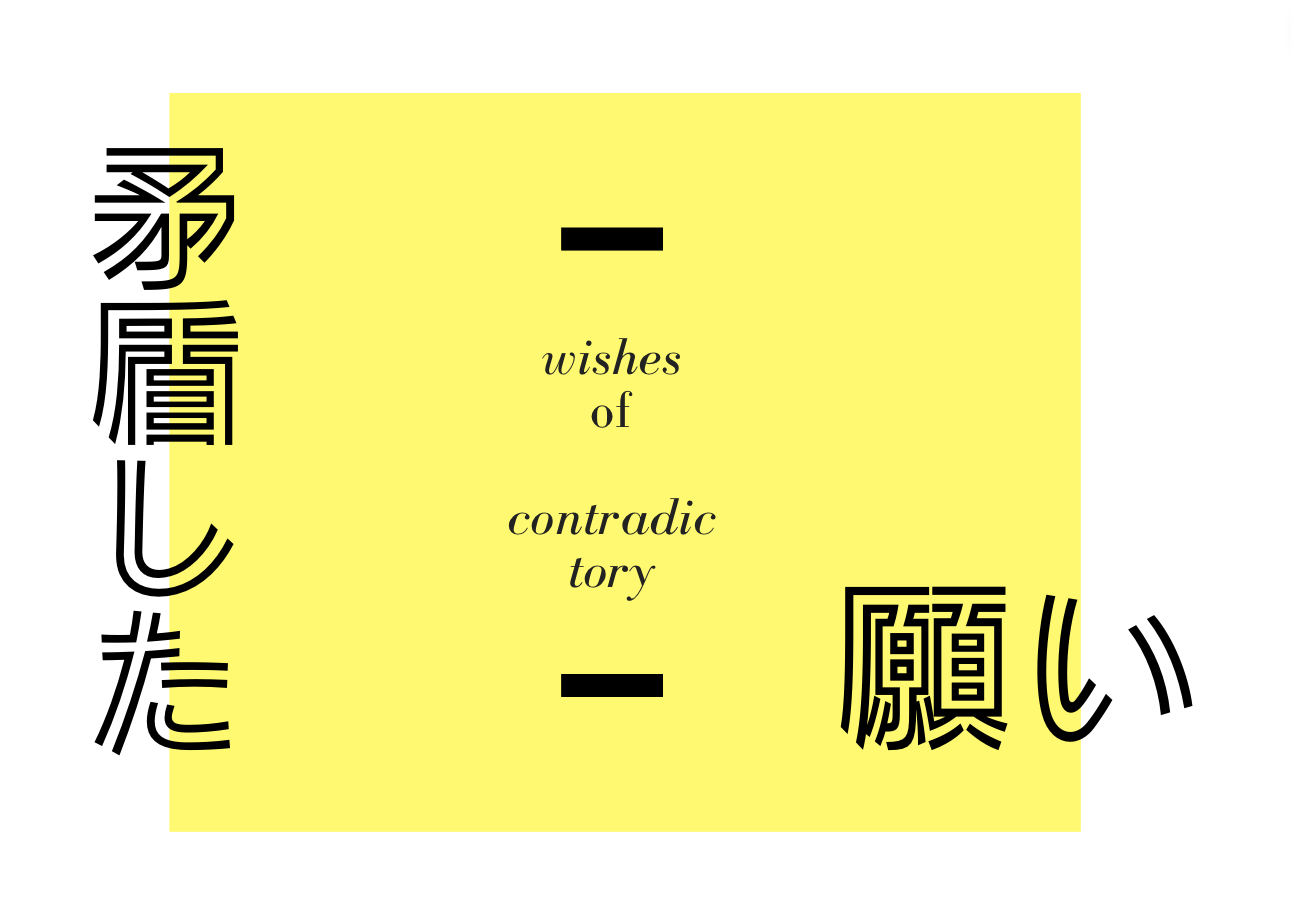 水戸くんと再会したのは、半年ほど前のこと。 土日休みである事がせめてもの救いで、自分の会社の定時が何時だったかを思い出せない私は、そこそこ社会人をエンジョイしているのだろうと思う。言っておくが、これは皮肉だ。 幼い頃見ていたテレビドラマで、「飲んでないとやってらんね〜」というフレーズを聞いてはどういう意味だろうかと思っていたが、その言葉を他でもない私が一番理解しているので世の中は上手く成り立っている。皮肉しか出てこないので、一旦酒で流し込む。 高校一年生の頃、同じクラスメイトだった水戸くんのイメージと言えば“桜木くん”という固有名詞だった。 中学時代相当なヤンチャをしていたというのは同じ中学の友人に聞いていたし、聞くまでもなく入学初日でそれはよく分かった。入学式を待たずして改変された制服、細い眉毛、当時の時代を反映している特徴的な髪型。なに一つ取っても、私とは人種の違う人間だとそう思ったのをよく覚えている。 「もしかしてさん?」 「………はい?」 「湘北高校一年七組の。」 「え、こわ……」 新手のナンパかと思った。けれど、ナンパにしては個人情報の特定が著しい。余計と恐ろしくてコの字型のカウンターで少し震えた午後十時四十五分、ちょうど頼んでいた一杯目のジョッキに口を付けた時のことだ。その後咳き込んだのは言うまでもない。 「分かんないよな、俺水戸洋平て言うんだけど。」 「え?あの不良の水戸洋平?」 「……間違ってないけどこの年でそれは恥ずいな。」 「全然気づかなかった……」 名前を聞けば確かにその面影があって、個人情報の特定が著しすぎる恐ろしいナンパではない事に一先ずは安心した。オールバックだった当時の髪型から変わって、爽やかに髪が降りている。高校時代がオールバックだったという、今にして思えば俄かに信じがたい事実を思い出して、何だか不思議な気持ちになった。 彼のすごい所は、一緒のクラスだった時から数年が経っていても思い出す事が出来る。ヤンチャな集団の一員であるのに、どこか親しみやすかったという矛盾だ。それは彼だけでなく、桜木軍団と呼ばれた他四人にも同様な訳だけれど。だからきっと、高校一年生の時の自分の思い出の中に、不思議と恐怖を感じる事なく彼と話をしていたという記憶が残っているのだろう。 「なに、さんバリキャリって感じ?」 「やめてよ、言われると鬱になる。」 「へ〜、相当病んでるじゃん。」 「病んでなきゃこの時間に一人で飲まないでしょ。」 私が社会で揉まれ、化粧も濃くなり、そして自分に仮面を被りながらなんとか社会人をこなしている一方で、水戸くんは元々柔らかい雰囲気を持ちながらも学生時代よりももっと柔らかくなったように見えた。 「さんもハイボール派か。」 「疲れた体に一番染みる気がして。」 「随分なブラック企業だね?」 「それでも転職しない私も変人なんだと思う。」 一口先に口はつけてしまったけれど、右手でジョッキの取っ手をギュッと握りしめていれば水戸くんがカチンと同じジョッキをぶつけて来た。しばらく放心している私を見て、「再会に乾杯でしょ?」そう言って揶揄うような少しだけ悪い顔でこちらを見ていた。我に帰った私を見ると、ハハハと聞き馴染みのある懐かしい笑い声が耳に滑り込んできた。 「さんは頑張る子だもんな。」 唐突に、水戸くんはそう言った。高校生の時から彼はとても気が利く人だった。おべっかと思わせないほどの自然さで紡いでいく水戸くんが、欲しい時に欲しい言葉をくれる水戸くんが、人に対して完璧なまでの優しさを見せる彼は、己に対して何も求めないのだろうか。 周りのクラスメイトが水戸くんの魅力に気づき始めた頃から、私は俯瞰的にそんなことを考えていた。水戸くんに救われる人は多い。けれど、彼は一体誰に救われているのだろうと。それがきっと桜木くんや、同じグループの仲間なんだろうと思いながらも、与えるものと与えられるもののアンバランスさを感じたのを思い出した。若干十五歳で、彼は人として完成されていたのだと思う。 「水戸くんここへはよく来るの?」 「ん〜、実は今日が初めて。」 「そうなんだ。」 「うん、でもさんいるならまた来ようかな。」 確かにどきどきとさせられるその言葉に高鳴りを感じながらも、きっとこれは私に対してだけでなく誰にでも言える言葉なんだろうと思った。親しみやすい分、水戸くん自身の本音や本心がどこにあるのか今も昔もまるで見えてこない。話しやすいクラスメイトとして記憶していながらも、それ以上深く関わらなかったのは水戸洋平という人間が一体何を考えているのか分からなかったからなのかもしれない。 「じゃあ私は来るの止めようかな。」 「なに、早速嫌われた?」 「水戸くんは優しいから、その優しさに漬け込みそうになっちゃう自分が嫌だから。弱ってる時ほど、欲しい言葉くれそうじゃん。」 私が、高校時代水戸くんに深入りしなかったのは、多分そういう事なんだろうと思う。無条件に与えてくれる聖母や神のような存在なんてどうかしている。確かにその優しさはとても魅力的だ。けれど、私も彼も同じ人間という生き物だと考えると、残ったのは違和感だった。人間には欲というものがあって、それは承認欲求だったり、根本的な食欲や睡眠欲もそうだろう。生きていれば必然的に体が欲するその欲を、水戸くんからは感じられなかった。 「……こりゃ参ったなあ。」 ただ一つ不思議なのは、彼の言動に違和感や不一致はまるでないという点だ。感情と行動はきちんと一致していて、そしてしっかりと本音で話しているのだろうと、その表情で読み取る事ができる。全てに嘘は感じられず、だからこそ余計と不思議だったのかもしれない。 「そんな参ってる水戸くんに今日は付き合うよ。」 「アンタの一言に参ってるのに?」 「一人で飲むよりいいでしょ?」 「そりゃそうだ。」 私のよく分からない提案に乗った水戸くんは、マイペースにハイボールを喉に流し入れていた。結局この時から彼とはこの飲み屋で時折酒を飲み交わす仲になっていた。所謂、飲み仲間というやつだ。 約束する訳でもなく、ふらっと立ち寄った時に出会せば一緒に飲むようになって分かったことがある。水戸くんとはお酒の趣味が合うらしい。好きなお酒だけでなく、ちょっとしたツマミや、好きな食べ物も不思議と同じだった。 私が質問をした分だけ、水戸くんは色々と教えてくれるけれど、決して自ら自分の事や身の回りの話をしようとはしなかった。酒を飲む場に求めるものなんて愚痴だったり、大抵自分の話が主役になりがちなのに。水戸くんは適度で心地の良い相槌を打って、私の生産性のない話をずっと聞いている。 「ちゃんってお酒強いんだな。」 「弱くないけど水戸くんほどじゃないよ。」 「な〜んか言葉に棘あるの気のせい?」 「え、そう?」 棘があるかどうかは別として、いい意味で水戸くんは空気のような存在だと、そう思う。居てもいいし、居なくてもいい。そんな言葉に集約すればとても聞こえが悪いけれど、これは寧ろ褒め言葉の一種だと私は思っている。大抵の人間は、居て欲しいか居て欲しくないかの二択に分類されるものだから、やっぱり水戸くんはかなり特殊で、私にとっても特別だ。 「名前で呼んでも頑なに“水戸くん”だね?」 「出会った時から水戸くんは水戸くんだし。」 「俺のメンタル鋼だと思ってる?」 「言うほど私水戸くんの事知らないもん。」 「凹ませるね〜?」 水戸くんはそう言って、大して凹んでもなさそうな笑顔でハイボールを飲み込んでいく。この半年間、一定の距離を保ちながらも、高校時代よりは彼のことを知れたと思う。ハイボールが好きなこと、あまり脂っこいものは得意じゃなく漬物が好きなこと、漬物の中でも特別長芋のわさび漬けが好きなこと。ちなみに長芋のわさび漬けは私の好物に数えられる代表的なおつまみのひとつだ。よく彼と一緒の皿を突いている。 「水戸くんは全部のらりくらり交わすよね。」 「俺ってちゃんにどう見えてんの?」 「なに、聞きたい?」 「聞きたいっていうか、興味あるっていうか?」 絶妙な距離を保っていると、そう思う。ある程度距離感を詰めながらも、踏み込みすぎないギリギリのライン。見えないところで多分駆け引きをしているのだと思う。水戸くんも、私も。かと思えば、こうして時折引っ掛かるようなこんなことを言ったりもする。相手に合わせる能力にきっと長けているのだろう。 「八方美人だなって。」 「それって絶対褒められないよな。」 「分かってるくせに〜、あざといなあ。」 「流石に手厳しすぎない?」 きっと女性に使うのが正しい言葉なんだろうけれど、これほど的確に彼を表現する言葉が他にあるのだろうか。誰からも悪く思われることなく、要領よく人付き合いができる水戸くんにぴったりな言葉だ。 「桜木くんの移籍のニュース見たよ。」 「そんな大々的に報道されてんだ。」 「同級生からNBA選手がでるなんてね?」 「ほんとだよな、吃驚する。」 水戸くんは私が聞いたことに対しては全て答えてくれるけど、あまり積極的に昔の話をしなかった。私でも桜木くんがプロとして活躍しているという事実を知っていたけれど、彼の口から桜木くんに関わる話はほとんど出てこなかった。お互いの共通項を考えても、その話が出ることの方が寧ろ自然なはずなのに。私があえて桜木くんの話を振らなかったから、という偶然が齎したものではないだろう。 「でも、水戸くん知ってたでしょ?」 知らないはずがない。少なくとも私が高校時代に見ていた水戸くんは、友人である桜木くんのサポートに全力だったし、多分それが彼にとっての人生なんじゃないかと私はそう思っていた。若干十五歳で“人生”なんて大袈裟に聞こえるかもしれないけれど、若干十五歳で彼は人としてしっかりと形成されていたんだと思う。だからこれは私の思い過ごしや、過剰な表現ではない筈だ。 「あれ、バレてた?」 「水戸くんにしては、珍しく。」 「恥ずかしいやつじゃん。」 「桜木くんが水戸くんに相談しない筈ないもん。」 どんどんバスケにのめり込んでいく桜木くんを、心の底から応援していた水戸くんを私は知っている。放課後の体育館での優しい眼差しだったり、仲間の勇姿を見るためにと遠征費を稼いでアルバイトに勤しんでいたことだったり、私の知らないところでもきっと色んな彼の姿があったのだろうと思う。 いつも明るく友達思いの水戸くんが、少しだけ切ない顔をしていたのが忘れられない。それは見逃してしまうくらいほんの一瞬で、偶然私が拾ってしまった知らない水戸くんだった。結局一年生の時以降クラスが一緒になる事はなくて、その後の水戸くんの事はあまり知らない。でも、あの時に見た表情こそが本来の彼の姿なんじゃないかと思ったのを覚えている。 「俺、夢とかって別になくてさ、」 こうして水戸くんが自分のことを話してくれるのは珍しいし、なんなら多分この半年でみても初めてかもしれない。まだ何も聞いていないのに、ヴェールが剥がされていくような不思議な感覚で、どきどきと鼓動が静かにテンポを上げていく。 「目の前にでっかい夢追ってる花道がいて、」 「うん。」 「俺もそれで夢持ってる気でいたって訳。」 「あ〜、なんとなく分かるなあ。」 「でしょ?」 分かる気がした。夢なんて寝てみるくらいのものしか私には手持ちがなくて、人生において絶対に叶えたい夢なんて持ち合わせてはいない。寧ろそんな目標や夢を明確に持っている人間の方が圧倒的に少ないだろう。桜木くんを通じて、夢を追っている感覚を持っていた水戸くんの感性は少し自分と通ずるものがある。 「夢って叶える為の目標なのにさ、叶えたら消えちまった。俺自身の夢って訳じゃないから当たり前なんだろうけど。」 仮面を外した水戸くんは、結構人間くさい。今までそう感じなかったからこそ、余計そう思うのかもしれないけれど。とても自分の感情に対して忠実に素直で、そして脆い。いつだって受け止める役割を担っていた彼に、そんな場所はあったのだろうか。与えるばかりでなく、与えられてきたのだろうか。これは世間ではお節介と言うらしいけれど、気になって仕方がなかった。 「海外まで付いて行くかと思ったけど。」 「はは、俺にも生活とかあるし無理っしょ。」 「意外とリアリズムだ。」 「夢見れるほど子どもじゃないからね?」 「よく言う、夢見てたくせに。」 「確かに、そうだったわ。」 紙の焦げた独特な匂いがする。焦げているのに、不思議と少し甘い。それは高級なバニラアイスの匂いと似ている。水戸くんが吸っているタバコの匂いだ。甘くて、ほんのり苦い。すぅっと静かに吸い込むと、ゆっくり時間をかけて頭上に吐き出した。 「水戸くんの素を初めてみた気がする。」 「つうか初めて見せた。」 「そっか、そんな貴重なものを。」 「俺の初体験持ってかれた〜。」 私も水戸くんから時折漏れ溢れている煙を吸い込んで、少しでも同じ気持ちを共有できればいいのにと、そんな事を思った。これから彼は画面越しに桜木くんの夢を一緒に追いかけていくのだろう。夢は消えたのではなくて、きっと形を変えただけ。彼がそう思えるようになるまで、私にはこの飲み屋に来る理由ができた。 「化粧さ、」 「ん〜?なあに。」 「薄くした方がいいよ。」 「突然失礼だね?」 自然体で会話をしてくれているのなら、それは嬉しい。高校生の時よりも確実に近づいたとそう思えるから。けれどつい数分前にそれを解禁してばかりなのに、水戸くんは遠慮なく今までの自分を脱ぎ捨てて私への距離を近づける。徐々に、という言葉を知らないんだろうか。 「俺はそっちの方が好きだから。」 これが本音なのか、それとも打算的なものなのか。どちらか判断に迷いながらも、確実に言えるのはどちらであっても彼は狡いという事実。言葉の真意に関わらず、こうする事で自分を私の中で印象付けるという術を知っているからだ。こんな事を言われて気にならない女なんて、きっといない。 「バリキャリの平日に仮面は必須。」 「そっか、まあ綺麗だからいいんだけどさ。」 調子が狂う。取り敢えずそんな時にできるのは、目の前のアルコールを勢いよく喉へと流し込むくらいだ。素面でいられる程、冷静に聞けるような言葉じゃない。根本的に、水戸くんが狡い男というのは今も昔もやっぱり変わらない事実でしかないらしい。 「じゃあ休日はその選択権俺にくれない?」 「……高いよ?」 「はは、そりゃタイヘン。」 結局、私も大衆と同じでこの男に滅法弱いという事実だけが浮き彫りになった。休日というのは次の土日なのか、それとも来週なのか、再来週なのか……そんなところまで具体で考えている私に、もう後戻りという選択肢はきっと残されてはいない。
矛盾した願い |