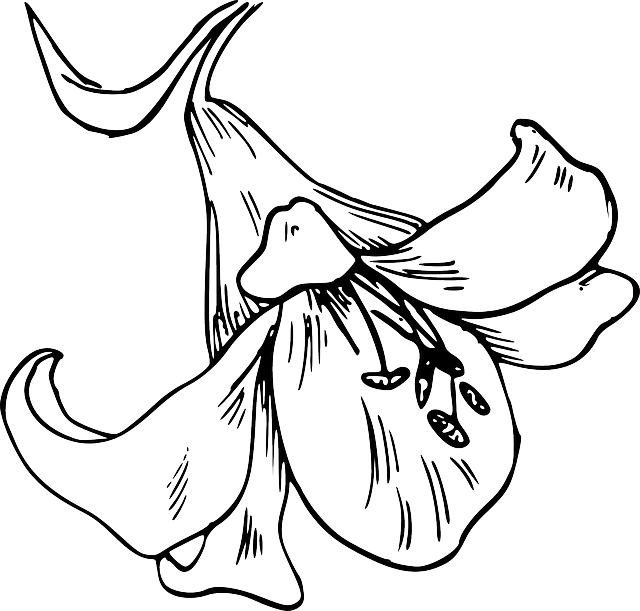 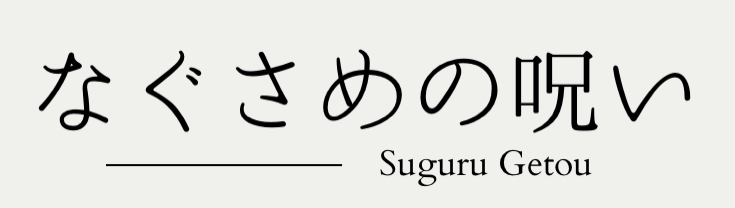 自分の判断が正しかったかどうかなど、きっと一生分からないだろう。つい最近の事のようにそれは鮮明に思い出せて、そしてどうしようもなく遠い事のようにも感じられて表現し難い。けれど、もう二度と同じ日常が戻ってこないという意味においては、後者の表現がニュアンスとしては正しいのかもしれない。 呪術高専に入ったのは、自分のためだった。自分の力を正しく、世の中の為に使いたいと思っていた訳じゃない。そんな自分に嫌悪感を覚えながらも、呪術高専は私にとって居心地が良かった。息がしやすいと感じたその理由は、一部の人間ならわかるだろう。人はマイノリティーを嫌い、マジョリティーを好む。私も例外ではない。私にとって呪術高専は自分自身の居場所で、そして私をマジョリティーにしてくれた。 けれど、その中でも五条悟と夏油傑はマジョリティーとは程遠い存在で、初めて私の価値観を変えた人間だった。自分だけが特別である事に弊害を感じ生きてきた私にとって、“特別“はいい意味を齎さない。けれど唯一無二でしかない彼らを見て、純粋に羨ましいとそう思った。それは憧れではなく、自分に対する劣等として時に跳ね返ってきた。“特別“を忌み嫌いたどり着いた場所で、私は“特別“に憧れる。結局は無い物ねだりで、もっと言い方を変えればただの度が過ぎる我儘だ。呪霊を祓う身でありながら、よっぽど自分の方が邪心に塗れた生き物のように感じられて皮肉だと思った。 「考え事か、眉間に皺が寄っているね。」 「それは気遣いの言葉に聞こえて、多分私の加齢に対する皮肉だ。」 「そんな事言ってると、余計に増えるんじゃないか。」 「夏油、昔より性格歪んだんじゃない?普通に、意地が悪い。」 事件を起こした夏油が呪術高専を追放された時、私は五条と共にいた。夏油の様子や雰囲気が以前と変わっているのは、なんとなく気づいていた。けれど、彼は安易と他人に自らの事を話す人間でもなく、例に漏れず私もそんな大多数の人間と同じだった。私は、彼にとっての特別ではなかったのだと思う。 それから間も無くしてから夏油の在り処を突き止めた私は、今もこうして彼と共にいる。自分が息をしやすいという理由で選んだあの場所を自ら捨てて、彼の隣を選んだ。それは、彼が私を否定も拒絶もする事なく、受け入れてくれたからできた事だ。そして、そんな彼が私を拒絶しなかったのは、私自身も自分の思想を口にしなければ、私が彼の思想について否定も肯定もしなかったからなのかもしれない。 「人である限り老いるものだよ、君も、私も。」 「じゃあお揃いだ、私たち。」 多分夏油にとっての“特別“は今も昔も一人だけで、それは私ではない。そんな事は昔からずっと分かっていた。私は誰にとっても、きっと特別ではないのだ。特別を嫌って入ったあの場所で、それを求めた私が愚かだと分かりながらも少しだけ寂しい。無断で退学し、夏油の元に身を寄せている私がこうして殺されず連れ戻そうともされないのは、私がそれだけ呪術高専からも必要とされていなかったという何よりの証拠になるだろう。 「お揃いだけど、全然似てないや。」 「似ていると何かいいこと、あるのか。」 「どうだろうね、分かんない。」 「自分と違うからこそ惹かれる、っていうのもあると思うけどね。」 「あー、確かになぁ。それは一理ある。」 マジョリティーに憧れていたあの頃の私には、きっと今の夏油の言葉は届かない。私は異質として虐げられるのが嫌で、決して特別が嫌だったのではなかったのかもしれない。そんな自分中心に回っている世界の中で、自分とは違う正しい夏油が私は好きだった。それは確かに特別で、自分と違うからこそ惹かれた“特別“だった。 「君は私と違うからね、。」 「回りくどいね。女は直球な言葉が欲しいもんだよ、案外。」 自分の信念に真っ直ぐに生きていたいつかの日の夏油を、思い出す。清々しいほどに自分に対しての迷いがなく、だからこそ彼は人に優しい。今もこうして私を受け入れてくれるだけの優しさを持ち合わせているのだから。彼が自分自身の信念に真っ直ぐなのは今も変わらず、その信念自体があの時と変わったというだけの話だ。真面目すぎる彼の性格が、それを二極化させて、二択提示しか与えなかったのだろう。 「よく夢に見るんだ。夏油が、また目の前から消えて居なくなる夢を。」 悪夢のような現実は、もう二度といらない。当時の私にとって、夏油は精神的支柱だった。そんな支柱を失った時に自分がどうなるかくらい安易と想像ができて、私は必死に彼を探して、全てを捨てて彼の元に身を寄せた。全てを捨てる覚悟よりも、夏油を失う事の方がよっぽど、私にとっては耐え難かった。彼も私の事をそう思っていてくれたらいいのにと思いながらも、それはいつもの私の無い物ねだりで、ただの我儘なのだと自分に言い聞かせて飲み込んだ。 「君は今も私と一緒だろう、それが答えじゃ足りない?」 「…いや、寧ろ足りすぎて少し怖いよ。」 私は夏油の傍にいる事は出来ても、彼を理解してあげることは出来ない。それも当然だ、私自身彼が何を思い何を理想としているのかその真髄を知らないのだから。聞けば教えてくれるのかもしれないけれど、聞いても理解できないような気がした。だからあえて、“聞いていないから知らない“という選択肢を作り上げた。 「でも私高専にいた時より、自分に素直になったの。欲深いんだ。」 「はは、いいね。自分の欲に忠実なのはいい事だと思うよ。」 「もし私が、夏油の体内にいる呪霊が羨ましいとそう言っても?」 「随分と奇想天外な事を、言うね。」 高専時代の私にとって、きっと今のこの環境は手を伸ばしても届かない憧れの場所だろう。夏油傑の隣にいるという事は、かつての私にとっても今の私にとってもそういう事だ。けれど、欲深く無い物ねだりの私はいつだってその先を望んでしまう。ならばいっその事、呪霊のように赴くまま欲望に沿って生きて、彼に取り込まれた方が幸せなのではないかという狂気じみた考えが浮かんだだけだ。そうすれば、本当の意味で夏油を理解できるだろうか。 「少々トリッキーだけど、そんな事言われて喜ばない男はいないよ。」 そう言って優しく手繰り寄せてくれる彼の優しさはあの頃のちっとも変わっちゃいないのに、どうして私はこんなに満たされないのだろうか。あの頃の私から叱咤されそうな、一見幸せそのものに見えるこの現実はぬるい地獄のような暖かさだ。甘美な褒美を与えるように触れる彼の指に、触れる肌に、私はもう離れることはできない。 あの頃の夏油をどうしようもなく愛おしく思う反面、もう私にとって“特別“になってしまった今の夏油を、やはり今の私は手放す事など出来やしないのだ。そんな事、呪術高専という唯一の自分の居場所を捨ててここに来た時から見えていた自分の未来だ。それが正しいのか、間違いなのかは別として。 「じゃあ、一緒にいない理由は無くなった。言質まで、取っちゃった。」 「随分と用意周到だ。」 この歪んだ幸せな世界が長く続くはずはない。限られた時間の中で、私はあとどれくらい夏油と一緒にいることが出来るだろうか。彼の目論みに違和感を感じながらも、私はもう後戻りなどできない。私たちはもうこの世界線で生きていく事しかできないのだから。 この歪んだ世界に光を齎すとすれば、それは私たちにとっての滅びと終焉を意味するだろう。けれど、もしかしたら無意識にそんな未来を私は期待しているのかもしれない。夏油を私以上に理解する、唯一の夏油の理解者である“特別“な彼であればそれは可能だろう。 最後まで自分が特別にはなれないのかと悲観する未来の自分を見据えながら、今日も私は彼に抱かれる。 これは、自分を慰めるための呪いだ。
慰めの呪い |