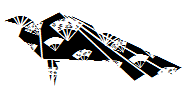 酷く胸糞の悪い一日だった。随分とあれから時間が経っているのに、気が治まらなかった。 指令が降りて現場に向かうと、そこには俺と冨岡の二人だけで、誰がどう意図してその組み合わせにしたのかは考えたくもなかったが任務となればそれも仕方ない。下された任務に対しては文句も言っていられない。 意見の食い違いは、本当に些細な事だった。あいつと任務に就いて上手くいくはずもないとでも言わんばかりに連携が上手くできない。自分ひとりであれば倒せたであろう鬼ですら、取り逃してしまった。 任務を遂行するにあったては基本的に失敗は許されない。それが自分達よりも格下の鬼であれば尚更だ。 結局は鬼を取り逃した。まともに戦えば負けると本能的に分かっての判断だったのだろう。ある意味でいえばそいつの判断は正しかった。確実に非は、こちら側にあった。 冨岡に対する苛立ちに加え、鬼を取り逃がしたというあってはならない結果に腹を立て、そんな自分自身にも怒りを覚えた。これ以上どこにもぶつける事の出来ない行き場をなくした感情が収まることもなく、気持ちが粗ぶったままだった。 任務を終えた俺は、鬼殺隊本部へと報告の任を済ませに行く。 冷静に考えれば反省すべき点だらけだったが、冷静に考える事が出来る程に感情の整理は出来ていない。加えて自らの失敗を報告しなくてはいけないのだから、余計と胸糞が悪い。今日は最悪な一日だった。 丁度報告を終え、胸に滾る怒りが収まりきらない時に一人の女を見かけた。確かという癸の隊員だ。 柱にもなれば一々格下の隊員の顔や名前など覚えているものではなかったが、その女には見覚えがあった。以前冨岡が剣術を付けている所を見かけたことがある。たまたま居合わせた胡蝶が言うには、どうやら同郷の知り合いらしい。どういう間柄なのかは聞かなかったが、見ている限りでは心を許しあっているような関係性に見えた。 万年一人でいるあいつにもそんな奴がいて、更にそれが女だった事もあって大して他人に興味のない俺の記憶の片隅にも残っていたのかもしれない。 「……風柱様。お勤めご苦労様です。」 「あ?」 俺が今どんな感情を持ち合わせてこの場にいるかも知らないそいつは、酷く癪に障る言葉で俺に一礼する。一般隊員が柱に会えば皆同じような事を言うだろうし、いつもの俺であれば一言返事をするか無視をして通り過ぎるだけだが、如何せんそうするには虫の居所が悪すぎた。 「おいお前。」 「…はい。」 「お前、冨岡の女か?」 俺に声を掛けられるとも思っていなかったのか少し戸惑ったように返事をしたその女は、次の質問に目を丸く見開いたようにたいそう驚くばかりで何も言わない。それすら、また酷く癪に障った。 「沈黙は肯定か。」 暫し返事を待ったが、女から回答はない。 虫の居所が悪い俺はその問いに根気よく待つ気など毛頭なければ、そもそも待つ必要もない。感情のままに、適当に空いている部屋へと連れ込んで、乱暴に床に転がした。それでも女は何も言わない。それが俺の負の感情を逆なでするとも知らないのだろう。腹が立つ。 「何故何も言わない。」 「…答えないといけないんですか。」 「お前今から何されるか想像つかないのか。」 想像がついているのであれば、もっと抵抗するはずだ。突然知り合いでもない男に適当な部屋に転がされて起き得る事など、そう選択肢の幅はない。もし分かっていないのであればどうしようもなく頭の悪い阿呆か、分かっていても特別抵抗してこないのであればそれももっと阿呆な女だ。結局こいつはただの阿呆なのかもしれない。 畳の上に転がした体を組み敷くように跨れば抵抗するだろうかと思ったが、それでも少し驚いたように目を丸くするだけで、そいつは抵抗する様子を見せない。 「分からない程馬鹿じゃないです。」 「なら抵抗でもしてみたらどうだ。」 ちょっとした気の違いだった。冨岡の女なのであれば、少し脅かせてやろうくらいにしか思っていなかった。いくら頭に血が上っていた状況だとしてもそれくらいの理性もあれば、俺の知性はそこまで落ちてはいない。冨岡に対する行き場を失った苛立ちをぶつけるというだけで、間の悪いその女を気の毒に思いこそすれどそれ以外に他意はない。怯えたように否定でもすればすぐに解放してその場を去るつもりだった。 異様なまでに冷静で、怯える事もしないその女にたじろいだのは寧ろ俺のほうだった。 「……抵抗した所で勝てないし、何をされるかくらい分かってる。」 急に、自分が犯した過ちに怒りが収まるどころか、炎が沈下されたように体に帯びていた熱気が冷めていくのが分かった。 俺は一体何がしたかったのだろうか。  最初に不死川という男を見たのはまだ鬼殺隊に入って間もない頃、任務についていた時の事だった。 戦況がこちらにとって不利になった時に現れた彼は、私たちが束になっても敵わなかった鬼を一撃で討ち取り、その名の通り風のように展開を変えた男だった。 あまりに一瞬の出来事で瞬きした頃には全てが終わっていて、任務が無事彼のおかげで終わったのだと一息ついて見上げた先にいたのは今まで戦っていた鬼よりも凶悪な顔面を引っ提げた男で、思わず自分の目を疑った。 「何見てんだ。」 背筋が凍るような恐怖を覚えた。彼が味方であったのは幸いな事ではあったけれど、私に植え付けられた彼の印象は恐怖以外の何物でもなく恐ろしかった。柱ともなる人間は、皆鬼のような化け物なのかもしれないとそんな事を思った。 彼が私の同期である玄弥の兄であると知ったのは、それから暫く後の事だった。この間の任務で見た風柱の話を玄弥にすれば、酷く機嫌を損ねたように去っていった彼に他の隊員がその事実を教えてくれた。言われてみれば何処か面影があった。 次に彼を見たのは義勇に稽古をつけてもらっていた時の事だ。 義勇は私と同郷で、昔からの知り合いだった。義勇はけして面倒見がいいと言えるほうではなかったけれど、昔から何かと傍にいる事も多く心の許せる存在だった。右も左も分からない鬼殺隊の中で心細く思う私をそれとなく気遣ってくれているのは不器用な彼の言動の中でも感じる事が出来た。最下級であり、下っ端隊員である私にも稽古を付けてくれるのはとてもありがたい事だった。 稽古を付けてくれた義勇はちらりと少し先にいる男に視線を移したが、暫くすると何事もなかったように稽古を続けた。その視線の先にいた男を私も映し出して、それがあの時任務にいた玄弥の兄である不死川である事に気がついた。 ただの一度、他の者も大勢いる中で出会っただけの私を彼が覚えている筈もない。普段あまり人と群れを成さない義勇が私といる事が聊か不思議だったのか、奇異を見るような目で私を見ていた。 「、どうかしたか。」 「ううん。」 「ならば集中しろ。」 「うん、ごめん。」 ただの平隊員でしかないのだから覚えてられていないのは当然のことだったが、覚えられていなくてよかったと何処か安心した。 最初に感じた彼への恐怖心が拭えずにいたからだ。傷だらけの体も、表情に加えて余計に恐ろしく思えた。私たちのような一般隊員は柱と遭遇する事すらほとんどないに等しいが、自分の幼馴染である義勇がある程度まともな人間でよかったと思う。柱は、恐ろしい存在という印象が根深く植え付けられていた。 義勇との稽古も終わり、一息付こうと場所を変えようとした所で再び彼を見かけた。 どうやら私の事には気づいていないらしい。柱ともなれば気配にも人一倍敏感である筈なのに、彼は酷く無防備なかんばせで子猫と向き合っていた。想像にもしていない場面に出くわしてしまった私は木陰に隠れるようにして彼を見ていた。 その子猫を撫でる訳でもなく、しゃがみ込んで視界を合わせるようにただじっと見つめているだけだったけれどその眼差しはどこか安らいだような優しみを帯びていて、今まで感じていた恐怖心を取っ払うだけのものがあった。 本当の彼は、優しい心の持ち主なのではないだろうかとふいに思う。自分を悪人にして嫌われ役を買う事を選んだのではないだろうかと。 それは本当にただの私の思い過ごしなのかもしれないけれど、玄弥が気を悪くしたように無言であの時その場を去って行ったのも自分の兄を勘違いされている事に対する複雑な感情からだったのかもしれないと勝手に思った。 「女、何みてやがる。」 気づかれていない事に油断してずっとその場に佇んでいた私の気配に気づいた不死川はギロリと一度こちらを見て、私は一礼して何も言わずにその場を走り去った。不思議と、恐怖心はあまり感じられなかった。 一度目に会った時にあった恐怖は消え、二度目でその印象はガラリと変わっていた。 もしかしたらこの時から、別の感情が私の中で呼び起されていたのかもしれない。 目の前に、不死川がいる。最初に感じていた恐怖はない。 礼儀として挨拶を交わしたら突然意味の分からない事を聞かれた。それを否定するのは簡単な事だった。何故ならそれは紛れもない事実で、私は義勇の女ではないからだ。 けれど私は簡単なその一言で否定の言葉を口にする事が出来ず、近くにある部屋へと腕を引かれそして転がされた。以前の私であれば確実に恐怖におののくような状況だったけれど、そこに恐怖は生じなかった。 何をされるかは分かっていた。この状況に察しがつかない程に馬鹿ではない自覚があったし、そこまで世間知らずな女という訳でもない。本来であれば抵抗すべきだと分かってはいたが、そんな気持ちにも不思議とならなかった。 「お前馬鹿なのか。」 何がこれから起きようとしているのかが分からない程馬鹿ではないにしろ、それを拒絶しない私は彼が言うように本当に馬鹿なのかもしれない。 組み敷かれている今の現状にも酷く頭は冷静で、義勇の女かと尋ねられた時には瞬時に答える事の出来なかった答えとは違って冷静に判断に至った。この先起き得るであろう事に対して、抵抗する理由が私にはなかったからだ。 先ほど彼は沈黙を肯定と読み取ったのだから、また黙っていればこの現状についても肯定とみなしてくれるのだろうか。暫く何も言わずに様子を伺えば、急に魔がさしたように我に返った不死川は私から離れるようにして距離を取った。どうして今のような状況になったのかは分からない。何か気に食わない事でもあったのだろうか。 「仕掛けてきたのは不死川さんの方でしょ。」 「お前冨岡の女じゃないのか。」 「…もし仮にそうだったら?」 一度身じろいだ不死川は一瞬の迷いを見せたが、私の言葉を肯定と受け取ったのか再び近づいてきた。けれどそれは先ほどとは違い、そうっと何かに怯えるようにしながら体を近づけてくる。あとは簡単だ、男女なのだから行き着く場所はひとつしかない。結局私は不死川と寝た。 全てが終わった後、不死川は私に柱とは思えぬような弱弱しい背を向けていた。それが何を意味しているのかが私にも伝わるようによく分かって、心を抉られる様だった。 「…悪かった。」 その言葉が彼の口から出てくる事だって、なんとなく想像の範囲内の出来事だった。 あれだけ荒々しく私に襲い掛かってきた不死川は途中から勢いを失ったように恐る恐るながらに私を抱いた。酷く丁寧で、そして優しかった。それが、どうしようもなく私には悲しかった。 彼に今回の任務で何があったのかは分からない。けれど何かしら理由がなければきっと彼はこんな事を私に仕掛けてくる筈がないのだから、それが義勇に関係する事だとはすぐに察しがついた。不死川は義勇を経由して、私を見ていたのだ。 「何で謝るの。謝らないでよ。」 「悪い。」 私が少し感情的にそう言えば、その事に対する謝罪を再び彼は述べるのだ。結局形勢は逆転し、彼は私に謝り通しだ。罪悪感に苛まれているようだった。 彼に抱かれる事で分かった事がひとつある。彼はどうしようもなく優しいという事だ。それはやはり私の思い過ごしではなく、事実として確立されてしまった。そして同時に彼に抱いていた微かな自分の感情にも確信を持った。 「私だって拒絶しなかったんだから謝る必要なんてないでしょ。」 謝る事が余計と私を惨めへと陥れるのだと気づいたのか、今度は私に代わって沈黙の時間を作り上げた。けれどその沈黙は私が彼へと抱いた微かな感情への肯定ではなく、どうしようもない罪悪感に何も言葉が出てこないというだけのものなのだろう。私と同じ意味を持ち得ない。 私は最悪な道筋で、彼への気持ちを確信して、そして同時にこの場で終わらせてしまった。 あの時彼を拒絶していれば、今よりは少しばかり状況はマシだったのだろうかと後悔の念ばかりが渦巻いた。考えたところで人生においてやり直しは出来ないのだから、過去を悔いる事は無意味で自分を更に苦しめるだけと分かっていながらもそう思わずにはいられない。 どうせならもっと乱雑に扱われたほうがよかった。こんな最悪な状況で、自分の不確かだった気持ちを確立させたくなどなかった。 「帰るわ。俺の顔なんて見たくもないだろ。」 一方的に期待を抱かせて、そして地獄へと突き落とすのだから彼は本当にずるいと思う。せめて捨て台詞のひとつやふたつ吐き捨ててくれたらよかったのに、あまりにも優しすぎるその言葉と滲み出る罪悪感が何よりも辛かった。 その中でも最も辛かったのは、残酷なまでに優しさを感じさせる彼に私が女としての感情を抱いてしまった事だ。 どれだけ想っても、その先に続くものなど何もないのだから。 ただただ生温いだけの絶頂が私に齎したものは、救いようのない恋心と、終わる事でしか始まらない恋だった。 生温い絶頂を召す |