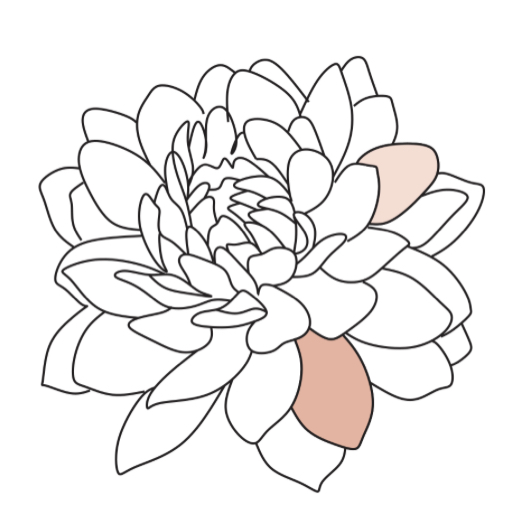 人間、ちょっとした事でも駄目になる。自分自身に信念があって、正しく真っ直ぐなのであれば問題はないのだろうけれど、私にはその確固たる自信も、覚悟も持ち合わせていなかった。だから、私は駄目になってしまった。私が、駄目にしてしまった。 中学の途中当たりまで、私はあまり水上敏志という男の事を知らなかった。それもそのはずだろう、彼は義務教育中にも関わらず、あまり学校に来ない生徒だった。別にいじめにあっていた訳ではない、噂に聞くとプロ棋士を目指していたらしい。いつからか、突然何事もなかったかのように学校に来るようになった水上は、掴み所のない男だと思った。 突然学校に来たかと思えば直後にあったテストではほぼ満点で学年トップ、運動をやらせても、何をやらせても飄々とした感じで、気づいた時には誰もが水上敏志という男に注目した。 注目の的であり時の人になっていた水上は、ものの数週間で学校にもクラスにも馴染んでいて、今までどんな顔かも思い出せない程の存在だった彼は、何事もなかったかのように皆の輪の中にいた。皆が嘗て抱いていた水上への違和感は消え去っていて、逆にその違和感を大きく膨れ上げさせていたのは、きっと私だけだろう。 「さんって、俺の事好きなん。」 突然、きの抜けた顔でこんな事を言われた事があった。中学二年生の頃一度だけ同じクラスになったきり、私は水上と直説的な関わりはなかった。同じ高校という共通点はあったけれど、そんな事を言ってはキリがないだろう。あまりに突拍子もない言葉に、私はしばらく否定も肯定も、出来なかった。 「それはどう捉えるべき?新手のナンパ、それとも、」 「同級生やしナンパにはならん、と思うけど。」 「……まあ、確かに。じゃあ、何で。」 「こっちの台詞やで。あんたがずっと見てくるから、気になるやん。」 この男の距離感が、私にはよくわからなかった。ほぼ転校生のような扱いで突如学校に来た彼が、完璧な中学生として馴染むまでの速度は異常だったと記憶している。何故、皆が何の違和感もなくそれを受け入れているのだろうか、当時の私には理解できなかったのだ。 「まあ別にいいねんけど。迷惑、してる訳と違うし。」 強烈なインパクトを残しておきながら、やっぱり彼のかんばせはいつもと何一つ変わらなくて、飄々としていて、どこか気が抜けたような感じだった。好きなのかと聞いておきながら何の感情にも触れていないような水上は少し怖いと思いながらも、彼に言われて私自身が無意識的に水上の事を目で追っているのだとようやく、自覚した。好きか嫌いかで言えば、好きでも嫌いでも、どちらにも該当しない。ただ、何かが引っ掛かるように、気になって仕方がない。 「物凄い顔してんで、自分。」 「…水上くんが変な事、言うからでしょ。」 「あ、そうなん?そらすまん。」 好きなのかと尋ねておいて、けれどその答えを回収しに来たという訳でもなさそうだった。ジロジロといつだって見てくるその女が、どんな女であるのかを、自分の目で見て見るかという、彼にとっては暇を潰すくらいの感覚だったのかもしれない。責めるでもなく、言いよるでもなく、だからと言って引いていく訳でもない。やっぱり、水上のことはよくわからないと改めてそう思う。 「でも否定はせえへんって事は、まるっきし嫌いって訳でもないんか。」 「物凄い自己都合な解釈だね、それ。」 「解釈なんて自分の都合ようしとかんと面倒やしな。」 やっぱり私が当初から水上に持っている印象は変わらず、何を考えているのか全くもって読めない男だなと思った。青春を謳歌する高校生という同じ生き物とは思えないほどに、無気力で、全てを悟ったように卒なく色んなことをこなす男だ。 この時点では、好きでも嫌いでもなかったけれど、嫌いではないと思った。そして、何を考えているか分からないからこそ、何故か私が彼の思惑を考え出すようになった。こうなると、水上は初めから分かっていたのだろうか。いくら私が彼の謎めいた思惑を模索しても、その真相を知る術はない。 そこから暫くして、私は水上と付き合うことになり、彼は私の彼氏になった。それが、今から数年前の出来事で、私たちは付き合って半年もしないで遠距離恋愛になった。水上がスカウトを受け、ボーダーへと入ったからだ。 水上からボーダーにスカウトされたと聞いた時、私は右から左に聞き流す程度にしか気に留めていなかった。世間ではボーダーが正義のヒーローのような扱いを受けているが、彼がそんな正義を背負って、玄界の為に戦うところを想像にすらしなかったからだ。 けれど、「スカウトされてんけど、俺。」とぼんやりと呟いて、そうなんだと適当に相槌を打った私に対する次の言葉で、私の予想は大きく裏切られた。 “ 俺ボーダー入るから、遠距離恋愛なるなあ “ ボーダーに入るという彼の言葉にも大層驚いたけれど、私がもっと驚いたのは、その次の言葉だった。思っても見ない言葉が短時間で連発して、思考が半分停止しかけていた。 「なんや、寂しくないんか?意外やな。泣いて悲しんでくれるもんやと。」 「悲しむ前に突っ込み所満載で涙も出てこないよ。」 「ツッコミポイントを無意識に生成しとるとか、俺も関西人やなあ。」 「ばか、それ違うから。」 遠距離恋愛になるなあと言った水上は、私と別れるつもりがないのだと知って、驚いたのだ。好き合って付き合った感じでもないし、どちらかといえば流れでそうなっただけで、元々執着心に疎そうな水上が、そこまで好きでもない私と遠距離になってまで付き合うという選択肢を選ぶとは夢にも思わなかったのだ。 「遠距離、するの?」 「ここ大阪やで。流石に通ってたら、死ぬやろ。」 「真剣に聞いてるんだけど。」 別に、ボーダーに入る事を止めたかった訳でもないし、そもそも私にはそんな権利もない。水上が私と、遠距離恋愛をしてまで付き合うメリットは何なのだろうか。寧ろ、そこに僅かながらでもメリットはあるのだろうか、私にはそれが理解できなかった。 「普通するやろ。それとも俺ら別れる理由何かあるん。」 結局どんなメリットがあるのか、私には最後までよく分からなかったけれど、水上に対する気持ちは、確実に変わっていた。彼女でありながら、彼女でないような自分を、この人が彼女にさせてくれた。それだけで、一生分の満足を得たくらいに、不思議と心が満たされた。 「あんた、俺の彼女やろ。」 結局この半年後、私たちは別れた。 私は大学を卒業して、社会人になっていた。ぼちぼちと、所謂“第一次ブームメント“に便乗した友人達が結婚をし始めて、ご祝儀貧乏とはこの事をいうのだなと思った。まとめてではなく、分散して結婚してくれたらいいのに。 水上とは、別れてから一度も会っていない。彼は、今何をしているのだろうか。遠い噂で、大学卒業と共にボーダーは辞めたと聞いたことがあった。けれど、誰も水上と今も尚懇意にしていない事もあり、その情報源はひどく不確かだ。生きてはいるのだろうけれど、私にはその軌跡を辿る事はできない。 高校の同級生の結婚式に呼ばれるのは二回目だったけれど、水上の姿はなかった。結婚式という堅苦しいものではなく、学校の知り合いを集めて同窓会の延長線上にあるような集まりに顔を出す者は多かったけれど、その大勢の中に、彼はいない。 あんな別れ方をしては、それも仕方がないのかもしれない。 水上との半年の遠距離恋愛は、私にとって過酷だった。自分でしっかりと彼を好きと認識するきっかけが遠距離になる事だったのだから、それは必至な感情だったのかもしれない。今まで特に意識することもなく隣にいた水上がいない日常は酷くつまらなく、退屈だった。周りの誰と話していても、水上ならこう言うだろうになと置き換えて、他の人間が馬鹿に思えた。 ボーダーという組織は、よっぽどの事がなければ本部近隣から離れることはできないらしく、彼が大阪に帰省する気配は微塵にもなかった。その代わりに、隙を見て気の抜けた関西弁で、私に電話をくれた。それが嬉しくもあって、唯一の支えだった事もあって、任務の都合で連絡が滞ったり、連絡がつかなくなる事で私の心は少しずつ崩壊していった。 そんな私を、水上も遠く離れた地で身に染みて感じたのだと思う。防衛任務で暫く連絡出来なかったと詫びてきた水上に、私は感情のままに泣いて、そして怒鳴った事があった。 「どうして会いにきてくれないの?私、水上の彼女じゃないの?」 こう言えば彼が困ると分かっているのに、現実的に大阪に帰ってこれる訳がないのだと分かっているのに、私は言っても仕方のないことばかりを紡いで、きっと水上を呆れさせてしまった。最初のうちは私を宥めるようにしていた水上も、何度も同じ事を繰り返すようになった私に、ついに一言だけぽろりと漏らした。 「ほんなら別れるか、俺ら。」 一瞬、その言葉に私は凍りついて、ピタリと涙と嗚咽を止めた。冷静に考えて、それが自分にとって有利なのか不利なのか、そして本意なのかそうでないのか。冷静に考えながらも、感情を抑えきれない私は、きっと水上に誘導されたのだと思う。 「だったら別れる。こんなに辛いなんて聞いてなかったし、もういい。」 「分かったわ。」 感情の籠っていない短い言葉に続いて「ほな。」とそう別れの言葉を告げられ、私たちの関係はたった二文字で終わってしまった。最初はなぜこんな簡単に終わらせることができるのなら、遠距離恋愛になってでも恋人でいる事を選んだのだろうかと憤慨したけれど、三日もすれば冷静になった頭が、後悔という二文字を貼り付けて何も手につかなくなった。 もしかすると、いつも通りのあの気の抜けた関西弁で、電話がかかって来るのではないだろうか。追加でもう一日だけ待ってみたけれど、もちろん電話がかかってくる事はなかった。それに耐え切ることが出来ず、電話をかけたのは私の方だった。 「どないしたんや。」 「この間はごめん。ちょっと冷静さに欠いてた。本当にごめんなさい。」 「ああ、もうええて。気にせんとって。」 やっぱりその声は、いつもの気の抜けた水上の関西弁で、この四日間の憂鬱が嘘かのようにスッキリと晴れていった。水上は、私を許してくれたのだと、そう思った。 「今度、私がそっちに会いに行くよ。もう帰ってきてなんて言わないから。」 私が求めるばかりになっていたこの関係こそが、よくないのだとようやく気づいた。これからはもっと対等な関係でいるべきだし、そうして水上との関係を再構築しようと思った。私がそうしたいと思う程に、私が水上を男として好きだから仕方がない。もう、充分に彼の事を好きになっていた。 「いや、別にそんな事せんでええで。てか、そこまでする必要ないやろ。」 「……なんでそんな事言うの。まだ、怒ってる?」 「別に怒ってへんよ。でも彼女でもないがそこまでする必要ない。」 「水上ごめん、本当にごめんなさい。別れたくない。」 「普通に別れたやん。それに俺他の子とヤッてもうたし、もう無理やって。」 衝撃的な言葉に、また私の思考が止まる。彼のその言葉は事実だろうか、正気だろうか。こんな時でも電波を通じて聞こえてくる水上の声はいつもと変わらないのだから、その真意は読みきれない。尤も、彼を感じられるくらいに近い距離にいたとしても、水上のかんばせはその感情を私に読み取らせないのだから、同じ事なのかもしれないけれど。 「その子の事、好きになったの?」 「いや。別にやっただけやし、好きとか嫌いとかない。」 「……好きじゃないならいいから、お願い。」 藁にもすがる気持ちだった。水上が他の女と体を交えていても許せると不思議とそう思ったのだ。その女に気持ちが完全に向いたという事でなければ、私たちはまた再構築できるはずだと。好きあって付き合った訳でもない私たちの始まりを考えれば、きっとどうにでもなるはずだ。 「ほな言うわ、俺お前の事もう好きちゃう。」 そこから先は、流石の私も弁解の余地も、反撃も、もう一度チャンスが欲しいと物乞いする事もなかった。それくらいに、水上は私に対して一ミクロンさえ可能性を残してはくれなかった。 こんな別れ方をしておいて、一体どの面を下げて水上に会えばいいのかは、もう彼と別れてから何年も経った今でも、私には分からない。けれど、もうそれだけの時間は経ったのではないかと、会うことくらいは許されるのではないかと、そう何処かで願っていた。 水上を忘れることが、私には出来なかった。 周りが“第二次結婚ブームメント“に便乗し始めた頃、私は結婚式の二次会で、懐かしいそのかんばせを視界に映していた。どれだけ望んで、泣いて、別れても尚忘れることが出来なかったその男が、目の前にいた。 「……水上、来てたんだ。」 「めっちゃ久しぶりやん。出張でこっち来てたから、ついでやけどな。」 もっさりとしたその出立ちと、気の抜けた関西弁は私が中学生の頃から見ていた水上とさほど変わっていなかった。本当に当時のそのままを体現してるかのような、何も変わらない水上を見て、上手く適合する言葉を私は必死に探し続ける。そんな言葉、ある筈もないと分かっているのに。 「ボーダーは?」 「普通に辞めた。大学でたら元々続けるつもりなかったしな。今は普通に社会人や。」 「そっか。辞めるつもりだったのは知らなかった。」 「どっちの方が自分にとって都合がいいか考えたら、最初から答えなんて出てる。」 もしかしたら、大学を卒業したら水上は私のところに戻ってきていたのではないだろうかと、今になって考えても仕方のない事を考える。もう直接聞いたところで、その真意は窺い知ることは叶わない。私たちが別れたあの時から、全ては分岐していて、過去は変えられなければ、あった筈の未来も分岐した時点で死滅するのだから。 「結婚するんやってな、よかったやん。」 あの時もっと私が冷静になっていれば、未来は違う方に分岐していただろうか。水上と一緒に歩む未来が、あったのだろうか。それは私にも分からなけれど、水上にも分からない。あの時に終わっていなくても、その次の分岐点で終わっていたのかもしれない。 本当は、分かっていた。私に一度でも手を出した事のない水上が、簡単に他の女と交わるはずがないのだと。冷静に考えれば、すぐに分かった。そのフィクションを、いかにもノンフィクションであるかのように言うことで、私を敢えて振ったのだろう。あのまま付き合い続けても、きっと私は日に日に精神的に壊れていっただろうし、関係を再構築するのは不可能だった筈だ。それを、水上は理解していたのだと思う。 「なんか心、篭ってないなぁ。」 「それはデフォルトをこんな感じに産んだ俺の両親に言うてくれ。」 逆に私との関係を壊しにかかった水上の分かりづらい優しさが、胸に氷柱のように突き刺さってどうしようもなく痛い。遠距離恋愛をしてでも私との関係を続けようとしてくれた水上の優しさに気づく事ができなかった私が、子どものまま成長できずにいる。 昔にたった一度だけ、遠距離恋愛になると分かったときに唇を重ねただけのその男が、私にとっては初恋の人で、今後一生上書きできない最愛の人なのだろうと思う。 「水上は、変わらないな。」 過去に戻れるならやり直したいと思うけれど、きっと過去に戻ったところで彼と幸せになる未来はないような気がした。私が私でいる限り、きっとこの恋は叶わないのだ。
|