 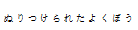 きっと、私のささやかな憧れが、彼にあるとは誰も知らないだろう。 牧紳一という絶対的なカリスマに、私は恋をした。ベダだと笑われるような、一目ぼれをした。けれど、それは自分の心の内に秘めておくものであって、そして、それを自分の心の内に隠しておけるだけの、安定したものでもあった。あの日、幼馴染の清信に誘われて見に行った試合に行かなければ、きっと私の永遠に成就することのない、救いようのない恋心は生まれる事はなかったのだろう。 他愛もない会話を交わしながら、最後に信長の甲高く響くあの声が響いた。私の日常。昔から、何も変わることなく続いてきた日常。人は、私と彼を幼馴染と呼び、時にそれ以上の関係なのではないかと勘繰りを入れる。 まるで感情の籠っていない、そんな言葉を紡げば、やはり清信は納得がいかないようにビービー言いながら必死になって私を試合に来させようと考えているようだった。見栄っ張りな彼にとって、自分の応援が誰ひとり居ないというその状況を避けたいだけであり、それ以上でもそれ以下でもない。本当に馬鹿でいつもの事ながら呆れた。雑音としか思っていなかった彼の声が、いい加減に煩く、耳障りになってきた頃、私はようやく首を縦に振りかざした。 そして、その試合会場で私が見た牧紳一は、誰がどう見ても一番光り輝いていた。それがただの憧れであるのか、恋であるのか、自分でもよく分からない程に、どうしようもなく光り輝く彼に惹かれていた。清信がイケメンだろと騒ぎ立てていた「神さん」など、私の視界にすら入らず、今となっては顔も思い出せない。渋々とは言え、幼馴染の応援をしに行くために来た試合でありながらも、私の視線の先にいたのは、終始一人だけだった。 放課後、私は柄にもなく、黄色い声援の後ろで、バスケットコートを見ていた。跳ねたり揺れたりする彼女達の中で、私は酷く浮いていたに違いない。もちろん、その先にある部員達の姿は私には見えなかった。こんな姿を信長に見られるのも何だか癪に障るので、私は踵を返そうと、正門へと体を向けた。 「青葉じゃん。お前も暇だねえ。」 ちょうど、一番関わりたくないタイミングで、一番会いたくない人物に出くわしたのは、私がコートを離れようと数歩歩きはじめた頃。信長のこちらを見るそのかんばせが、酷く偉そうで、やはり思い描いた通りに私の癪に障った。 「何、この間試合来て嵌まった?バスケ。」 「別に。ただ通っただけじゃん。」 そう言えば、やはり彼もワンパターンで、いつものように少し癇癪を起したようにピーピーと騒ぎ立てる。幼馴染ながら、本当に彼は真っ直ぐな馬鹿だと思う。騒ぎ立てる彼を、誰か制裁してくれはしないだろうか。煩い彼の声が、突如静まり、その少し後に、痛そうな信長の声が響いた。 「部活サボるとはいい度胸だな、清田。」 今、まさしく私が望んだ通りに、信長を制裁したのは部長である牧だった。あの試合以来、初めて見る彼の姿だった。 暫く二人は、茶番とも取れるようなやり取りを交わしていたけれど、ひょんな事で、牧の視線がこちらを向いた。彼からしたら、ただの見知らぬ女の一人である、私の方へと。 「もしかすると、君が沢田さんか?」 真っ直ぐな瞳が、私を射抜き、その名を呼んだ。一体だれかこんな状況を予想しただろうか。私は、お決まりのように、予想にさえしなかったこの状況に、返事すらする事なく、ただ蹲りそうな体を必死に直立させる事で必死だった。 「はい。」 必死な思いで紡いだ一言に、牧は少しはにかんでこちらを見直した。 「清田の幼馴染とは随分と物好きなんだな。」 そう言う彼は、年相応な高校生のように見えた。とてつもなく大人の様に見える彼が、一瞬、少しだけ近くに感じられた。ものものしい雰囲気を醸し出すには、酷く優しげなそんな笑みだった。 「幼馴染は好きでなるものではなく、気づいたらなってるものですから。物好きではないですよ、きっと。」 「なるほどな。」 何故か、思った以上に私の口は動いていた。 信長のビービーと騒ぎ立てる声をあれ程疎ましく思っていながらも、今は、その煩い彼の声がいい具合に私の混乱を誤魔化してくれているようだった。 「まあ、愛想つかさないで仲良くしてやってくれ。」なんて言葉に私はぶんぶんと勢いを付けて首を振りおろした。そうすれば、牧は挙動不審でしかない私の態度にまた笑った。彼の笑顔がどうしようもなく優しくて、私の中で抱かれていた何かは、確実に色濃くなっていった。 あれから、私は時間を見つけてはバスケ部の練習を見に行くようになった。信長の言ったとおりのようで、そこは少し癪に障ったけれど、牧と話すきっかけを与えてくれた事に免じてそこは目を瞑る事にした。私は、生まれて初めて胸に宿したこの未知なる感情に、必死に食らいついていた。 「また来たのか。」 「はい。見に来ては、迷惑ですか。」 「そうは言ってない。」 牧は、私が何を目的にここへ来ているのかを、きっと知りもしないのだろう。だからこそ、逆に彼と話しやすかった。「愛想つかさないで仲良くしてやってくれ。」というあの言葉で、私が暇を見つけては幼馴染のバスケを見に来ていると勘違いをしているのは、目に見えて分かり切った事実だった。牧は、口癖のように私を見て、あの言葉を漏らす。 「やっぱりお前は物好きだな。沢田。」 そう言って笑う彼が、いつだって魅力的過ぎて、私の胸はいつだって酷く痛んだ。バスケをしている時からは想像もつかない程に、棘がとれた薔薇の花のように、彼が酷く柔らかく見えた。もうそれが、憧れではなく、違うものであると私は確信を得ていた。 これは、恋に違いないだろうと。 「牧さんだって、きっと、物好きですよ。」 「ほう。」 タオルで隠れていた彼の顔が、私を向く。 「私みたいな物好きと話す牧さんも、やっぱり物好きなんだと思います。」 私の人生で、彼と関わる事はきっと組み込まれていなかった事に違いない。何の共通点もなければ、私と彼は天と地ほどに違うだろうから。輝かしい彼に比べて、私は何も持ち得ない、酷く一般的で何処にでもいるようなただの少女A。彼は話しの主人公になれても、私は到底ヒロインにはなれない。それ程に、私達はかけ離れている。 「そうかもしれないな。」 「私が物好きっていう所は否定して下さい。」 「沢田が自分で認めたんだろう。」 「物の例えじゃないですか。」 他愛のない会話が、どうしようもなく、私の心を揺らした。こうして、落ちついた素振りを見せるのに、一体私が苦労しているのか誰もしらないのだろう。 「いいじゃないか。似たもの同士っていう事で。」 嘘でも、その言葉が嬉しかった。どうしようもなく、とてつもなく、私の胸の内を高鳴らせた。 「来週の日曜。」 彼は、一度言葉を止めて、バスケットコートを見た。私も、そんな彼につられる様にコートの先を見た。そこには、一年にしては酷く生意気で、憎らしい程の活躍を見せる、信長がいた。 「日帰りの合宿がある。沢田、お前も来るといい。」 信長が放ったシュートが、リング板にはじける事無く、網の中を抜けていった。 楽しみにしていたドラマが、あった。毎週、毎週、待ちきれない程に楽しみにしていたそのドラマは、私の一週間を酷く長く感じさせる。待ちきれないと、本当にそう思わせるほどに長い。しかし、それと反比例するように、日曜日はあっという間に私の前に現れた。 柄にもなく、都心まで買い物に出かけ、ないお小遣いを散財し、私は白いブラウスを新調した。高校生になってばかりにしては、酷く大人びたそのブラウスは、やはり今の私に似合う事はなかった。もしかすると、いつまで経ってもそれが似合う日はやってこないのかもしれない。母親から借りた真っ赤なルージュを引いて、私はまるで自らが試合に挑むかのように、背伸びしたように気張っていた。 合宿先についた私は、やはり酷く浮いて見えた。自分が部外者であるという事実が身にしみるような、鋭い視線が私を射抜いていた。こんな時に居てほしいと願う、信長は最早お約束と言わんばかりに、寝坊という名の遅刻に違いなかった。 「沢田。」 柔らかく、甘い声が、私の鼓膜を通っていく。ようやく、私はほっと肩を撫でおろし、遠慮気味に手を振って牧の元へと小走りで向かっていく。 「早いな。」 「信長と一緒にされては困りますから。」 「ふん。お前らしいな。」 そう言って、彼は一度、上から下まで私を見ると「私服だと随分と変わって見えるんだな。」そう言って、やはり笑った。それがどういう意味であったかは、私には分からない。けれど、その笑顔に惹かれた私にとって、真意など最早どうでもいい事だった。 少し、私は驕っていたのかもしれない。これが夢でないのであれば、まるで私は彼の恋人であるかのような、そんな幸せな錯覚に陥っていた。誘われた時点で、私の心はまるきりその幸せな錯覚にとらわれていたのかもしれない。 「折角来たんだ。応援、期待してるぞ。」 「はい。もちろん。」 笑ったそのかんばせが、くるりと、後ろを向いた。紳一、と私が呼ぶ事など出来ない、その名を綺麗な声が紡いだ。振り返った彼は、到底私なんかには見せてくれた事のない、私が彼の好きなあの笑顔以上に、表現しようもない少し照れくささを漂わす様な、そんなかんばせを向けた。 「じゃあな。また、後で。」 私は、何も言えなかった。頷く事すら、出来ない。私の錯覚が、やはりただの錯覚であり、驕りに違いなかったのだと気づいたのは数分放心した後の事だった。 聞き覚えのある声が、私を呼ぶまで、私の中は真っ白で、そして空っぽだった。 「つらいね。」 「…どうして。」 私がそう二つ返事をすれば、隣の男は、困ったように私を見ていた。そのかんばせが、私を一番残酷へと陥らせると、きっと知らずに。 「信長はああいう性格だから気づいてないだろうけど。君の瞳は、真っ直ぐに牧さんを見てたからね。」 ゆっくりとかんばせを上げると、そこには、嘗て信長が私のタイプであろうと言った「神さん」がいた。ああ、何処が神さんなんだ。こんな残酷な事を言う神様を私は知らない。読み方は、違うけれど。 「彼女は、牧さんの彼女だ。」そう言って、彼の視線の先にあるものを、私も一緒になって眺めた。そこには、酷くお似合いな牧と、その彼女が並んでいて、幸せそうに、私の好きだったあの笑顔が向かい合わせに並んでいた。神が二人を見る目と、私が二人を見る目が、どことなく、同じような気がしていた。 「牧さんああ見えて結構天然な所あるから。きっと君への悪気はなかったと思うんだ。」 牧の隣にいる、大層綺麗なその女は、やっぱりストーリーのヒロインになれるだけの素質を持っているように、輝いている何かが見えた。それに引き換え、私はやはり少女Aから何も変わらない。私には、ヒロインになれる素質などなかった。そう、知っていたのに高望みをした上で驕った自分を呪った。 「どうして分かったんですか。」 「そうだね。きっと、君と僕は同じだからだろうね。」 牧の口からよく出た言葉が、思いだされて涙が出そうになった。本当の似たもの同士というのは、きっとこういう事なのだろう。私は、暫し神という名の男と茫然と失恋した先を眺めていた。そうした所で、事実は何も変わらないと、知っていながら辛い現実を焼き付けるように、ずっと、見ていた。 「お、青葉じゃん。」 ちょうど、一番出くわしたくないタイミングで、一番会いたくない男の声が響いた。信長は、いつだってタイミング悪く私の前に現れるものだなと、何かを通り越して笑いがこみあげそうになった。 「遅いよ。遅刻じゃん。」 「まあギリギリ間に合ったからセーフっしょ。」 「最低じゃん。アンタ。」 最低で、一番醜いのは、私だと分かっていたのに。これは違いなく、八つ当たりというものだろう。先ほどまで隣にいた神は、気をきかせてくれたのか、もう姿は見当たらない。 「てかお前!何その口紅ギャグだろ。まじ笑える。」 息を整えた信長は、ようやく私のその見慣れないかんばせを見つけると、ケラケラと面白いものを見るように笑った。八当たりの延長で、そんな彼に一度げんこつを喰らわせた。よく牧が、彼にしていたように。 「でも私もそう思う。馬鹿みたい。」 本当に。何を勘違いしていたのだろう。今は、失恋したという事実よりも、自分の痛さが酷く惨めだった。買ってばかりの、背伸びをした真っ白のブラウスの袖で、ぐいぐいと真っ赤なルージュを拭きとった。信長は、そんな私を不思議そうに見ていた。「何、それ本当に馬鹿じゃん。」そんな言葉に、何かが吹っ切れたようだった。 「私、帰るね。試合がんばって。」 私は、ヒロインになりたかった訳じゃない。少女Aが嫌だった訳じゃない。ただ、あのかんばせが私に向けられているという、その事実だけで嬉しかった。その隣を、と夢見た私は、やはり少女Aのまま、そこから前進することは出来ないのだ。 真っ赤になった袖口が、その真実を私に教えているかのように、鮮やかに輝いた。 20120209 |