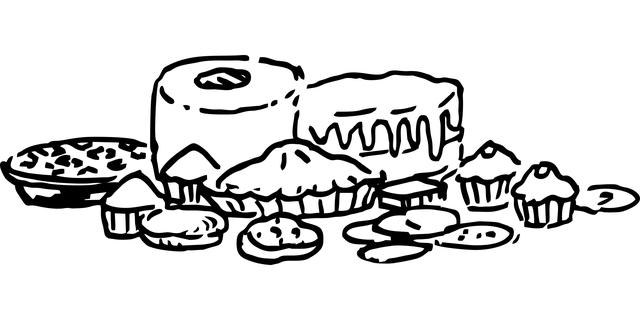 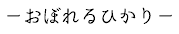 五月になれば家を出るつもりだった。元々背伸びをして借りたその家は私の給料には見合っておらず、給料を下げてまで営業をやめた私には二年目の更新を機に家を出るという選択肢しかなかった。そんな時に世の中はコロナに包まれ、東京には緊急事態宣言なるものが出されていた。自粛が求められる中での引越しも難しく、在宅勤務で残業がなくなってしまった私にとって無理をしてこの見合わない家賃が発生する家に更新料を払ってまで住み続ける選択肢もない。事は緊急事態でありながらも、判断に迷うものだった。 「だったら俺のところ来いよ。」 思っても見ない天元の言葉だった。彼は前職の同僚で、私の彼氏だ。一年浪人して大学に入った私は実質彼よりも一つ年上になるのだが、彼には甘やかされっぱなしだ。いつだって甘やかさればかりの私はきちんと自立をしないといけないと思うようになり、冗談半分でありながらも「いい加減俺離れしてちゃんとも自立しろ。」なんて言うものだから、引越しを迷っていた私には寝耳に水だった。 確かに彼の家は広く、私一人がしばらく居候した所で何も問題はないだろう。きちんと書斎もあるのだからお互いがリモートワークでも差支えがない。こんなありがたい提案はないと思う反面、また自立の機会を失ってしまったと少しだけ気が引けていた。 「ねえ、今日何食べたい?天元が食べたいもの何でも作るよ。」 「どういう風の吹き回しだ。コロナにでもかかったか。」 「ひどい言い様。会社から有給ある人間は積極的に取得してほしいって言われてさ。暇なの。」 「あー、なるほどな。通りでが積極的に料理するなんておかしいと思ったわ。」 ひどいなと思いつつも、そう言った後に一生懸命自分が何を食べたいのか考えてくれる天元は優しい。きっと大して料理もできない私が作れる範囲内の食べたいものを必死に考えてくれているのだろう。表面的な言葉では見えにくいその優しさも、どうしようもなく嬉しく思えた。 「洋食な気分。」 「じゃあハンバーグは?ワインも用意しようか。」 「んじゃ、それで。」 十時になると彼は家で仕事を始める。極力邪魔をしないように、部屋の片隅で本を読んで時間を潰した。小説を読んでいながらも時折料理のレシピ本を読んだりしたが、思いの外それは楽しい時間だった。彼のために何を作るのか、それを考えるのが楽しかった。 彼がオンラインでの商談を始めて、私は部屋を移してごろごろと転がりながらテレビを見ていたがそれも暇になって買い物へと出かける。たいして作ったことのないハンバーグのレシピをスマホで確認しながら食材を選んでいると、彼と結婚するとこんな日常なのかなとそんな事をふいに考えた。 ちょうど買い物を終えて彼の家へと戻ると商談を終えたのか、再び黙り込んで仕事をしている彼がいた。 「おう、帰ったのか。買い物?」 「うん。ハンバーグの材料と、赤ワイン買って来た。」 「そりゃご苦労さん。」 視線はパソコンに向いたまま、ぽんぽんと手をおいて私に構ってくれる。私が前職を辞めたのはもう一年程前の事になるが、なんだか一緒に彼と働いている事を思い出すようだった。 同期の中でも彼は抜群に仕事ができた。分からない事は何でも彼に聞けば解決したし、きちんと相談にのってくれる時間も設けてくれた。そしてそれが成功したと伝えに行くと、今のようにしてもらっていた事を思い出したのだ。結果として私は営業には向いていないと気づいて職場を変えたが、それでも彼と一緒に働いた日々はいい思い出だった。 「天元が商談してる所ちらっとだけど久しぶりにみたな。やっぱりすごい。」 「当たり前。出来が違うんでね。」 「私もあのまま会社に残ってたら、今頃トップセールスだったりして。」 「頑張りは認めるがそれはないだろ。何せ俺、いるし。」 少し上から目線なその言葉と相反して、天元はきちんと私の視線に立って物事を見てくれる。本当に人間ができているのだと思う。自分の彼ながらも本当に尊敬していて、そして自慢の彼氏だ。世の中がコロナで苦しみ、大変な時に私はこんなにも満たされていていいのだろうかと少し後ろめたいくらいの気持ちだった。 「早く作って来いよ。腹減った。」 「うん。頑張る。」 「思いの外早く終わりそうだからよ。」 きっと、私が張り切って料理をするなんて言ったものだから気を利かせて仕事を片付けてくれたのだろう。これはあまりにも自己都合的な解釈だろうかとも思ったが、私がそう思えるくらいに彼は気が効く男なのだ。全くもって公私ともに仕事の早い男だ。 スマホでレシピを確認しながら肉をこねる。しばらくすると暗くフェイドアウトしてしまう画面を必死に立ち上げながら手順を確認して、こねあげた肉をフライパンの上に乗せた。訳もわからず今日買ったワインでも流し入れてみれば美味しいだろうかと思い立ってレシピに載っていない手順を踏んでみる。失敗したか成功したかは、食べてみるまで分からない。冒険する必要性もない所で初心者は好奇心を発揮しがちなものである。 「天元仕事終わった?」 少し離れたキッチンから声を張って尋ねたら、片手をあげて終わりそうだと知らせてくれる天元がいる。私が彼と結婚して専業主婦にでもなれば、きっとこんな感じなのだろうか。これが毎日だったらそれもそれで飽き飽きするのかもしれないけれど、少なくとも今の私には間違いのないささやかな幸せだった。 仕事が本格的に終わったのか、彼はキッチンに私が作り上げた代物がきちんと完成しているのかを確認しに来る。 「…見た目は普通にうまそう。」 「見た目はね。ワイン入れて遊んでみたから味は保証しないけど。」 「いいんじゃね?遊び心満点で何よりです。」 白いシャツで後ろから私を包み込んで、フライパンの上に並んでいる肉の塊を見るとそんな皮肉っぽくも捉えられる一言が添えられる。冒険したのは私なのだから、別に腹が立つこともない。ただただそれが食べれる代物であってくれと私も祈るばかりだ。 無事に皿に並べられたハンバーグを前にワイングラスに赤い液体を注いで行く。私は普段もっぱらチューハイしか飲まないからよくわからないが、並々に注いだワインを見て彼は呆れたように笑っていた。 「どこぞの安いチェーン店のワインみたいな量だなこれ。」 「いいじゃん。どうせこれくらいの量飲むんだし。」 「相変わらず大雑把だな。花嫁修行でもしてみたらどうだ。」 言われて見て確かに自分自身が女として欠落している部分が多い事を自覚せざるを得ない。いつだって彼の家にいる時に料理を振舞ってくれるのは天元だった。私はそれを横からじっと見つめながら、料理アプリの動画再生のように正確な彼の料理に感心するばかりだ。こういうところがきっと、私が自立できていない部分なのだろうと思う。 「花嫁修行は別にしても、今日一日色々して天元と結婚したらこんな感じなのかなって思ったよ。」 「何、お前専業主婦がいいわけ。」 「そうじゃないけど。結構楽しいなと思って。もうこのまま住んじゃおうかな。」 冗談半分でそんな事を言えば、また小言を言って馬鹿にされると思っていた。お前はやっぱり自立できていないなとか、俺がいないと何もできないのかよと、どこかそんな決まり切ったパターン化された切り返しが来ると思っていたのだ。 けれどその予想は悉く砕かれる。営業時代彼によく言われた言葉を思い出した。お前の切り返しは想像の範囲を超えないと。こう言われた時にどう切り返すのか、よく天元に聞いては捻りが足りないと言われたものだ。そんな彼はいつだって思ってもみない場面で、思いもしない言葉を投げかけてくるのだから、きっと次の言葉も私は予想してもいなければ、想定できるものでもなかったのかもしれない。 「元々そのつもりだったけどお前、違うの。」 想定していない切り返しではあったけれど、彼にしてはあまりにも普通すぎる言葉だった。 「否定しないんだったら少しは女子力あげて花嫁修行しとけ。」 コロナが齎したものは、世間からバッシングを受けてもおかしくないような、私にだけ贅沢な結果を生み出していた。やはり彼には敵わない。美味いか不味いか、得体の知れない肉の塊に彼はフォークとナイフを入れた。
|