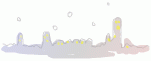 私達は所謂家族というカテゴリーにあてはまる。姉と、弟という関係が有難くもあって、少しうっとおしい。私と赤也は血の繋がっていない、再婚同士の連子だった。 私達の関係が姉弟という関係だけでなくなってから数カ月、私は以前よりも頻繁に彼のいる実家に顔を覗かすようになっていた。 あまり家に立ち寄る方ではなかった私の頻繁な帰郷を素直に喜んでくれている両親を見る限りでは、今の所私達の本当に些細な変化に気づいていないという事なのだろう。きっと誰も気づかない程に、私達の関係は変わってはいないという事でもあるのだろう。 「お、帰ってきた。」 「ただいま。母さんは?」 「台所。」 「そう。」 玄関に鍵をかけて彼に言われた通り台所にいくと予め私が帰って来ると聞いていた母が腕によりをかけてとても食べ切れそうにない程の料理をこさえ、「おかえりなさい。」そう言ってくれる。私も何も迷うことなくその言葉に返答を漏らした。 二階からは少し豪快な鼾が聞こえてきて、確かめるように耳をすませる私に母は照れくさそうに「お父さん、お昼寝中なの。」とだけ言った。 そんなどこにでもある幸せな光景が、かつて互いの伴侶を裏切ってまで貫いた浮気からなされたものかのかと思うとどうにも不思議な気がしてならなかった。 不倫の末にゴールインした先にこれ程までに幸せな家庭があるとはきっと誰も想像していなかっただろう。嘗ての伴侶も、その親も、そして私と赤也だって。 「土産は?」 その言葉の先にあった赤也の顔はさして喜んでいるようでもなく、ただ普通に姉が家に帰ってきたというそれだけのものだった。 「隣の県から帰って来るだけで毎回お土産買う訳ないでしょ。」 「ちぇ、気利かねえの。」 それでも赤也は私の鞄の中を覗き込むようにして確認して、本当に何も目ぼしいものがないのを確認するとつまらなさそうにこたつに足を入れた。私も鞄を置いてその中に足を放り込む。 「場所、取り過ぎなんスけど。」 「いいじゃない。いつもどうせ一人で踏ん反り返って占領してるんだから。」 「アンタの足冷たいからこたつが冷えるんだよ。」 「それはすみませんね。」 私達は再会に喜ぶでもなく、だからと言って黙り込む訳でもなく、程いい具合に姉弟らしいやり取りをしていた。まさか私達が今姉弟という関係から少しだけ進歩した関係になっているとは思えない程に、ここには付き合いたてのカップルのような初々しさなどあったものではない。 彼を一人の男として見ながらも、やはり何処かこれが本来の家族の姿なんだろうななんて私は呑気に考えていた。何一つ欠けない幸せに満ち足りた家族像であるとばかりに。 「お土産じゃないけど飴ちゃんあるよ。食べる?」 赤也が酷く退屈そうにしているものだから、私はなんとなく鞄の中をがさごそと探ると随分年季の入った飴玉が一つを見つけた。ふうっと袋についた小さなゴミを吹き払うと彼に差し出してみる。 「…馬鹿にしてんの?」 「え?うーん…まあ、ちょっとは。」 「むかつく。」 赤也は不機嫌そうにしながらも私の手の中にあった飴玉を強引に奪い去ると、紙を破いて口の中に放り込んだ。ガリガリと早速音を立てている彼はリモコンに手をつけて目まぐるしくチャンネルを変えていく。 台所から仄かに香って来る香ばしいおかずの匂いと炊いているご飯の甘い匂いが鼻を通り過ぎていく。その香りに釣られたように小さく響いた私の腹の虫に彼は一言だけ皮肉めいて呟いた。 「色気より食い気。」 してやったりな顔で笑う赤也にさして腹を立てる事もなく私はただ目まぐるしく変わっていくテレビを見ていた。すると逆に赤也の方がシカトをこかれたとばかりに再び不機嫌そうに顔をしかめて、ついにはテレビの電源を消してしまった。 「今、面白そうなテレビあったのに。」 「何か言えよ。むかつく。」 「だって本当に色気か食い気どっちか選べって言われたら私間違いなく食い気を取るだろうし。」 そう言えば彼は然して興味もなさげに「へえ。」とだけ私に投げ返して来る。だから私も「うん。」とだけ適当に相槌を打つ。これ程までに自然な姉弟のやり取りもないのだろうなあなんて私は悠長に考えていた。 時々不思議に思う。私と赤也の血が、繋がっていない事に。 ここまで自然な自分たちの関係が、不思議でならなくなる時があるのだ。そこに居て当たり前で、他人であって何処までも近い赤也の存在があまりにも心地がよくて。その心地よさは血の繋がりからくるものなんじゃないかと疑ってしまう程に、彼の隣は心地がよかった。時折振りかかって来る嫌味の言葉も本来の意味を為さぬようにただ私を安心させてくれるだけだった。 「最近何してた?」 私は彼の口からどんな言葉が出てくるのかを予め把握しておきながらも、尋ねる。 「別に。ゴロゴロしてた。」 「太るよ。」 「食い気女にだけは言われたくないね。」 悪態付く赤也を見ると、ほんの少しだけ彼が太ったようにも見えた。もちろん普通の人間に比べればまだ細い方ではあったけれど、やはり部活を引退して彼は暇を持て余しているのだろうなと容易に想像出来た。 「もうテニスやらないの?」 私はさりげなく尋ねた。もう彼にとってテニスという存在は、大きくないのかもしれないと思ったからだ。 彼がテニスを始めたのは間違いなく私の影響だろう。彼と家族になる前から唯一私の取り柄とも言えるそのテニスが、彼を惹きつけていた。私を超えるという目標を既に達成してしまった彼にとって最早テニスは輝きを失っているのかもしれない。彼が目標としていた私は、彼に遠の昔に追い越されてしまったのだから。真田も、幸村も、柳も、もう、彼の前にはいなかったのも要因の一つだったのかもしれない。 「…さあね。俺にも分からねえ。」 「やればいいじゃん。あんだけテニス好きだったんだから。」 「だったら青葉も辞めなきゃよかったじゃん。」 「私は 私がそう言えば彼は「知ってるっての。」なんて言いながらこたつの中で私に背を向けるようにして転がってしまった。 私は彼のテニスが好きだった。私とは違って枠に嵌まらない、自由なテニスをする赤也のテニスが羨ましくもあって少し妬ましかった。彼は私に持っていない物を持っていた。それは上手さでもなく、体力でも経験でもなく、何にも囚われる事のない強さだった。私にはそれがない。何もかもをかなぐり捨てて勝利だけに執着する程の情熱もなかった。 いつの間にか私は自分でテニスをする事よりも、彼のテニスを見ている事の方がよっぽど好きになっていた。だから私はテニスを捨てた。 でもそんな私の好きな彼のテニスが今、消えてしまうかもしれない。少し怯えながらも彼の名前を呼ぶと、彼は私に背を向けたまま躊躇ったように言葉を紡いだ。 「なんつうか、こう、…追いかけるモンがねえと燃えきれねえんだよな、俺って。」 やはり予想通りの彼の言葉に私は頷くしかなかった。私には彼にテニスを強制することはできない。いつかこうなるとは、分かっていた事だった。 「アンタがまたテニスするってんなら話は別かもしんないけど。」 「それはないね。今私がテニスをしたにしたって私はもう、赤也を追う立場でしかないから。」 すると彼は思い出したように「あー、そっか。そう言えば俺アンタよりも強いんだった。」嫌味もなくさらりとこんな言葉が彼の口を出た。私はもう、彼の目標でも何でもない。立派に私を追い越してしまった、一人の男だった。 「追いかけられるだけなんて刺激のないのは嫌いだね。」 赤也はそう言った後に痒いとばかりに背中をボリボリと掻きむしっていた。 炊飯器のタイマーが炊きあがりを知らせたのとほぼ時を同じくして家の中が真っ暗になった。今まで稼働していた色んな電化製品も音を潜め、不気味な程に静寂が家を包み込む。 赤也が確認するように外を覗いていたけれど、近隣の住宅も綺麗さっぱり真っ暗闇に包まれていた。 揚げ物をしていた母は急いで油を切って、二階への階段をパタパタとひた走る。きっと父を起こしに行くのだろう。起こした所でどうなる訳でもないのに。 赤也は割と落ちついていて、私の隣に腰を降ろしてこたつに足を投げ入れた。もう暖を生まないこたつが赤也が入れ込んだ冷気によって急速に冷めて行った。そして暖を取るように、前触れもなくキスをされた。 バックミュージックにしては少しロマンティックに欠け、騒がしく日常的な母の声だったけれど、私はこの居心地のいい暗闇で目を閉じた。 初めて弟と交わしたキスはとても姉弟らしく自然であって、それでいてただの男と女が交わすソレでもあった。 ( 20110321 ) |