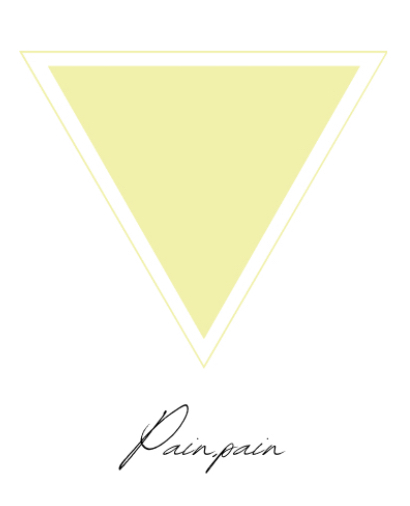 リョータが帰国した事は既に私の耳にも入っていた。想像していたよりかは早く帰ってきたのかもしれないし、あれだけ辛い別れをしたのだからどうしようもなく長かったのかもしれない。自分の感情でしかないのに、私自身がそれを理解出来ないでいる。別れてから確実に年をとっているのだから、それなりの時間が経過している事は間違いないのに。 リョータの帰国を知らせてきたのは三井さんだった。 私がどんな気持ちで別れたかを知っているくせに、この人は相変わらずデリカシーがない。うそだ。デリカシーがないんじゃない、過剰なまでにお節介だ。帰ってきたんだから会いに行けよなんて言われたけど、どんな顔で会ったらいいのか分からなかった。 会いたいと望めば物理的に会える距離に、リョータがいる。そう考えると体が勝手に前進しそうになりながらも、背中に重い重い鉛を背負ったように尻もちをつきそうになる。バランスをとるだけで精一杯だった。 「…。」 三井さんはリョータの新しい住所を紙に書いて私に握らせたけれど、結局その紙を暫く握りしめていたら汗で滲んでよく分からなくなった。リョータ、どこに住んでるんだろう。二十三区にいるのかな。考えるなら会いにいけばいいし、会いに行かないなら考えなければいいのに。頭ではそう理解している筈なのに、結局全てが矛盾する。 「ねえ、でしょ。見間違える筈ないし。」 「……なんでここ知ってるの。」 「三井さんが教えてくれた。」 リョータに会いたくなかった訳じゃない。あれが大恋愛と言えるのかどうかは分からないけれど、少なくとも私にとっては大恋愛だった。燃え上がるような恋という表現も違うけれど、こんなに人から大切にされている事を身をもって知る事はなかったし、それだけ人を好きになった事もなかった。 「俺が結構強引に聞いて、教えてもらった。」 私が三井さんに対する苦言を漏らしそうになったのをいち早く察知したのか、リョータはそれを否定するように、ズバリ確信へと迫る。別れてからそれなりに時間が経っていても、やっぱりリョータは私と付き合っていた彼氏だったんだと他人事のように思った。 「そっか。」 「うん、待ち伏せするような事したのはごめん。」 「ううん、大丈夫。」 「そうでもしないと会ってくれないと思って。」 やっぱり、リョータは私の事をよく分かっていると思う。それもそうか、別れる直前まで私の彼氏でいたいと懇願したリョータを、好きだからこそ終わりがあるなら今すぐに終わらせたいと同棲していた家を出た私なのだから。 リョータじゃなくてもわかる事なのかもしれない。少なくともリョータ以外だと、三井さんもそう思っていたのだろう。そうでなければ流石に許可なく私の職場の在処を教えたりはしないだろう。 「なんかたくましげだね?」 「そっか?」 「うん、首なんかも太いし体がガッチリしてる。」 「まあバスケしかしてなかったからな。」 暫くして、お互い言葉に詰まって黙り込んだ。会えなかったその時間分だけ話すことなんて沢山ある筈なのに、とてもそんな気分にはなれなかった。 リョータに会いたくなかった訳じゃない。でも、会いたかった訳でもない。理由は明白で、自分の知らないリョータになっているかもしれないという恐怖が拭えなかったからだ。不器用ながらもどうしようもなく優しくて、まっすぐに私だけを見てくれていたその眼差しが、あの頃と変わってしまっていたら私はそれを受け入れる事ができるだろうか。 「リョータ、ここ会社の人に見られちゃうから…」 「あ、うん。そうだよね、ごめん。」 二人して会社のロビーから離れて少し歩いたところで、沈黙を破るようにリョータが口を開いた。 「ここから家近いから来ない?」 「……それはどうかな。付き合ってる訳じゃないし。」 「やましい事なんてしないからさ。」 「……でも、」 「ほんとに。コーヒー飲むだけでいいから。」 こんな切ない顔をしてくるリョータに、私が断るなんて事をできないって知っているくせに。だからずるい。私はリョータのお願いに滅法弱い。でもそれはリョータの願望を叶えているようでもあって、私自身の願いでしかないのだ。それは昔だけでなく、きっと今でも。 リョータと別れた時、リョータは泣いた。もう少しだけの彼氏でいさせて欲しいと懇願した。こんな幸せな言葉はないと思いつつも、こんな残酷な言葉はないと思った。結局、私はその日のうちに一緒に住んでいた家を出た。自分の決意が揺らがないうちに、早急に。 リョータは海外遠征の話を私に隠して、そして知らない間に辞退を申し出た。これも三井さんがなんとなく漏らした一言で、私が知るきっかけとなった。 何故言わなかったのかと聞けば、何て事もないように、あれなら断ったからと軽く言ったリョータと言い合いになった。願っても、努力しても、運があっても、そのいずれも持ち合わせていないと叶わない壮大なその夢を簡単に諦めてもいいのかと。そして、それが私との別れを意味しているからあえて何も言わず断っていた事だって、全部全部わかった。だから、辛かった。 「ここ、入って。」 「…お邪魔します。」 結局私たちは、別れの道を選んだ。リョータの夢を優先して欲しかったし、それは私にとっても夢だったのかもしれない。その代わり、きっぱりその日で私はリョータの彼女でいることをやめて実家に戻った。 それでも、リョータからもう一度だけ会いたいと言われ、別れていながらも何度会いに行っただろうか。その度に好きだとくぐもった声で愛を紡がれ、最後だからと抱かれた。 別れる事は想像以上に簡単だった。でも、リョータを完全に切り離すのは想像以上に困難で、結局は私自身がリョータを求めていたという他でもない証拠だった。会うごとに好きになって、これから遠い地に行くリョータに想いが募ってどうしようもなくあちこち痛んだ。 「適当に座っといて。コーヒーはミルク多め?」 「あ、うん。ブラックでいい。」 「……好み、変わったんだ?」 「どうだろうね。そうなのかもしれない。」 本当はブラックのコーヒーなんて飲めない筈なのに、なんだかそう言いたくなった。少し大人っぽく、より男らしくなったリョータを見て、自分だけが変わっていないような気分に陥った悪あがきだ。 「俺は変わってないけどな。」 「変わったよ、首の太さとか腕の太さとか。」 「中身は変わってないでしょ。」 「…確かめてないし、分かんない。」 本当は分かってた。私が一番変わって欲しくなかった部分が、リョータに色濃く残っている。二人でバイトを沢山入れて、節約して買った大きな白いソファーも、機能性よりも見た目重視で買った四角い大理石のテーブルも、配置換えをする度に困る二メートル六十センチの長すぎるテレビ台も、全部リョータと一緒に選んだ思い出の詰まった家具が、そのまま私の視界に映っているのだから。 「アメリカではバスケの事だけ考えて生きてたよ。」 そうであって欲しいと、私もそう思っていた。だからよかった。そうじゃなければ、泣きながら別れた私が浮かばれない。それにリョータが渡米しても尚私を引きずっているのも、私の本意じゃない。それくらいの覚悟なら、渡米する必要なんてないのだから。 「かっこいいね、リョータは。」 「…どうかな。」 リョータは昔から自己肯定力が低い。その分、他人のことを、私のことを過剰に肯定して、そして大切にしてくれる。自分には勿体無い彼女だと、聞いているこちらが反応に困るくらい大切にしてくれた。 「日本に帰ってきた時、の事を考えられるように。だから、アメリカではバスケだけに集中するって覚悟決めてた。」 結局、リョータは昔と変わらない。この二人の思い出の詰まった家具を、私と別れた今でも大事にしているリョータが変わった筈なんてない。家に一歩入った時から、そんなことには嫌でも気がついていた。 「変なことしないんじゃなかったっけ?」 「うん、だからぎゅってする以上はしないから。」 「彼氏いたらそれも駄目なやつじゃん。」 「…いるの?彼氏。」 かつて二人で大奮発して買った四人がけのソファーの端っこに私を追いやって、逃げ場のない状態でリョータの腕が恐る恐る私を抱く。首筋にあたった鼻が、懐かしいリョータの匂いを吸い込んでやっぱり泣きそうになる。 「待っててくれなんて言われた覚えないもん。」 「…なんだ、言ってよかったんだ。」 「どっちにしたってもう遅いじゃんね。」 懐かしいリョータの匂いが鼻腔を通り抜けてなんとも言えない気持ちになる。決して強く抱きしめられている訳でもないのに、包まれているリョータの体は以前とは比較できないほどにガッチリと筋肉質で、少しだけ固かった。嗅覚ではリョータと認識しているのに、少しだけやっぱり違うんだなとそんな事を思う。 「さ〜。」 「ん?」 「もっかい俺の事好きになってよ。」 「え〜、なにそれ。」 セットされてないリョータの髪が首すじをくすぐるように、こそばゆい。やっぱり昔を思い出してしまって、思わず手が伸びそうになって、冷静になって一度仕舞い込む。多分、少しだけ心が弾んでいたからだ。今のこの現状は、私がリョータと別れる時に望んだ再会に、少し似ているような気がしたのかもしれない。 「本当にあと一回だけでいいから。」 「リョータ自分勝手だなあ。」 「何回でも謝るけど、好きだからしょうがないじゃん。」 付き合っていた頃を思い出してしまいそうな、完璧にまで再現された家具と部屋に、私の気持ちもすっかり戻っているのかもしれない。でも、それは正確に言えば戻った訳じゃなくて、今も尚変わらない気持ち。シンプルに、そういう事なんだろうと思う。 「もう一回は好きになれない。」 「…俺の事殺す気?」 「だって嫌いになってないしずっと好きだもん。」 はぁ〜、と気の抜けたリョータのため息とも言えないような声が聞こえて、私の感情も今度こそ緩んで、やっぱり泣いてしまった。言いたくて、ずっと言えなかった言葉。言いたくても、そこにリョータはいなかったのだから。 自分から会いに行こうとしなかったくせに、帰ってくるべきところに帰ってきた感じがするのは何故なんだろうか。寧ろ帰ってきたのは、リョータのはずなのに。 「……やっぱり殺す気だ。」 「一回くらいはいいかもね。」 「辛辣すぎる。」 「だったら、嫌いになった?」 散々待ち侘びたのだから、これくらい聞いてもいいだろうかと自分の我儘が遠慮なく口から滑り落ちていく。それを、昔と変わらず受け入れてくれるリョータがそこにいると分かっている私だからこそできる、最高の贅沢だ。 「やっぱり一回死にそう。すき。」 少しだけソファーのスプリングがバカになっているような気がして、それを確かめるようにボンボンと軽く飛び跳ねてから、もう一度リョータの逞しい胸板に勢いをつけて飛び込んだ。 「………もう待たない。」 結局、久しぶりのキスも別れる前と同じで少ししょっぱい。 痛みと言っても、種類は一種類じゃないのかもしれない。どうしようもない悲しみによって生まれる痛みもあれば、何にも変え難い幸せが痛みとして襲ってくることもあるらしい。多分、両方を経験したからこそ、相乗効果で後者の痛みが私を幸せに誘ってくれるのかもしれない。
ペインペイン |