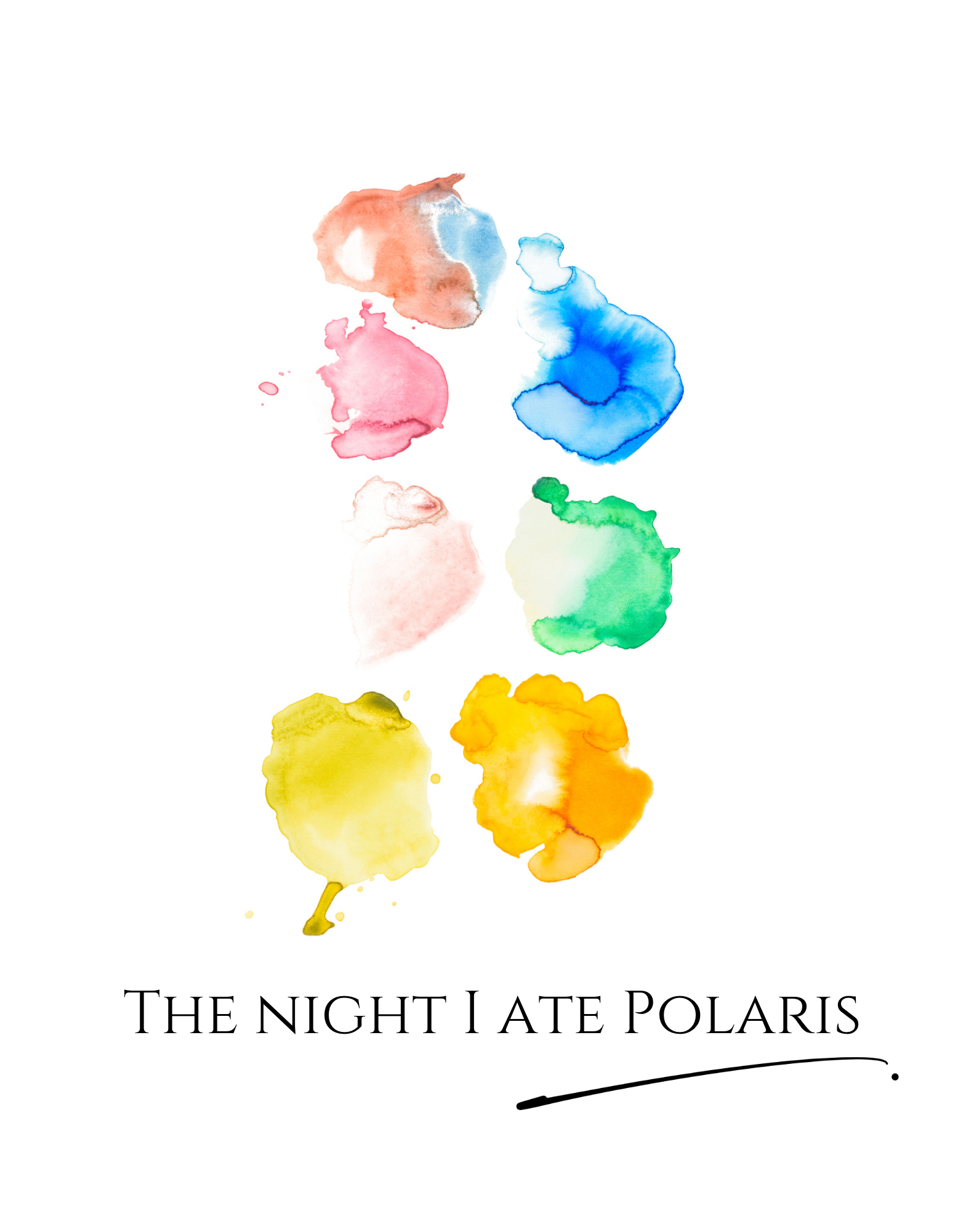 心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。 The behavior will change if the mind changes. Habits change if action changes. Personality will change if the custom changes. The destiny will change if the personality changes. ウィリアム・ジェームズ William James 1842~1910 心理学の授業で教わった言葉だ。どこかの偉人の言葉らしい。 偉人の言葉が名言になるのか、名言だから言葉を発した人間が偉人になるのか、はたまた偉人は生まれながらにして偉人になる才能を持ち合わせてこの世に生み落とされるのか………エトセトラ。 授業に集中しているのか、していないのか、そもそもするつもりがないのか。どれにも該当しないようで、もしかするとどれにも該当するのかもしれない。そのいずれが正解か突き詰めたところで誰も得をしないし、何の解決にもならない。それが答えだ。 人格や性格を変える事は想像以上に難しいもので、分かっていても治せない・変わらないなんて事はこの世にごまんとある。その中の一つが、とある男の直向きすぎる恋心についてだ。 入学してリョータを知った時、それは既に始まっていた。彩子への直向きな恋心の事だ。同学年でそれを知らない人間はいない。 それ程に誰がどう見ても三年間変わる事のなかったリョータの恋心、それもまた“変わらない”その一つだと思っていた。バスケをする時のリョータの真剣な眼差しと、彩子を見つめる時の柔らかで特別な眼差しと。その二つは対比するように見えて、実は一緒なのだろうと私はそう思う。どちらも、曇りなく一点を見つめているからだ。 「なあ、話聞いてる?」 「……え?」 「え、じゃあねえし。さっきからずっと上の空。」 「白出汁派か麺つゆ派の話だっけ。」 「耳鼻科行く?」 たまにこうしてリョータの話を聞きそびれる。白出汁か麺つゆかで悩んだのは昨日の私で、食欲のない熱帯夜に素麺を湯掻いた時のことだ。ちなみに私は白出汁わさび派だ。 「ってたまに俺の話聞いてなくない?」 「そう?リョータは麺つゆ紅葉おろし派でしょ?」 「………良い加減そのネタから離れろよ。」 大学の授業も終わり校舎を離れ正門へ続く坂道、上半身を少しだけ後ろに倒しながら前に進む。待ち構えるように柵に肘を突っかけてその上に頭を乗せているのはリョータだ。彼はうちの学生ではない。私の高校時代のクラスメイトで、今は違う大学に通っている。 随分機嫌が悪いようだ。 約束をしていただろうかとリョータの前へ辿り着く前に一度坂の途中で立ち止まる。スマートフォンの履歴を辿ってもそんな形跡はない。二十三時三十八分、眠気に耐えかねた私がおやすみの挨拶を送って、一分と経たず同じ文字を重ねるようにリョータの返事………そして、リョータからのおはようの文字で止まっている、トーク履歴。 あまりまめな方ではない私が、半分夢の中へと旅立ちながらも必死の思いで、お・や・す・み、何故この四文字を打ったのかを思い出す。理由は簡単だ。さもなくば、今のこの現状がその都度繰り返されるからだ。 「まじで既読くらいつけてよ………生きてんのか普通に心配になる。」 そんな馬鹿な、言いかけるより先に私の生ぬるい体温を確かめるようにリョータの左手が絡みついた。冗談で言っているようには見えないその表情と、丸め込んで包み込むようにぎゅっと握り直されてしまうとやっぱり何も言えなくなる。 「私が高校三年間皆勤賞だったの知ってるよね?」 「だから余計にじゃん。」 「あ〜、まあ……それはそっか、ごめん。」 彼の独占欲が強い事は昔から知っていた。でもそれは私にという訳ではなくて、彩子という存在があって初めて生じる感情や欲でしかない。だからこの現状が半年経った今も尚、私の中ではぼんやりとはっきりせず、輪郭を見出せていないのかもしれない。 「練習あったんじゃないの?」 「ん〜、サボった。」 「それは………よくないね?」 「そうさせた張本人だろ。」 「……まぁ、そうなんだろうけど。」 リョータは実家から神奈川県内にある大学へ通っていて、私は都心を少し通り越して東京の端っこに位置する場所で家を借りて大学に通う。遠距離と言えば遠距離恋愛をしている人間から怒りを買う程には近くて、気軽に会えるというには結構遠い。中々に絶妙な距離感だ。 大学に入ってもバスケを続ける選択をしたリョータには一般的な大学生ほど暇も余裕もなくて、私達は月に一度か、よくて二度顔を合わせられるかどうかといった状況だ。 慣れたような顔付きで正門で待ち構えていたけれど、実際これは相当なイレギュラーという訳だ。会えて嬉しい感情がありながらも、やっぱりどこかそれが自分事ではないような非現実を感じる場面が多々あるので不思議だと思う。 「でもバスケは休んじゃ駄目でしょ。」 「……分かってる。」 「次からは鬼電してくれていいから。」 「その前に既読つけて返信すりゃ済むじゃん。」 「保険だよ、保険。」 ならば何故私はずっとこの非現実のような現実を生きているのか。その理由を遡っていくとようやく話は冒頭へと戻っていく。結局、直向きに彩子へと向いていたその感情こそがリョータそのもので、変わる事がないと思っていたからなのだろう。まさかその矛先が自分に向くとは夢にも思わなければ、現実になってもそれは夢とほぼ等しい位置付けだ。 「んで、ここら辺でオススメの店あんの?」 「てか帰らなくて平気?」 「……なんだよ、帰す気なの?」 「明日も練習あるでしょ。」 「……ない。」 「うそ、流石にそれくらい覚えるIQはある。」 顔も、性格も、趣味や好み、声質だって何もかも彩子と違う個体でしかない私に、その感情が向いているという事実。半年が経っても現実味を帯びてこない。何故それが私なのか、ぼんやりした頭で考えたところで答えに辿り着くはずもない。 「……会ったら帰りたくなくなるのくらい察してって!」 離れてみて気づいたその感情こそが今の自分の気持ちだと言ってくれたリョータ。半年前に始まったこの関係を、世間では恋人と呼ぶらしい。そんな甘ったるい名前のついた関係に、私の感情は追いつかない。 ならばそれは何故追いつかないのか。直向きに彩子を見つめるその彼を、他ならぬ私もまた追っていたからだ。それが恋だという自覚は持っていて、しっかりと確立された感情だ。だから、いつまでもこの関係に現実味を持つ事ができない。 「えっと、」 「………」 「お酒でも飲みにいこっか?」 お互いお酒を飲める年齢になったのに、リョータとはほとんど飲みに行った事もない。先日友人に連れて行ってもらった居酒屋を目指して歩いていくと、無言の肯定が指の隙間を絡めていた。 「リョータって普段どんなお酒飲むの?」 「え〜、普通。」 「普通……ビールとかハイボールとかレモンサワーとか?」 「うん、泡盛とか。」 「普通の概念も十人十色って事かな……」 一度ほろ酔い気分で帰宅した時の事だ。せわしないメロディーが鳴り響くスマートフォンをスライドして電話に出た時、酷く彼が怒っていたのを思い出す。随分とふわふわした甘ったるい声が出ていたらしく、それ以降その話題には触れないように生きている。 「お酒強いんだね、やっぱ沖縄の血?」 「まあ弱くはないと思う。」 「あんま飲みに行かないの?」 「部活もあるし、まあ別になくても生きてけるから。」 あっけらかんとしたその顔は、暮れていく夏の空を見上げてそう言った。案外、私は彼の事を知らないらしい。 普段どんなお酒を飲んで、そもそもお酒自体を好んでいるのかどうか、飲みに行く時はどんな店にどんな面子で行くんだろう。私の知っているリョータは高校時代で止まったままだ。 彼の眼差しの先にはいつも彩子がいたこと。私が知っているのはせいぜいそんなところだ。かき集めた所でそれほどしかない情報量で、けれど私は彼に恋をしていたのだ。 「……やっぱうそ。」 「ん、なに急に。」 「が飲みに行ったって聞いた時、誰いたかとかどんな話したのかとか………そんな事考えたらたまんなかったから。」 「……難しいな、つまりどういうこと?」 「にそう思われたくないからしてないってこと!」 なんで一から十まで言わないと分かんないんだよ馬鹿!まで付いてきた。言われてみれば確かに納得が出来るはずなのに、私の頭は本当に彼が言うように残念な構造なのかもしれない。通りで授業の内容も入ってこない訳だ。 「なんかさ、」 「……なんだよ。」 「やっぱなんでもないかも。」 「絶対なんかあるじゃん。」 「じゃあ忘れた。」 どうしてその感情が私に向いたのか、その理由を私は知らない。離れてから好きだと気づいたと彼は言うけど、じゃあ何がそうさせて、私のどんな所がリョータの好きに触れたのだろうか。聞きたい反面、それを聞くのは少し怖い。 「こういう暑い日ってビールが美味しいんでしょ?」 「おっさんみたいな事言うじゃん。」 「たまにはおじさんの気持ちも分かってみようかなって。」 「それよりも分かるべき事あるだろ絶対。」 もうとっくにリョータは私を真っ直ぐ見てくれているのに、私は彩子を見ていたリョータを見続けているのかもしれない。自分が彼にとって彩子を超える存在になれている自信もなければ、そもそも比べる必要もないのだって本当は分かっているから。 「ぼんじりの唐揚げ食べたい。」 「なにそれ、うまそ〜。」 「ビールで流し込みたくなるかな?」 「わかんね、でもなるかも。」 二人で居酒屋の扉を横に開くと、少し遅れていらっしゃいませと響く。当たり前のように年齢確認をされて、私達はそれぞれ学生証と免許証を提示して中へと通される。店内は想像以上に混み合っていて、横並びで座らされた席はリョータが当たり前のように手前に座って、奥まった角の席に私を座らせた。 「本気でビール飲む?」 「うん、大人の階段登ろっかな。」 「それ使い方違くね?」 「リョータは泡盛?」 「と一緒の。」 じゃあビールと言いながら私が注文パネルをもたもた触っていると、リョータの腕が伸びてきてお目当てのビールのページを見つけてプラスボタンを二度押した。続けるように器用にページをめくりながら迷う事なくぼんじりの唐揚げを見つけ出して注文ボタンを押すと、厨房の方から何度か甲高い音が響いていた。 「うわ〜、」 「なんだよ。」 「想像通りすぎる味でびっくりしてる。」 「……だから普通にやめときゃいいのに。」 早々に運ばれてきた黄色い液体の上積みを掬うように喉に流し入れて広がった苦味。まだおじさんとは分かち合えないのかもしれない。苦い経験を沢山積み上げると、この苦味が旨味に変わるんだろうか。 ビールジョッキよりも突き出しで出てきたメカブをちみちみと飲むように両手を添えて喉に通していく。 「どれが好きなの?」 「え?」 「だから、お酒。」 「どれって言われてもなあ……」 「じゃあ前は何頼んだ?」 「この柚子はちみつサワーってやつ。」 「…ん、」 リョータはまだ三分の二以上が残された私のジョッキを通り越すように再び腕を伸ばして注文パネルを器用に動かしていく。サワーのページで柚子はちみつサワーを選ぶと当然のように注文ボタンを押した。 「まだ全然飲めてないけど。」 そう言うと、リョータは自分の半分になっていたビールを喉仏を上下に揺らしながら綺麗さっぱり飲み干した。 「俺が飲むからいいでしょ。」 躊躇う事なくそう言ったくせに、私の返事を待つ前に照れ臭くなったのか私のジョッキを奪うように自分の方へと手繰り寄せて口をつけた。彼が最初に飲んでいた空のジョッキが下がったのとほぼ同時に、柚子はちみつサワーが私の手元にやってきた。 「……甘いの好きなんだ?」 「うんまあ、そうかも。」 「高校ん時も甘ったるいのよく飲んでた。」 「あ〜、パックのいちごみるく。」 「それ。」 何を言った訳でも、お願いした訳でもないのにすぐに気づいてくれる優しさが好きだった。他の誰もが見逃すような些細な事に気づいてくれるリョータの事が好きだった。彩子を一途に想い続けられる純粋なリョータが好きだった。だから、自分の想いが通じる日が来るなんて本当に夢の中でさえも考えた事はなかった。ただの一度も。 「甘いとさ?」 「うん。」 「ジュースみたいで沢山飲めちゃうよね。」 「それ落とし穴だから。」 「それは前回飲んだ時に私も思った。」 「それは俺の前だけにしといて。」 運ばれてきたぼんじりの唐揚げは程よい塩加減と油が口に広がって、それは柚子はちみつサワーで流し込んでも十分に美味しい。このジューシーで喉の渇くぼんじりの唐揚げを食べすすめていけば、自ずと私は酔っ払う事が出来るだろうか。 「案外強かったりして?」 もっと酔いが進めば、もう少し気の利いた言葉や心の奥底に潜んでいる喜ばしい感情を解放する事が出来るような気がして。 空調の真下に座る私には冷たい風が直撃していて、ついさっき滲んでいた汗が冷たく体を冷やしていく。肌寒さを通り越して寒さを感じた時、注文パネルでメニューを辿っていた私の手を遮ったリョータは会計ボタンを押して財布を取り出していた。 「まだ来てばっかじゃん。」 「強くない人間は家で飲むのが一番安全だろ。」 「え〜、」 二千円に満たない会計を済ませて店を後にすると、ぶわっと体を纏うようなベタベタとした湿度と夏の夜の風が通り過ぎていく。夜でも少し遠くのどこかから控えめな蝉の声が聞こえている。 「コンビニどこ?」 「この間お酒貰ったからうちにあるけど。」 「…………」 人通りの少ない通りに入って信号待ちで立ち止まると、ふわっと背後から覆い被さるようにリョータの温度に包み込まれる。もう自分自身でもそんな事実はとっくに知っているはずなのに、やっぱり私はリョータの彼女になったんだと他人事のようにそんな事を思った。 「夏だけど?」 「……冷えてんだからちょうどいいでしょ。」 信号が赤から青へと変わる九十秒にも満たない短い時間で、私はしっかりと彼の彼女を自覚して、そして満喫する。 いつもどこか他人事のように自分達を見てしまうのは何故なのか。人は満たされるとぼんやりするものらしい。幸せボケなんて言葉があるが、それは私の事を指しているのかもしれない。 「コンビニ行くの?」 「……他にも買うもんあるし。」 心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。 偉人の残したこの非科学的な名言を、仮に信じてみる事としよう。ならば既に動き始めているこの運命は、軌道修正を繰り返す事でより私に都合のいい運命になっていくのかもしれない。 リョータの向けるその眼差しに自信を持った今の私の行動が変われば、全てが動き、そして運命を変えるのだから。 「酔ったかも。」 人目がない事を確認して、嘘を吐き出したその唇を重ねてみることにした。
ポラリスを食べた夜 |