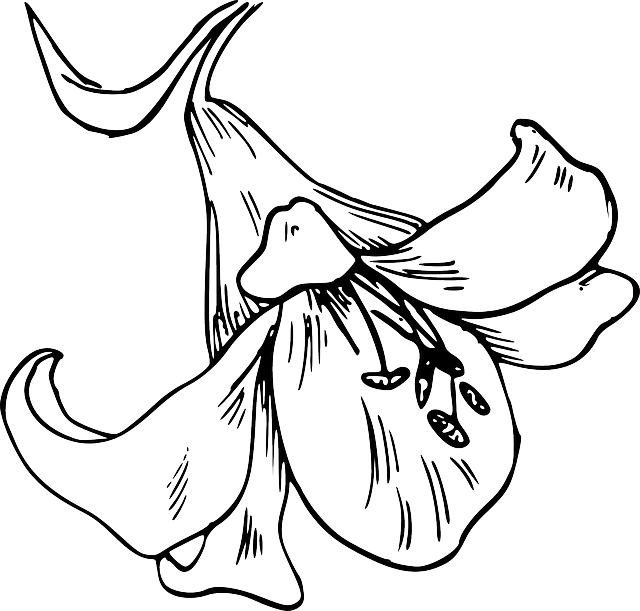  私は研修資料を刷りに席を立つ。二十部必要らしい。数十ページであればそれも時間のかからない単純作業だったが、生憎今回の資料はそれをも遥かにしのぐ枚数だったのだから暫くコピー機の前で紙が刷られる音を聞く羽目になった。面倒だなあと心の中で悪態をつきつつ、それくらいしか能がない私には仕方のないことだと言葉を口に出すことはない。 社内に複数コピー機はあるけれど、島毎に定められた所定のものがあるので、人が来るたびに一度中断をしてコピー機を譲り、それが終わればまた大量印刷に戻る。そんな繰り返しをしていたら、もう昼になっていた。 大量の紙と戦いながら、一つ一つホチキスでとめる。一つ終わるごとにお握りを一口かじり、また作業に戻る。そんなことをしている間に昼休みもあっという間に終わってしまうのだろうな、そうぼんやりと思っていた。 「何だよ。昼くらいちゃんと休んだらどうだ。」 「そういう原田さんだっていつもデスクでぱくぱくお握り食べてるじゃないですか。」 「俺がカフェスペースで弁当広げて律儀に一時間休んでたら気持ち悪いだろ、絶対。」 「確かに。それは気持ち悪いです。」 「だろ。俺は男だから別にこれが普通なだけだ。」 ふうん、と私は先輩に向けていた視線を再度大量の紙に戻し、お握りを一口かじる。面倒だなと思いつつも、思えば入社してから変わらないような毎日を過ごしているのもあってか慣れてしまった気もする。これが、私にとっての日常だ。 「あと何部だ?」 「とりあえず全部刷ったんであとは留めるだけです。あと十部くらいかな。」 「半分貸せよ。」 私のデスクに山のように詰まれたそれを見て彼は二つ置いてあったお握りをぺろりと平らげて、手を伸ばしてきた。大柄なせいもあってか、同じコンビにで入手した同じお握りも彼の前では驚くほどに小さいものに見えた。同じものを食しているとは思えない。 「いいですよ。私の仕事ですし原田さん研修で忙しいでしょ。」 「その研修で俺が使う資料をお前が作ってるんだろ。」 「あ、そっか。これ原田さんが使うんでしたね。忘れてました。」 「目の前の仕事を黙々とこなすのはいいが…お前もうちょっと考えて行動したらどうだ、。」 「いいじゃないですか。結果的には手に渡れば同じだし。細かいことは。」 「……たまに思うけど、って冷めてる所あるよな。」 「心を冷まさないと、やっていけない世の中が悪い。」 「おいおい。」 彼のように頭を使わないとできない仕事をしている訳ではないのだから、割り切ってやっている方が気持ちも楽だろうと思うから。 こんな彼との会話もごくごく日常の一部だ。隣にいる彼とは、仕事の関係上もあり会話をすることが多かった。 「いいから貸せよ。」 ごそっと私のデスクの山を乱雑に半分鷲づかみにして、自分のテーブルにどんと置いた。時折紙をめくる音と、私よりも大げさに音を立てたガッチャンガッチャンと響くホチキスを鳴らしながら。 「今回の研修、随分人数多いですね。一対二十なんて私なら無理だな。」 「文句も言ってられねえんだよ。大人は。」 「子供って言いたいんですね。私のこと。」 「にしては察しがいいな。」 少し私をからかうようにそういいながら、大きな表情で笑みを作る。彼が訳隔てなく皆に同じように接しているという事もあるけれど、皆から慕われている理由がよく分かるようなそんな彼のかんばせだ。まさに研修の担当者としては、満点に花丸までおまけできるほどに彼は適任だろう。私と違って、自分にしかできないと誇れる仕事だと思う。 「 「はい。頼んでないけどありがとうございました。」 「冷めてるを越して、捻くれてるな。」 「そんな。私からしたら最高の御礼の言葉なのに。」 「お前は言葉の勉強から再スタートしろ。」 私のデスクにあった十部を彼に渡すと、彼は急に周りをシャットアウトしたように集中して仕事に取り組み始める。いつ見てもすごい集中力だなと感心するほどに。 そんな状況が一時間ほど続いた頃。いったいこの人の集中力はいつまで持ち続けるのだろうか、と見習う姿勢も込めて時折見ていると急に目があってしまった。見ていたのはこちらの筈なのに、驚いたのも私のほうだった。 「何だよ。何事だ。」 「別に。」 「惚れたか。」 「原田さんは私の冷めた心を逆に勉強した方がいいですね。」 「お前がじろじろ見てくるからだろ。」 あきれたように少し笑いながら、彼は一息つくように置いてあった紙コップのコーヒーを口にした。 少し、昔のことを思い出す。私が入社した数年前のことだ。彼は営業だった。それもトップセールスの。違う畑にいる彼を、たまに通りがかりに見るくらいだった。今も変わりはないけれど、やっぱり何処にいても彼は人気者で、才能のある人だった。自分とは一番遠い存在と思っていた私は、実のところ彼があまり得意ではなかった。 「原田さん、なんで営業から移動してきたんですか。今更ですけど。」 「ほんと今更だな。何年前の話だよ。」 「私が入社した頃バリバリのトップセールスだったから。」 「求められてるうちが俺も会社にとって花だからな。移動しろって言われたからしたまでだ。」 移動しても尚、その才に長けているのだから本当にすごいと思う。きっとほかの部署に移動になったとしても彼は何処でも活躍できる才能を持ち合わせているのだろう。彼のようになりたいとは思わないけれど、凄いなと毎回改まってしまうほどには彼はすごい。 「何だよ。俺が営業に戻った方がいいと思ってんのか。」 「原田さんがそうしたいならそうすればいいけど。私に口出しする権利なんてないですし。」 可愛くねえの、そう言って再び彼はデスクへと向きなおしてパソコンと睨めっこを始める。私も同じように彼に向いていた椅子を回して前へ向き直る。黙々と仕事こなす。理由は、残業をしたくないからとかそんなちっぽけなものくらいだ。 「俺結構ここ気に入ってるからな。移動なんてしねえよ。」 「ふうん。」 お互い視線は交わさぬまま、ブルーライトを映し出す画面を見たままふいに会話を続けた。 仕事は着実に減っていく。残量が少なくなっていくのと平行して、終業の時刻が近づいてくる。ようやく長い一日が終わろうとしている。あともう少しで帰れる、そう思う事のできる終業時刻間際が私にとっては一番の幸せなのかもしれない。 ついに待ちに待ったその時を迎え、私はデスクを片付けていく。 「帰るのか。」 「はい。仕事、終わったので。」 「もう少し待てよ。」 追加の仕事でもあるのだろうか。不安を露骨に出してしまっていたのか、私を見て彼は苦い笑みを浮かべる。そうではないと、一言だけを付け加えて。 「飲みに行きたいと思う俺の気持ちくらい察して欲しいもんだ。」 「そういうのは永倉さんが適任だと思いますけど。」 「俺はを誘ってるんだよ。お前には恩を売っておかないといけないしな。」 「何言ってるんですか。まるで意味が分からない。」 ただ飲みたいというだけで私が付き合って、何が恩だ。強いて言うのであれば恩を売ってるのではなく、借りを作っているのではないだろうか。まったく持って意味を理解できなかった。 私が言葉の意味を考えている頃には、行動の早い彼がジャケットを肩にかけて帰る支度をしている。 「いいから。すべこべ言わずに行くぞ。」 人に対する気遣いのできる人であるのは間違いないけれど、強引な一面を持ち合わせている彼は先ほどまで帰ろうとしていた私を置いてさっさと進んでいく。彼が何を考え、何をしようとしているのか私には分からない。凡人には奇人の考える事など分からないのかもしれない。 「寒いしおでんか?いや、焼き鳥もいいな。どっちがいい。」 「恩を売る割には自分勝手ですね。」 「じゃあお前は何がいいんだよ。」 「え。何だろう。しいて言うならイタリアン?」 別に一緒に行くとは言っていなかったけれど、ふと聞かれて思わず考えて返事をしてしまった。そうすると彼はニカっと大きく笑って私より遥かに上から私を見ている。策にはまった私を見て笑うような、そんな気がしていた。 「女ってのは何かと言っちゃイタリアンだな。ってことはお前もしっかり女って事だ。」 「いや、そりゃ女ですけど。」 「俺には柄じゃねえが連れて行ってやるよ。」 彼が目の前に出てくるしゃれたイタリアンを食べているところが言葉のとおり柄でなく、想像すると違和感でしかない。いつもの彼であれば、押し通してでも焼き鳥屋かそこらへんの居酒屋に行こうと言うだろう。何かその真意に裏がある、そう思わざるを得ない。 「今日は奢ってやる。その恩は来週返してくれればそれでいい。」 この人は何を言っているのだろうか。暫くその意味を図りかねていたが、街に出た時にもしやと考える風景があった。日本という国はいつからこんなにイベントに乗っかるようになったのだろう。ほとほと呆れながらも、私も少し笑ってしまった。 「そんなに義理が欲しいですか。」 「馬鹿。本命の間違いだろ。」 「甘いものなんて大して好きでもないくせに。」 「まあな。」 そういって、彼は何処にあるかも分からないイタリアンを探してふらふらと街を歩き続ける。帰ろうと思えばそのまま帰れるけれど、私は自然とその背中を追って街を歩いていく。 毎日会社での仕事に心の中で悪態をついていた私も、思えば一度たりとも辞めようと思った事はない。行きたくないと思うことはあっても当たり前にいつだって会社に向かう。そんな当たり前の事に違いはないけれど、思い返してそうだったのかと思い当たることがあった。 何だかんだいいつつ、私の居場所を確保してくれるそこが、私が嫌いではないのだ。言葉とは裏腹に、心地よさを感じている自分自身に気づいた。彼の隣は、悪くない。 「やっぱ、焼き鳥にしねえか。」 彼なら、こう言うと思っていた。 私は先導するように目の前に見えた赤提灯の暖簾をあけて、店の中へと入っていった。 ( 2020'02'07 ) |