 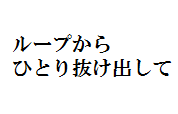 道端に捨てられていた猫を拾ったのは、いつかの、夏の日の事。拾い上げた子猫には、小さな外傷が見受けられた。特別猫に思い入れがある訳でもなく、捨て猫を拾うような、親切と分類される人間でもければ、その子猫を拾ったのは、本当に、ある意味で偶然であり、気まぐれでしかなかった。 彼女は、稀にやってくる気まぐれによって、子猫を小脇に抱え込み、いつかによく通った道へと足を進ませる。三十分ほど歩いた先に、年季の入った薄汚い白い建物。彼女は、ノックをすることもなく、ドアノブに手を伸ばした。十年ぶりに、きっと、目にするであろう、男の顔を想像しながら。 「ノックもしないで入って来るなんて、随分と礼儀知らずなお嬢さんだ。」 青葉の脳裏に描かれた人物と、目の前の男の姿が、見事違わず一致する。十年経ったところで、彼は、あの頃と何一つ変わってはいないようだった。すっかりおじさんになっていてもいい彼の歳にしては、幾分も彼は若く見える。気に食わないのを別にして、彼の本来持ちえる、ハンサムという言葉が、十年経った今尚、彼にそれを体現させているのだろう。 「女をとっかえひっかえしている先生は、昔の弟子の顔も忘れるんですか。」 「……弟子?俺が取った弟子は、一人しかいない筈なんだがな。ちなみに俺は女の患者しか見ない質だ。」 「残念ながらこの猫は雌ですよ。」 そう言えば、彼は一度困ったような顔をしたけれど、それ以上は何も言う事もなく、私の小脇に抱えられた猫を抱え上げた。診察台の上でブルリ、と震える子猫を見て、少し昔の出来事が脳裏をよぎった。かつて、同じように猫を拾い、自分自身の手で殺めてしまった事を。 「お前なら、こんな怪我くらい容易く治せるだろうによ。」 「生憎、私は、医者ではありませんから。」 ああ、あの人らしい、と青葉はふと思う。わざとらしく、自分の存在を懐かしむ様なそんな態度は、得意ではない。彼はよく青葉を知っていた。過去の師弟関係というものの大きさが、二人から窺い知れるようでもあった。 「…変わらないな。そういう所。」 「そういう所、とは?」 「言葉のまんまだ。いい意味にも、悪い意味にも、強情だってことだ。」 青葉は、足を止めて、立ちつくす。彼の目が、以前の青葉を、まるで宥めるかのように、優しく突き刺さる。青葉自身、分かってはいた。その性格が、何をするにしても、命取りになるという事を。 「…いや。そうだな、お前をそうしちまったのは、きっと俺なんだよな。」 青葉が医者を志した経緯に、大それた理由はなく、ただ単に世の中の役に立つだろうという、漠然とした善の意識でしかなかった。 十六歳の夏、青葉は街中で、様変わりした張り紙を目にする。『医学に関心のある女性、住み込みで急募』 青葉にとって、応募しない理由が見当たらなかった。張り紙に書かれた住所を辿り、三十分程歩いた先に、年季の入った薄汚い白い建物。青葉は、ノックをして、返事を待つ。けれど、返事はない。恐る恐る伸ばした手に、ドアノブがガチャリと音を立て、中へと青葉を誘う。 「おお!…いや、ノックもしないで入って来るなんて、随分と礼儀知らずなお嬢さんだ。」 一度青葉を見て、歓喜に声を上げたように見えたその男は、突然何を思い立ったのか、威厳を見せつけるような、先ほどよりも低い声で言い直す。その部屋からは、心なしか、親が以前飲んでいたバーボンと同じ香りが漂っていた。 色々と問題点は見受けられたが、それでも医者を志す青葉にとって、それはまたもない好条件に違いなかった。青葉は、少し躊躇いながらも、その男との共同生活をスタートさせた。それが、十六歳の、秋に差し掛かった頃のはなしだ。 医者を志し、この男 シャマルの元で青葉が共同生活を初めて、一年が経った頃、青葉は医学にどっぷりと浸かりこんだ生活をしていた。軽い気持ちで志した医学に、青葉は魅了されていたのだ。その教えの親であるシャマルが、“天才”と称される医者である事を青葉が知ったのは、出会った後の事であった。 シャマルと青葉の奇妙な共同生活のさ中で、彼女は買い物帰りに負傷した子猫を見つけた。子猫を可哀想に思う気持ちと、相反し、これくらいの事であれば自分の腕を試す事が出来るのではないだろうか。そんな、自尊心だけが独り歩きを始めた。結果、青葉はその子猫を自らの手で殺めてしまったのだ。助かる筈であったその命を、一つ、その手が奪い去ってしまった。 「…なんの事を言ってるのか分かりませんが。そもそも私は頑固である自分に、誇りを持っていますので。」 「だからそういう所が強情だっていうんだよ。頑固と強情は、似ているようで、少し違う。」 そこで、青葉の医学者への道は、途絶えた。医学を深く知れば知るほど、傷つく事に気づいたからだった。そして、深く知れば知るほどに、彼の体には、見えない無数の傷があり、それを自力で乗り越えているのだと、到底敵いっこない程の強さを知ってしまったからだった。 医学への諦めは、ついていた。元々、医学を志した理由も大したものではなかったからなのかもしれない。けれど、一つ、それとは他に、青葉の中には、諦められないものが存在していた。日に日に膨れ上がっていく、それを、胸に抱いて。 「なんだって、お前、そんな面で殺し屋なんかやってんだよ。」 「ヒットマンに顔は関係ないでしょうに。そもそも、この顔がヒットマンらしくないというのであれば、敵を油断させるという武器にもなる。寧ろ、この顔に感謝しなきゃいけないくらいね。」 「綺麗な顔に生んでくれたってのに。聞いて、親が泣くぜ。」 「ヒットマンに親なんて、もう、居ないも同然です。」 相手を間違っている事など、百も承知だった。寧ろ、自分を彼女自身が疑ったほどに、感情には疑問しか残らない。青葉が彼に抱いていた感情は、尊敬であって、親しみであって、そして、尊敬や親しみ以上の、ある一定のラインを越えた感情だった。人はそれを、恋、と呼ぶらしい。 己の感情に気づいた頃、それが、叶わないものであると認識した青葉は、如何にしてシャマルとの共同生活を終わらせるかという事ばかりを考えるようになる。まだ十代であった青葉にとって、当時のシャマルはあまりに大人で、そして大きかった。思いを告げる所か、努力することすらしようとはせず、ただ感情から逃れるようにして、青葉はついにシャマルとの生活空間から飛び出した。シャマルの元で学んだという事で、マフィアからのオファーを受けたのだ。そして、今、十年という月日が過ぎ去り、青葉はシャマルの前にいた。十年という長い月日の中で、きっと自分は何かしらの変化を遂げただろう。けれど、シャマルは何も変わらない。何一つ、変わってはいない。それが、嬉しくもあって、でも、複雑で、なんともいえない、妙な心境を青葉に抱かせた。 「先生は、最近どうですか?ところでそのお酒、美味しい?」 「お前に酒の話をされるなんて、なんか調子狂うな。一緒に居た時はお前、未成年のガキんちょだったからなあ。」 「何年前の話をしているの?もう私、立派な大人です、先生。」 青葉がそう言えば、思い出したようにシャマルの手が、ボトルへと伸びていく。嗚呼、やっぱりこの人は、変わらない。何もかもが変わらず、時が止まっているようだった。ただそこに、かつての自分自身がいないだけで、それ以外は全て シャマルが、こちらを向く。手持無沙汰だったのか、「お前も飲むか?」なんて、答えの分かり切った問いかけを投げつける。もちろん青葉が首を振って拒絶すると、彼は「やっぱりな。お前もそういう些細な所は変わってなくて、正直ホっとする。」なんて、いかにも彼らしくない言葉を吐きだした。女を落とす、口説き文句には、幾分も弱弱しい。かつての彼の口説き文句とは、比べる対象にすらなり得ない。 「なあ、青葉。先生なんて堅い呼び方、いい加減やめろよ。お前、俺が何度も何度も何度も何度も「先生」って呼べって言ったところで呼ばなかったくせに、今更、当てつけのつもりか?」 酒が入ったからなのか、それとも元々彼の口がお喋りであったのか、はたまたその両方であったのか、彼の長い台詞が青葉の耳を滑る。「じゃあ、」そう言って、青葉は続ける。彼との共同生活をしていた頃に、戻ったかのような、あの時のままの、ありのままの自分で。 「…シャマル。貴方には“天才”を謳うだけの才能と実績がある。事実、私はシャマルの事、誰よりも尊敬していた。私にはシャマルの言う事為す事、それが全てで、それが私の中での真実だった。けれど、シャマル。貴方は一つだけ、嘘をついているの。」 青葉も、突然口を滑らせたように、言葉を紡ぎだす。しっかりと、その先に、シャマルを見据えながら。 「言って、みろよ。」 十六歳になった、あの夏。張り紙の結句には、こう、記されていた。『どんな病も治せる医者、シャマル』と。半信半疑のままシャマルとの共同生活をスタートさせ、そしてその言葉の意味を理解するまで、そう時間は要さなかった。彼は本当に天才を謳うだけの、実力も、実績も、全てを持っていた。彼は万能医であり、そして、治せない病はないのだと。 「俺がいつ、お前に嘘をついた?俺はいつだって、お前には真実だけを教えてきたはずだ。」 シャマルの言う事、そして、教えてくれる事、それはどの教科書に載っているものよりも正しかった。シャマル自身が、教科書のようであって、教科書以上の、何にも叶わない唯一無二の存在だった。それはきっと、昔だけでなく、今も尚。 けれど、彼は確実に嘘をついたのである。青葉がその嘘に気づいたのは、彼との共同生活を終えようとする、ほんの少し前の事。シャマルには治せないものがある。確実に、一つ。 「私がここを出た本当の理由、それは、シャマルが私の病を治せなかったから。」 焦らす様に、そう言えば、彼の大きな手のひらが、青葉を引き寄せる。バーボンの独特な甘い香りが、抱擁の行為以上に眩暈を引き起こしているのだろう。約十年ぶりのシャマルの懐があまりに暖かくて、そして、最後に抱きしめてくれたあの頃と何も変わらず、歓迎でもしてくれているかのように優しくて、思わず、縋りたくなる。 「馬鹿か、お前。俺がお前の考えてる事くらい、見抜けなかったとでも思うか?」 ふわりと、シャマルの唇が落ち、暖を生む。ねっとりと絡んだ舌に、まとわりついたバーボンの味に、酔いしれる。「大人になったお前にしか分からん味だ。」息継ぎを与えるだけのその台詞の後に、再び舌が放り込まれた。 「これでまた、俺は完璧な医者になる。お前の病も、治したんだからな。」 果たしてこれが正式な治療法なのであろうか、少し手荒過ぎるような気もしたが、青葉は何も言わずに、それに従う事を決めた。多少手荒な方が、治りが早い。それは昔からシャマルの口癖だった。 いつの日か、たとえば、原因不明な胸の痛みを訴える患者が尋ねてくれば、間違いなく彼らは言うのだろう。「恋は病である。」と。 ( 20110727 ) |