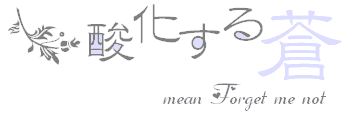どうしても言い出せないことがあった。それを口にしたらきっと終焉がやってきてしまうから。今から一ヶ月以上も前に決まった事、それが前日と迫っていてもまだ跡部に告げることができないでいた。今までの跡部との時間がそれを告げることによって無くなってしまうと思うとどうしても告げることが出来なかった。でも、どうしてばれてしまったのだろうか。跡部が息を切らしながら校門まで走ってきたかと思うと急に怒鳴り始めた。跡部にしては珍しい言動の数々に青葉も驚きを隠せない。そんな跡部の右手には小さな花が押し花のように乗っていて、彼はそれを見ると更に眉間に皺を寄せて今にも泣きそうなくらいに切なく目を瞑った。 青葉にはその小さな花に見覚えがあった。  それはほんの三日前に起こった最近の出来事だった。 形式上付き合っている、という肩書きがあっても青葉と跡部の関係は曖昧なところをさ迷っていた。恋人でいた時間よりもマネージャーとしての時間の方が長かったから。好きなことには違いなかったが、それは普通の恋人達とは少し違っていた。恋人というよりそれはどちらかというと友情に似ていた。 「いいじゃないたまには。今日練習ないんでしょ」 「することに何の意味がある」 「べつに何もないけどたまには恋人気分もいいかなって」 「事実恋人なんだ。気分なんざ必要ねえだろ」 「とても恋人とは思えないからせめて気分だけでも」 「・・・何が言いたいんだ」 「取り合えずデートしてくれたらいいんだって」 もしかすると初めて跡部に我侭を言ったのかもしれない。すると跡部は声に出して了承はしてくれなかったけれど、車に乗らずに先々と歩き始めた。ぶっきら棒だけどその分とても優しい人。そんな事は付き合う前から知っていた。元々が近すぎたのだ。付き合う前から近すぎた。付き合う前から付き合っているようなそんな錯覚をしてしまうくらいに、今と昔の関係は全くとして変わらなかった。でもそれに不満は感じなかった。変化がなくても跡部の傍に居れること、それだけで十二分に満足が出来るのだから。だからこそ最後に変化を求めたのかもしれない。何か一つ形に残しておきたいってそう思ったから。不審そうにこちらを見てくる跡部に青葉は微笑み返してとある場所に連れてきた。青葉が幼い頃に遊んだという緑溢れる公園だった。 「東京にもこんな場所があるんだな」 珍しい光景に跡部も満更でもなさそうだった。少し嬉しい。跡部の表情がいつもより緩んでいるように見えたから。温室育ちでろくに子ども遊びも知らないであろう跡部に色んな遊びを教えた。それは青葉自身でさえも懐かしくなるような出来事だった。遊び疲れるほどに、本当に遊んだ。 「ねえ跡部」 夕焼けが沈み始めた頃、青葉はやっと足を止めて立ち止まった。 「あたしといると楽しい?」 「随分と唐突な質問だな」 「いいから答えてよ」 「・・・まあ悪くはないんじゃねえのか」 「あたしも跡部といて悪くはないよ」 「言い方を改めやがれ」 「跡部が言い始めたんじゃん」 そう言うと跡部は 「うるせえ」 とだけ言って後ろを向いてしまった。本当はそれも狙いのうちの一つだった。 懸命に咲いている蒼くて小さな花を足元に見た。昔からよく知っている花だった。今まではその花の意味なんてよく理解できなかったし、自分とは関係のないことだからと何とも思ってはいなかったが今になってその花が自分の心情を表してくれているような気がした。別に花を摘む趣味なんてない。そんな柄でもなければ女らしい自分でもなかったから。でもこの花を跡部に渡す事で何かが変わるんじゃないか、いや変わればいいな、そう思って蒼くて小さなその花を一輪摘み上げて掌に収めた。 甘えるのは昔から苦手だった。花を摘むような女の子らしくもなければ自分から抱きついてキスをせがむ様な女でもなかった。しかし今それが出来てしまったのはこの蒼くて小さな花のおかげなのだろうか。青葉は逞しくて大きい跡部の背中に後ろから抱きついた。未だ嘗てしたことのない、小さな甘えだった。 「ねえ跡部、あのさ、」 手に持っていた一輪の花をぎゅっと握り締めた。 「キスして」 自分なりに本気だった。その証拠に握り締めていた花が平たくなっている。跡部と知り合ってから初めての甘えだった。だからきっと跡部もその本気を何かしらの形で理解してくれると思っていた。振り返って、手を引いて、強引に唇を奪ってくれると思っていた。しかしそれはただの希望であってそこから先の進展は、何も、なかった。 「何柄でもねえこと言ってんだ」 「・・・跡部、あたしね」 「たまには面白い事言うじゃねえか」 「・・・・・・・・・・・・・」 驚くどころか笑われてしまった。見たこともない青葉の甘えに跡部はくすりと笑って彼女の髪をさらりと撫でた。こういった事態を想定していなかった訳ではなかったがやはり言葉が出てこない。すると跡部は不思議そうに顔を覗きこんで来たから、その時にはいつもの顔に戻っていた。 「やっぱり冗談だってばれちゃった?」 強がる事しか出来ない自分に出来ること、それはたった一つだけだった。 青葉は手に握った蒼くて小さな一輪の花を跡部には見つからないように彼のポケットに滑り込ませた。  そして話は三日前から冒頭へと戻るのだ。 今日で最後のこの学校、思えば幼稚舎からの付き合いになるから随分と長い間を過ごしたのだなと思う。友達との、テニス部との、そして何より跡部との思い出の詰まったこの宿舎を中々出る事が出来ないでいた。日も暮れて夕暮れも終わり闇が照らされても青葉はその場を動く事が出来なかった。辺りには誰もない。職員室の明かりもなければ生徒だってもちろん人っ子一人見当たらない。青葉は校門の前にどっしりと腰を降ろしている大きな木の下で想いに耽っていた。転校する、両親にそう告げられたときに無力な自分を呪った。権力も財力も何も持ち合わせていない自分は親の申し出に反発する事なんてできるはずもなかったから。でもどうしても跡部には言えなかったのだ。告げた瞬間に別れも告げられるような気がしていたからだ。だから何も言わなければ最後まで跡部の彼女でいられると思った。 頭上にポツリと雫が降り注ぐ。天気までもが最後の余韻を邪魔する。とことんついていない。時計を見るともう随分といい時間で青葉が立ち上がった、丁度その時だった。 「青葉」 取り乱したように息を上げて荒々しく名を呼ぶのは跡部だった。青葉と呼ばれることなんて滅多になかったから一瞬誰だか分からなかった。しかし何故ここに跡部がいるのだろうか、そんな事よりも驚いたのは見たこともないような跡部の姿だった。雨に降られて濡れた体も、取り乱した息も、怒鳴りにも近い声も、全部跡部らしくなかったから。初めてみる跡部の姿だった。何もかもが跡部らしくなかった。 「これは一体何のつもりだ」 跡部の手に持たれている一輪の花、青葉にはその花に見覚えがあった。元々生命力の弱そうなその小さな花はしゅんと萎れて色もくすんで見えた。 「・・・ばれちゃったんだ、ね」 「だから何のつもりかと聞いてるんだ」 「だって忘れて欲しくなかったから」 「・・・青葉」 距離を保ったまま二人して雨に濡れた。きっと跡部は全てを知ってしまったのだと知った。だってこんな跡部の姿、普通じゃ考えられない。今にも泣いてしまいそう程に切ない顔をしている跡部なんて知らなかったから。テニスをしている時でさえもそんな跡部を見たことがなかった。だから少し嬉しかった。自分の事でこんなにも必死になってくれている跡部の姿が、目に焼きついて離れない。本当は今すぐ喚き泣いて抱きついて弱音を吐きたかったけれど、それをしたら今度こそ離れられなくなりそうで青葉は歩み出そうと進めた右足を引っ込めた。 (本当に好きだったんだよ跡部) それを声に出していう事は所詮弱虫な自分には出来ないけれどせめて心の中で叫ぶくらいは許されるだろう。青葉は心の奥底に本当の気持ちを飲み込んでそのまま雨に打たれた。 「こんな花なんてなくてもお前を忘れろということの方が難しいだろ」 「・・・跡部」 「お前を忘れることなんて出来るはずもねえだろ」 跡部は制服のポケットから取り出した勿忘草を取り出してまた瞳を揺らした。するとカツカツと靴を鳴らしてこちらに向かってくる跡部は走り出して目の前に現れた。息を上げて声も荒げてバカと叫ぶ跡部は握り締めていた勿忘草を投げ捨てて急に体を引き寄せてキスをした。 「こうすればお前は行かないのか?」 「それは無理だよ」 「なら何故あの時キスをせがんだんだ。あの時こうしていればお前はまだ俺の隣にいたのか」 「分からない、分からないよ!でも確証が欲しかったの!跡部があたしのことを好きでいてくれたっていう、確証を持ちたかったの」 「・・・そんな確証さえ持てなかったのかよ」 「こんな花なんかなくても、俺は 青葉は何かを告げようとしていた跡部の唇を奪ってその言葉を塞ぎこんだ。雨に打たれて濡れた互いの体に熱を取り戻すかのように抱きしめあってキスをした。今までにしたこともないまるでドラマのようなキスだった。何もかもを忘れて、鞄も放り投げて触れ合うだけに時間を費やすような、それは本当に燃えるようなキスで燃えるような恋愛だった。果たしてこれが望んだ結果だったのだろうか。 何かの形が欲しかった。 沢田青葉という存在を記憶に留めていて欲しかった。 この勿忘草は覚えていてくれるのだろうか。
|