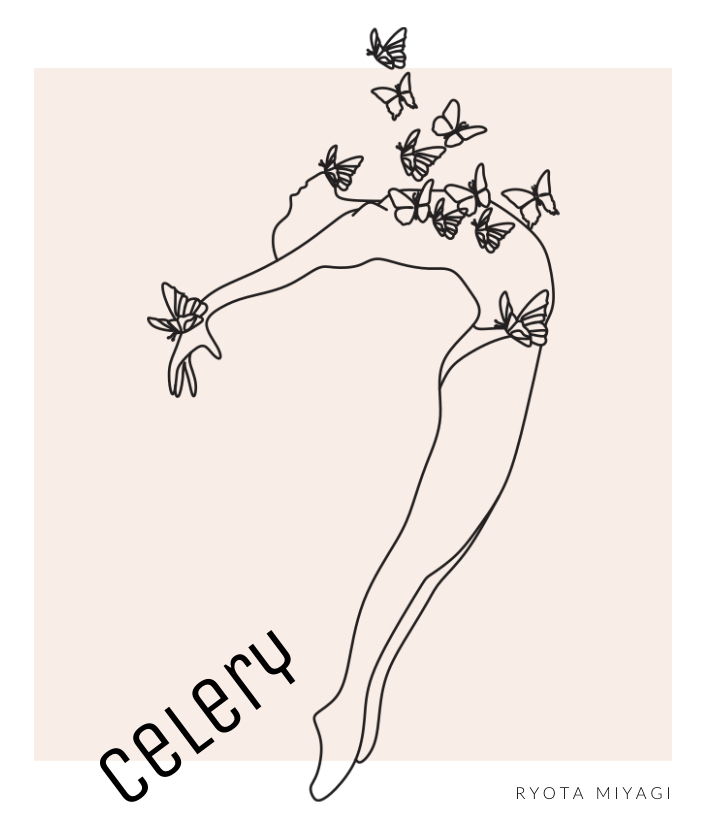 育ってきた環境が違うから………ふいにそんな歌詞が頭の中を掠めていく。昔に流行った曲らしい。なんとなく知ってはいるけど、その有名なワンフレーズしか私の耳は知らないのでその先の結末は私の知らない物語だ。 リョータと一緒に住むようになってようやく一ヶ月が経つらしい。 付き合ってからはもう数年以上が経過しているのに、“恋人”である事と“生活を共にする”という事はまるで違う事象であると知らしめられる。正直な話もう知らないところなんてないと思っていたのかもしれない。 「ほんと吃驚しちゃうよ。」 「なにが?」 「だって右太ももの付け根にホクロあるのも知ってるくらいだよ?」 「……いやそれ俺も知らね〜し、そもそもその発言自体に俺が吃驚じゃね?」 よく主語がなくて何の話をしているのか分からないと言われるけど、私の頭の中では無事成立しているので特別問題はない。属性と性分が生粋のツッコミであろう彼から一度的確なツッコミが返ってくるけれど、それでも大体のニュアンスで話を理解してくれる。 つまりそれは私との付き合いの長さを示している訳で、私たちにまだお互いに知らない事があるなんて一緒に住むまで思ってもみなかった。 一緒に買い物に行ってもそれは如実に出る。 買い物籠には私がよく調理方法を知らない緑色のごつごつした野菜が入っていた。沖縄出身のアピールでもしているのか?一度チラリと彼を見ても逆にそんな視線に怪訝な顔をされたのは私の方だ。 それはアピールでも何でもなくて、彼の家ではごく当たり前に食卓に並んでいたのだろう。育ってきた環境が違うと好き嫌いとかそういうもの以前に文化が違うものらしい。自分のアタリマエが改めて世間のアタリマエではないのだと気付かされる。 籠に入れてくるものだからそのまま購入はしたものの、今もゴーヤは冷蔵庫に眠っている。籠には入れても調理はできないらしい。ツッコミそうになったけれど、それは彼の役割なのでグッと押し込めた。 「なに作んの〜?」 「焼きそば。」 「……この材料で?」 「そうだけど、え……逆に間違ってる?」 まさか冷蔵庫で寝かせている(あえてそう表現している)ゴーヤを入れるのが宮城家では正解なんだろうか。というか普通にパッケージに書いてある材料をそのまま用意してまな板の上に並べた筈だが……眼科の受診は必要だろうか。 「スパムとか。」 「スパム……か、そう来たか。」 「え、入れない?ふつう。」 「どうだろうね?少なくともうちの地元ではふつ〜ではない。」 ソース焼きそばという名のついたものがある事自体は知っている様子だったけど、宮城家の焼きそばの正解を聞いてみるとどうやら塩焼きそばをベースに野菜とスパムが入っているらしい。取り敢えずゴーヤは入っていないようで、よく分からない安堵感に息をつく。 「そしたら宮城家の焼きそばとは違うかもね?」 土曜の昼過ぎまで寝ていた私は部屋着のまま台所に立つ。 寝込んでいた時間の分だけ吸収された私の匂いを吸い込むようにリョータの顔が肩先に埋もれていく。これは私のよく知っているリョータの癖だ。止まり木を見つけた小鳥のような、そんな馴染みのある姿。 馴染みのある一面を見ると、何故だか私まで落ち着く気がする。 「なら家の焼きそば食べる。」 「家の焼きそば普通の焼きそばだけど。」 「俺ん家のも普通だけど普通じゃねえならわかんないじゃん。」 「いやいやそれはないでしょ。」 少なくともスパムに馴染みのない私にはかなりイレギュラーな焼きそばで、どう頭を捻って知恵を絞り出したところでまず出てはこない創作レシピだ。多分そのインパクトを超える感動は私の焼きそばにはないだろうと思う。何故ならパッケージ通りに炒めて蒸して粉末をかけて終わりだからだ。 もやし、人参、キャベツ、玉ねぎを炒める。焼きそばの具材が袋詰めになって販売されているので日本はとても親切な国だ。あとは百グラム二百五十六円の広告の品で買いだめをして冷凍していた豚肉をフライパンに放り込めば大体完成だ。 水をぴろっと入れて適当に粉を振ればそこそこの焼きそばが完成する。逆にこんな適当な調理法で美味しくなるんだから世の中はどうかしている。 「はい、できた。」 「紅生姜は?」 「私はつけない派、リョータのに乗せよっか?」 「じゃあ俺もいらない。」 「あ、そう?」 不揃いな二つの食器を取り出して、白くて面積の大きい皿の方には少し多めに盛り付ける。一人暮らしをしていた私の家具をそのまま持ってきた我が家はまだ二人暮らしの仕様になっていなくて、色々と不揃いだ。 元々持っていた自分の家具家電だからか私はあまり気にならなかったし、一緒に住むにあたって初期費用は抑えたかったので新しく買おうと言うリョータを説得してほとんど見慣れたものがこの家の中には溢れている。 それに耐えかねたのか、同棲して二日目の夜にリョータが小さい箱を二つ持って帰ってきた。促されて箱を開いてみると、色違いのお揃いのマグカップが入っている。そこからは麦茶を飲む時も、夜寝る前に晩酌をする時も全て無条件でこのマグカップが使われる。もちろんリョータの仕業だ。 「青のりもかけないの?」 「あ、うん。あるけどかける?」 緩やかに首を横に振るリョータは、家の味をそこまでして味わおうとしているのだろうか。全国的な標準な味にしかなっていない筈なのでなんだかこちらがプレッシャーを感じてしまう。 「焼きそばと言えばトッピングはこれだけだから。」 「……たまご?」 「そう、生卵。」 「え、生でかけるの?」 「うん。」 全国的に標準な焼きそばだと思っていたけど、生卵をかけるのすら驚かれるので何が標準でどこからが家独特なのか分からなくなる。けれど確かに上京してから外で焼きそばを見かけても生卵が乗っているのは見たことがない。衛生的な意味合いでついてないだけだと思っていたけどそれは特殊なんだろうか。 「うちの地域ではみんな生卵かけてたけどなあ。」 「マジで?超初耳。」 「土曜の昼は焼きそばかたこ焼きじゃないの?」 「……それも初耳。」 沖縄は本土じゃない分やっぱりかなり独自な文化を持っているのかもしれない。土曜日の昼と言えば食卓にたこ焼き器が置かれていてくるくる回すか、焼きそばが出てきたのが記憶に強い。ソース文化だ。全国決まって土曜日の母親はなるべく労力を使わない料理をしたがる、そんな私のアタリマエ。 私は首を傾げながら卵をテーブルの角でこんこんしながら、漏れ出ないように慌てて皿の上に盛られた焼きそばに乗せる。乗せた後はぐしゃっと、あまり品がないと自覚しながらもかき混ぜていく。 「……十分俺の常識を超えた焼きそばだ。」 「そう?おいしいよ。」 馴染みのない焼きそばと、その風貌にリョータはゴクりと唾を飲み込みながらこちらを見ている……私からしたらスパムの入った塩焼きそばの方が結構衝撃的ではあったのだけれど。 「ちなみに……おいしいシュウマイと言えば?」 「なに急に。」 「いいから教えてよ。」 「は〜?じゃあ崎陽軒。」 確かに有名だし、美味しい。そこは沖縄独自のものじゃなくて、ちゃんと神奈川の文化を引き継いでいるのか。リョータのアタリマエは少しだけ難しい。 「じゃあ豚まんの定番は?」 「豚まん?肉まんならあのコンビニのかな。」 そうか。そもそも豚まんという呼び名ではないのか。肉まんという単語も知っているけれど、私にとっては豚まんの方が馴染みがあるのでそこも違うらしい。上京して結構経つけど改めて文化の違いを感じる。 「……アイスキャンデーと言えば?」 「ガリガリくん?」 「なら土曜お昼のテレビはズバり?」 「…ブランチ?」 多分焼きそば以外の部分で言えばリョータの回答の方がよっぽど標準に寄っているのだろうと、理解自体はできる。やっぱり私のアタリマエとリョータのアタリマエは違っていて、そしてそれぞれのアタリマエがこの世界には無限に存在しているのだろうと思った。 「そっか……ちなみに生卵かけてみる?」 食卓に二つ持ってきていた卵を手に持ってみると、異世界のものを見るような目をしたリョータがやっぱりもう一度生唾を飲み込むようにして間を置いてから頷いた……そんな一大決心なんだ。 「別にそのまま食べてもいいし。」 「……食べてみたい。」 「じゃあ、はい。」 少し冷えた卵を手渡すと、慎重になりながらこんこんとテーブルの角に卵を叩きつけるリョータを見ながら、少しだけドキドキする。自分のアタリマエが世間のアタリマエではなかったこともあるけど、それが彼に受け入れられるのかどうか。 「いただきます。」 私の真似をするように卵に箸を入れてかき混ぜて、少し間を置いてから麺を啜る。ラーメンを食べる時はもっと勢いよく食べるのに、何かを吟味するように恐る恐るゆっくりと中太な麺が吸い上げられていく。 「えっ………」 「ごめん、口に合わなかった?」 「めちゃ美味い………」 黄身が絶妙に絡みつくソースのかかった麺と、普段は苦手な白身もすき焼きの時と焼きそばの時だけは絶妙な味を出すところも私が焼きそばが好きな理由な訳だけど、それを含めたこの感想なのだろうか。 受け入れられるかどうかを気にしていた筈なのに、それは簡単に喜びへと変わる。私の好きが、アタリマエが、リョータに伝わっていると思うとなんとも不思議でふわふわとした気持ちだ。 「美味い!」 「家の焼きそばお口に合いましたか。」 「これがアタリマエになるくらには。」 「家の母が喜ぶ科白だね?」 「ほんと、目から鱗。」 全く違う土地で育って、違う文化を育んできた私たちはお互いのアタリマエを共有していく。恋人になっても知ることの出来なかったそれは、“生活を共にする”事でしか感じ得ないただの贅沢なのではないだろうか。 焼きそばひとつでこんな気持ちになるとは誰も思わない。 けれど一番重要なのは、自分のアタリマエではなく私のアタリマエを知ろうとしてくれているリョータ自身でしかない。そんな彼のチャレンジと大冒険がなければ、この瞬間的な幸せは存在し得なかったのだから。 つまりそれは結局、私が彼に惚れているという何よりの証明だ。 知らないおじさんに同じことを言われても嬉しくはないし、友人に共感されたところで「そうなんだ?」の一言で終了だ。ただ唯一、その意味を持つ人間だから。 「スパム入りの塩焼きそば食べたくなった。」 「は?こんな美味しい焼きそばあんのに?」 「それぞれの良さがあるからまた別物かもじゃん。」 「なんだよ、急に。」 想定していない野菜が籠に入っても確認することなくレジに通してしまう私も、結局はリョータと同じ気持ちなのかもしれないとそう思って。壮大な勘違いと自惚れなのかもしれないけれど。けれど、確実な幸せを拾い上げて。 「リョータが好きなものは私も知りたいし好きになりたい。」 考えてみればとても恥ずかしい言葉なのかもしれない。けれど、不意に無意識で出てきた言葉でもあった。それが私自身の本音でしかないからだ。新しい発見は、時に幸せを運んで来るのかもしれない。 「はい、反則。」 「は?」 「自覚ないならもっと反則だしペナルティ。」 「え〜?」 どんなペナルティがあるのかと構えていれば、「あとでね」そう言われて、もっとずるい。そんなの考えてしまうに決まっているのに。そんな私を分かっているだろうから、それこそ反則だし、重大なペナルティをつけないといけない事案だ。 育ってきた環境も文化も、持っているアタリマエも違うのに、好きという感情ひとつでアタリマエを共有できるこの世界を私は今まで知らなかった。長くリョータと付き合ってきたのに、また新しい幸せを履修するわけだ。 「美味しい焼きそば食べた後にね?」 その言葉に、血が巡る音が耳に劈いた。 そろそろ地元の豚まんが恋しい。 近いうちに私の大好きなアタリマエを彼のアタリマエにするべく、地元に連れて行こうと思う。好きなものがどんどん増えていく世界は、とても私だけに都合がよくできているらしい。 ずっと言えずにいたことを、本当は彼が籠に入れた未だ冷蔵庫に寝かせているゴーヤのことも、今はそれを少し食べてみたいと思っている、そんなことも。 あの曲の続きを、少しだけ聞いてみたくなった。
celery -セロリ- / 2023'06'08 |