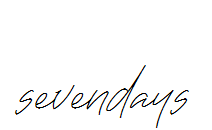  人は私のことをこう呼ぶ。無頓着な女と。それが何を意味して、指しているのかは私には分からない。それが物欲に対してなのか、人に対してなのか、それともその全てに対してなのか。 「なあ。」 「なに。」 「何考えてんだ。」 何を考えているのか。そう言われて一体私は今何を考えていたのか、ようやくその事について考え始める。考え始めたところで何も考えてなど居なかったのだから何も答えは出てこない。もしかすると、皆が言う無頓着というのはこういう事を指しているのかもしれないと思った。 「今何考えてたのか考えたけど何も考えてなかったみたい。」 「何だよそれ。お前今の状況分かってんのか。」 今の状況も然程意識していなかったので、辺りを見渡してなんとなく掴み取る。 今日は土曜日だ。会社も休み。金曜日という事もあってお酒を買って彼の家で飲んでそのまま寝て、起きたのが今の現状だ。まだ眠気眼な私に彼がくれた程よく冷ましてくれたホットコーヒーを飲んで一息ついていた所。何てことのない、ただの土曜日だ。 「コーヒー飲んでるね。今。」 「そうじゃねえだろ。」 コーヒーを飲んでいる事以外に一体何があるというのだろうか。思い当たる節がない。それとも私には見えない何かが知らないところで何かをしているとでも言うのだろうか。そんな心霊現象は勘弁蒙りたい。 「何でそんなに連れねえんだよお前は。」 「どういう意味。」 「普通こんな格好してればそういう雰囲気にもなるだろうが。」 「ああ、そっか。」 あまりにも自然すぎて、逆に意識することを忘れてしまっていた。息をすることに対して意識をしないのと同じように、彼に後ろから抱きしめられるのもそれに限りなく近かった。 「照れるとか、喜ぶとか、そういう感情ないのかよ。」 「…それって呆れてるって事?」 「いや。この俺にそんな事できるお前をちょっと尊敬してる。」 「うそばっか。」 私のそっけない返事に、彼は少しムキになったように私を抱きとめる腕に力を増しているようだった。会社では絶対に見ることの出来ない、彼の子供っぽい一面だ。彼と付き合うまでは、私も知らなかった一面。 私たちは白い皮製の大きなL字ソファに座りながらも、そのスペースの四分の一ほどしか活用できていない。それは私の後ろには彼がいて、彼の前にはすっぽりと私がはまり込んでいるからだ。 「俺がこうしたいと思ってるからってのはあるが、普通こういうの嬉しいんじゃないか女って。」 「やっぱり今までの彼女とかは、喜んでた?」 「……お前、昔の女の話聞いてくるなんてデリカシーないな。」 「なんでよ。別に、意見として聞きたいと思って。」 「お前に嫉妬って感情はねえのかよ。」 言葉の意味は分かりつつも、それに該当する気持ちを患ったことはないのかもしれない。私が無頓着と言われる所以そのものなのだろう。学生時代から友人の色恋沙汰を聞いてああでもないこうでもないと、時に笑ったり泣いたり情緒が不安定で大変だなと一歩外からそんな彼女たちを見ていたと思い出した。 「例えば、嫉妬ってどういう時に起きるの?」 「そうだな。よくあるパターンだと、他の異性と喋ってるとかそんなんか?」 「ああ、あのよくドラマとか少女漫画であるやつ。」 「あ〜、そうそうそれだ。」 私も彼も一度目を瞑って、そんな光景を瞼の裏に映し出してみる。けれど、特に先ほど聞いたような感情が私に挑んでくることはない。いつだって会社で見ているその光景と、何ら変わりがないからなのかもしれない。 もしこれが、彼が同じ会社の人間ではなければ私も世の女が患う嫉妬という感情に飲み込まれるのだろうか。やきもきして、どうしようもない不安と苛立ちに襲われるだろうか。 「やっぱ分かんないかも。」 「そういう俺も想像したはいいが特に、って感じだな。いつも会社で見てる光景だし。」 限りなく近い感想を述べた彼に私は少しほっとしていた。そもそも論、彼がそんな事でいちいち嫉妬に狂っていたら私はおちおち会社で仕事も出来ない。ましてや、そんな彼だったら今一緒に此処にいる事もないのだろうけれど。 「一々そんなんで嫉妬してたら身が持たねえ。」 「うん。嫉妬体質でなくてよかったかも。なんかしんどそう。」 私たちのこの光景もかなり滑稽なものだろう。後ろから抱きしめられて特に喜ぶでもなく照れるでもなくマイペースにコーヒーをすすっている私と左之は、ムードも何もない会話を交わしているのだから。なんだかよく分からない構図だ。世の中こんなカップルいるんだろうかとそんな事を思った。変なカップルにさせてしまっているのであれば、それは間違いなく私のせいだろうけれど。 よく分からない光景だけれども、私にはこれが一番しっくりくるのだ。当たり前のように傍に彼がいて、他愛もない話をして、一緒に昼寝して、たまにちょっとじゃれて。穏やかな休日だ。 「お前も飲むか、おかわり。」 「あ、うん。飲もうかな。」 私の空になりかけたマグカップを見て彼はようやく私から離れた。自分のマグカップなんてもうとっくに空っぽになっていたのに、きっと私が飲み終えるのを待っていたのだろう。何て出来た彼氏なのだろうかと自分の事ながらに思う。 彼がいなくなって、急に冷たい風が吹き込んできたように寒気を感じた。男の人は暖かいんだな、そんな暢気な事を思った。 キッチンから戻ってきた彼は私にマグカップを差し出す。湯気があまり出ていない方のマグカップを私のほうへ、そして湯気がいきり立っているのは彼の手元に置かれる。気遣いも完璧だ。 「左之あついよ、これ。」 「犬猫じゃあるまいし。どんだけ猫舌なんだよ。」 貸してみろと彼は私のマグカップを取り上げて、一度温度を確認するように口をつけた。私が猫舌であることを理解している彼はいつだって少し温いコーヒーを私に作ってくれる。以前私が自分の適温、と教えたその温さかに合わせて。 「火傷したか。」 「多分してないと思う。」 「見せてみろ。」 いいよと言う私に構わず私の前へとしゃがみ込んでくるものだから、仕方なくぺろりと舌を出す。一通り確認して問題がないと判断したのか、その舌を絡めとるように彼の口が重なってきた。 「なあ。」 「なに。」 唇を離した左之は、妙案を思いついたとばかりに私の名を呼ぶ。人に舌を出させておいて不意打ちでキスをしてきた後に思い浮かぶ事なんて、ろくでもない事だと相場は決まっている。 「今みたいなキス、他の女としてたらお前どう思う。」 先ほどのようにもう一度私は考え始める。具体的でなさすぎるそのシチュエーションに中々想像が追いつかない。仕方がないので、会社で左之と接点の多い女子社員Bをその対象にすることにしようと決めて再び考え始める。 これが俗に言う、嫉妬というやつかと。女子社員Bが彼とイチャついている段階で既に気分が悪い。その先の行為なんて言語道断だ。 「ねえ左之。」 「なんだ。」 「気分悪いから、やめてね。」 そう言うと彼はさぞ嬉しそうなかんばせを覗かせる。いつだって私よりも高い位置にあるその彼の綺麗な顔が、自分を見上げていた。いつもと違う状況に、どきりと一度だけ鼓動が早鐘を打った気がする。 嗚呼、結局彼の術中に嵌ってしまった。彼は最初から私に嫉妬をさせたかったのだ。気持ちが分からないわけではない、こんなにも全てのことに対して頓着がない彼女なのだから。私が男でも、もしかしたら同じ事をしていたかもしれない。そもそもこんな可愛げがない私を、よく受け入れてくれるなと。彼もまた変な人に違いない。 「次第だろ。」 「そんな事したらちょんぎっちゃうよ。」 節操もない事を口にしておきながら、言葉にそぐわない程私は彼に甘える。どうしようもなく甘えたい気分に陥った。それは彼の術中に嵌っているという事に違いはないけれど、今日はその術中に嵌ってみるのもいいかと観念した。 自他共に無頓着と認める私にも、隠された部分にしっかりと普通の人間が持ちえる感情を持ち合わせていたらしい。 会社で見る彼は、皆の原田左之助だ。謂わば公共のもの。けれど、こうやって一緒にコーヒーを飲むのも、広いソファーをあえて活用しないのも、不意打ちでぺろりとキスをしてくるのも、それは私しか知らない彼の一面であって欲しいと、そう思った。今まで嫉妬という感情と戦うこともなく、日々を過ごす事ができたのは彼の最大級とも言える愛情をもらっているに他ならないのだ。結局、私も左之に心酔している。スーツを脱いだ休日の左之は、私だけのものでいい。 「好き。」 土曜日の昼下がり、 初めて、彼に恩が返せたかもしれない。
|