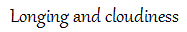  六年という月日の長さを、改めて実感させられる。 ザンザスが氷付けにされてから、もう六年だ。凍らされた彼をはじめて見た時、私は絶望の渦に落ち、途方にくれた。何故彼が氷付けにされているのかは分からず、唯一その理由を知っているスクアーロは何も教えてくれなかった。 きっと恋人を氷付けにされた人間など、私以外にこの世に一人も存在しないだろう。誰も理解が出来ないに違いがない。どれだけ願っても、泣いて縋っても、その厚い氷は解けなかった。 けれど、時の流れとは残酷なもので、それが無限に続くように長く感じたのは最初の一年だけだった。すぐに、それが日常になっていった。 「スクアーロ、ボスが呼んでる。」 「何だ。次はフィレ肉の注文か。」 「さあね。私は知らない、内容までは聞いてないから。」 六年の時を隔てて、ザンザスは私の元へと戻ってきた。どれだけ恋焦がれ、待ちわびても帰ってこなかった彼は、何事もなかったかのように蘇って私の前へと現れた。彼の記憶は、六年前から時を進めていない。 私の六年と、ザンザスの六年は違う。けれど、時が動いていない彼にとってすべてが変わっているのはあまりに惨い事だろう。それが分かっていながらも、彼にとって空白の六年間を確実に生きて過ごしてきた私には理解が出来なかったのかもしれない。 「冷たいね、最近。」 「何を期待してやがる。頭の悪い女は面倒だぞ。」 「別に、スクアーロになんて期待してない。」 明らかにスクアーロの態度がザンザスの目覚めで変わった。その理由など彼の口から語られずとも理解ができたけれど、私は何も気づいていない頭の悪い女のように今までと変わらず話しかける。気づいていないふりをしているだけだとスクアーロが分かっている事だって、分かっていた。いつまで私はこの頭の悪い女を演じないといけないのだろうか。はっきりと言ってくれたほうが、幾分も気持ちは楽だった。 私が絶望の淵にいたあの時、救ってくれたのは他の誰でもないスクアーロだった。 ただただ泣く事しか出来ず、任務すらまともに遂行できない私をいつだって気にかけて傍にいてくれたスクアーロがいたからこそ今まで生きてくる事が出来たと言っても過言ではない。どうしようもなく口の悪い彼の言葉は、酷く優しく私を思いやっている言葉だった。 いつの間にか、ザンザスがいない事が日常になっていく。もちろん凍りは解ける兆しすら見せない。私は何処かこのままザンザスは戻って来ないのではないだろうかと考えるようになり、その考えに心を痛めることもなくなった。人間慣れ程怖いものはない。 「少ししたら行くと伝えておけ。」 「すぐ来てよ。私が怒られる。」 「よく言う。お前だけは大して怒られた事もないだろ。」 「分からないよ、殴られるかもしれない。」 「ありえねえ。」 精神を病み、泣き、喚き、収集がつかない私を見捨てることなくずっと傍にいてくれて抱きしめてくれたのはスクアーロだ。自分自身もザンザスが凍り付けにされている事が精神を病むほど辛いに違いないのに、それでもそんな事は微塵にも感じさせずいつか必ず自分がこの呪縛を解いてやると私を励ました。 暫くして私は任務にも戻れるくらいに回復し、日常を取り戻した。理由は簡単だ、ザンザスがいない悲しみよりもスクアーロが傍にいてくれるその事実が勝っていたからだ。 時折、ザンザスが氷付けになっている部屋へと出向いて、確認をする。氷は解けない。その光景を見るたびに私は少しばかり安心していたのかも知れない。もしこの氷が解ければ、また私は過去の自分に戻る必要があるのだ。私には今が、何よりも大切だった。 「お前も早く出てけ。」 「いいじゃんたまには。この間までずっと一緒にいたじゃん。」 「が勝手にいただけだろ。語弊を感じる。」 私が回復してからも、スクアーロは暫く私に手を出してこなかった。何故かと聞いても興味がないからという一点張りだ。けれど私が情緒不安定に陥ればいつだって彼は私を抱きしめてくれた。そのまま感情のままに気持ちを伝えたとき、少し迷いも見せながらも彼は私を抱いた。私を抱く時、いつも彼は後ろめたいようなばつの悪そうな顔をしていた。俺も好きだと言ってくれた事は、一度もなかった。 「馬鹿女に構ってる程暇じゃねえんだ、出てけ。」 「子供でも作っちゃえばよかったかな。」 「…そのブラックジョーク笑えないぞ。俺の命がいくつあっても足りねえ。」 ザンザスの事は好きだ。けれど、それは過去の話だ。私は六年間氷付けにされていた訳でもなく、きちんと息をして生きてきたのだ。ザンザスの時間軸とは違う分、気持ちも変わって当然だ。それはザンザスが戻ってきた今も尚、変わらない。どれだけ薄情な女と罵られてもいい。殴られても構わない。それでも、よかったのに。 「俺が二度もあいつを裏切る訳にはいかない。」 結局のところ、私はザンザスには勝てないという事なのだろう。スクアーロがザンザスに誓っている忠誠は昔から揺るがない。私の入り込む隙なんて、きっとない。ザンザスが目覚めた今、スクアーロにとっての一番は私ではないのだから。 「そんなの好きにさせといて、ずるいな。」 「勝手にが俺の魅力に惚れただけだろうが。」 「学生の時から私の事好きだったくせによく言う。」 どうしようもなく優しい人。私に対しても、そしてザンザスに対しても。きっと彼は一生自分の幸せを手に入れることが出来ない不幸体質だ。人に尽くしすぎるのは彼の特徴であって、そして最大の長所であり欠点だ。 ゆりかご事件がなければこんな感情に悩まされる必要もなかったのに、私は今後どうやってザンザスに接していけばいいのだろうか。いつまでも、ママ事を続けていくのだろうか。それは私にとっても過酷で、何も知らないとはいえザンザスにとっても残酷な現実だと思った。 「泣くな。お前は六年間の願いを叶えた、それが事実だ。」 そう言って私の涙を拭ってくれるのだから、たまらない。 「…詰めが甘いな。こんな事されたら余計好きになる。」 「阿呆。さっさと行け。」 スクアーロの優しさに救われた私は、彼の優しさに今後も一生苦しまされるのだろう。 思慕と白濁 |