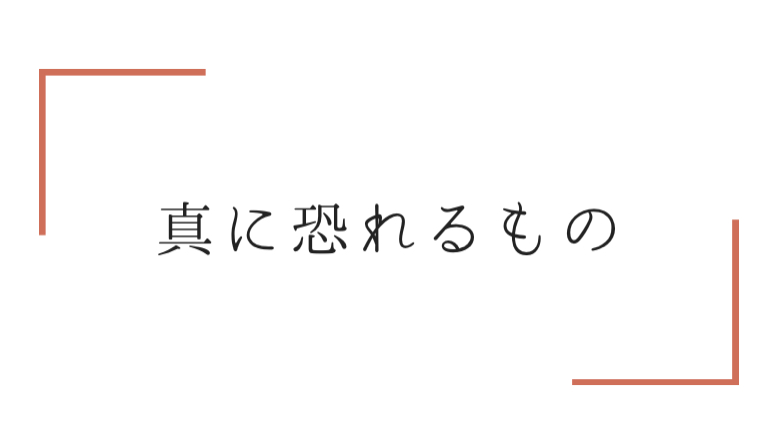 ベッドの軋む音以外に、そこには何もなかった。 時折、臨也が私を罵るように何かを言うだけで、私はそれに何も答えない。それは、静雄とするセックスよりも、幾分も私らしいと感じる事の出来る時間だった。 静雄と付き合ってから二年が経つ。それを人は長いとも言い、自分達の歳くらいでは普通の長さでもあると言い、取り方はきっと人それぞれなのだろう。あまり数は多くはないけれど、今まで付き合って来た誰よりも一番、静雄が純粋で、真っ白だと分かる。刺々しく、荒々しい彼は、本当の所、彼の姓にあるように、誰よりも平和を望む純粋な男だった。だから私はそれを、自分の醜い部分で染めてしまうのが恐ろしかった。二年という歳月が過ぎ去っても尚、私は彼の前で本当の私を出せずにいる。それがきっと、私達が付き合っていられる秘訣なのだろうと思う。 「ねえ。何を考えてるの?」 行為を終えて横たわる私に、そんな言葉が意味もなく降りかかる。大して知りたくもないくせに。臨也にとっての私の価値は、きっと、静雄の彼女というその一点のみにしかない。私も彼を心の底から求めている訳ではない。そもそもこんな男に純粋に好意を抱かれても困るのは私の方だ。私が心の底から求めているのは、今も昔も変わらず、静雄という存在でしかなかった。それを前提に、私は臨也と今の様な行為を度々繰り返しているのだ。その行為に、きっと、愛はなく、そして必要ない。 「別に。なんだっていいじゃない。それを知って何になるの。」 「俺は君に聞いたんじゃなく、ただ、こういう場合は何を考えるのかっていう人間の心理を追求したいだけだよ。それとも、俺が人を越えて、君に興味を持っているとか思った?」 私が聞き返しても、結局は臨也の口車には勝てない。私は、いつだって、この男のいいなりだった。所詮口では彼には勝てないのだと、そう、思い知らされる。 「…冗談は顔だけにして。」 「酷いなあ。そんなに残念な顔してる?俺って。」 「鏡、見てみれば?」 「傷つくねえ。まあ、人には好みってものがあるから、しょうがないか。」 俺は静ちゃんとは似ても似つかないからね。 「でもあれだ、が本当はアンアン啼くのが趣味じゃないって知ったら、静ちゃんどんな顔するんだろうね。」 「悪趣味。」 「自分でも思うよ、俺は悪趣味だって。」 そう言いながらも、彼は絶対に告げ口する事はない。彼は元より告げ口をするつもりなど微塵もなく、私が恐怖におびえるその表情を見たいだけなのだと、数年の付き合いで理解できるようになった。もし、例え彼が告げ口をしてみたところで、きっと、静雄の反応は私と臨也の思い描いている通りになるのだろう。 「俺と似ているが、どうして静ちゃんに惹かれるのか俺には分からないな。未だにね。磁石のプラスとマイナスが引き寄せられるようなものなんだろうか。俺には理解に苦しいよ。」 「残念ながら、マイナスとマイナスは、引き寄せられないんだよ。」 「どうだろう。俺と君がある意味“繋がった”という事は、強ちそうも言ってられないんじゃないか?」 「……下品な男。」 きっと、静雄は私と臨也の現状を知ったとしても、何もしない。それが私と、そして臨也の見解だ。例えば一方的に臨也に強姦でもされたのであれば、きっと、地球が破滅するほどに彼は暴れるだろうけれど、その行為に私の同意があったのであれば彼は何も言えないだろう。私に対しての、いくらあっても足りない無限の優しさが、私を傷つける事を許さないのだ。私と臨也が所謂セフレという関係にあると知った所で静雄は私を叱る事は出来ない。どうしようもなく、優しく、真っ白で純粋な人。私と、臨也じゃ、似ても似つかない人。 「……こんな事をアンタに話すのは、なんか、気に食わないんだけどさ。」 「だったら何故、あえて、俺に話そうとする?」 そんな事は私自身、分からない。ただ話したくなった訳でもなく、本当にただの、気まぐれだと思う。それを口に出さなければ、忘れてしまうような、私の本来の目的が消えうせてしまうような気が、少しだけしていた。 「初めて静雄とした時ね、私は無言だったの。別に気持ちよくなかった訳でもないし、入ってるか入ってないかが分からなかった訳でもなく、私は初めての時から声はあげなかった。それが私にとっての普通で、私以外の人にとっても普通だって思ってた。でも静雄は違った。ずっと、不思議そうに私を見てた。そのままの私を見て、徐々に不安げに顔を歪ませていって、ようやく私気づいたんだ。ああ、そっかって。それからはずっと、アダルトビデオに出てくる女優のように声をあげるようになった。 自分を偽ってまでも声あげる程に静雄が好きなのに、なんで私達はマイナスとプラスになってしまったんだろう。」 「…あれ?さっきはマイナスとマイナスは引き寄せられないっていってたじゃないか。」 臨也の口角が、ニッ、と釣り上がって私は思わず言葉を閉ざした。私の先ほどの話と、辻褄が合わなくなる。彼の前で、こんなボロを出そうとは、とんだミスをしてしまった。それこそ臨也の思うつぼだからである。 「…ただの戯言よ。気にしないで。」 「そう言われると余計に気になるのが、人間の心理ってもん。」 「アンタに言うのは、癪に障るの。」 話を反らしたくて、軽めの布団の中に、手を伸ばした。ガサガサと布団の中を弄り、そっと手を置いた。自分らしくもない、大胆な行動に驚いていたのはやはり私だけで、臨也はいかにも面白いものでも見るような目で、私を見ている。見下されているようなその目が、嫌ではなかった。 「言ってる事と、やってる事が、比例してないよ。」 まるで勝ち誇っているような臨也の表情を瞳に映し出して、私はすぐに布団の中に全身を覆い隠した。続く様にして、少しくぐもった臨也の声が、耳元で心地よく響いた。 「君も損な性格だね、。」 「なにが。」 「分かってるくせに。」 そんな事、分かりたくもなかった。静雄の女というブランドのない私に、臨也はきっと見向きもしない。私と静雄は磁石のようにプラスとマイナスで繋がっていて、私と臨也は、かろうじてマイナス同士でありながらも仮の状態で繋がっている。私の持っているプラス分子がなくなり、私単体の何のブランドも持ちえない状況になれば、私は全てを失う。分かっていながらも、分かりたくはなく、そして、分かってはいけない。そんな私すら、彼は見透かす様に知っている。 最初は、ほんの出来心だった。静雄の事を好きだからこそ辛かったあの頃に、声をかけてきたのは折原臨也というかつての同級生だった。いい奴ではない事は知っていたし、依存する事などこの世が滅んだところでありえないと、そう思っていた。だからこそ、関係を持ったのかもしれない。お互いの需要を供給出来る、ドライな関係。 「俺の事 「違う!」 臨也の言葉が最後まで紡がれるのを待たずに、私の慌てんぼうな口が遮った。聞きたくなかったから。聞いてしまう事によって、それがやはり事実であるのだと、認めてしまうような気がしたのだ。 本当に静雄が好きだった。これまで付き合ってきた誰よりも優しくて、大切で、そして私を大切にしてくれた、かけがえのない人。今でもその思いは微塵も変わらない。彼が好きであったが故に出来た私の隙は、臨也に付け込まれてしまった。臨也にとっての私が何の意味も持たず、静雄の彼女というブランドでしか私を見てくれないのは分かっていた。静雄への気持ちを残しながらも、私はいつのまにかダシにする人材を間違えていた。静雄とこれからもずっと付き合いを続けるために、自分を解放させる場所が私には必要だった。それが臨也で、私は彼を利用した。 「気づいたら、逆転してるって事もあるでしょ、たまには。」 マイナスの分子を持った臨也が、私と似ている臨也が、心地よかったのだ。静雄と一緒にいる時よりも、乱暴で、雑で、優しも感じられない、そんな臨也を、次第に私は求めて行った。似た者同士は、きっと、心地がいいものだったのだろう。 けれど、どれだけ居心地がよくとも、磁石のマイナス同士は本当の意味での融合を知らないのだ。私からブラス分子である静雄を取り払えば、私と臨也を繋ぐ分子は、何一つなくなってしまう。気づけば私は、これ以上ない程に恋焦がれた彼を、ろくでなしの男との繋がりの為に、利用したのだ。そこに未来はないと、分かっているのに。 「いつの間にか、俺に惹かれてたってさ。」 当初、畏れることは、静雄を失う事だった。静雄を失いたくなくて、臨也との関係を持ったそんな私が今、真に畏れるもの、それは
|