|
「青葉!」 向こうから私を呼ぶ活気に溢れた声が響いた。平助の声は独特だから分かりやすい。そもそもこの名で私を呼ぶ者など新撰組の中では彼だけだった。 「ああ平助。どうしたの、巡察中?」 今夜の食材を買いに京の街を歩いていた私は平助と出くわして少し気を安らげた。今や物騒なこの京の街だが、色んな意味でも有名な新撰組の一員である彼がいるのであれば少しは不安も取り除かれるものだった。 しかしよくよく平助を見てみるとあの浅葱色の羽織を羽織っている訳でもなく、あのいつもの軽装な彼の服がむき出しになっていた。 「いんや。実はただの使いっ走りなんだ。食事当番の奴がちょっとしくじっちゃってさあ、んで俺が駄目になった食材を代わりに買いに来たって訳。」 彼でも使い走りにされるのかと思うと少しだけ可笑しかった。しかしそれも当然か。いくら彼が幹部であるとは言っても平助は年少者には違いない。そして文句を垂れながらもきっと引き受けてしまう彼の憎めない性格が皆から愛されているのだろうと容易く想像出来た。 「組長でも所詮は使い走りなんだね平助は。」 「……馬鹿にしてんだろ。」 「当然。そんなの今に始まった事じゃないでしょ。」 そういうと平助はちぇと詰まらなそうに髪を毟った。私と平助はこんな、本当に他愛のない関係だ。少しとは言えども私の方が彼よりも年上だったこともあってこういう会話も珍しくはなかった。 「いい加減子ども扱いすんなって。」 そして彼は口癖のようにこう言うのだ。私はこんな決まり切った答えを聞きたいがために平助をおちょくって遊んでいたのかもしれない。友達というよりは、きっと、弟という存在に近かった。 私には同年代の友達というものが殆ど居なかった。弟がいるせいもあってか年下の扱いにも慣れていたのもあったからかもしれない。私にとって平助は友達というよりは弟が一人増えたようなものだった。屯所内に同世代があまり居ない事もあってか平助が私といる時間は他の人に比べても多かった。それが私に懐いてくれているようで、少し嬉しく思っていたのをよく覚えている。 そして彼と知り合ってから数年が過ぎ去った今も、私と平助の関係はこんな平行線のまま継続されているのだ。きっと自分でも無意識の内に彼を成長することのない、子どもだと思い込んでいたのだと思う。 「そもそも青葉だって俺よりたった一つ年上なだけだろ。」 「一つでも年上は年上なの。」 「そうやって歳に拘ってる方がよっぽど餓鬼じゃん。」 「生意気な。」 私は変わらない平助の態度を見ると笑ってしまった。すると平助も釣られるように恥ずかしそうに少しだけ笑っていた。それは酷く平和な笑い声だった。この危険な街が、今は少しだけ暖かく感じられた。 私達は同じ八百屋で食材を買いそろえると寄り道することなく真っ直ぐに帰路へとついた。 家族分の食事を作って、それを食べて、私の一日は体外それで終わってしまう。枠にはめられたようなこの生活が安堵するようでもあって、何か物足りないとも思っていた。実は少しだけ、平助が羨ましかった。 常に危険と隣り合わせではあるけれど彼の毎日はきっと充実したものなのだろう。やりたい事、しなくてはならない事、それが見えている真っ直ぐな瞳をしている彼が羨ましかったのだ。彼はきっと自分の信念の為に生きていて、そしてそれを体現している。私はこれといった信念も、目標すらなかった。ただ毎日を枠の中で生きているに過ぎない。 たまに思うのだ。私は平助を“年下”で“子ども”と言う事で自分にそれを言い聞かせているだけなのではないだろうかと。本当は分かっていた。彼の方がよっぽど私なんかよりも大人である事。 「青葉!青葉起きてるか?」 もの思いに耽っていた時に響いた平助の声に私はようやく正気に戻る。 「……平助?こんな夜遅くにどうしたの?」 私が尋ねると彼は罰が悪いように、はにかむようにして笑って口を開いた。 「いやあ、あのさ、腹減っちまってさあ……。」 彼は自分の腹を抱えると事の経緯を話し始めた。結局買いたした食材も調理に失敗してしまい、今日のおかずが極端に少なかった事。その後の土方からの説教で余計と腹を空かしてしまった事。掟の厳しい新撰組では時間外の食事は許されていないらしく、そもそも食材もないのだからどうしようもなくうちにやって来たというのが真相らしい。 「なあいいだろ?いつものアレ、作ってくれって。」 せがむ様に言ってくる平助に私はやれやれと言いながらも少し嬉しく思った。例えどういう形であれ、人に頼られるのが嬉しかった。私は彼の言ういつものものを拵えに台所へと向かう。 「なあ、具はおかかにしてくれよ。」 「この間は梅がいいって言ってなかったっけ?」 「この間梅だったから今度はおかかがいい。」 はいはいと言った後に私は「やっぱりそういう所が子どもなんだよ。」なんて言いながら白飯を湿らせて三角に握っていく。彼が“いつもの”と言うように、私が彼にせがまれて握り飯を拵えるのはそう珍しい事ではなかった。今日のように小腹を空かしている時や、島原帰りの時など、機会は決して少なくはない。 三角に握られた白飯におかかをねじ込んでもう一度握り直すと、早く、早くと急かす平助に手渡した。 「んー、これこれ!やっぱり青葉の握り飯はうめえんだよなあ。」 とびっきりの笑顔で私の握り飯を食べてくれる平助に、私はいつも救われている気がする。握り飯なんて誰が握っても大差ないのに、それでも彼はいつだってこのとびきりの笑顔で言ってくれた。 それでも私は素直に喜べない。ありがとうとは言わない。何処かそれが照れくさい。 「青葉もういっこ。」 「え?」 拵えた握り飯は二つ。いつもの平助ならそれで満足してくれる筈だと思ったのだが彼はまだ腹が減っていると言ってもう一つ作って欲しいと言った。立ちあがって「なあ頼むよ。」なんて言ってくる平助が心なしか大きく見えた。握り飯二つでは足りなくなったのは彼が成長しているからなのだろうかと思ったが、きっと夕食が少なかったからなのだと私は完結させた。 「次は梅のやつな。うん。梅がいい。」 呑気にこんな事を言う平助に私はやはり先ほどの事は自分の思い違いであるのだと、そう思った。やっぱり彼は変わらない。出会ったときから変わらないんだと。 「我がまま平助。」 それから程ないとある日、私は初めて死を覚悟し、それを見た。 京の街が月日を重ねるごとに物騒なものになっているのは知っていたし、肌で感じていた。平助が以前よりも忙しいと言っていたのもきっとそういう事なのだろう。分かっていながら何処か自分だけは大丈夫という根拠のない自信に私は安心しきっていたのだ。 道外れで浪士に出くわしてしまった。 身の程知らずの私は、対抗できる刀すら持ってもいないのに口で応戦してしまった。きっと他所の女よりも気が強いと思う。この後の状況が想像できるのに私の口は留まる事を知らない。 「青葉!」 巡察中だった平助の声に私は急に力が抜けてヘタリと地に座り込んでしまった。 私に向けて降ろしていた刀はまさに皮一枚の状態で平助に受け止められ、驚く程簡単に決着がついてしまった。キイイン、キイイン、と二度ばかり金属の擦れる音が耳を掠めると、次に耳を掠めたものは浪士の絶命する何とも言えない声だった。 「……刀も持ってねえのに何でこんな事すんだよ。」 私を見る平助の目が冷たかった。初めて見る彼のこの眼差しに私は動けなくなる。ようやく自分がどれほど無謀な事をしていたのかを自覚するに至った。平助のただならぬ怒りで、私は我に返ったのだ。 「ごめん……ごめんなさい平助。」 そこには今まで私が知っている平助とは違う顔をした平助がいた。あんなにあどけなく笑う彼が、いつだって私が子どもだと馬鹿にする彼が、そこにはいなかったのだ。 私は平助の手を借りて立ち上がる。自分が彼を見上げるようにしている事から、今更ながらも平助がいつの間にか私の背丈を越えているのに気づいたのだった。 「なあ青葉、頼むからこんな無茶もう二度としないでくれよ……頼むって。」 浅葱色の羽織が、そっと私を包み込んだ。 その日からというものの、私の買い出しには新撰組の人間が護衛につくようになった。きっと平助が上の人間に言ったのだと思う。屯所として使わせてもらってる身分である彼らにとってそれは断りづらい提案でもあったのだろう。しかしさすがにそんな事に幹部を付けてくれる筈はなく、私は買い物の度に監視されているようで窮屈さを感じていた。 確かに安全なのかもしれない、いや安全なのだろう、確実に。でもそこにいるのは毎回私の知らない顔だった。急に平助が恋しくなった。きっと恋愛感情とか、異性としてとか、そんな事じゃなくて、もっと単純な感情だ。 平助に会わなくなって一週間ほどが経っていた。こんなに長期間彼と会わないのは出会ってから初めての事。何だか落ちつかず、私は意味もなく屯所の入り口でうろうろと足を動かせる。 「……八木さん家の青葉ちゃんじゃないか。」 言われて私はようやく立ち止まる。 「どうしたの?こんな所で。あんまり挙動不審にしてると……斬っちゃうよ?」 にっこりとそういう沖田の言葉に私は固まったように小さくなって大きな彼を見た。すると彼は間を置いてから「冗談だよ。ここ笑う所。」なんて言ってきて、平助が彼の冗談は冗談に聞こえない、笑えない、と言っていたのを思い出して背筋が凍った気がした。 「もしかして平助かな?」 「え?」 他人の口から出た平助の名に私はきっともっと挙動不審になっていたのだろう。沖田は私を見ると「分かりやすい子だな。その顔は当たりって顔だ。」言って笑われた。 「平助は君はあんまり感情が表情に出ないって言うけど、僕にはそう見えないな。」 「平助そんな事言ってたんですか?」 「そりゃあもう。君の話はみんなよく知っているよ。」 彼が言うには、平助は屯所内で私の話をよくしているらしいというのだ。そんな事とは露ほども知らなかった私は少しばかりその事実に恥ずかしくなった。不本意だけれど、きっと、絶対、私の顔は色づいていたんだと思う。目の前にいた彼が笑っていたから。 「もっと頑固で表情の硬い子かと思ってたけど、話と全然違うんだな、青葉ちゃんって。」 すっかり彼の波長に流されてしまっていた頃、沖田は私の転々とする表情に満足したのか、そのお喋りな口を一度閉ざしてから、もう一度言葉を紡いだ。 「平助は今、大坂にいる。出張中だよ。」 続けて聞いていると彼の帰ってくる日はまだ未定であり、早くとも二週間後、長ければ一カ月後になるかもしれないと沖田は告げた。 去っていく沖田の背中を見送りながら私は軽い苛立ちに苛まれていた。何故彼は私に何も言わずに行ってしまったのだろうか。少なくとも私は平助との仲をそれなりのものだと思っていた。だからこそ私にはその事が腹立たしく、憤ってしまったのだ。 おいてけぼりをくらった私は、私が彼をいつも子ども扱いする以上に、子どもに違いなかっただろう。 日に日に平助に会いたいという純粋な気持ちと平行に苛立ちも同等に募っていった。待てど待てど平助は帰って来ない。出張先で万一の事でもあったのだろうかと考えもしたが、沖田が言うには命にかかわる様な仕事をしに行っている訳ではないというからそれを信じるしかなかった。 「あれ?今日も待ってるの、平助の事。」 私が屯所の傍を通りかかると沖田は楽しそうに同じ言葉を私に向ける。それは毎日繰り返される日常になりつつあった。きっとこの人は私の事をからかいたいだけなのだろう。平助から聞いていた話がこんなところで役に立つとは思いもしなかった。 「待ってるんじゃないですよ。……一言、言いたくて。」 「青葉ちゃん。それ世間では待ってるって言うんだよ。」 今度は彼の言葉が正論すぎて私は何も言えなくなってしまう。私は彼に一言怒ってやりたかったのだ。何故声をかけることなく出かけてしまったのかと。でもそれは言いかえれば、彼の帰りを待ちわびている私に違いなかったのだ。沖田の言葉によって気づかされるだなんて、聊か、いや、余計に気に食わなかった。 「明日も待ってるよ。」 「遊びに来てる訳じゃないんです!」 こんなやり取り、一体何日続けたのだろうかと思うと気が遠くなりそうだった。結局平助が京に帰ってきたのはそれから一週間後の事で、彼が私に一言の断りもなく京を経ってから実に一カ月が過ぎた頃だった。 「……………」 待ちわびていた筈の平助の帰還の日。私はいつものように屯所の前で彼の帰りを待っていた、筈だった。私は彼の姿を少し遠くで見つけると、気づかれるより先に家へ飛び込んでしまった。 平助が帰ってきてから暫く経った。私は外に出るのを避けるようになった。買い物は極力母に頼むようになったし、日課であった庭掃除すら人目を気にしながら短時間で済ますようになっていた。 平助に会うのが少し怖かった。彼が京に戻ってきたあの日、彼はまた一回り大きくなったように見えた。それが背丈や体の大きさの問題であるのか、それとも精神的なものであるのか、そのどちらでもあるのか、私には分からなかったけれども。とにかく怖かった。会うのが怖かった。何故、だなんて自分でも分からなかった。 「あんたねえいい加減少しは手伝ったらどうなの?……病人じゃあるまいし。」 母は私が明らかに家の外に出たがらない事を不審がっていた。いつだって率先して家事をしていた私が変わってしまったと嘆いてもいた。私は明らかに平助を避けていた。無意識というよりは、きっと本能的に。 そこから程なくして、私は本当に病に冒された。 少々風邪をこじらせてしまったらしい。  私の風邪は思っていた以上に重症らしい。熱が下がらない上に食欲もない。普段健康体な私が病に伏せっている姿などきっと似合わないのだろうななんて他人事のように、働かない頭で考えていた。 そう言えば平助は元気だろうか。私みたいに流行り風邪に侵されていたりはしないだろうか。彼を避けている私からこんな言葉が出るのも可笑しな話か、ばかばかしくて笑えてきた。 遠くで話し声が聞こえてきた気がした。聞き覚えのある、酷く懐かしい声が襖の奥で私の名を呼んでいる。 やがて襖はそっと音を立て、私が避け続けていたその本人を曝け出していた。 「よう青葉!熱、下がらないんだって?」 病人を前に不謹慎な!なんて思ってしまう程に勢いの付いた彼の声が私の熱を少しばかり楽にしてくれた気がする。久しぶりに聞いた、平助の、独特な声。 「ただの微熱だよ。」 「嘘つけ。そんな顔でよく言うぜ。……全く。」 平助は私のおでこに自分の手を重ね合わせると「熱っ」言ってから離した。平助の手が少し冷たくて気持ちよかった。でももう少しそのままで、なんて強情な私はきっと口が裂けても言えないんだと思う。自分の事ながら本当に素直になれない女だと思う。 「なあ青葉。」 「なあに。」 平助は間を置くとゆるく髪を毟った。彼は少し困るとこうする、一種の癖だ。 「……総司から聞いた。青葉が毎日屯所の前で待ってたって。」 やっぱり沖田総司という人間は皆が言うように随分とお節介で嫌がらせのような事が好きらしい。私は確信した。平助にはこの事を言わないで欲しいと念を押したのが逆に仇になったのだという事が今なら理解出来る。 「いや、あのさ、………嬉しかったんだ。」 「だから私は待ってない。ただ屯所に用事があっただけ。」 見え透いた嘘をついた。でもきっと平助くらいならごまかせると思った。え?って言ってあたふたする彼が想像出来た。事実、少し前までの彼はいつだってこうして私に遊ばれていたのだから。 「こんな時くらい素直になれよな。」 痛いくらいに真っ直ぐな平助の眼差しが私を射抜いていた。私を浪士から守ってくれた、あの時の目と同じだ。 「私はちっとも嬉しくなんかなかったよ。何にも言わずに、ほっぽかされて。」 そういうと彼は小さく「ごめん。」そう言った。突然の辞令で告げる間もなく夜明け前に出発してしまったからだと説明してくれたけれど到底私の気は収まらなかった。そもそもこんな事を平助に怒れるほど、私達の関係がはっきりしているものではないから私も何も言えないけれど。 暫く沈黙が続いた。互いに気まずい時間が延びていたが平助がその沈黙を破った。 「そうそう。これ作ってきたんだ。俺のお手製だ。」 急に優しくほほ笑む平助は音を立てて何かを取りだした。巻かれた笹を剥がしていくと見えてきたのは白い物体だった。それは違いなく、よく私が彼に拵えてやった握り飯だった。 「……病人に握り飯なんて聞いた事ない。普通こういう時はお粥とかじゃないの?」 声を振り絞って悪態ついた私に平助は笑った。 「そりゃあそっちの方がいいんだろうけどな。俺、これくらいしか作れねえしさ。」 あまりにも素直すぎる返事が帰ってきて私は一瞬返答に困ってしまう。しかし本当に食欲がなかった。いい加減何か口にしなくてはいけないことは分かっていたがそれでも体が受け付けようとはしなかった。 だからありのままを彼に伝えた。「…食欲ない。」「分かってる。」「なら分かるでしょ。」「でも食わなきゃその内お前死んじまうだろ。」私が引かなければ平助も引いてくれそうになかった。 「青葉のには敵わないだろうけどきっと美味いだろうから。」 ニカっと笑う平助に無表情な私。きっと私が無表情なのは風邪である事以外にも理由があるだろう。 私は平助の前では感情を留めてしまう所がある。きっと無意識ながらだけれど。平助よりも大人でいなくてはいけない、そんな誰が頼んだ訳でもない義務感に駆られていたのだ。平助は私の弟のような存在で、私は姉のような大人びた存在でなくてはいけないと。 今思えばなんて浅はかな考えなのだろうかと思う。所詮歳は上と言えども大差ないもの。勝手な固定観念が私を縛りつけていて、平助もそれに気づいたんだと思う。 「……こんな時くらい甘えて欲しい。なあ?甘えてくれよ。」 平助は私を見て、諭す様な優しい声で語りかけた。思ってもいなかった、兄のような言葉を。 くしゃくしゃと私の髪を揺らす平助の右手がやっぱり冷たくて、気持ちよくて、私はその優しい言葉に縋って彼の手を握りしめた。熱を冷ますだけでなく、違う何かを得るために。きっと。 平助に支えられながら私は久しぶりに起き上がって、座った。 彼はご自慢のお手製握り飯を私に差し出した。私も、それを受け取ってみた。持ってみてようやく私は分かった。私の拵える握り飯との大きさの違いに。私が握るよりも二倍近くある大きな握り飯。彼は立派に成長していた。私なんかよりもよっぽど、大人になってしまった。 本当は心の何処かで分かっていた。でも本能がそれを認めようとしなかった。それを認めた時点で私はきっと彼を弟しででもなく、だからといって友人としででもなく、きっと男として見てしまうだろうから。彼を好きになる自分の心を知っていながら、止めていたのもまた私だ。 「こんな大きい握り飯、食べられる訳ないじゃん……」 塩でしか味付けされていないただの握り飯がこんなに旨いものかと思った。彼も私が作った握り飯をこんな気持ちで食べてくれていたのだろうか。だとすれば少し、嬉しい。 不格好で、質素な味だったけれど、あまりの美味しさに私は久しぶりに泣いてしまった。 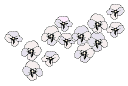 ( 20110213 ) |
