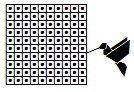 十五歳になった時、私は婚約者を鬼に喰われた。本来であれば、喰われるのは私の筈だった。庇われて死ぬのは私ではなく、婚約者だった彼になってしまった。これは一生私の傷として記憶から消えることもなければ、決して消えてはならないものだ。 計り知れない悲しみを埋めるには鬼という生き物に憎しみを抱き、あの悪の根源となるものを根こそぎ排除する事に意識を集中しなければ到底生きていくのも辛いほどに壮絶な事だった。 身内や、それに等しい大切な人間を殺された者のその後の人生は想像を絶するものだと覚悟をしていた。実際、鬼を滅するという任務がなければ常に悲しみに打ちひしがれるしか、無限に続く時間の中で私にはやる事がなかっただろう。鬼殺隊という部隊がこの世に存在していた事に感謝の念を抱かずにはいられなかった。 婚約者を失って間もなく、私は鬼殺隊の存在を知り、迷うことなくすぐに入隊を試みた。 けれど世の中そんなに甘くはない。つい先日まで戦いの伊呂波も知らぬようなただの女は何の戦力にもならず、気持ちだけでは何も出来ないのだと思い知らされた。婚約者を目の前で失った時、少し遅れてやってきた鬼殺隊の隊員に一度弟子入りをしてみる事を勧められ、ある人物を紹介された。当時の私にはそこへ行く以外には選択肢がなかったのだからすぐにそこへ向かい、弟子入りして修行を始めた。 私の師になってくれたのは、想像していたよりも遥かに若い男だった。元柱だという。 そこで二年間の間修行に耐えた。鬼の事、鬼を倒すにはどうすべきなのか、鬼殺隊の事、本当に色んな知識を授けてもらった。そして、彼が鬼殺隊にいた頃の話も、修行も終盤になった頃初めて聞くことが出来た。 彼は師と名乗るにはあまりにも若く、何故鬼殺隊を引退したのか理解に苦しいくらいの男だった。元柱というのだから私から見ても能力に長けている人間という事は分かっていたけれど、引退したその事実が不思議でならなかった。 彼の右手には数本足りない指があった。上弦の鬼と遭遇した際に手傷を追わされたのだという。 指の数本失ったくらいで現役を引退する必要もないのではないかと尋ねたが、真剣を振るうという事は相当に難しいことで、五体満足でないとどれだけの才があっても難しいという事だった。彼の生い立ちや生き様、すべてを聞くことによって次第に私は彼に惹かれていった。 自分自身が何故鬼殺隊を目指そうとしたのかという目的を思い出すと、酷く心が痛んだが、自分の意思とは関係なく好きと思う気持ちを制御する術もなく、結局私は自分の師と恋仲になった。まだ婚約者を失って二年弱のこの状況で、とても薄情な女だなと自分のことを卑下したが、それで何かが救われるわけでもなかった。 最終選別に参加し、生き残った私は見事念願だった鬼殺隊の隊員になる事が叶った。元々鬼殺隊を目指したのは婚約者を殺された恨みを晴らす事だった。もちろん自分と同じような人間を一人でも少なくする為にという気持ちもあったが、今は違った。師である彼の鬼滅隊で成せなかった無念を私が成すのだという目的へと変貌していた。 私は、薄情な女だ。自分の事ながら酷いなと思い、亡き婚約者に対して顔向けできるものではなかった。 命じられる任務を着々とこなし、私は着実に階級を上げていた。鬼滅隊に入隊し半年、婚約者を失って二年と半年、私は一人の柱から継子にならないかと声をかけられていた。 「……何で私なんですか。」 「何でって。そりゃお前はそこそこ強いし、俺が育ててみたいって思ったからだろ。不本意か。」 「もちろん光栄ですけど、私より強い隊員なんてそれこそ大勢いると思って。」 「お前だったら派手に化けると思ったんだよ。それだけだ。」 柱になりたいと思っていた訳ではなかった。彼が出来得なかった事を全うすることで彼の無念を晴らす事が出来ると思っていた私にとっては、ある意味隊員になった時点で概ねの願いを叶えていたのかもしれない。死んだ婚約者が聞いたら泣くような酷い話だ。 鬼を滅するという任務に対しての疑念や迷いはなく、そこには全力を尽くす気概ではいたが、いざ継子の話を貰うと少しばかりの不安が過ぎった。 ここに入隊した以上、皆死を覚悟している者ばかりだ。私とて、入隊を志した頃は捨ててもいい命だと思っていた。けれど、師である彼が生きている事によって自分の命を惜しいと思うようになっていた。鬼は一体でも多く滅したい、それは私の心からの本音だ。けれど、死ぬのは怖い。 「迷う理由はなんなんだよ、お前。」 「……死にたくないって思っただけです。」 「だから継子にしてやるって言ってんだ。強くなれば、お前が思ってる恐怖も減るだろ。」 私にこの提案をしてきたのは音柱である、宇髄天元という男だった。何度か任務で一緒になった事がある程度だったのだから、正直この話を持ちかけられた時相当に驚いた。彼とは戦法も異なる私にとっては、声をかけられた理由もよく分からなかった。 けれど彼の言うことにも一理あった。 確かに私は継子になる事によって、確実に今よりも強くなることが出来る。そうすれば、彼が言うように死の確率も低めることができるかもしれない。最初は怖気づいていたものの、悪い話ではないと思い、私はその誘いを受けて彼の継子になる決断を下した。鬼殺隊を志した時と比較して、私の思想は随分と歪んでしまっているような気がしたが、人を守りたいというそこだけは揺るぐことのない信念にすべてを委ねる事にした。 宇髄の継子になってから更に修行を重ねていき、私は更に階級を上げていた。ただの非力な町民でしかなかった自分が、いくら有能な人間に鍛えてもらったからといってここまで戦う事の出来る人間とは夢にも思わなかった。 別に強くなりたかった訳ではなかった。最初は、婚約者を殺された悲しみを忘れるために志した鬼殺隊だった。けれど、それを目指す事によって師と出会い、その目的も捻じ曲げて私は隊員になった。隊員になった今は、いかに死なないかという事を考えて過ごしている。年月を重ねて、私という人間は醜い生き物になってしまった。鬼と同じとは言わないまでも、それに近しいものがあるのではないかと自覚するほどに、人の欲に忠実だった。 時折任務が下されて現場へと向かう。宇髄の言うとおり、彼の継子になった事で私は以前よりも更に強くなり、死に対する恐怖も薄れていた。奢ってもいたし、油断もしていたのだと思う。ちょっとした隙を見せる事で、人は簡単に死ぬのだという事をまざまざと思い出させられる出来事に遭遇した。自分の判断のひとつの過ちで、同行した隊員の一人を失う事になり、私もまた、深手を負った。 「。」 「…すみません。油断しました。」 敵は、宇髄がきちんと処理してくれたものの、犠牲を出してしまったのは他でもない自分のせいだと自覚があった私はこの後に続く言葉に目を堅く瞑った。本来であれば、私が身を挺して庇わなければいけなかった隊員を一人死なせてしまった。 「、俺が継子にお前を選んだ時に言った事忘れたか。」 どうして私は全力で戦うことが出来なかったのだろうかと後悔した。いくら自分の命が惜しいとは言っても、守れる力がある者がそうでない者を守るべきだと分かっていた筈なのに。命を惜しんで動けなかったのではなく、自分自身の奢りで油断をした自分を悔やんだ。自分自身が鬼殺隊にいる中で命を惜しんでいるという事に対してどうしようもない恥を覚えた。 「一番はお前の命、二番は堅気の人間だ。忘れたか。」 「…でも、」 言おうとして、すぐに怒号のような宇髄の声が私を射した。 「無茶すんな。…無事でよかった。」 その言葉が出た直後には、分厚い彼の胸板の感触があった。私はてっきり叱られるものだと思っていたのだ。油断した事によって死なせた命が紛れもなくあったのだから。けれど、彼は違った。確かに私が継子になったその直後に言った言葉を繰り返して、私が今生きている事に全力で感情を示してくれた。 不思議な感じだった。怒られているというのは事実に変わりないのに、どこか暖かで、心が穏やかだった。同時に、自分の器の小ささに涙が出そうになった。自分の鬼を滅する事への覚悟が他の隊員よりも薄く、ただ少しだけ力に恵まれていただけであった事をどうしようもなく恥ずかしく思ったのだ。けれど、それは隊員になる前の何も持ち得ていなかった自分に何かを与えてくれた師のように暖かく、そして愛おしかった。 「宇髄様ごめんなさい。」 「…分かったら、死ぬな。絶対だ。」 「…はい。」 厳しく育てられた反面、自分を死なすまいと思ってのこともあったのだと再認識して、この時はただただ泣くばかりしか私には出来なかった。 場にそぐわない場面で、何故か自分の性質をふいに思い出した。 それからも厳しい修行は続いた。 ひとつ変わったのは、私が自発的に訓練以外で鍛錬をし始めるようになった事だった。先日の一件で、もっと強くならなねばいけないのだと強く思ったからだった。 以前よりも気持ちは改まっていた。自分の命は確かに惜しい。死にたくはない。だからこそ、どんな敵と遭遇しても負けないように死なないまでに強くなればいいのだと考えたのだ。そんなに事が簡単に出来ることであれば今頃鬼は全滅しているのだろうが、それでも私はそれを糧に修行に励んだ。 「張り切ってんなあ。どうしたよ。」 「宇髄様が死ぬなって言うから、死なないように鍛錬してるんですよ。」 「そりゃ関心だな。お前見かけによらずいい子だな。」 「……どんな見かけなんですか、私。」 この時には既に、また鬼殺隊にいる自分の存在意義が変わっていたのかもしれない。亡き婚約者の為でもなく、その屍を乗り越えて修行してくれた師の無念を晴らす為でもなく、きっと別の意味だった。 「宇髄様も死なないでくださいね。」 「あ?なんだ藪から棒に。」 「私にも同じ事言うんだから、私だって言う権利あるでしょ。」 「お前俺と同等になったつもりかよ。」 彼は笑ってくれてはいたけれど、少し出すぎた真似をしてしまったと縮こまっていたら、力強い右手が私の頭上に圧し掛かった。拳骨でも食らわされるのかと以前のように瞼をぎゅっと閉じたけれど、待ち受けていたのはふんわりと優しげな右手が私の髪を左右に撫でるという、思いがけないものだった。 「俺のとこに来るか。」 思っても見ない言葉でありながら、どこか待っていて、期待していた言葉でもあったような気がした。 私には師として私を育ててくれた男がいる。それは同時に私の恋仲に当たる男だ。けれど、それは鬼殺隊に入ってから一度も口にしたことはなかったし、もちろん宇髄にも伝えてはいなかった。 正直、心は揺れなかった。普通の女であれば迷うことなどなく断るのだろうけれど、私にはその迷いがなかった。 「飽きたりしないです?」 「なんだそれ。そんなのお前次第だろ、。」 「じゃあ、頑張ろうかな。」 その後、初めて宇髄と唇を交わし、そのまま夜を共にした。彼以上の男はいないと思った。今自分自身がしている事が本来あってはいけない事とは分かっているし、真実を告げれば宇髄とはこの夜を共に過ごす事は出来なかっただろう。私は宇髄と居たいが為に何も言わなかった。 私は気が違えたおかしな女なのだろうかと不安になる。 婚約者の事は好きだった。本当にすぐに夫婦になる心積もりだったし、愛だってあったと思っていた。これ以上愛せる人など今後一生出てこないとそう思っていた。 婚約者が殺され、私は鬼殺隊を志し一人の男の下へと弟子入りする。婚約者の仇である鬼を成敗することで生きていくと、一生彼を背負って生きていくと心に決めていたのに、弟子入りした先の師匠と恋に落ちた。 絶対に師である彼以上に生涯好きになる人間はいないと確信していた。彼が出来なかった事を私が体現することで私は彼の出来なかった役目を果たせているのだと思っていた。だからこそ、隊務を遂行するたびにどうしようもない爽快感があった。やりきったと自分で思える瞬間は何より嬉しかった。 けれど、宇髄の継子になって、分かったことがあった。 「飲み込み早いよな、いやまじで。」 そんな些細な一言が嬉しかったのがきっかけだった。けれど、師である彼が好きである事には揺らぎがなかった。けれど宇髄は私の扱いが大層上手かったのだと思う。 叱るわけでもなく、ほめる訳でもなくきちんと追い込む。終わった後に悪かった部分をしっかりと伝えて、よかった所を伝えてくれる。厳しい修行をしている中で、私にとってはちょっとした褒美のような楽しみだった。 「宇髄様、好き。」 「そんなの聞かなくても知ってる。」 「……ひどいなあ。」 私の問いに対する答えが欲しかった。言葉としてはなかったけれど、宇髄は言葉ではなく態度で示してくれた。それが言葉で何かを得るよりも幾分も嬉しかった。宇髄が好きだと自覚した時には既に、私の中には過去二人の男の姿はなかった。理由は簡単だ、何故ならばもう気持ちが完全に宇髄に向いていたからだ。 鬼殺隊に入ってから二年、私はついに柱になった。 婚約者を十五で亡くし、師の元を十七で離れ、柱になった私ももう十九になっていた。鬼殺隊員となってから、自分が叶えたいと思っていたことは大方叶ったような気がする。あとは日々鬼を滅する為に尽力するばかりだと本当にそう思うくらいに。 私は今も宇髄の隣にいる。彼の隣は本当に心地がよく、他の誰にもない安心感があった。ずっと流されやすい人間だった私も十九にもなれば、もう子どもではない。例えこの先どんな事があっても宇髄に対する気持ちが変わることはない。今までもその時々には今の彼が一番と信じて疑わなかったが、あの頃と今とでは覚悟の質が違うのだからと自負していた。 「任務ないと暇だなあ。」 「おいおい。平和ボケしてんじゃねえよ。」 「なんか幸せだなって思って。」 そう言えば、ハァ?と聞きなれた声が耳を掠めて限りなく心地いい。いまだかつてこれ程までに穏やかな気持ちですごせる時があっただろうか。婚約者を亡くしてからの人生を考えると今が一番心の平穏が保たれていた。心身ともに健康的な気がしていた。 縁側で暇を持て余して足をパタパタしている所に大きな足音がして振り向くと、私に覆いかぶさるように後ろに座って長い腕が伸びてくる。何をする訳でもなく、ただぼうっとしながら時々他愛もない会話を交わす今の状況は、まさに平和ボケを起こしても何もおかしくない現状だ。本当に、幸せで、満たされていた。 「天元様、重い。」 「幸せの重みだろ。」 「あ、そっか。」 私の頭上に顎を乗せてぼうっと暇を潰している彼との会話に、こんな日々はいつまで続くのだろうかと考え、無限に続けばいいのにと思う。そんな事を考えている時に、またふいに自分の性質を思い出した。 嫌な感じがした。今が一番幸せと感じているからこそ、恐怖だった。今回は私の事ではない。その心配は私ではなく宇髄の事だ。 今まで自分がしてきた、たどって来た道を思い出す。全ては結果に過ぎなかったけれど、私は婚約者を捨て、師を捨てた。そして宇髄を選んだ。彼は私の事を身を挺して庇ってもくれるし、誰よりも大事に扱ってくれた。それは私が満たされるほどに丁寧に愛してくれた。 だからこそ、突如不安に駆られるのだ。今まで自分がしてきたように、私は捨てられるのではないだろうかと。そう考える理由は簡単だ、人の心は移ろいやすいという事を他の誰でもない私が一番身を持って知っているからだ。 「天元様、好き。」 「なんだよ今更。知ってるっての。」 「…天元様は?」 「ってたまに頭悪いよな、まじで。」 今までは言葉よりも態度で示してもらう方が嬉しかった。それが何よりの証拠だと思っていた。けれど今は違う。どれだけ安っぽい言葉でもいいから繋がっていられる確証<言葉>が欲しかった。 これだけ幸せな現実が、残酷にも酷く恐怖の時間を広げていく。私は幸せを感じながらも、一生この恐怖に怯えて生きていかなければいけないのだろうか。自分が犯した過去の罪が、今になって私に償いを求めているようなそんな気がしてならない。 後ろにあった彼の温もりが、背中の冷やりとした感じと相まって気持ちが悪い。ぎゅうっと先ほどよりも力を増して私を抱きとめてくれたその腕が、言葉よりも確実な証明を私に返答してくれているはずなのに、気が狂いそうな程に怖いのだ。 たまらず後ろを振り返ると、一度驚いたような彼の顔があったけれど、すぐにあきれた様にかんばせを緩めて、私の髪を優しく揺らした。 「お前、今すごいアホ面してる。」 嗚呼、やっぱり私はこの人が好きだなと思う反面、やはりこびり付いた恐怖はぬぐい切れなかった。きっと、一生ぬぐう事のできない私の“咎”なのだ。 その“咎”はいかなる時も終焉のひとひらとなる花びらを散らせて、私を狂わせるのだろう。
|