 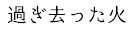 人は皆、幸せになりたいと漠然と思うものだ。誰も不幸になりたいと思いながら生きる者はいないだろう。 けれどその幸せの定義は人によって違い十人十色だ。同じ形をした幸せ像など、世界平和くらいなのだろうと思う。皆違って皆いいなんて綺麗ごとのような言葉があるけれど、本当にそうなのだろう。幸せの定義に正解がないように、また不正解もないのだ。 私が心地の良い最後の眠りについた時、私が感じたもっとも“幸せ”だった瞬間は今思い出してもやっぱりどうようもなく優しく、そして唯一私が持っていける大切なものだと思った。 これは、今から四年前、全ての戦いが終わった直後に彼と旅行に出かけたときの私の記憶で、走馬灯だ。 過去に任務で行った事のある宿の温泉に向かう彼との道中に他愛もない会話をして時を過ごした。本当にどうでもいいような内容でいつもであればすぐに忘れてしまうようなものだった筈なのに、今も鮮明に思い出すことができる。 鬼殺隊が解散となって間もなくの出来事だった。平和になった世で私は一体何がしたかったのだろうかと、今まで考えても見なかった事を考えて、自分自身この戦いの終焉を想像できていなかったのだと理解した。それほどに私たちが目標としていた世界は、手に入れるのには難しいという事を物語っていた。 恐らくあと四年、良くて五年が経った頃に自分の人生に悔いを持たぬようしっかりと“旅支度”をしようと思った以外にまだ具体的に何をしたいのかを考えられていなかった。 すれ違う同じくらいの齢の女がする事と言えば、一体何なのだろうか。同じ齢の娘と言えばもう所帯を持っている者がほとんどで、その間を鬼殺隊で過ごした私には良くわからず、そしてそれに目を向ける余裕すら持ちえていなかった。 私の右側で少し前を歩く彼に追いつこうと少し歩みを速めて追いついても、暫くすると全く同じ距離が小さく開いてしまう事で咄嗟に思いついた、最初はただの思いつきに過ぎなかった。 「ねえ、手繋いでよ。」 「…なんだそりゃ。子ども返りか。」 「今までした事ないなと思って。」 どうしようもなくそうしたかった訳ではない。けれど、もう何も気にすることのない世の中になったという証明として何か形があればいいのにと考えた時に出てきた私なりの答えを口に出して初めて少し恥ずかしく思った。 彼のかんばせは左側からだと上手くうかがい知ることは出来ないけれど、口元が少し飽きれたような形を模っているように見えて急に自分の発言に自身が熱を帯びていくのを感じ取った。 「ごめん自分で言っててすごい恥ずかしくなった。やっぱ今のなしね。」 そのままを口にすれば、彼は何も言わず少しだけ歩幅を私に合わせるようにして再び歩き始める。その大きな背中を見るだけで、不思議と心が落ち着く気がした。 天元とは同じ任務に就くことが多かった。何度となく死を意識した瞬間もあったが、いつだってその覚悟を決めた時視界に映し出されるのはこの大きな背中だった。いつだって私の右前で私を庇うようにしてくれた私の定位置とも呼べるようなものだ。その大きな背に守られ、私は今もこうして地を踏んで、彼の隣を歩いていくことが出来る。 「おい。」 「…ん?」 急に彼は立ち止まって、高い位置から私を見下ろしていた。てっきりからかわれるものかと思っていたが、そういう訳でもないらしい。思っても見ない言葉に、私も歩みを止めた。 「お前がそっちにいたんじゃ繋げるもんも繋げないだろ。」 暫く唖然としている私に何だか満足そうにしながら一度ほくそ笑みながらも、「別にいらねえならいいけどな。」そう言って再び長い足で歩みを進めて距離を開けていく。 距離を再び詰めるように私が小走りで彼の右側へ向かうと、スッと手が差し伸べられて素直に私もそれに手を付ける。子ども返りなんて半分ばかにしたような表現をしていたのに、しっかりと指と指の間を埋めるようにして握られた手のひらの温かさに、じんわりと幸せが広がっていくような気がして、平和とはこういう事なのだろうかと他人事のように思った。 「文句言ってた割りには、じゃん。」 「お前の夢叶えてやったのに文句言われるとはねえ。」 「私の夢、小さすぎない?」 その言葉に一度振り返った彼のその柔らかいかんばせが、より幸せを増長させているように感じられて胸が締め付けられるようだった。態度と言葉が正反対になっているのは、お互いご愛嬌だ。 まるで犬の散歩のように少し私の前にいる彼に長い腕が、私をしっかりと導いてくれているように思えた。 彼の左側にあった私の居場所は、この日以来変わって、そして固定された。 丁度日が暮れかけた頃、私たちは見覚えのある宿にたどり着いた。 以前訪れてからそこまで長い時間が経っている訳でもないのに、とてつもなく懐かしく見えるような気がした。出迎えに連れられて部屋へと向かう。当然の事ながら以前と違う部屋なんだなあとどうでもいい事を考えながら、見覚えのある部屋を横目に流しながら廊下を進んでいくと突き当たりの部屋に通された。 「今日は内湯の所空いてないのか。」 「生憎本日は既に埋まっておりましてご用意している湯へご足労頂く形になります。」 任務で宿に来た時のことを思い出す。その時は生憎一部屋しか空いておらず二人で同じ部屋に泊まることになったのだが、内湯がついていた事を彼の言葉で思い出した。 任務で来ていた私たちに一緒に入るという概念はもちろんなく、順番を決めて風呂に入ったが、今日はその部屋も埋まっているらしい。 露骨に嫌な顔をしている天元に、女将が気を利かせたのか付け加えるように言葉を漏らした。 「今はお食事時ですから、湯には何方もいらっしゃらず寛いで頂けるかと思いますよ。」 私たちは小さく纏まった荷物を降ろすと、すぐに風呂へと向かった。 ◆ 着物を脱いで、脱衣所の籠に入れる。今まで着ていた隊服に比べてとても簡単に脱ぐ事のできる着物がなんだか着心地が悪く、すうっと開放的な気分に陥った。隊に入って六年、私の日常も常識も大きく変わったのだなとふと思う。 身一つで湯が湧き出る場所へと踏み入れると、本当に女将が言っていた通りそこには水が流れる音が木霊するだけで、人影は見当たらない。 子どもの頃に戻ったようにはしゃぎながら掛け湯を済ませて足を入れると、きゅうっと身が締められるような体温よりも少し熱いくらいの湯が出迎えてくれた。無意識に痣を出した時よりも少し熱いように感じられた。 「本当に誰もいないよ。貸切状態で内湯よりも豪勢かも。そっちはどう?」 わざとらしく口元に右手を添えて大きく声を出してみると、少しのためらいがあったのか、遅れて彼の声が耳元へと届いた。 「…誰か居たらどうすんだ。恥ずかしい奴。」 「どうせ誰もいないくせに。」 「今は居ないってだけだろ。あんまりはしゃいで溺れるなよ。」 湯が零れ落ちる所に背中を向けて全身を暖めると、最後の決戦で負った傷が少し疼く様な気がして離れると、竹で男女の湯を隔てている所に背をかけて全身を伸ばしてみる。きっと耳のいい彼の事だから、背中を合わせるようにこの竹の後ろにいるのだろうと確証もなくそんな事を思った。 未来のことを考えると同時に、少しだけ過去の事に目を向けた。 昔から天元によく言われていた言葉があった。過去を悔やんでばかりいると次に死ぬのは自分だと。―――確かにその通りだと、本当にうそ偽りなくそう感じていた。 自分の役割、大儀を全うする為であれば命は厭わないというのがこの業界における暗黙の掟だったりする中で、私は過去に引っ張られる事が多かった。後悔せざるを得ない仲間の死も沢山見ていたのだから致し方ない部分も多い。 けれどそれでも彼はいつだって過去は振り返らず、先のことを考える男だった。先を読んで動いていた彼だからこそ、私は何度もその大きな背中で守ってもらえた訳で、今ここで生きているのだとも理解している。 「入隊してからの六年、あっという間だったな。」 「なんだよ今更。思い出話か。」 「そうだね。思い出話に出来るのが何より幸せなのかもしれない。」 「随分と謙虚なんだな。もっと大それた幸せはないのか。」 「どうかな。もしかしたら今が一番幸せなのかもしれないと思うんだ。」 きっと私には他の人間と比べて残された時間は短い。短いからこそ、猶予が分かっているからこそその限りある人生をきちんと支度して、生きることが出来るのかもしれない。特別な時間だ。 いつ体の自由が利かなくなるか分からないこの体で、思い残す事がないよう全うしたいと純粋に思った。 私の言葉にその裏側の感情もきっと読み取っている天元は、何も言わない。言わずとも理解してくれる事が、理解してくれる人がいるのだという幸運に恵まれた自分を前に、守りきることが出来ず死んでいった仲間のことがふいに脳裏を掠めていった。 「顔が見えてないからこそ言えるんだと思うんだけど。」 彼を目の前にしてしまうときっと言う事が出来ない言葉。 素直に甘える事も得意でもなければ、口をついて出てくるのは皮肉っぽい言葉ばかりだ。それは私だけでなく、彼にも少し当てはまるのだから類は友を呼び、そして似たもの同士というものなのかもしれない。―――そんな私たちには、これくらいの距離が必要なのかもしれない。 「何の皮肉だよ。」 「そういう所本当に捻くれてるよね。私もだけど。」 「しおらしい言葉を聞いた事がないもんでね。」 「それはお互い様。いや、“それも”か。」 弱者は守られるもの。―――ずっと、入隊してからそう考えていた私にとって、多くの仲間の死は受け入れがたく、後悔の連続の日々だった。別に自分の力に奢っていた訳ではなかったけれど、それでも私はその自分の信念を前に何度も挫けそうになり、戦っていた。 自分の信念によって自分が壊れそうになっていた時に彼からかけられた言葉が、全てを救ってくれたのを思い出したのだ。 ―――守れる力のある奴が、守れるもんを守ればいい。 何かから急に解き放たれたような気がして、一気に気持ちが楽になった。全ての概念がその言葉で救われた訳ではなかったけれど、少なくともその時の私には必要な言葉だった。そして、それを体言してくれた彼に、私は感謝せざるを得ない。 「天元がいてくれて、よかった。」 今こうして自分の運命を受け入れて生きていける事も、過去を清算できる事も、全て彼がずっと私の傍にいてくれたからだと素直にそう思うことが出来るのだ。 「今更気づいたのか。」 また悪態をついたように、ふっと笑いの息が漏れる彼の言葉が竹を伝ってしっかりと耳へと伝わってくる。 「私が過去を振り返るのは嘆いてるんじゃなく、未来に繋げる為なんだよ。知ってた?」 きちんと過去を振り返って、過ちを認めて、強くなるためだと彼は知っていただろうか。知らないと、今頃目を丸くして驚いていればいいのにな、と少し私も悪態をついたようにそんな事を思う。 「だからもう振り返らない。」 振り返らなくても、もう私にはきちんと正しく伸びる未来への道があるのだからその必要もないだろう。きっと、口に出さずとも彼ならそんな意図もしっかり汲み取ってくれると思って、口を閉ざした。 少し冷えた上半身を沈めるように、首まですっぽりと一度湯に漬かると意を消したように立ち上がった。 「のぼせちゃいそうだから、もう出るね。」 ◆ 宿が用意している浴衣に火照った体を通して、暖簾を潜った先には既にどっしりと腰をかけて私を待っている彼の姿があった。女の風呂は長いだの、腹が減っただのいつもの皮肉めいた言葉が飛んでくるのだろうかとなんとなく構えて、彼が口を開く前に私が先手を打つ。 「ごめん、お待たせ。お腹空いたね。」 早く戻ろうと口にしかけた時、大きな胸板がすぐそこまで迫って、私をすっぽりと覆い隠した。真っ暗な視界の中で、ただただその大きな懐が私と同じように火照って、暖かい。 「…何してるの。」 「いいだろ別に。任務じゃないんだし。」 いつ誰が来るかも分からない、廊下でふいに感じた熱に少し戸惑いながら委ねると、きゅっと更に体を手繰り寄せられた。 「お前はもう、普通の女にもどれ。俺が許す。」 その一言が何を指しているのか、すぐに理解できて自然と涙が伝った。いつからか泣かなくなった私に、その感覚を取り戻したのはやはりこの男に違いないのだから本当に敵わない。 熱を帯びたその体温が、痣が出そうな程に私を暖めて、そしていつだって落ち着かせてくれる。  四年が経っても、何一つ変わらないその温もりに抱かれて、私は安心して眠りにつくことが出来る。すぐにまた目が覚めたら日常が待っていそうな程にいつもと同じような声色で、おやすみの一言を紡ぐ。 走馬灯と、今私が抱かれているその温もりが重なって、心地よく眠れそうな気がして深い眠りについた。 四年の旅支度は、しっかりと私に道を開いてくれた。 過ぎ去った火 |