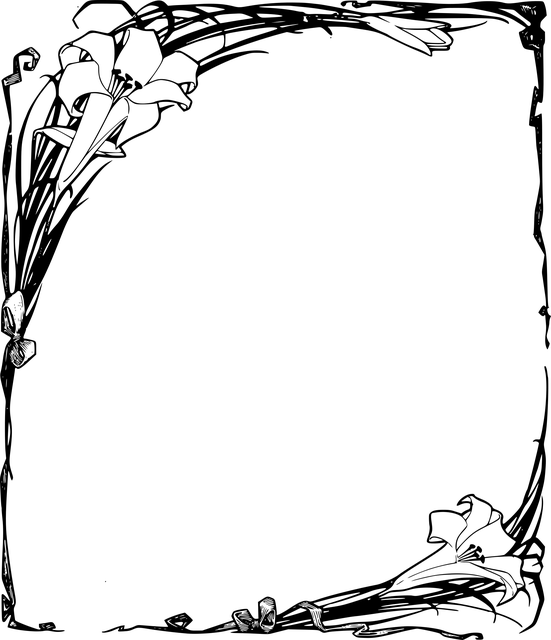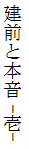左之はよくもてる男だ。 何故だろうか、と思う。荒っぽいし、おおざっぱで、すぐに短気を起こすのに昔から女性人気が高い。確かに背は高いし、程よく締まった体をしていて、二枚目でもある。舞台役者のような二枚目とは違うけど、一度彼に見つめられただけで好きになっただの、結婚したいだの、妊娠しただの、騒ぐ女性が多かったのも確かだった。 私自身は彼の幼馴染だからこそ、ずっと離れることなく近くで彼を見てきたけれども、いつだか左之の夢を聞いたとき私は笑ってしまったことがあった。 「…嘘でしょ。嫁もらって静かに暮らしたいなんて。」 単純に意外だった。彼の普段からの荒っぽい言動を見ている限りでそんなことが夢だとはそれこそ夢にも思わない。幼きころから彼を知っている私だから、という訳ではなく原田左之助という人物を知っている者であれば皆が同じ反応をするだろう。 白か黒かでしか感情を示さない彼が、珍しくばつの悪そうなかんばせを私の前に映し出していた。 「別にいいだろ。ただの夢だよ。」 髪を上に結わっている左之は、気まずいように髪を触った。そんなことをするもんだから、赤い彼の髪が少し結い紐からはみ出てハラリと顔にかかった。 「左之だったら、喧嘩で日本一になれますようにとかそういうのだと思うじゃん。」 「随分と俺のことみくびってくれるな、お前は。」 そう思わせるほどに、彼は少年がそのまま成長したような、本当にやんちゃな青年だった。良くも悪くも、色々割り切れないことが多いのもひとつの特徴だろうか。 お酒にも強いようだし、何より左之は義理堅いところがあるからか、つるんでいる連中は絶対的な信頼を置いているようだった。 感情的ですぐに手が出るけど、いい奴ということは私も知っている。小さいときから誰よりそばにいて彼を見てきた私が言うのだから、きっと間違いはないだろう。だからこそ驚いてしまうのだ、男臭い輪の中心にいるような彼の見当もつかないような、夢に。 「そういうお前はどうなんだよ、。」 自分だけ言われっぱなしなのが心地悪かったのか、彼は言葉をそのまま投げ返してきた。 言われてみて初めて思う。そういえば自分自身の将来の夢なんて、考えてみたこともなかった。ただ漠然と日々を過ごしていて、気づいたら大人になっていて、何も変わることなく不変的な未来があると思っていたのかもしれない。 「…考えたことなかったかも。」 「お前もそこで”好きな男と添い遂げてえ”とでも言っておけば可愛いのにな。」 「別に左之にそんな事思われたって得、ないしな。」 「可愛くねえ奴。」 そう左之は言って苦笑めいていたけど、我ごとながら本当にその通りだと頷いてしまう。何か目標がある訳でもなく、信念がある訳でもなく、どこかふわふわと流されている人生のような気がした。 彼の夢に驚きはしたものの、自分とは違って明確な夢を持っている彼を、私は少しうらやましく思った。 「ま、左之もその夢は今ではなく随分と先のことになりそうだけどね。叶えば、の話だけど。」 「分かんねえぞ。案外、すぐにって事もあるかもな。」 左之はそういうと、少しだけ不適に笑って見せた。やんちゃさが見え隠れするような、そんないつもと何も変わらない不変的な毎日が私は気に入っていたのかもしれない。 将来の夢がないのではなく、ただただ今という現実に欲しい物は全て揃っていたから。もしかすると自分はそんな、とんでもない幸せ者なのかもしれないと思った。 「いや、そんな訳ないか。」 「ん?」 「ううん。ごめん、ただの独り言。」 夢がある彼を羨ましく思いつつも、私は今のままでいいと、そうとも思い始めていた。特に今の環境に文句は思い浮かばず、毎日がどうしようもない程幸せと感じることはないにしろ、負の感情を覚えることもほとんどない。自分をそう分析することのできる自分の能天気さに、感謝すべきだろうか。 幼い頃から今も続く、私を取り巻くこの環境が不変のまま続いていけばいいなと思う。ただ、それだけでいい。 伊予の夜が、更けていく。 左之の意外な夢を聞いてから数ヶ月が経ち、季節は秋になった。少し肌寒いと思う日も増えてきたが、それでも左之は夏場とさして変わらぬ格好をしていた。見渡すと木々の枝に跨る葉が赤く紅葉している。 「すっかり秋。」 「だな。読書か食欲かってなったらお前は食欲だな、。」 「まあそうだね。でも左之だって読書ってガラじゃない。」 「違いねえ。」 こうして共に秋を感じて、冬になって、また春が来れば今二人で紅葉を見るように春が来たと私たちは桜を見るのだろう。昔から今までがそうだったように、変わらずに。 「早く色づかないかな。一面真っ赤になった、紅葉がみたいなあ。」 「そうだな。 「そうなの?知らなかった。…て何でそんな事に無縁そうな左之が知ってるの。」 「別に知ってるんじゃなく、ただ聞いたってだけだよ。」 当然の如く、伊予で生まれた私は伊予を出たことがない。それは左之もそうだ。きっと私は一生伊予に居て、伊予で死ぬんだろうなあと漠然に思う。外に出て行く理由も、何も持ち合わせていないから。伊予を離れるなんて考えることだってなかった。 でも、左之のその言葉で、京の都で紅葉を見てみたいと思った。きっとそれは叶うことはないし、叶えたいと思っていた訳でもないけれど、単純に興味があったのだ。伊予以外で見る紅葉は、そんなにも違う世界なのだろうかと。 「いつか、行けるといいな。」 唐突に、左之は呟くようにして言ってみた。私が隣で、「え?」ともらすと黄金に輝く瞳をこちらに向けて、小さく笑う。 「何だよ。行きたくねえのか?」 いつになく左之が大人びて見えて、なんだか調子が狂う。 私も思ったままをきちんと伝えればいいのに、それを一歩手前で阻んでしまう。今更素直な感想や感情を左之に伝えるのがどこか照れくさかった。思った事をそのまま口に出せる左之とは違い、私はその損得について一度考えてからしか前に進めない節がある。 「左之が行きたいのは、色町のほうなんじゃない?」 「ああ、島原か。それも悪くねえな。」 「ほら、やっぱり。」 素直になれない自分をもどかしく思いつつ、彼はそれに対して気遣った返事をくれた。私の素直じゃない言葉に、きちんと望んだような言葉を返してくれたからだ。そのことに少しほっとした。 「まあ気が向いたら、いつか連れて行ってやるよ。」 ニカっと笑う彼に、一瞬胸がざわついた。嬉しくないのかと聞かれたら、きっと嬉しい感情に違いなかった。それが例え、かりそめの話だったとしてもそう言ってくれた事が嬉しかった。この胸のざわつきが左之に対する何かなのか、それとも今後何かが起こるという前兆によるものなのか、私には分からない。控えめに私たちの髪を揺らす秋風の元、私たちは視界の上の方に映し出される赤い葉を見ていた。 「覚えてたら、付き合ってあげてもいいよ。」 虚勢を張ったその言葉に、「生意気な奴。」そう言って彼の大きな手のひらが私の髪を豪快に揺らした。今まで何度となくされていた不変的なその行為が、どこかむず痒いようでいつもと違う気がしていた。 街が騒がしい。事情を知っていそうな人間を捕まえて、何があったのかと尋ねるも皆一様に私の顔を見ると気まずそうに視線を逸らして知らないと言った。何かあったと顔に書いているようなものなのに、私には教えてくれない。 家に帰り夕食の支度をしようとしていた頃、意外な人物から私は知りたかった真相を聞くことになった。 「…左之助くん、切腹したらしいのよ。」 母の言葉に、息を呑んだ、なぜ彼が切腹をしなくてはいけなかったのか。そもそも、どうしてそうなったのか。私には想像にすらできない。いつだって不変的に傍にいた左之が、腹を切ったなんて。 「。」 「そんなの嘘に決まってる。左之の質の悪い冗談でしょ?」 「……まだ生きてる。今日が峠みたいだから、気になるなら行きなさい。止めはしないから。」 母の言葉を聞くと返事もせずに私は飛び出していた。どこに行けば彼がいるのかも分からない。どういう状況なのかも分からない。今日が峠であっても、それでもまだ彼が伊予の地で息をしてくれているならそれだけでも私にとっては充分だった。 経緯は分からないものの切腹をした男の元へ向かっている私は、きっと親不孝な娘だと思う。心の中で一度だけ両親に侘びを入れて、私は思い当たる場所へと息を切らせながらも走った。 結局、彼は一番親しくしていた同士の所にいた。敷かれた布団の上で、眠っている左之を映し出して私はどうしていいのか分からず、佇む。止血のために巻かれた布からは、今もなお鮮血が見受けられる。このままでは、彼は死んでしまうのではないかと柄にもなく取り乱した。 「。」 「ねえ!なんでこんな事になったの?何で左之の事止めないのよ!」 左之の旧知の仲であり、同じく私の幼馴染である彼に私はまくし立てるようにして告げる。自分でも冷静ではないことに気づいていながらも、最早制御できない。 私がこれだけ大声を上げても、左之は一向に目を覚まさない。覚ましてはくれない。 少し時間が経過して落ち着きを取り戻した私に、彼は何故こんな事態になったのかを一から順を追って説明してくれた。お偉方と揉めた事。切腹の作法も知らぬ下郎と言われたという事。その二つを聞いた時点で今のこの現状につながる工程は想像ができた。 「…馬鹿。ほんっと馬鹿なんだから。」 馬鹿とは何だって起き上がって私の額を小突いてくれる左之がそこに居ればよかったのに。もちろん、そんな光景はなかった。 「こんな下らない事で死んじゃったら、あんたの夢も叶わないじゃん。」 結局私は精神的な疲労と、泣き疲れで彼の隣で寝てしまっていたらしい。元々物音などには敏感で、すぐに目が覚める方だったから彼が目を覚ました時に一番に気づいてあげられるのは自分だと思っていた。 近隣を探し回った。彼が居る可能性のありそうな所は全て潰した。伊予内を駆けずり回ったけれども、彼の姿を見つけることはできなかった。それは一時的な話ではなく、それ以降彼の姿を目にしていない。あれから八年の時が経った、今尚。 記憶がついた頃から当たり前に一緒に四季を感じてきた左之がいなくなって、八年が経つ。人は環境に適応していく生き物らしい。思い出すことはあっても、だからと言って精神を病むわけでも具体的な障害が出る訳でもない。 私はまだ、伊予にいた。あの時と変わらず、伊予を出る理由もないから。 左之が居なくなってから考えたことがある。伊予を出て彼を探しに行こうと。けれども誰もが反対をして、私が行くことを許してくれなかった。今にして考えてみるとそれは尤もな意見だと思う。あのときの私はどうかしていた。だから今もなお、私はここで暮らしている。 ふと、思う。 彼は今頃何をしているのだろうと。 別に当時から恋焦がれていた訳ではない。今だってそれが恋心だったのかと言われたら分からない。でも、確実にあの瀕死の状況でありながらも目が覚めたときには居なくなっていた彼が生きているのは間違いないと何処か根拠のない自信があった。 「。ちょっと時間ちょうだいね。」 母親に呼び止められる。何を言われるかは、何となく察しがつく。 左之と将来の夢を語っていた時とは違い、私はかなり歳を取ってしまった。周りの女友達はもうとっくに妻になり、母になっていた。それもつい最近ではなく、かなり前の事。私は世間様では行き遅れた女なのだ。 ここまで相手もなく過ごしてきた私だからこそ、両親の期待値も高くなっていたのだと思う。いい所のお侍さんなり、幕臣なり、そういう男性を紹介されることが多くなってきた。 私だってこのまま一生一人でいいとは思っていなかった。今後両親も居なくなった後、一人だけで生きていく勇気もない。けれど、何処か踏み切れないでいた。 八年前には、こんな事になっているなんて夢にも思わなかった。 将来の夢がなかった程に現状に満足していた私は、もうどこにもいない。あの男が伊予を去ってから、一度たりとも私は満足という言葉を体現したことがない。 今になって思う。将来の夢とは、ないもの強請りなのだと。あの時には分からなかった。何故なら、あの時には、私が望むものがそこにあったから。手放してその大きさを知るとは、きっとこういう事なのだろう。 結局話は縁談で、その人物は京の都にいるらしい。いい人だからと、母は言うけれども母自身会ったこともない人物の何を持っていい人と言っているのだろうかと不思議に思った。最もこの歳になるまで独り身の私がそうさせているのは火を見るより明らかだから何も言うことはできない。 母は伊予から出たことのない私が京の都に行くことに対して何も思わないのだろうか。娘の幸せを願うといいつつ、世間体を考えているのではないかと思った。 伊予には楽しくも、苦しく辛い思い出も多い。今まで伊予を出なかったのは出る理由がそこになかったというだけの話。京の都へ嫁げというのであれば、私には伊予を出る理由ができる。それも悪くないかもしれないと思ったのだ。 縁談話を持ちかけられてからひと月、私は伊予から京の都へと旅立った。 縁談相手が悪ければ伊予に戻ればそれでいい。それともその人と共になると文を書いて都で新しい人生を謳歌するのも悪くないかもしれない。何より京と言えば、一つ覚えている事がある。紅葉が綺麗と聞いて行ってみたいと思ったこともあった。もっとも、それを教えてくれた彼はどこに居るのかも分からないけれども。 彼がしてくれた些細な昔の約束を思い出して、私は初めて伊予を出て京へと向かった。
◆建前と本音 -弐- |