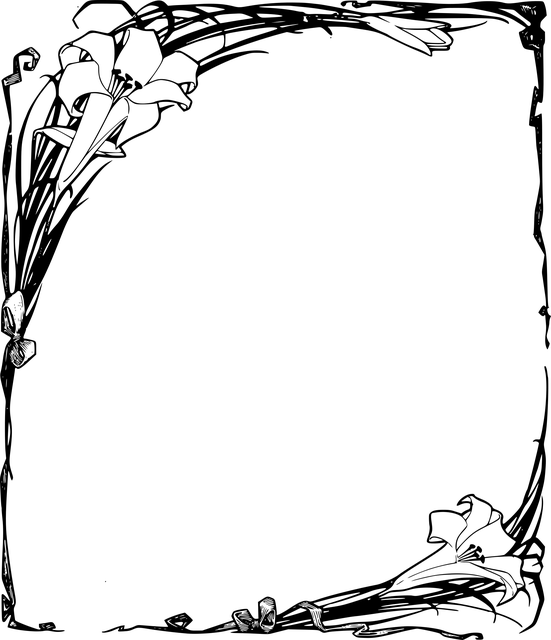長年行ってみたいと思っていた望みの場所に、望んだ人といた。こんなに心が穏やかなのは久しぶりだった。今までも穏やかでなかった訳ではない。別に暴れまわったいたという事ではない。けれど、いつからか笑う事すら、怒る事すらなくなった。そうなるきっかけがなかったというのもあったが、何にも動じないくらい心が冷め切っていたのだと思う。 「何って。旅行だよ、約束を果たすための、一人旅。」 「あぁ?」 咄嗟に出てきたのが、こんな数秒で見破られそうな意味を成さない言葉で自分自身でも相当な無理を感じていた。この後、どのように乗り切るのか最善を考える事に集中力は移り変わっていた。 「もう少しマシな冗談言えないのか、お前は。」 「別に嘘じゃないよ。私だって人生で一度くらい京の都に出てみたいってそう思っただけ。」 「臆病なが何の理由もなく伊予から出る訳ねえだろ。」 言われて、彼のもっともな言い分に私も思わず頷きそうになる。流石だと思う。伊達に長い付き合いだけあってよく私のことを分かっているかもしれない。もしかしたら、私以上に。確かに何のきっかけもなく私が伊予を離れるはずがない。自分自身でも見抜けなかった事実に、少し押し黙った。 「…私って臆病者だったっけ。初耳。」 「だからずっと傍にいてやっただろ。」 「何それ。頼んでない。」 「お前の強がりだけは何年経っても変わんないな。」 「性分や性格なんてそうそう変えられないんでしょ。」 「違いねえ。」 彼と話すのはものすごく気が遠くなるほど久しぶりの事なのに、会話の一つ一つに昔どこかで聞いたことのあるような言い回しを感じて妙ににしっくりときた。つい数日前まで一緒にいたような、伊予から左之が居なくなったのがついこの間だったかのように感じられる。 「言いたくねえってんなら聞かねえよ。」 「…え?」 次にどんな言葉を彼に返そうと必死に考えていた頭が、ふわっと宙に浮くようだった。 「聞かないの?」 「無理強いするほど俺も子供じゃねえさ。」 私の知っていた左之とは、やっぱり一味も二味も違う。昔の彼であれば私が話すまで聞いてきただろう。そんな面影も、しつこさも今の左之には感じられなかった。今日は彼に驚かされてばかりだった。 暫く沈黙が続く。でも、不思議と気まずさは感じない。かつて彼といた時と同じように、特に無言の時間も苦ではなかった。先ほどまで少しざわめ立っていた気持ちも、今は穏やかな海の水面のように落ち着きはなっていた。 「左之は、なんで京に?」 ぽろりと口から漏れるように出てきた単純な疑問に、私は再び黙り込む。 言ってはいけない事を言ってしまったと思った。左之にとっては、きっと触れられたくないことに違いない。今彼が現世で息をして人として生きているのがそれを語っているような気がした。彼は今も尚、生きている。あんな出来事があった後でも、こうして。 「そんな顔すんなよ。別に気にするな。」 「ごめん。無神経だった。」 「そんな事ねえよ。それに、お前には聞く権利ってもんがあるだろ。」 彼の口から出てくる言葉が、真相が気になった。知る権利を私がもし持っているというのであれば知りたいと思った。それがどのような結末になったとしても。 聞くことで、この八年間抱き続けたもやもやから開放されるかもしれないと。 「 ご馳走してやるからと彼はその場から歩を進めていく。断る理由のない私もその大きな背中を追ってパタパタと駆け出した。どこに行くのだろうか。まさか、島原ではない筈と自分に言い聞かせる。 今日(京)の夜は、長い 左之に連れられてやってきたのは、小料理屋だった。 好きなもの頼んでいいからと言われて品書きを見ていた時、彼は早々に酒を注文する。相変わらず、今も昔と変わらずお酒が好きなんだなと今日久しく昔と変わらない彼の面影を見つけて少しだけ嬉しくなった。 「酒があった方が話しやすい事もあるしな。」 「そうじゃなくても呑むでしょ。」 「まあそれもそうだが、俺だって酒に力を借りたい時だってあんだよ。」 伊予にいたころの左之は、自分の弱みを見せることに対してとても抵抗を抱いているように見えた。私のことを散々強がりと言っていたけれど、私と同じ位彼も強がりだ。私の強がりと、彼の強がりは少し種類が違うものなのだろうが、本質は一緒のような気がしていた。 つい今しがた昔と変わらない彼を見つけて嬉しく思っていた私だったが、すぐに現実へと戻される。荒っぽかった彼には想像しがたいほどに、今の左之は柔らかい。 「何処から話すか。…、お前は何知りたい。」 そう聞かれて、少しばかり考えた。何処からといえば、彼が私の前から消えてからだけれど実際聞いてしまっていいものなのかという戸惑いもあった。 そんな私を察したのか、左之は私の返事を待つことなく話し始めた。伊予で起こした、切腹事件の話を。 「死に損ねた俺の看病してくれてたって事は、知ってたからな。」 共通の知人から聞いていた内容を左之の言葉を元になぞっていく。彼が伊予を出る時の話に入ってから本格的に私は耳を済ませて聞いていた。私の知らない、彼の八年を。 彼の話はざっとまとめるとこうだ。 伊予を出て、傷が塞がるのを待って大坂へと単身向かい槍術を習得したと。その後江戸へと行き、先ほど私も見たかつての左之の兄貴分と似た彼がいる新撰組の元となる部隊と出会い、幕命を受けて京へと上ってきたのだと言う。聞けば聞くほど、何も違和感のない左之らしい八年間だと思った。 「ひとつ聞いてもいいかな。」 「何だろうな。」 「答えたくなければ答えなくていいけど…何で伊予から、私の前から居なくなったの。」 一瞬だけ、答えづらそうに困った顔をしたけれど、盃に入ったお酒をくいっと飲み干すと、意を消したように彼は口を開いた。 「そりゃああれだ。面目が立たなかったからでしかないな。」 何で、とまた聞こうとしたけど一度考えてから言葉を止めた。男として、左之にとっては屈辱的だったのだろうと思った。死に損ねたのを私に見られたのも屈辱だったのかもしれない。男としての誇りに、傷が入ったのだろう。切腹の作法も知らないと吹っかけられただけで実際にそれをやってのけようとする彼なのだから、そんな死に損なった自分を仮にも女である私に見られるのは死ぬよりも恥ずべきことだったのかもしれない。 けれど彼の口から出てきたのは、私が思っていた内容と相違する。 「好きな女の前で、あんな格好悪い姿を見せ付けてどうしていいか分からなくなった。」 一瞬鼓動がなった。でも冷静に考えて、それが私ではない他の女を指しているのだと思い直して、落ち着かせた。落ち着かせたところで、落ち着きはしないのだけれども。 そんな私を見て左之が笑う。少し、照れくさそうなかんばせを浮かべて。 「お前の話だ、。」 「………理解に苦しむ。」 「まあ、昔の俺だったらこうも素直には言えてなかっただろうけどな。」 聞いているだけのこちらが恥ずかしくなるまでの、直球な言葉に対して返事に困っていた。ここで嬉しいと両手をあげて気持ちを言葉にするのも違うと思うし、だからと意って否定する意味もない。何より私自身、彼のその言葉に嫌な気がしていないからだ。 不思議に思う気持ち、疑う気持ちがあるにしろ何より私の心は弾んでいた。幸せだった伊予での過去の生活を思い返しても、心臓がここまで脈を打つほどまでに何かに胸を高鳴らせたことはなかった。 「お前に将来の夢を話したのだって、お前に向けて言ったつもりだったから笑えるだろ。」 「……何それ。」 「餓鬼だったんだよ。それで伝わってると思ってた。」 思考回路が停止する。彼の言っていることを理解するまで、もう少しだけ時間を要しそうだ。未だ嘗て想像にすらした事のない彼の想いに、うまく言葉が出てこない。素直に嬉しいと言えることが出来たのならすぐに解決できる話なのだろうけれど私にはそれだって出来ない。 どうしようもなく優しく私を見る左之に、泣きそうになった。 まだまだ大人になりきれて居なかったあの頃の左之の想いを知って、得体も知れない気持ちに陥った。泣いたりなんてしたら、してもいない勝負に負けた気がするから意地でも涙なんてこぼさないけれど。必死で堪えた。 「伊予に帰る勇気もなくてな。」 「左之の意気地なし。」 「そうだな。本当に、そうだと思う。」 「…否定しなよ。昔みたいにムキになって。」 「泣きそうな女の前でそんな事言えるかよ。」 それを合図とでも言わんばかりに、私の頭上にはふわりと大きな手が宛がわれる。酷く懐かしいようでいて、私の知らない暖かい手。昔の左之と今の左之を重ね合わせて、ついに雫が走った。 「泣くなよ。」 「泣いてなんて、ない。」 「俺も大人になったんだ。お前も少しは大人になれよ。」 本当にその通りだ。私は今も尚、大人になれていない。彼が伊予にいた時から何も成長していない。後退していることはあるかもしれないけれど、本当に学びのない人間だとつくづく思う。こんなにも目の前に、大人になった彼を映し出して著しくそう感じた。 「…外でたら、大人になる。」 この場で彼と対面にいると、昔の強がりな私から変わることなんて出来ないと思った。素直じゃない自分を少し憎みながらも、左之が言った言葉を思い返す。人間そうも性格や性分を変えられるものではないと。そう言い聞かせて気を張った。そもそも性分なんて、変えられるものであればそれは性分とは言わないのだから。取り合えず御託を並べて自分を落ち着かせた。 「じゃあ、帰るか。」 そう言って、私たちは店を出た。 まだ冷静さに欠いている私は、ご馳走様の一言を紡げない。先ほどの想像にもし得ない彼の言葉にまだ思考が追いついていなかった。 彼はそんな私を見て苦い笑みを浮かべる。 「外に出たら大人になるんじゃなかったのか。」 「大人、だよ。充分ね。」 「まだベソかいててよく言う。」 言われて目元を拭う。拭って、それが彼の悪戯だと気づく。動揺している私を、からかっている。不意に冷静さが蘇り、頭の回転が速くなる。腹が立つと、そんな事を思いつつ私も彼に悪戯を仕掛けてみようと考え付く。 「私が京に出てきた理由、聞きたい?」 少し奇妙に思いながらも、彼は首を縦に振った。掛かったと、私は喜びに唇を動かす。 「京に来れば、左之に会えるんじゃないかって思った。」 それは後からつけた理由でしかなかったけれど、彼をあっと言わせられただろうか。今日は左之に言われっぱなしだった。最後くらい、私も悪があきしてをみてもいいだろう。たった一つの、小さな嘘から出た誠を。 「駆け引きが出来るようになったとはな。」 「…左之だって。」 しかけておいて、結局私は負けてしまう。再び視界が滲んで、歪む。今日くらいは強がらず、自分の感情の赴くままに動いてみるのもいいかもしれない。柄にもなくそんな事を思った。 逞しい彼の胸板に、どきりと胸が鳴る。 自分自身が求めていたものが何であったのかを思い知った。 「酒に助けられたかも知れないな。」 そう言って易しく私を抱きとめる彼に、どうしようもなく胸が熱くなる。恋がどういうものであったのか、この時初めて知ることとなった。伊予に共に居た頃、私が彼に抱いていた感情が恋心であったのだと、確信した。 大人になった魅力的な彼にどうしようもなく恋焦がれながら、昔のやんちゃな彼を思い出してどうしようもなく愛しく感じてそれを胸の中に閉まった。 「…俺の夢も叶う日が、いつか来るかもしれない。」 物語は、再び動き出した。 建前と本音 -完- |