 「お前と居ると、居心地がええんじゃ。」 私にとって、この言葉はさして記憶するほどの事ではなかった。確かに仁王の隣は、悪くない。その程度にしか考えていなかった私にとって、その言葉一つで何かがどうなると言う程に、彼に恋焦がれていた訳ではなかった。 強いて言えば、彼氏にしても悪くはないと思ったのだ。昔からの友人であり、気心の知れている仁王であれば、そうなる事も悪くないと、そんな安易な考えだったのかもしれない。年頃の人間というものは、やたらとパートナーを欲しがるものだ。私も俄かなミーハーに乗っかるほどに、年相応な年頃だったのだろう。 決定的な言葉もなく、私は仁王の隣にいる事を選んだ。何も申し分がない仁王の隣を選んだのだ。きっと長続きはしないのだろうという、淡い考えを留めながら。 時は、順を追って過ぎていく。 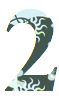 大学生になった春、私は一人暮らしを始めた。学校の距離的にいえば一人暮らしをする必要など、何処にもなかったけれど、そうすることで、まっさらになって人生を一からリセット出来るんじゃないかという安易な考えからの行動だった。そうすれば仁王とも会いやすくなるだろう、そんな小さな思いもあった。けれど、彼も何故か一人暮らしを始めた。まるで、私と同じように。 「何食べる?」 「そうじゃの。なんじゃろなあ。」 食にあまり関心のない彼は、いつだって曖昧な言葉のままで、的確な何かを伝えようとしない。けれど、私はこんな会話も嫌いじゃなかった。強いて言えば、私も何処か彼の様な要素を多分に持っているからなのだろう。きっと、私達は似ていた。好きというよりは、本当に居心地がいいから傍にいるような、そんな言葉の方がよっぽど正しく思えた。 結局、私はほとんど家に帰らない生活を送っていた。自分をまっさらにしたくて借りた部屋も、引っ越した時のまま、段ボールが無造作に転がっている。たまに必要なものを取りに帰るくらいしかないあの家は、私にとって何の感情も齎さない。 「家引き払わんの?」 「うん。親に同棲してるってバレてもまずいし。それに友達呼ばれたら私行くとこないし。」 「友達って言ってもほとんどが青葉の知り合いじゃろう。」 「ああ、まあ確かにそうかも。」 起きて、学校に行って、テニス部の人間とそれなりに交流して、仁王とまた家に帰る。それなりに幸せで、傍から見た私は酷く充実しているだろう。 学校が落ちつくと、バイトを始めた。仁王が先に見つけたバイト先で、私も働く。家でも、学校でも、仕事でも、何処を見ても私の隣には仁王しか居なくなった。次第に、彼しか私の周りに居ないように思えてきた。大学二年の、春。 彼と付き合うまでは、独占欲なんて言葉、考えた事もなかった私は、次第にその欲望に渦巻かれていった。 それなりに友達と遊んで、時には一人の時間があって、部活もして、仁王と付き合うまでの私は、仁王と過ごす以外の時間を持っていた。けれど今、私にはそれがない。そんな私に、今、彼が居なくなったらと思うと身の毛がよだつ程にゾっと震えるような気がした。世界が、変わってしまった。 「昔、雅治が私と似てるって言ったの、覚えてる?」 付き合うきっかけになったあの言葉を、今改めて思い出した。あの頃は、彼に賛同したその意見にさえ、今の私は頷く事が出来ない。 「なんじゃ。突然。」 「やっぱり似てないなって、そう思ったから。」 「例えば?」 一度、本音を吐きだそうとしたけれど、口を閉ざした。似ているというその一点から始まった私達にとって、その唯一の繋がりが途切れた時、全てが無に帰してしまうのではないかと思ったから。彼がそう思ってくれているのであれば、それでいいと言い聞かせた。 「何でもない。やっぱり似てるや、すごく。」 そう言えば、彼は「そうか。」とだけ言って、テレビのリモコンを回した。 やっぱり彼と、私は、似ていない。私だけが、依存している。きっと仁王は私が居なくても生きていけるだろうけれど、私はそうじゃない。それが、私達のれっきとした違いだった。彼の不安そうなかんばせを、私は一度たりとも目にした事がなかった。それが逆に、私を不安へと誘っていく。 「…なんじゃ、そん顔は。」 「ううん。私には不相応な幸せだなと思って。」 「謙虚な奴。」 「そうかもね。」 適当に言えば、目があって、そっと肩を抱き寄せられた。昔は、これが堪らなく心地よかったけれど、それを今は思いだす事が出来ない。彼が近づけば近づくほどに、私の心はどんどんと狭くなり、息苦しさを覚えた。 死に物狂いで、そんな感情を薙ぎ払って、私は彼の背に手を回した。  大学生活も折り返しに差し掛かった頃、私は初めて、主の居ない家で、一人の時間を過ごしていた。ゼミの合宿があると、さも面倒くさそうに背中を丸めていた彼を最後に見たのは、もう二日も前の事だった。私は、久しぶりに与えられた一人の時間を、完全に持て余していた。昔の私は、こんな時は何をしていたのだろうか。そんな事だけを考えて過ぎて行く時間は、酷く重たく、長く感じられた。 久しく帰っていなかった実家に帰ると、家族皆で旅行に行っているらしく、そこにあったのは彼の家と何も変わらない、静けさだった。押したチャイムに反応しない我が家の前で突っ立っている私に、近所の世話好きな叔母さんが話しかけた。そして私は、その事を知るに至った。急に、自分の居場所が、何処にもない様な気に陥った。 辛うじて持っていた合鍵で戸を開けると、そこにはあまり懐かしみのない我が家があった。まるで、私が知らない所に来たかのような、酷く歓迎されていないような気がした。私が知っていた頃の我が家とは、何処か少し変わって見えた。私の知らない所で、世界は変わっていた。いや、きっと、私の世界が変わったのだ。私の世界は、いつの間にか、私と仁王の二人ぼっちになっていた。 結局何もせずに実家を出て、いつぶりになるかも分からない、本当の我が家に帰ってきた。あの頃、期待に満ち溢れて借りたこの部屋に、私は帰ってきた。入りきらんばかりに溢れたポストをこじ開けて、両手が塞がったまま私は戸をあける。目の前には、引っ越した頃の何も変わらない、段ボールだらけの我が家があった。 女らしくなろうと、買い揃えたキッチン用品も、一度すら使われる事無く寂しく飾られていた。スーパーの安売りでまとめ買いをした、無意味なトイレットペーパーの束が、転がっていた。 一度たりとも鳴った事のない、ベルが響いて、私は驚きながらも、足音を立てないように覗き穴に視点を合わす。 「……何してるの。」 「そげな言い方はないじゃろ。これでも心配したんじゃけどな。」 取りあえず、仁王を部屋にあげて、二人して座った。コーヒーを入れようと、新品のやかんに水を入れると、思ったよりも早く、ピュウと音が鳴った。 「ねえ。」 「どうした。」 「このトイレットペーパー、どう思う?」 ロールが束になっているそれを指さすと、当然のように彼は首をかしげた。きっと、私も同じ事をされたら、同じ反応をするだろうと思いながらも。 「私ね、これは私が幸せだったっていう証だと思うの。」 「…ほう。」 この家を忘れるほどに、きっと私は彼に夢中になっていた。いつの間にか、私には仁王しかいなくなっていた。だからこそ、私は表現しようもないほどに、苦しいのだろう。 「やっぱり私達は似てないよ。私は、雅治ほど強くない。」 私が居なくても何でも出来てしまう彼は、私とは違う。きっと、付き合ってから初めての、私の本音だった。けれど、それをまるで間違いだとでも言いたげに、彼は小さく笑った。 「やっぱり似とる。俺と青葉は、そっくりじゃ。」 「どこが。」 「気が付いたら、二人ぼっちだって所かの。違うとすれば、俺が一人ぼっちから二人ぼっちになった事じゃろうなあ。青葉は、二人ぼっちになってしまった、って感じなんやろうが。」 初めて、彼の本音を聞いたような気がした。これだけ長い間一緒に居ながらも、きっとお互いの本音を、私達は一度たりとも交わした事はなかったのだろう。それもそれで、何だか可笑しくて、今まで思っていた事がずっと軽く感じられた。本当に、私達は、似ていたのかもしれない。 「だから、今更手放すつもりはないぜよ。」 追い詰められないと、きっと私達は本音を言えない。そんなどうしようもない所が、酷く似ているらしい。 「…なんか、幸せって怖い。いつか壊れそうだから。」 「同感じゃ。」 こんな幸せを知らなければ、きっと私は得体の知れない恐怖と、背中あわせに生きていく事もなかっただろうに。幸せを、素直に幸せと受け止められない不幸体質を恨みながらも、やっぱり彼の隣は恐怖と共に、心地よかった。私達の世界は、どうしようもなく、狭い。 未知と、幸せは、似ている。そう考えてしまう私達は、やっぱり、似ている。一生こんな感情と戦うと思うと、ゾっとする。けれど、私はそれ以上に、この男と離れる事を恐怖に思うのだろうから、どうしようもない。恐怖と隣合わせの幸せを教えてくれた彼と、離れる事などきっと出来ないのだろう。知らず知らずに、私は彼に依存しきっていた。世界が、広がることなく。 別れた方が、きっと楽であるはずなのに、私達はやはり、その選択肢を選ぶ事は出来ない。 「ああ。幸せになりたいなあ。」 「あほう。今、幸せなんじゃろ。」 ぽつりと、欲望が口走った。けれど、彼の言っている事は正しい。けれど、きっと、私が言ったその言葉も、やっぱり正しい。 「あ、そうだった。」 幸せを恐怖としか捉えられない私達は、変わっている。きっと、普通の感覚ではないのだろう。傍に居たい人が傍に居て感じる幸福と、恐怖が、同居するその感情に名前はないのだろうか。きっと私達には、天変地異が起こったのだろう。そう、思った。
|
