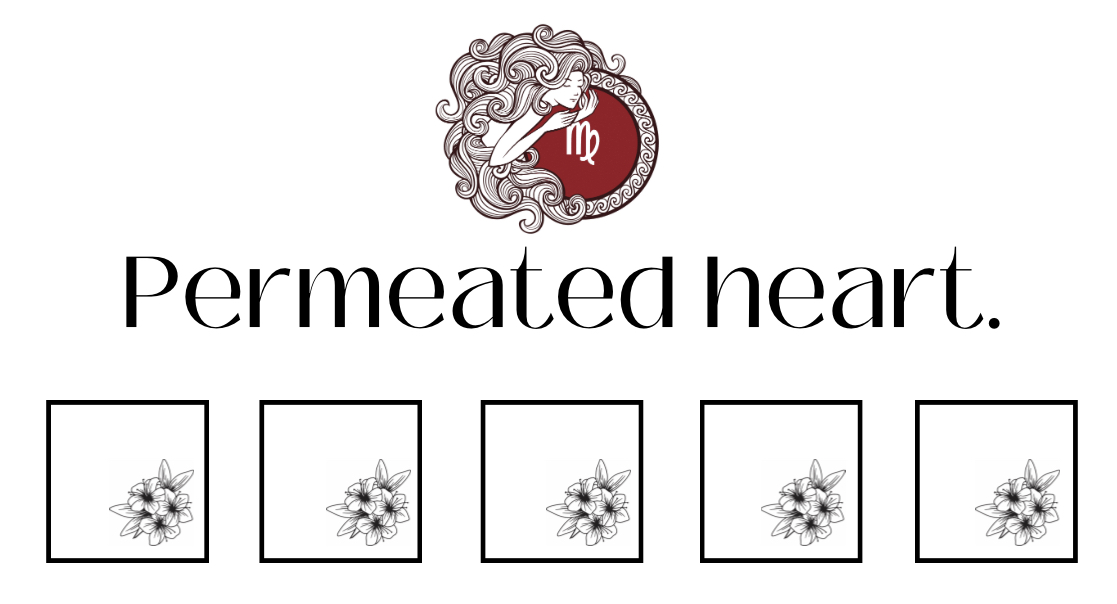 六年ぶりに再会した、春のこと。 幼馴染だったリョータと再会した。私が大学で上京をする事になり、引っ越しを手伝ってもらったのがきっかけだ。お互い偶然を装った、ほとんど必然的だったその再会は私とリョータを繋ぐ関係性を真新しいものへと変えた。どうやら、私はリョータの彼女になったらしい。 幼馴染という長い間継続された私たちの肩書きと、中学から高校卒業までという長い期間離れていたからか、いまいち距離の詰め方がよく分からない。会うのにだっていちいち理由が必要で、会いたいからという本音以外の建前を必死になって探している自分がいた。 先日お互いの連絡先を交換して、そこからほとんど毎日メッセージのやり取りをしているけれど中身を読み返してみると、これが本当に花も恥じらう女子大生になろうとしている恋する乙女の文面か今一度わからなくなって頭を捻る。 起床の挨拶、天気の話、昼ごはんの写真………仲睦まじい老夫婦のような内容しか出てこない。そろそろゲートボールにハマっていますという自己紹介が始まったらどうしようかと自分でも心配になるレベルだ。こういう時、一般的にどんな会話をするのが正解なんだろうか。分からないけれど、ゲートボールの話じゃない事はかろうじて分かっている。 先日引っ越しを終えた私は、細かい家具を買い揃えたいという会うには適当なそんな理由を思いついて、リョータに今までと少し文面を変えて誘いの一文を差し込んだ。 “拝啓、宮城リョータ様。お元気ですか?沖縄と違って東京の春は随分と寒いのですね。ところで、私の部屋には必要最低限の家具家電しかない訳ですが、もし良ければ一緒に買い物へ出かけませんか?PS.お返事はイエスの一択でお願いします。メンタルは割と弱い方です。” 送信して読み直して、自分の情緒が著しく乱れているのが文章全体に蔓延っていて泣きたくなった。数時間前に茶色い唐揚げが沢山映った映えの意識など皆無な写真を送った後に、このテイストの文面だ。スマホを乗っ取られたのかと疑うのが最早正しいのかもしれない。 暫くしてリョータから電話がかかってきて、随分といろんな事を突っ込まれた気がするけれど、あまりよく覚えていない。覚えているのは、明後日の土曜日、横浜の少し外れにある大型ショッピングセンターに十時半という約束だけだった。 初めてスマホ越しに聞いたリョータからの電話は、デートの約束を取り付ける内容だった。通話をオフにしてから、じんわりとなんとも言えない気持ちが充満した。 とてもとても淡いデート前のやり取りを回想していた訳だが、現実というものは想像以上にハードで、想像通りにいかないものらしい。十時半、私は某ショッピングセンターに到着するとすぐにリョータと落ち合った。 「見てリョータ、これ可愛い。」 「どこに置くんだよ、邪魔でしょ。」 「じゃあこっち!これも可愛い。」 「機能性考えたらこっちの方がいいだろ。」 さっきからこの調子だ。私の目に入った私好みの家具は悉くバッサリとリョータに切り捨てられている。買い物を始めてから三十分、私が可愛いという言葉を発したのは実に十八回。リョータが私の可愛いに斬撃を入れたのが十九回。なぜか、リョータの方が一回分多い。同じ商品に、二度斬撃を入れられたという事だ。私の買い物籠にはまだ何も入っていない。 「……もしかしなくても喧嘩売ってますか?」 「は?全然売ってない。」 「一億回くらい否定されてる気がするんだけど。」 「被害妄想激しすぎだろ。」 「可愛いもの部屋に置きたい乙女心じゃん。」 「ゴミになるんじゃ勿体ないないだろ?」 付き合ってから初めてのデートなのに、このやりとりは一体なんだ。幼馴染として存分に心を許しているから、という前提があるのは一万歩譲って分かる。少し譲歩しすぎたかもしれない。 初めてのデートだからと舞い上がっていた自分を恨めしく思う程、甘さの欠片もありはしない。私と、私の家の事を本気で思ってこその言葉なのかもしれないけれどこうまで否定されると悲しさを通り越して腹が立つ。 「そんなデリカシーないとは思わなかった。」 「お前の性格知ってっから言ってんじゃん。」 「……墓穴掘ってる。」 「……今のは悪い。ごめん。」 籠を元あった場所へと戻す私に、ようやく焦り始めたリョータが腕を掴んでくる。もう墓穴を掘りまくっているので、これ以上は墓穴を掘らないでほしい。その腕を掴んでどこに行くのか見ていると、エスカレーターを登っていく。フードコートが見えて、私は席に座らされる。何か説明くらいは欲しいものだし、何を食べたいかくらい聞いてくれてもいいのに。 家族連れやカップルで溢れている建物内で、私はぽつんと窓の外を見る。快晴と呼べるカっと太陽が照っているいい天気だ。それと対比するように、自分の感情が晴れずにもやもやする。 「ん、食べよ。」 「……お腹すいたとか言ってない。」 「食べて機嫌なおしてよ。」 「食べれば機嫌治るほどちょろくない。」 「いいから食えって。」 目の前には美味しそうな茶色い物体。すんすんとほんの少し鼻を動かしてみると、甘酸っぱい匂いが鼻を掠めていく。多分、間違いなく、私が好きそうなその茶色い球体を眺める。毎日映えもしない茶色い食べ物ばかりリョータに共有していたせいもあってか、私の好みは丸分かりらしい。正確に言えば、子どもの時から好みが変わっていないのがバレているのだろうと思う。 「あ〜ってしてみ?」 「バカップルみたいじゃん。」 「バカは置いといてカップルだろ。」 「どうかな。」 「顔赤くするくらいなら認めとけって。」 「…むかつく。」 美味しいものに罪はないし、私は滅法自分の空腹に弱い。癪だと思いながらも、控えめに口を開けるとフォークに刺さったミートボールが運ばれてきて、想像通りの少し甘酸っぱいちょうどいい味が広がった。リョータは「ふはっ……」と一度可笑しくて笑っていたけれど、私がじとっとした目で見るとその笑いを打ち消すように自分の口にもミートボールを運んで相殺した。 「もっと食う?」 「………うん。」 「雛鳥の餌やりしてるみて〜。」 「墓穴掘るの好きなの?」 「普通に可愛いって言ってんじゃんか。」 ぶっきら棒な癖に、たまに不意をついてこんな事を言ってくる。沖縄時代のリョータと今のリョータは明確にそこが違う。私が油断した瞬間を狙うようにして、私を刺しにくるのだ。不意打ちというものは心臓に悪いので、いっその事心臓ごと取り外してしまいたい。破壊力が凄まじい。 「うまい?」 「……うまい。」 「肉の塊好きだったもんな、昔から。」 「墓穴用のスコップ買っていけば?」 「怒んなって。」 リョータがくしゃっと笑うから、なんだか私まで可笑しくなってしまってつられて笑えてくるから不思議だ。ちょろくないと言いながらも、こんなにちょろい女もそうそういないだろうと思う。こんなに楽しそうに笑うリョータを見て、全てが相殺されてしまうのだから改めてリョータの存在が自分の中でどれ程に大きいものなのかを思い知らされる。 ミートボールと、つい最近付き合ってばかりの彼氏の無邪気な笑顔で些か機嫌を取り戻したちょろい私は、改めて宮城リョータという男にときめきを覚える事になった。 「クッションくらいなら邪魔になんないだろ?」 それは私が可愛いと言っていたもので、リョータが自分の財布からお金を出して買ってくれた本日の唯一の戦利品となった。 バスと電車を乗り継いで最寄りの駅まで戻ってきた。私とリョータが無事家に着いた頃にはすっかりと夕方になっていて、改めて時間の流れの早さに驚かされる。私はリョータに買ってもらったクッションを抱き抱えながら、それをどこに置こうか狭い部屋をあちこちウロウロとしていた。 「そんなに嬉しいんだ?」 「え、うん。だって可愛いじゃん。」 「ふうん、やっぱちょろい。」 「ちょろくていいもん、実際ちょろいし。」 ちょろいというのは最早自分でも認識している事なので否定もしなければ、カチンと何かの逆鱗に触れる事だってない。人間、なんでも認めてしまえば案外楽になるものらしい。冷静に考えて、彼女という生き物なんてちょろい方が可愛いに決まっているのだから。今日、私が気づいた事実だ。このあざとさは、きっとまだリョータにはバレていない。 「あ、ちょっとそこ私の特等席。」 「いや、来客優先っしょ。」 「リョータはこたつにでも入っとけばいいじゃん。」 「普通にあっちいだろ。」 二人分に満たない私のソファーで、椅子とりゲームのように私とリョータが場所の取り合いを繰り広げる。ぐっと力を込めてリョータにタックルをかましてみると「…うぉ」そう言って私を抱き抱えてそのまま地面へと転がった。まさか巻き添えを食うとは夢にも思わない。 「んだよ、ガキか。」 「六年分の青春を取り戻してるんだよ。」 「しょうもねえ。」 「そんな事言って、顔めっちゃ笑ってる。」 「そっちもそうじゃん。」 下敷きになっているリョータの右手が私の首筋に絡んでくる。ついさっきまでの幼く年相応なくしゃっとした笑ったかんばせから色を変えて、急に色素の薄い茶色い瞳が私を捉えてくる。ゆっくりと、少しだけ上半身を浮かせたリョータに引き寄せられた。 思っていた以上に、柔らかくて、その感触をもう一度確かめた。 急に体を起こしたリョータに、私もバランスを崩して二人して目線が交わって妙な気まずさが漂っていた。もう一度、とそんなシチュエーションに持っていく為には私たちにはまだまだ経験が足りなくて、私は畏まってリョータの前で正座座りになった。 「あっち向いてみ。」 「…ん?」 私は言われた通りくるりとリョータに背を向けてみる。暫くすると後ろから両手が伸びてきて、その両手が私を狭いソファーの上に乗せた。狭いソファーを二人で活用する、最大限の使い方なのかもしれない。リョータはソファーに腰掛けて、私を挟み込んで後ろから手を回した。 「これで座れるじゃん。」 「……そうだね。」 先ほどの一連の流れで床に転がってしまったクッションを拾い上げて、これでもかと抱き抱えた。これは二人でソファーを有効活用する画期的な方法なのかもしれないし、お互いこの火照りを今は見せたくないという事なのかもしれない。
透過された心臓 |