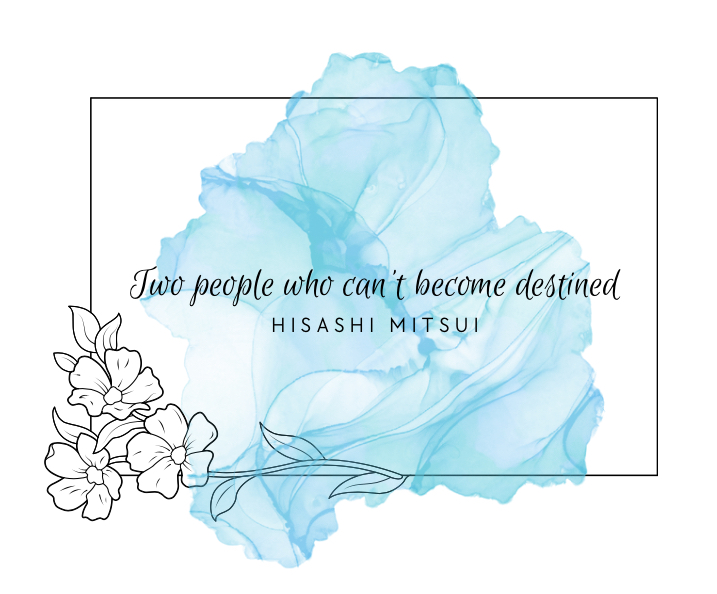 運命なんて、きっと存在しない。そう思っていた私の前に、恐らく運命の人は存在していた。それは多分、リョータだったんじゃないかと私は思っている。そして、リョータも同じことをかつて私に言ってくれた。 「さ〜、ダンナの結婚式いく?」 「もちろん。だって嫁紹介したの私な訳だしね。」 「そうだったわ、じゃあ久しぶりに会えんな。」 「言うて先々週飲んだじゃん。」 電話の向こうのリョータは「そうだっけか?」と言ったかと思えば、また来週と一方的に会話を終わらせた。 事前に告知しておくが、私とリョータの会話から話が始まっているだけで、これは私とリョータの恋の話じゃない。運命の人だと紹介したかと思えば、恋じゃないと矛盾した事を言っていることは重々承知の上だ。 会話で分かる通り、私とリョータはとてもフランクな友人関係だ。高校を卒業し、それぞれ別の大学へと進学して、社会人になった今も頻繁に顔を合わせる友人でしかない。 男女に友情など存在しないと周りから言われる事はあったが、愛情よりも友情を優先させたのは私とリョータの共通の決断だった。かつて、私たちはほんの一瞬ばかり付き合っていた事がある。高校三年の受験が終わった時、進学先の違う私たちは寂しさから付き合う事にした。嘘のような本当の話で、付き合ったその日、私たちは別れた。ほんの一瞬とも言えない、ほぼなかったような事実だ。 今みたいに毎日クラスで顔をあわせて会えなくなるんだねとなんとなく二人で話している間に私が泣いて、その後リョータもつられるようにして泣いた。離れたくないねって言えば、リョータが付き合おうと言った。返事は当然、イエスの一択だ。 ならば何故そんな運命的な二人が僅か一日で別れたのか、誰にもした事のないその話を今ここでしてみようと思う。これはリョータと私の恋の話じゃないのに? 愛情には、高確率でいつか終わりが来る。 勢いのまま、衝動的にお互いキスをしそうになって、私がリョータの学ランを握りしめてそれを阻止した。一度キスなんてしてしまったら、もっと好きになるからだ。普通ならそれで何も問題はないだろう。ここでリョータをもっと好きになったら、もう戻ることなんてできる筈がなかった。 友情には永遠があるのかと言えばそうでもない。時に些細なことがきっかけで終わることもあるし、何がきっかけでそうなるかなんてわからない。始まるという事は、同時に終わる事でもあると若干十八歳の私はその一瞬でそれを頭に過らせたのだ。 友情ではなく、愛情を優先した時の事を考えた。愛情を優先して、愛情が終わった時の事を考えた。愛情が終わった先に愛情がなければ、友情など存在するはずもない。だから、私は友情を優先した。つまりは、そういうこと。 泣きながらリョータにそれを話した時、リョータもやっぱり泣きながら賛同した。この一瞬の、たった数分の付き合いで私たちは恋人関係を終わらせた。始まりも、終わりも、ずっと泣きっぱなしだった。 そして、今も良好な友情関係を築き上げている。それだけの事。 運命とは、必ずしも恋人になったり、結婚をしたり、愛し合う事だけじゃないと私はそう思っている。だからやっぱり今も、私にとってリョータは運命の人だし、手前味噌だとしても、リョータにとっても同様なんだろうと思う。 大学に入ってから出来た友人を、高校時代からある程度交流のあった赤木さんに紹介したのは他でもないこの私だ。純粋無垢なその友人には幸せになって欲しかったし、赤木さんならそうしてくれるんじゃないかと思っただけのこと。案の定、私のお節介は正解だった事が今ここで、証明されている。 私は新婦側の友人席で、リョータは新郎側の友人席だ。披露宴が終わって二次会いく前には一緒に合流しようねと声をかけて、私たちは静かに二人の馴れ初めを綴った映像を視聴している。 まだ披露宴も序盤だ。いい映像でとても感動的だ。それが両人共に知人である私にとっては、より一層込み上げてくるものがある。そんな私を差し置いて、リョータのテーブルの方が騒がしくて目を向けると、懐かしい男が視界に映った。 三井さんだ。男泣きをしている。 披露宴の序盤でこの調子。最後まで見届けられるんだろうか。見ているこちらがそんな心配をしてしまうくらい、ウゥ…と音声付きで泣いている。「アンタみっともないから早くハンカチで拭いて!」リョータにハンカチを渡されて、そのハンカチで鼻をかんで拳を喰らっていた。私はというと、まるで映像に集中できない。多分私だけじゃない筈だろうけれど。 こんなに号泣している男が何故ハンカチを持ってきていないんだろうか。この歳にもなって自分の特性を理解していないのか。けれど、なんとなく私には今目の前に映るこの一連の流れが、事前に予測できていたような気がするのだ。 三井さんは、見かけによらず熱い男だったりする。 元不良のくせに、最早その面影がないほどに真面目な男だ。バスケ部に戻ってからそれはすぐに分かった。とても真摯に向き合っていたのがバスケ部でもない私にもよく分かる。バスケ以外のことに関してはややデリカシーに欠けているのも、三井寿を語る上で忘れてはいけない。 結局三井さんの男泣きを見ていたら、披露宴はほとんど終わっていた。お色直しで席を外していたタイミングで、湘北バスケ部の面々が一人残されていた赤木さんに声をかけていて、案の定そこでも三井さんは拳を喰らっていた。 平和と言えば平和で、なんとなく想像通りの結婚式は終わった。途中見逃した場面はあったような気がするけれど、想像通りとは言いながらもとても素敵でいい結婚式だった。 私はそこからリョータと合流して、二次会までの時間を潰す。どこ行く?なんて話をしていたら、まだ余韻に浸っている三井さんも何故か一緒についてきた。普通に考えて小暮さんと一緒にいればいいのに、何故かまだ時折声を詰まらせ泣いている。重症だ。 「ちょっと三井サンあんた俺らと一緒にくるつもり?」 「…んだよ、悪いのかよ。」 「悪いとかじゃなくてアンタいるとシケるでしょ。」 「お前の性格その眉毛以上にひん曲がってんな。」 「うるさいな〜、つかアンタのせいで俺までダンナに殴られたんだからな!ほんっと、めんどくさい。」 結局三井さんはぶつぶつ文句を言いながら、たまに思い出しているのか声を詰まらせて泣いて、そして私たちについて来た。情緒が忙しそうだ。 リョータとゆっくり話そうと思ってたけど、多分二人の漫才のような掛け合いを見ていたら二次会の時間なんてあっという間に来てしまうだろう。いい退屈凌ぎにはなるのかもしれない。リョータはとても不服そうだけど。 某イタリアンファミリーレストランは、私とリョータが学生の頃から今も尚よく足を運ぶ店だ。 私には四つほど好きなメニューがあって、その時々の気分で注文を決める。そして、その四つの中からリョータも一つ選んで、当たり前のようにシェアする。もうそんな行動に何も違和感はない。特別お互い確認する事なく注文して、運ばれてきて皿を二枚並べて、交互に食べていく。 「なに、温泉卵なしにしたの?」 「うん。披露宴でも卵の料理いくつかあったじゃん。」 「あ〜、確かに。あれ美味かった。」 私たちが当たり前のようにお互いシェアしているその光景に、三井さんは不思議なものを見るような眼差しを向けてくる。途中から三井さんがいたのを半分忘れていた。気を取り直して、こほんと一度咳をはらってみる。 「えっと、三井さんも一緒に食べます?」 「いや、いい………てかお前ら付き合ってんの?」 まったくもってご尤もな意見だろうと思う。自覚がない訳じゃない。私も、リョータも。ただ、それを聞いてきた相手が三井さんだったのがリョータにとっては特別だったのかもしれない。今は和解していい関係である二人も、かつては因縁なる関係性だったのだから。 「付き合ってないっすよ、一応元カノだけど。」 「は?え、まじか。」 「別に嘘ついてもしょうがねえでしょ。」 私たち以外に、付き合っていた事実を知っている人間はいない。誰にも話した事はなかったし、二人で誰にも話さないでおこうと決めていたからだ。付き合っていないと否定するのも違うと思ったし、事実を捻じ曲げるのも違う。でも、それは私たちだけが知っていればいいことだからと着地していた筈だった。 「一回は俺のツバついてんの!変な気起こすなよ三井サン。」 「別にそう言うつもりで聞いたんじゃねえよ!」 私の入る隙なんて微塵にも用意はされていない。私の話をしている筈なのに、おかしくないだろうか。このやり取りだけを見ていれば、リョータの運命の相手は私じゃなくて三井さんなんじゃないだろうかなんて思ってしまう。やっぱり運命って、恋や愛だけじゃないのかもしれない。 「も!笑い事じゃねえし!」 こうして、運命の人であるリョータと何気ない日常に笑っていられる私は、やっぱり正しい道を選択したんだと今改めてそう思った。私に必要なのは恋という駆け引きで脆くなる関係性よりも、たった一人しかいない宮城リョータという存在そのものの方がよっぽど大切だ。 結局私の想像通り、二次会までの時間はあっという間に過ぎ去っていった。昔から思っていたけれど、リョータと三井さんは仲がいいのか悪いのかよく分からない。まあ、確実に悪くはないのだろうけれど。不思議な関係性だ。やっぱりこれも運命なんだろうか。 そこまでは概ね私の想定通りに事は進んでいた。未来を予習してきたという訳でもないのに、割と自分でも驚くほど正確に。三井さんが、私とリョータについてくるのもいくつか想定していたパターンの一つだった。何も驚かない。寧ろ、一番その確率が高いと読んでいた。 そんな私に、今日初めてとなる想定外の出来事が起こった。 披露宴で男泣きをし、リョータに差し出された他所行きの綺麗なハンカチで鼻をかんで殴られている三井さんを難なく想像できた私に?そんな事なんてあるだろうか。私自身が多分、一番驚いている。それは前触れなく突然やってきた。 「リョータもう帰るの?」 「言ってなかったっけ。明日試合、バスケの。」 「え〜、全然聞いてないんだけど。」 「じゃあ言ってねえんだわ。で一緒に帰っとく?」 「う〜ん。」 だからどうって訳でもないのに、リョータが帰ると言うと少しだけ迷いが生じる。別にリョータが帰ったところで、周りは知り合いばかりだ。困ることなんて何もない。 大抵の場合、リョータにこう言われたら私も一緒に帰るだろう。高校生みたいに一緒に帰るその道すがらにドキドキしたい訳じゃないし、別にドキドキはしない。楽しいのは間違いないけれど。どことなく感性の似ているリョータがそう言うなら頃合いなのかもしれない、そんな事を漠然と思うくらいだ。 「残りたいんだろ?残りゃいーじゃん。」 結局感性が似ているからこそ、私が今何を考えているのかもリョータには簡単に分かるのだろうと思う。事実、私も同じようなことをリョータに言ったことがあるからだ。既視感を覚えるのは、きっとそれだろう。 「まあ、あんま飲み過ぎんなよ。」 「わかった。リョータ明日頑張ってね。」 「うん、ありがと。」 あまり感情が豊かな方ではない私が、唯一人の顔色を窺わずに済むのがリョータだ。別に、だから運命の相手だと思っている訳じゃない。もっと、もっと、そう思う要素なんて沢山ある。それに、大事なことは案外言葉で言い表せられない言語化不能なものなのかもしれない。 ぽん、と撫でる訳でもなくただ単に頭上に置かれたリョータの手に、無限の安堵を感じてしまう。だから、何も考えずに力を抜いて笑って「またね」と、そう言えるのだろう。 とてもいいムードを作り出して申し訳ない。 やっぱり私の運命の人はリョータなんだって事を話しているようにしか聞こえないだろうと思う。私が第三者なら、結局これは私とリョータの話じゃないか!と言うだろう。けれど忘れてはいけない、これはリョータとの恋の話ではない。それは冒頭で述べた通りだ。 そもそも、数十分前の話を少し思い出して欲しい。 想定外の事が起きたと言ったのを覚えているだろうか。私が驚いたのは、リョータのスケジュールに、という訳じゃない。もちろん知らなかったという事実はあったものの、そんな事生きてれば日常的にあるだろうし、わざわざ“想定外”と言うほどでもないだろう。問題は、リョータじゃない。私への想定外を齎しているのは、三井さんだ。 「三井さ〜ん、ねえってば!」 やっぱりあの時、リョータと一緒に帰っておくべきだったのかもしれない。完全に後悔している。 結婚式の二次会なんてそんなものなんだろうけど、みんな結構ぐちゃぐちゃに酔っ払う。自分が楽しむ事で精一杯だ。もう到底終電を気にしていないのか、誰も時計に目を向けない。私が純粋な気持ちで楽しめていたのは多分リョータが帰って三十分くらいまでだ。何度呼んでも、三井さんは目覚めない。 三井さんが酒に強いのかどうかは知らない。元不良のくせに謎に高いコミュニケーション能力で案外誰とでも打ち解けるのが早い三井さんが、今日は珍しく一人で静かに飲んでいた。よほど披露宴に感動したんだろうかとたまに横目でチラリと見てはいたけど、割と早い段階で寝潰れてしまった。 三井さんを起こしにかかっている途中で、周りは私たちを忘れたように各々終電に向かったり、三次会をやろうとふらふらと出ていく。状況は最悪だ。 三次会にいくグループに混じった訳でもなく、終電に飛び乗れる訳でもなく、結局私と三井さんだけがその場に取り残されている。捨て置いて帰ればまだ終電には間に合う。言うまでもないが、私にそんな鬼のようなメンタルは存在しない。百八十を超える大男を担ぎ、華奢なハイヒールで残り五分しか待ってくれない終電とバトルを挑む性格でもない。 一度バチンと頬と叩いてから、つねる。悪意はない。けれど覚えていることもないだろうからと随分派手にやったとは思う。ようやくボヤボヤしながら返事もなしにぼうっと目を覚ました。三井さん、そう呼んでも返事はなかったけど辛うじて目は薄ら開いている。 自分の肩に三井さんの大きく長い腕を枕のように巻き付けて立ち上がった。犬の散歩をしてるような気分だ。重いけど、まだ辛うじて足を動かしてくれているだけ最悪の状況は回避できている。最悪から数えて二番目の最悪くらいの状況だけど。 「三井さん、自我取り戻しません?」 「…………」 黙ってればイケメンなのに勿体無い。そう思ってたけど、黙っててもこの人はスーパースターには程遠い。黙ってても残念感はちゃんと存在している。お酒のせいだから不可抗力なんだろうけど。 このままの状態でタクシーに乗り込んでも三井さんが家に着くイメージはつかない。喋らない酔っぱらいとはそれ、すなわち限界突破。幸い明日は日曜日だ。ネオンが光る暗闇へと少し進むと、いかにもという紫色をしたライトが点っている建物があった。ため息をついて、目が合わないよう配慮されている閉鎖的な入り口へと足を踏み入れた。 あれだけ酔い潰れてた訳なのだから大層五月蝿いのかと思っていたが、予想に反してこんな所で三井さんのお育ちの良さを感じることになるとは夢にも思わなかった。 一度深く被せた布団はしっかりと被られていて、そして綺麗に目を閉じて時折耳を近づけると聞こえるくらいの音量ですぅすぅと息をしている。イビキの一つもない。これが育ちがいいのかどうかは知らないが、多分悪くはないだろう。すやすや眠っている三井さんの寝顔を見て、黙っていたらイケメンだった事を思い出した。何気にまつ毛も長い。 私はというと、二次会でついた色んな匂いに耐えかねて一度シャワーを浴びた。服は脱いでも、案外こういう時は髪にその場の匂いが染み込んで気になるものらしい。シャワーを終えて、起こしては悪いと最低限タオルで水気を取って、そのままそれを巻いてソファーで寝た。そして、ちょうど少しの肌寒さを覚えて起きたところだ。 「…ん、三井さん起きてたんだ。おはよう。」 目は開いてるみたいだけど、返事はない。三井さんも今起きてばっかりなんだろうか。その割には驚愕の顔でこちらを見ている。まぁ、多少は驚いても仕方ない状況だろうけれど、自分の酔い方を考えたらそこまで想定できない現実でもないだろうに。 「責任取らせてくれ!」 「いや、なんの話ですか。」 「俺と付き合えって言ってんだよ!」 「え?三井さん、やってないよ。」 「ば…!女がそんな言葉使うなよ!」 突然口を開いたかと思えば、これだ。全くもって意味がわからないし、私の言葉に対して過剰なまでに反応してくる。この人こんなに顔がいいのに、もしかして童貞なんだろうか。女という生き物に幻想を抱きすぎてはいないだろうか。 「やってないのに寧ろなんの責任で…?」 百歩譲って、酔っ払った三井さんが酒の勢いに任せて私を襲うなんてあり得ないことが事実あったのなら、さっきの言葉にも整合性がある。けれど、私はきちんと何もない事実を告げているのに、この反応だ。考え方が昭和?とにかく古風すぎる。 「女の後輩にこんな所連れて来させただけでも重大な責任だろうが。」 「は、はぁ…そうなんですね。それはどうも。」 何をそんなに気にしているんだろうか。このホテル代を私に払わせたことに対する罪悪感だろうか。そんなもの気にしなくても、請求するに決まってるのに。三井さんのことをよく知っている訳じゃないけれど、やたらとケジメをつける人だって事は知っている。バスケ部に戻ってきた時も、そうだった。 「…根本的に気になる事、聞いてもいいですか。」 「この際恥もねえし何でも聞けよ。」 「三井さんにとって、付き合うって感情ベースじゃないんだ?好きとか、嫌いとかさ。」 別に私は三井さんに襲われた訳でもないし、孕った訳でもないのに。単純に不思議だと思った。そんな責任の取り方、少なくとも私の周りでは聞いたことがない。そもそも、そんな罪悪感から付き合ってもお互い何もいいことなんてないのに。 「は?人間なんだから感情ベースに決まってんだろ。」 「そこは真面なんだ。じゃあ気使わなくていいですよ。」 また急に罰の悪そうな顔をする三井さんに、どこか内心ほっとしている自分がいた。この意味の分からない急展開に、少なからず私も心がついていかずに疲弊していたのかもしれない。気を遣ってもらうくらいにはただの顔見知りだし、気を遣われすぎると困るくらいの距離感だからだ。きっと、これでまた何かの飲み会で会ってもどうとでもなる。 「そういう感情がなかったら言ってねえって事。」 「本気で言ってます?二日酔いの幻覚じゃなくて。」 「…聞くなよ。てか言わせんな。」 多分昨日の酒は残っているんだろうけれど、それでも力強い三井さんの眼差しが刺さって、私まで変な気持ちになった。変な気持ちなっていいのか、ここはそういう場所なんだから。悪いのは私じゃないし、こんなところにいるからであって、やっぱり結局三井さんのせいだ。 「というか…、正確には思い出しちまった。」 この人、何言ってるんだろう。 「なんだよ、その虚無顔。」 「そういう仕様ですけど……」 多分三井さんも混乱してる筈だけど、私も相当混乱している。虚無顔になったのは、今のこの流れがいまいち掴みきれていないからだ。三井さんの二日酔いの幻覚じゃないなら、私の酒が残っているんだろうか。もしかしたらそうなのかもしれないし、そうである理由が欲しい。 「でもよく考えたらそれって三井さんに得しかない責任の取り方じゃなくないですか?」 私って可愛くないな、そういう自覚はある。人に自分そのものを見られるのは苦手だし、あまり深い付き合いをするのも苦手だ。だから私にはリョータがいて、それで十分だった筈だ。受け入れず拒絶するにしても、もう少し言い方ってもんはあるだろう。自覚がある分、私は今きっと余裕がないんだろうと思う。目一杯、平気なふりをするのは物心ついた時から私の癖だ。 「…そりゃそうだ。でも思い出しちまったんだよ。昔、お前が宮城の隣で笑ってた顔。俺には見せないその顔が羨ましくて、可愛いと思ってたんだなって。元カノだって聞いて、絶対に駄目だって思ってたら酒進んでたんだよ、悪かったな。」 この男、自分が今相当に恥ずかしい事を言った自覚はないのだろうか?二日酔いの幻覚じゃないかと聞いた時は聞くなよとほんのり恥ずかしそうにしていたくせに、このかなり年季のこもった壮大な愛の言霊に関しては、寧ろ冷静な顔をして言うものだから恐ろしい。なんなら、それくらい当然だろうの勢いなので、聞いているこっちが恥ずかしい。 「私にとってのメリットって何です?」 「…お前なぁ、性格バージョンアップしてね?」 「いや、聞かないといけないと思って。」 「あ〜、安定した収入、とか?」 「そうなの?ものすごく意外なんですけど。」 「心折ってくるなよ。」 そう言った後に、無理なら無理って早く言えよと、半分やけくそな三井さんが見えた。そこは、粘ってでも言ってくる訳じゃないんだ。炎の男とか呼ばれてるくせに。諦めの悪い男だと自認しているくせに。これくらいのことで、たった一回のラリーで終わってしまうんだ。 「可能性ゼロだったらこんな事聞いてないとか、そういう事思わないんですか?」 何か一つ、私にも理由を作らせてくれたらいいのに。物事の歪みに滑り込ませて、自責ではないとその穴に付け込もうとしているずるい大人でしかない私。それに対して、目の前のかつての先輩は誠実で、とても素直な感情を伝えてくれた。それだけで本当は十分なのに、そこに理由をつけたがる私はただの贅沢者なんだろう。 「…付き合いたい理由、聞いてないから。」 「お、おう…。」 そうだったっけ?と言いながら、慎重に言葉を選んでいるもんだから焦ったくなってこちらから仕掛けてやった。ちょっとぐらい私と同じ気持ちを味わえばいいと思う。 「ずいぶん積極的なんだな、お前……」 「そうしないと進展なさそうな三井さんが悪い。」 「大切にするには手順、大事だろうが。」 「態度と言葉が一致してないの、認識した方がいい。」 ベッドに膝をついて、これ見よがしに目を瞑ったのに、やっぱり私の想像通り感触はない。寧ろ、私のまだ乾ききっていない髪に完全に目が覚めたのか、めっちゃ冷てえじゃねえか!?と声をあげて風呂場にドライヤーを取りに走った。ムードの読めない男だ。でも、憎めもしない男だとも思う。 「なんでキス強請ってるのスルーするんです?」 「普通に寝起きで歯も磨いてねえし、酒残ってる。」 「じゃあ私が歯磨けばいい?」 「ちげえって、普通に考えて俺だろ。」 結局付き合ってくれと言われ、ラブホテルにいる私たちは何もなく終わった。けれど、多分付き合うことになったらしい。キスはしてくれなかったけれど、その代わりドライヤーで恐る恐るながら髪を乾かしてくれた。 「で、結局理由聞いてない。」 「お〜…明日言う。」 「月曜も会いたいなんて、完全にそれもう私の事好きなやつじゃん。」 私がその見え透いた確信へと触れる。少しくらいは照れ隠しに否定だったり、はぐらかしの言葉があると思っていたのに、続いたのは沈黙だ。見上げた三井さんは真っ赤になりながら歯を磨いていた。 「悪いかよ…。」 もういい大人の筈なのに、学生時代のような甘酢いっぱい気持ちになるから三井寿という男は私には読みきれない男なのかもしれない。取り敢えず、ちゃんとは胸は苦しいので、彼女になってみるのもありなのかもしれない。 私には、運命の人がいる。そしてそれは三井さんではない。でも、たった一つ今わかったことがある。運命の人が恋人になるとは限らない。不器用って、意外と愛おしいらしい。初めて知った事実だった。
運命になれないふたり |